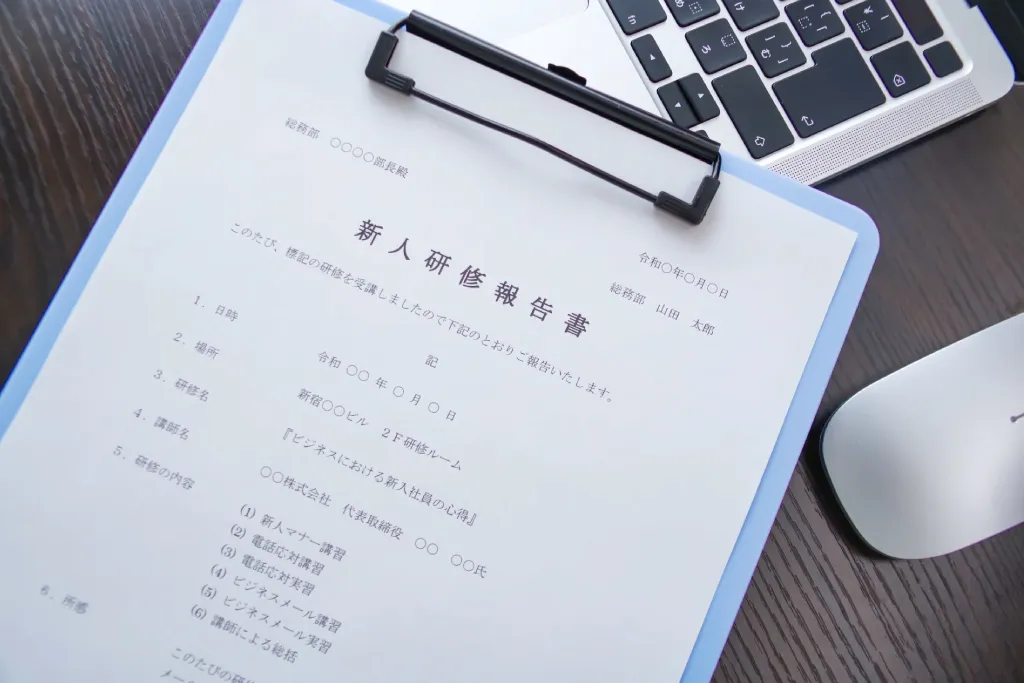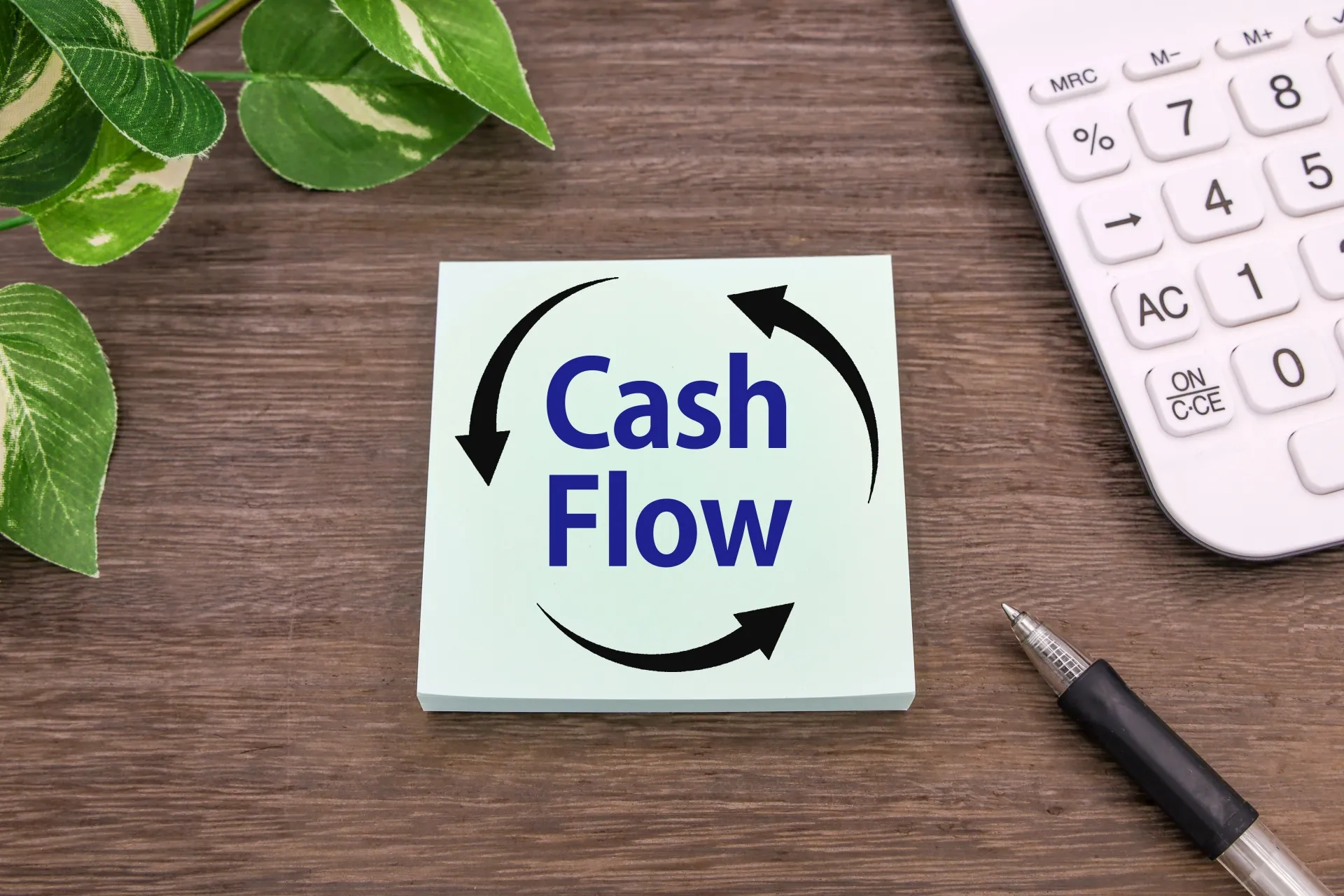- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 主体性研修で受け身社員が変わる!自ら動く社員の育て方を解説
主体性研修で受け身社員が変わる!自ら動く社員の育て方を解説

変化の激しい現代のビジネス環境では、社員一人ひとりが自ら考え、行動する「主体性」の重要性が高まっています。しかし、主体性は一朝一夕で身につくものではなく、育成のためには体系的なアプローチが必要です。
当記事では、主体性の定義や自主性との違い、研修を行う目的、具体的な研修プログラム例などを詳しく紹介します。研修を成功させるための実践ポイントや導入企業の成功事例もあわせて掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
Toggle『部下・後輩の主体性を引き出す チームビルディング研修』について詳しくはこちら
主体性研修とは

主体性とは、自らの意志と判断によって行動し、その結果に責任を持つ姿勢を指します。特にビジネスの現場では、「何をすべきか」を自分で見極め、目標達成に向けて能動的に行動する力が主体性とされます。
似た概念に「自主性」がありますが、自主性は与えられた課題に対して率先して動くことを意味し、主体性は課題そのものを自ら見つけて行動に移す点が異なります。
主体性研修は、このような主体性を社員に育ませることを目的とした研修です。変化の激しい現代において、上司の指示を待つだけでは成果は出せません。主体性研修を通じて、各自が課題を見出し、目的意識を持って動ける人材を育成することが、企業の競争力向上にもつながります。
主体性研修の目的

社員一人ひとりが指示を待つのではなく、目的意識を持って行動することで、個人のモチベーションや生産性、チームへの貢献度が高まります。
ここでは、主体性研修が持つ3つの具体的な目的について解説します。
目的意識を持って仕事を行わせるため
多くの社員は、日々の業務に追われる中で、「なぜこの仕事をしているのか」という目的意識を見失いがちです。言われたことだけをこなす日常が続くと、やりがいや達成感を感じにくくなり、モチベーションの低下や組織へのエンゲージメント不足につながる恐れがあります。
主体性研修では、まず「自分の仕事の目的」や「その先にある意義」を問い直す機会が与えられます。目的意識が芽生えることで、単なる作業にも意味が生まれ、やる気や責任感が強化されます。自分の仕事が会社や社会にどのように貢献しているのかを理解すれば、日々の行動が前向きになり、自発的な取り組みも増えていくでしょう。
主体性を育てる第一歩は、「なぜ働くのか」を明確にすることです。
主体的に動くことで生産性を上げるため
主体性を持つ社員は、自分の業務に対して「もっとよくするにはどうしたらいいか」を考えながら取り組みます。そのため、業務上の非効率な部分を自ら発見し、改善策を提案・実行する力を持つようになり、チーム全体や組織の生産性向上につながります。
また、主体性が高い社員は「指示がなければ動けない」という状態に陥りません。状況を見て判断し、自ら行動を起こせるため、無駄な待ち時間が減り、業務のスピード感が増します。特にリモートワークのように上司の目が届きにくい働き方では、主体的に動けることが大きな武器となります。
社員の能力は高いのに成果が伸びないという組織では、主体性の欠如が原因になっているのかもしれません。主体性研修を通じて一人ひとりが自律的に考え行動する習慣を身につければ、自然と全体のパフォーマンス向上が期待できます。
自分がどのような役割を求められているか理解してもらうため
仕事において主体性を発揮するためには、自分が組織の中でどのような役割を担っているのかを理解することが不可欠です。役割が不明確なままでは、「自分が何をすればよいのか」「どこまで責任を持つべきか」が分からず、結果として受け身な姿勢に陥ってしまいます。
主体性研修では、「自分には何が期待されているのか」「チームの中でどのような貢献が求められているのか」といった点を、対話やワークショップを通じて明らかにします。
役割の理解は、自分の強みやスキルを生かすヒントにもなります。また、他者の役割との違いを認識することで、周囲との協働や支援の仕方も見えてきます。役割を正しく理解し、自らの立場で最大限の価値を発揮できるようになることは、主体性の育成にとって非常に大切です。
主体性研修のカリキュラム例

主体性研修と一口に言っても、対象者の経験や役職、目的によってアプローチはさまざまです。ここでは、主体性を育むのに効果的なカリキュラムをいくつかご紹介します。若手社員から管理職まで、階層ごとに適した研修内容を知り、自社に合ったプログラム選定の参考にしてください。
若手社員研修
入社から3年目までは、仕事の基本が身につき始め、やりがいと同時に将来への不安も感じやすい時期です。この時期に「自分は何のために働くのか」「どのようなキャリアを描きたいのか」といった問いに向き合うことで、仕事への主体性が育まれます。
若手社員研修では、過去の経験を振り返り、将来のビジョンを明確にすることで、職場で主体的に行動するための意識とスキルを身につけることを目的としています。
【研修カリキュラム】
| 1 | 今までの自分を振り返る | 経験の棚卸しを通して、仕事の意義や価値観を再認識する |
| 2 | 将来像(マイビジョン)を描く | 「ビジョンマップ」を用いて将来の目標を可視化・言語化する |
| 3 | 対人スキルを磨く | 傾聴・伝達・ホウレンソウを学び、信頼関係を築く力を養う |
| 4 | 【演習】ドミノコンテスト | チームで計画・協働しながら作品を完成させ、達成感を得る |
| 5 | 自分の人生は自分で決める | 愚痴からの脱却・主体的思考の切り替え・ポジティブ思考を学ぶ |
| 6 | メッセージカードを描く | 将来の自分への手紙を書き、自身の言葉で想いを定着させる |
主体性の育成は一度の指導で完結するものではなく、段階的かつ継続的な支援が必要です。本研修は、その基礎づくりとなる重要なステップとして、若手社員の「これから」に希望と具体性を与える内容です。
ジョブクラフティング研修
仕事に対する「やらされ感」や無力感は、若手社員から中堅社員まで広く抱かれやすい課題です。ジョブクラフティング研修は、仕事に対するネガティブな意識を、前向きな主体性へと転換させるアプローチとして注目されています。
ジョブクラフティング研修は、目の前の仕事を「誰かにやらされるもの」から「自分で価値を生み出すもの」へと再定義することで、日々の仕事にやりがいを見出し、内発的な動機付けを強化する内容です。働き方改革や離職防止といった観点でも、多くの企業が導入を進めています。
【研修カリキュラム】
| 1 | オリエンテーション | 研修の趣旨と全体像の共有 |
| 2 | ジョブクラフティングとは | 「やりがいの再定義」とその効果について解説 |
| 3 | ジョブクラフティングの考え方 | ジョブクラフティング3つの視点(仕事のやり方・周囲との関係・考え方)を理論と事例で学ぶ |
| 4 | 仕事のやり方への工夫 | 日々の業務を洗い出し、自分の強みや改善点を発見 |
| 5 | 周りの人への工夫 | 他者との関係性を再構築し、相互理解を深める |
| 6 | 考え方の工夫 | 仕事の目的を再認識し、視点を広げる |
| 7 | アクションプランの作成 | 学びを振り返り、現場での具体的な行動計画を策定 |
ジョブクラフティングの考え方を理解することで、受講者は業務そのもののデザインを変えられると分かり、自分の仕事に主体的に関わろうとする意識が芽生えます。
キャリアデザイン研修
急激に変化するビジネス環境では、社員一人ひとりが将来を見据えて自らのキャリアを主体的に描く力が求められます。キャリアデザイン研修は、社員が自身の価値観と会社の理念を結びつけ、仕事への意欲や会社への貢献意識を高めることを目的としています。
キャリアデザイン研修では、自己理解を深めながら、社会とのつながりや会社で果たすべき役割を考え、主体的に行動できるキャリアの起点を築きます。
【研修カリキュラム】
| 1 | オリエンテーション | 研修の流れを確認し、参加目的を明確化する |
| 2 | 価値観を探る | 自分が働く上で大切にしている価値を見つける |
| 3 | 環境変化を知る | 会社や社会を取り巻く変化を理解し、自分の立ち位置を考える |
| 4 | 会社の理念に立ち返る | 組織の理念と自身の価値観の重なりを探る |
| 5 | 自分の将来像を描く | 貢献したい姿を明確にし、キャリアビジョンを言語化する |
| 6 | 行動計画を作る | 明日からできる具体的な行動を決め、グループで共有する |
この研修では、自分自身がどのように会社へ貢献できるのかという視点を持ち、実現するための第一歩を明確にするプロセスが組み込まれています。企業理念との接点を見つけることで、仕事の意味づけが深まり、他人の期待ではなく、自分の意志で行動する土台が整います。キャリアを自分事として捉えることこそが、主体性を育てる最大の鍵です。
リーダーシップ研修
初めてチームを任されたリーダーや、新任管理職にとって、「どうすればチームをうまく導けるのか」という悩みはつきものです。
リーダーシップ研修は「リーダーシップは才能ではなく行動である」という考えのもと、ワークと振り返りを通じて、日々の業務にすぐに生かせるスキルを体系的に習得できる内容です。リーダー層が成果を上げるための行動を8つに分けて学ぶ中で、リーダーとしての自信を深め、チームの成果に貢献するための第一歩を支援します。
【研修カリキュラム】
| 1 | オリエンテーション | 研修の目的や進め方を確認し、参加意欲を高める |
| 2 | リーダーシップとは/役割認識 | 成果を出すためのリーダーの役割を理解する |
| 3 | 8つの基本行動①~③ | 「目的を示す」「計画と進捗管理」「伝える・聴く力の習得」という3つを学ぶ |
| 4 | 8つの基本行動④~⑧ | 「仕事の任せ方」「優先順位設定」「叱り方・褒め方」「心理的安全性」「自責の姿勢と学び続ける力」を学ぶ |
| 5 | 振り返り・課題設定 | 弱点の洗い出しとアクションプランの立案 |
| 6 | その他 | 研修全体の気づきを整理し、今後の実践に向けて再確認する |
自分のリーダー像を言語化し、行動に変えるプロセスを通じて、単なるスキルの習得にとどまらず、主体的なチーム運営の基礎を作ります。リーダー自身が自責の姿勢を持ち、部下の主体性を尊重することで、組織全体の自律性が育まれていきます。
コーチング研修
部下の成長を促し、チームの力を引き出す上で欠かせないのが「信頼に基づいた対話力」です。コーチング研修では管理職やリーダー層を対象に、部下との関係性を土台から見直し、現場で生きる対話力を育てます。特に、チームを率いる立場にある方が、自分の言葉で信頼を築き、部下の内発的動機を引き出せるようになることが大切です。
【研修カリキュラム】
| 1 | 21世紀の第五の資産 | 信頼・関係性の重要性を理解する |
| 2 | チームワークのベネフィット | 強いチームをつくるための視点を共有 |
| 3 | 求められる管理職像 | 時代に合ったリーダーの姿とは何かを考える |
| 4 | 自己診断と課題確認 | 現状のリーダー行動を見直し、改善点を探る |
| 5 | 影響力を高める7つの役割 | チームによい影響を与える行動特性を習得 |
| 6 | コミュニケーションとは? | 情報伝達から対話への転換 |
| 7 | 信頼を築く関わり方 | 安心感・個性理解・関係構築の要素を学ぶ |
| 8 | 話させることで生まれる効果 | 傾聴・承認を通じた成長支援の実感 |
コーチング研修では、問いかけと振り返りを繰り返す進行により、「気づき」から「腹落ち感」へとつなげ、単なるノウハウに終わらない実践力が養われます。学んだことを職場に戻ってすぐ試せるよう、多くのワークが組み込まれており、学びの即効性も高い内容です。
チームビルディング研修
チーム全体の力を引き出すためには、メンバー一人ひとりの主体性を尊重しながら、共通の目標に向かって協働する仕組みが必要です。チームビルディング研修では、チームでのコミュニケーションと目標達成をテーマに、アクティビティを通じて「自ら考え動く力」を実感しながら学びます。特にリーダー層や中堅社員が、どのように周囲を巻き込み、チームの中で主体性を引き出せるかを体験的に理解することを目的としています。
【研修カリキュラム】
| 1 | 導入・アイスブレイカー | プログラムの目的を確認し、チームの一体感を醸成する |
| 2 | アクティビティ① | 「ワープスピード」「スピードボール」などで目標設定とモチベーションの違いを体感 |
| 3 | アクティビティ②・③ | 「ブラインドスクエア」「フープくぐり」などで、主体的に動けるチームづくりを体験 |
| 4 | ワールドカフェ(対話) | 職場とのつながりを意識しながら、学びを言語化・共有 |
| 5 | まとめ・チェックアウト | 研修での気づきを明日からの行動へ落とし込み、言葉にして終了 |
この研修で特に注目すべきは、アクティビティ後のワールドカフェ形式での対話です。体験を言葉にして共有し合うことで、個々の気づきが深化し、「なぜその行動が重要なのか」が腑に落ちる構造となっています。メンバーそれぞれの強みが発揮されるチームとはどのような状態か、主体性を引き出す関わり方とは何かを実感するこのプロセスこそ、行動変容の起点になります。
1on1研修
1on1ミーティングは、単なる面談ではなく、メンバーのやる気と成長を引き出す重要なマネジメント手法です。1on1研修では、1on1を効果的に機能させるために、リーダー自身がまず「どのように部下と向き合うべきか」を問い直し、自身のリーダーシップを再認識するところからスタートします。
1on1を通してメンバーの主体性を育み、自律的な人材育成を行うには、リーダー自身の関わり方やスタンスの変化が大切です。
【研修カリキュラム】
| 1 | リーダーシップ/経営理念・ビジョン | 経営理念と自分のビジョンを重ね合わせ、言語化する |
| 2 | メンバー育成の考え方 | 管理型から支援型マネジメントへ。自立型人材の育成視点を学ぶ |
| 3 | 成長・成果を加速させる1on1 | 面談との違い、継続による効果、成功と失敗の事例を理解する |
| 4 | 状況対応型リーダーシップ | 部下のタイプに応じた関わり方を身につける |
| 5 | 1on1実践エクササイズ | ツール紹介、準備ワーク、ロールプレイ、振り返りで実践力を高める |
1on1の本質は「対話による成長支援」です。相手の話を傾聴し、問いかけを通じて考えを引き出し、自ら気づいて行動を選択する力を高めていくプロセスを実感し、ロールプレイなどで練習を重ねることで、現場で即実践できるスキルとして定着させます。
主体性研修で社員を育てるポイント

社員の主体性を引き出すためには、研修内容はもちろん、実施環境や運用面にも工夫が求められます。ここでは、主体性を育む際に押さえておきたい4つの実践的なポイントを紹介します。
心理的安全性を高める
主体性を引き出すための土台となるのが「心理的安全性」です。研修中に発言や行動を否定される恐れがあると、人は自発的な行動を控えるようになります。事前に「批判しない」「否定しない」などのグランドルールを設け、参加者同士が尊重し合える場をつくることが不可欠です。
また、企業全体としても、失敗を許容する文化や、上下関係にとらわれず意見を言いやすい風土を並行して整えていくことが、社員の主体的な挑戦を後押しします。
研修の目的とゴールを明確にする
研修の目的が曖昧なまま進行してしまうと、受講者は「なぜこの研修を受けるのか」という納得感を持てず、結果として受け身の姿勢になりやすくなります。事前に「何のために実施するのか」「何ができるようになってほしいのか」といった目的とゴールを明確にし、参加者に共有しましょう。
ゴール設定の際には、定量的・定性的な評価指標を合わせて提示し、成果が可視化できる形にすることで、研修の意義や効果も測定しやすくなります。目的が明確になれば、参加者も自分ごととして主体的に学びに向き合えます。
考える余白や選択の余地を多く与える
主体性は「自分で考えて決める経験」の積み重ねから育まれます。そのため、研修ではあえて答えを与えすぎず、「考える余白」を残すことが大切です。
例えばグループワークの際、細かい指示ではなく課題の目的だけを伝えれば、参加者は自分たちでやり方を模索しながら取り組むようになります。また、席の選び方や話し合いの進行役の決定など、自由に選べる場面を多く設けることで、「自分で決める」「選ぶ」ことに慣れる訓練にもなります。小さな選択の積み重ねが、仕事への自律的な姿勢へとつながります。
ポジティブフィードバックやリフレクションを行う
研修の場で得た気づきや挑戦が、自己肯定感や行動変容につながるようにするためには、ポジティブなフィードバックとリフレクションが欠かせません。参加者の発言や行動に対して「よかった点」「取り組みの価値」を積極的に言語化して伝えることで、小さな成功体験を認識させ、次の主体的行動を後押しします。
また、自分の体験を振り返り、学びを整理するリフレクションの時間を設けることで、研修の内容が「自分の成長にどうつながったか」を明確にできます。
主体性研修の成功事例

ここでは、実際に研修を通じて社員の意識や行動の変革を促している企業の事例を2つ紹介します。研修の導入背景や工夫点、社員への働き方を知ることで、自社に取り入れる際のヒントになるでしょう。
| SONY |
| ソニーでは、新入社員が自ら設定したテーマに半年間取り組み、成果を発表する「新人テーマ研修」を実施しています。配属後すぐに企画立案から調査、関係部署との連携、提案までを主体的に進め、自ら考え行動する力を育むことを目的としています。この研修を通じて、論理的思考や巻き込み力、仕事の意義を実感する貴重な経験を重ねることが可能です。 |
※出典:SONY「研修をきっかけに新機能を考え、半年で開発。ソニーの新入社員が本気で取り組む「新人テーマ研修」とは。」
| 伊藤忠商事株式会社 |
| 伊藤忠商事では、社員一人ひとりの成長が企業成長の原動力になるとの考えから、人材戦略を経営の中核に据えています。働きがいの向上や成果に応じた評価制度を整えるとともに、キャリア面談や社内研修、オンライン学習の導入などを通じて、主体的なキャリア形成を支援しています。近年は「学び続ける姿勢」を重視し、DX推進や生成AI活用などを含む多様な成長機会を提供しています。 |
まとめ
社員の主体性を高めることは、単なる行動の活性化にとどまらず、企業の生産性向上や競争力強化にも直結します。若手社員にはキャリアの目的を明確にさせ、中堅層にはやりがいの再定義を促し、リーダー層にはチーム全体を巻き込む力を育てるなど、階層に合った主体性研修を実施し、主体性を高めましょう。
主体性のある人材こそが、変化の時代における企業の成長を支える鍵となります。
関連記事
Related Articles

【診断問題有】怒りの衝動を鎮める!アンガーマネジメント「6秒ルール」のテクニック
アンガーマネジメントは、怒りの感情を適切に理解・コントロールするための心理トレーニングです。怒りのメカニズムやタイプ...
企業研修