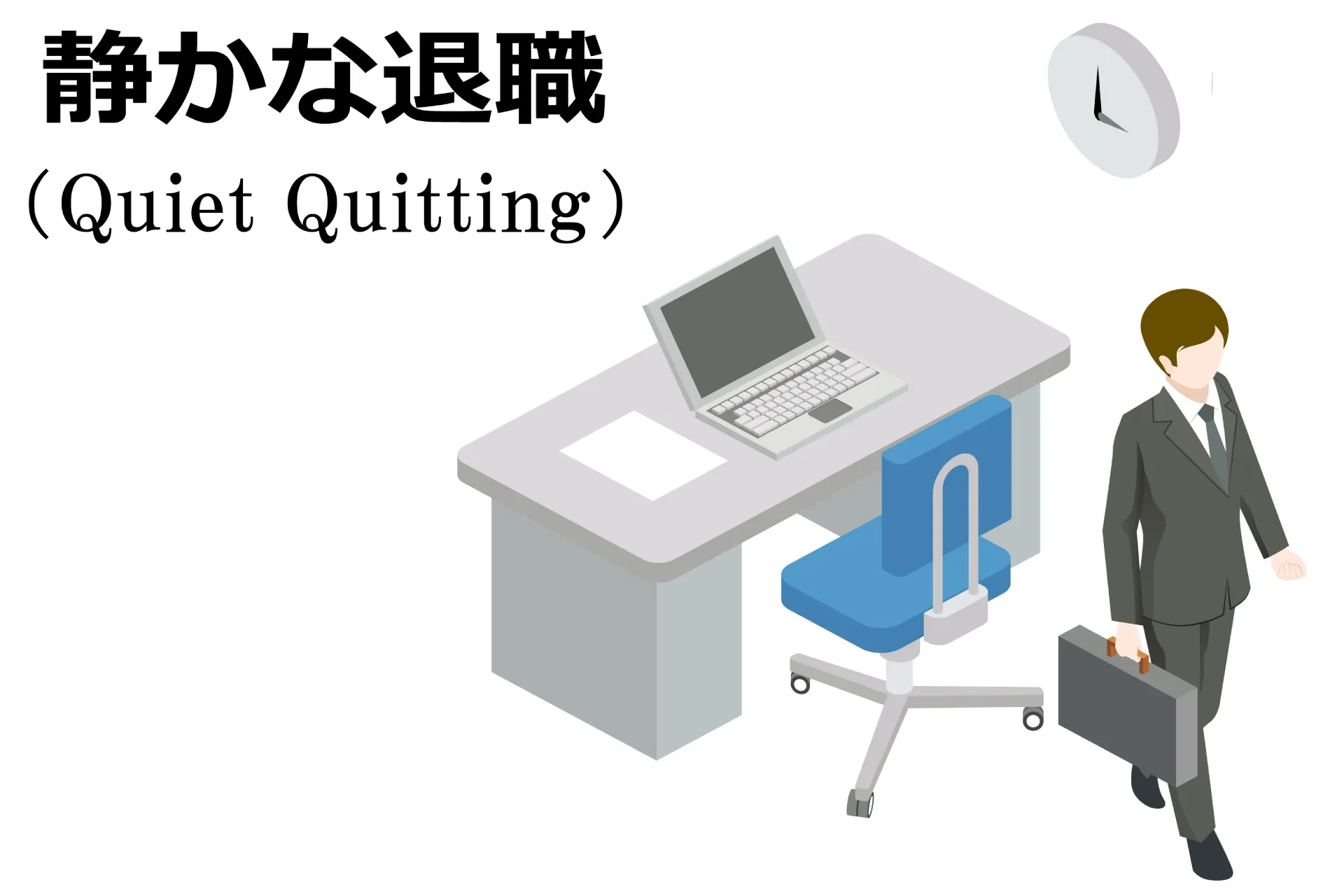- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- HRトレンド
- 【2025年10月】育児・介護休業法が改正!いつから対応が必要か徹底解説
【2025年10月】育児・介護休業法が改正!いつから対応が必要か徹底解説
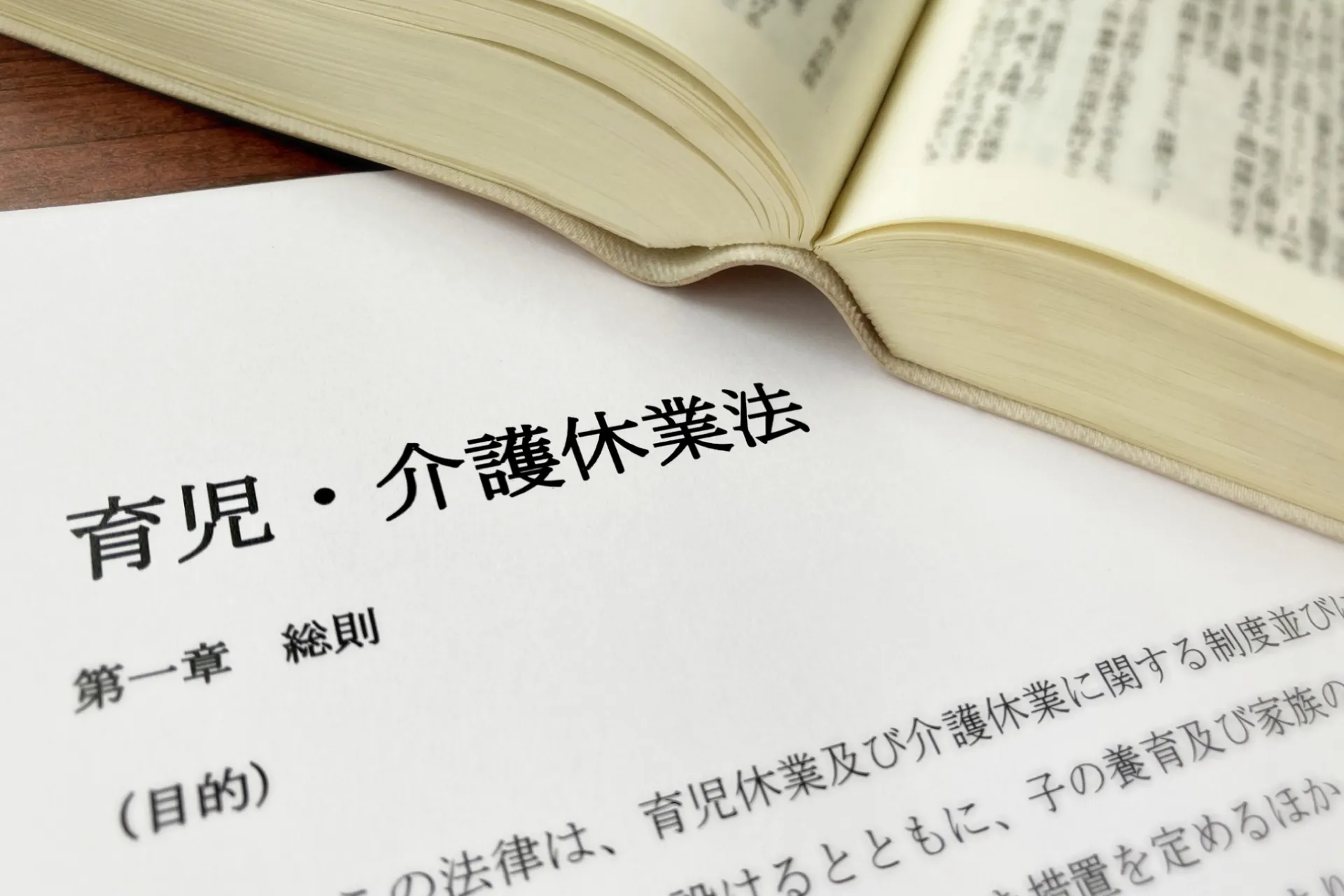
この記事は2025年1月14日に公開した記事を再編集しています
2025年8月12日更新
少子高齢化に伴い人口が減少する中、持続可能で安心できる社会を作るには、就労と子育て・介護を両立できるようにする必要があります。育児・介護休業法はその一環を担う法律ですが、時代の変化に合わせてより柔軟に働けるよう、2024年5月に改正されました。
当記事では、改正された育児・介護休業法の変更内容について分かりやすく解説した上で、事業主が行うべき対応を説明します。育児・介護休業法は全企業が対象となるため、改正内容を確認しておきましょう。
目次
Toggle育児・介護休業法の改正とは?いつから施行される?

男女ともに仕事と育児・介護を両立できる環境づくりを目的として、2024年5月に育児・介護休業法が改正されました。改正育児・介護休業法は、2025年4月1日から段階的に施行されました。主な改正内容は、以下の3点です。
| 1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 |
また、同じく2024年5月には次世代育成支援対策推進法も改正されています。これにより、2025年3月31日を予定していた法律の有効期限が、2035年3月31日まで延長されました。
※出典:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)」
育児・介護休業法の改正1|柔軟な働き方を実現する措置の拡充

育児・介護休業法の改正における「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」では、小さな子どもを育てる従業員向けに、仕事・キャリア形成と育児を両立できるよう体制が整えられました。以下では、それぞれの改正内容について詳しく解説します。
柔軟な働き方を実現する措置・個別の周知と意向確認の義務化
対象の労働者が柔軟な働き方を実現するために、事業主には措置の実施および労働者に対する個別の周知・意向確認が義務付けられます。対象者は、3歳以上・小学校就学前の子どもを養育する労働者です。
事業主は以下の5つの措置の中から、2つ以上を選択・実施しなくてはなりません。テレワークや新たな休暇は、原則時間単位で取得が可能です。
| ・保育施設の設置運営など ・始業時刻などの変更(フレックスタイム制や時差出勤など) ・テレワークなど(10日/月) ・新たな休暇の付与(10日/年) ・短時間勤務制度 |
対象となる労働者は、事業主が実施した2つ以上の措置のうち、1つを選んで利用できます。また、そうした措置を選択・利用できることを、子どもが3歳を迎えるまでに面談や書面交付などで労働者に個別に周知し、意向を確認しなければなりません。なお、事業主で実施する措置を選択する場合、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)などから意見聴取の機会を設ける必要があります。これらは、2025年10月1日から施行されます。
【2025年10月~】所定外労働を制限する対象者を小学校就学前に拡大
2025年10月から、所定外労働(残業)の制限を請求できる対象者が「3歳未満の子の養育者」から「小学校就学前の子の養育者」に拡大されます。これは育児と仕事の両立を支援するための重要な改正で、保育園・幼稚園に通う子どもを持つ家庭にも恩恵が広がります。
| 改正項目 | 改正前 | 改正後 |
| 残業制限の対象 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
| 管理監督者の扱い | 短時間勤務制度と併用可 | 短時間勤務制度と併用可(変更なし) |
| 他制度との併用 | 管理監督者(労基法第41条) | 同左(変更なし) |
この制度は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、会社が労働者に所定外労働を命じることを禁じるものです。労働者が請求しやすくするためには、あらかじめ就業規則等で制度として明文化し、周知しておくことが重要です。
また、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかどうかは、作業の繁閑や代替要員の確保状況などを踏まえ、客観的に判断する必要があります。単に「残業が必要だから」という理由だけで拒否することは許されません。フレックスタイム制を導入している企業でも、この残業免除制度は併用可能です。企業としては、育児中の従業員の働きやすさを確保するために、制度の整備と柔軟な対応が求められます。
看護休暇の対象を小学校3年生まで・取得事由に入卒園式を追加
看護休暇とは、病気やケガなどで子どもの看護が必要となった際に取得できる休暇制度です。子どもが1人の場合は1年で5日まで、2人以上の場合は1年で10日まで、労働者に休暇が付与されます。看護休暇中の給与に関しては特に法律上の規定はなく、有給・無給のどちらでも構いません。
看護休暇については、対象となる子の範囲や取得事由など、複数の制度変更が行われました。改正前と改正後の違いは下表の通りです。
| 改正前 | 改正後 | |
| 名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
| 対象となる子ども | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
| 取得事由 | 予防接種・健康診断・病気・けが | 改正前に加えて、感染症による学級閉鎖・入園式・入学式・卒園式 |
| 労使協定の締結で除外できる労働者 | (1)雇用期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下 | 週の所定労働日数が2日以下 |
変更後は、対象となる子どもが小学校3年生まで拡大されるほか、入園式・卒園式などの行事参加を理由とした休暇取得が可能になります。また、労使協定の締結によって除外される労働者の範囲が縮小され、勤続6か月未満でも看護等休暇を取得できます。名称についても変更されるため、就業規則などを見直す際は注意が必要です。これらは、2025年4月1日から施行されています。
【2025年10月~】時短勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク等を追加
2025年10月からの改正により、3歳未満の子を養育する労働者に対して「短時間勤務制度」を適用できない場合の代替措置として、新たに「テレワーク等」が追加されました。これは、多様な働き方の選択肢を広げ、育児との両立支援をさらに強化するための変更です。
| 改正項目 | 改正前 | 改正後 |
| 代替措置の選択肢 | 1. 育児休業制度に準ずる措置 2. フレックスタイム制 3. 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4. 保育施設の設置・運営等 | 1~4に加え 5. テレワーク等 |
短時間勤務制度の対象外とできるのは、「業務の性質や体制からして制度の適用が客観的に困難な場合」に限定されます。この場合、労使協定の締結が必要であり、具体的な対象業務を明示した上で、代替措置の実施が求められます。
なお、テレワーク等はICT業務に限らず、勤務地も自宅やサテライトオフィスなど柔軟に設定可能です。導入にあたっては、保育施設への送迎など家庭環境に配慮し、性別によって対象を限定するような制度設計は避ける必要があります。
また、テレワークを実施するために新たな部署の設置や人員配置の変更まで求められるものではなく、現実的にテレワーク可能な職務への適用にとどまる点にも注意が必要です。企業としては、制度改正にあわせて就業規則や社内体制の見直しを進めておくことが重要です。
【2025年10月~】仕事と育児の両立に関する意向の聴取・配慮の義務化
妊娠・出産の申出時や子どもが3歳になる前のタイミングで、仕事と育児の両立について労働者に個別の意向聴取・配慮を行うことが事業主に義務付けられます。配慮の例としては「両立支援制度の利用期間の見直し」「労働条件の見直し」「勤務時間帯・勤務地の配置」「業務量の調整」などが挙げられます。
また、ひとり親家庭の場合は子の看護等休暇等の付与日数を配慮すること、子どもに障害がある場合などは短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長することなども望ましいとされています。労働者への意向の聴取は、面談や書面交付などで行う必要があります。これらは、2025年10月1日から施行されます。
育児・介護休業法の改正2|育休取得状況の公表義務拡大と次世代育成支援対策の推進

育児・介護休業法の改正における「育休取得状況の公表義務拡大と次世代育成支援対策の推進」では、主に育休の取得を後押しするような変更が行われました。どのように変更されたのか、以下で詳しく解説します。
育休の取得状況の公表義務を300人超の事業主に拡大
現行法で従業員数1,000人超の企業にすでに課されている、男性労働者の育休の取得状況の公表義務が、従業員300人超の事業主も対象になります。ここで指す育休とは、育児・介護休業法で規定された「産後パパ育休を含む育児休業」「第23条第2項(3歳未満の子どもを育てる労働者に所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)または第24条第1項(小学校就学前の子どもを育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育休制度に準ずる措置を講じた場合の休業」が含まれます。
従業員300人超の事業主は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度における「育児休業等の取得割合」もしくは「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のどちらかをインターネットなどで公表しなければなりません。
| 育児休業等の取得割合 | 育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数 |
| 育児休業等と育児目的休暇の取得割合 | (育児休業等をした男性労働者の数+休暇制度を利用した男性労働者の数)÷配偶者が出産した男性労働者の数 |
育休の取得状況は一般の方が自由に閲覧できる方法で公表する必要があり、自社のホームページに掲載する形でも問題ないと考えられますが、厚生労働省は「両立支援のひろば」への公表を推奨しています。また、男性労働者に合わせて「女性の育児休業取得率」「育児休業平均取得日数」などの公表も任意で可能です。これらは、2025年4月1日から施行されています。
行動計画策定時の育休の取得状況の把握・数値目標の設定を義務化
育児・介護休業法と同時に、次世代育成支援対策推進法も改正されました。次世代育成支援対策推進法とは、次世代を担う子どもたちの健全な育成を支援する目的で、2005年に施行された法律です。国や自治体、事業主は、次世代の育成支援に向けた行動計画を策定することが求められています。
次世代育成支援対策推進法の改正により、従業員100人超の企業は一般事業主行動計画策定時に「育児休業取得状況や労働時間状況の把握と数値目標の設定」が義務となりました。従業員100人以下の企業は努力義務です。育児休業取得状況には男性の育児休業等取得率、労働時間状況にはフルタイム労働者1人あたりの月ごとの時間外労働と休日労働の合計時間数等が適用されます。
これらは2025年4月1日から施行され、施行日以降に開始または内容変更された行動計画が対象となっています。
次世代育成支援対策推進法の有効期限を2035年まで延長
次世代育成支援対策推進法の改正により、法律の有効期限が10年間延長されました。次世代育成支援対策推進法は2025年までの時限法として制定されましたが、延長により2035年まで効力を発揮することが決まっています。この内容は、2024年5月31日にすでに公布・施行されています。
それに伴い、くるみん認定制度も継続されますが、今後認定基準の一部が見直しされる予定です。くるみん認定制度とは、一般事業主行動計画を策定した上で一定の条件を満たした場合、申し出ることによって厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けられる制度です。
育児・介護休業法の改正3|仕事と介護の両立支援制度の強化等

育児・介護休業法の改正における「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」では、労働者の介護離職を防ぐ措置が主に講じられています。ここからは、詳しい改正内容をわかりやすく解説します。
両立支援制度等の個別周知・意向確認を義務化
家族の介護が必要な労働者に対し、事業主は介護休業や両立支援制度、介護休業給付金に関して個別に周知し、利用の意向を確認する必要があります。介護休業とは、要介護状態にある家族の介護や世話をするために労働者が取得できる休暇です。両立支援制度には、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、所定労働時間の短縮などが含まれます。
個別周知・意向確認は、オンラインを含む面談・書面・FAX・電子メールのいずれかで行うFAXや電子メールは労働者が希望した場合のみ可能です。その際、労働者に介護休業や両立支援制度の利用を控えさせることは認められません。これらの内容は、2025年4月1日から施行されています。
両立支援制度等の情報提供や雇用環境整備を義務化
事業主は、労働者が40歳に達するまでに、介護休業や両立支援制度、介護休業給付金に関する情報を提供する必要があります。その際、介護保険制度の周知も望ましいとされています。情報提供の方法は、オンラインを含む面談・書面・FAX・電子メールのいずれかで構いません。
また、労働者が介護休業や両立支援制度を円滑に申し出ることができるよう、以下の4つのうち、いずれかの措置を講じることも義務となりました。1つだけではなく、複数の措置を講じることが望ましいです。
| ・介護休業や両立支援制度に関する研修の実施 ・介護休業や両立支援制度に関する相談窓口の設置 ・介護休業の取得や両立支援制度の利用に関する事例収集・提供 ・介護休業や両立支援制度の利用を促進する方針の周知 |
これらの制度は、2025年4月1日から施行されています。
介護休暇で勤続6か月未満の従業員を除外する仕組みを廃止
介護休暇とは、要介護状態の家族の介護や世話をするために、対象家族が1人の場合は1年で5日、2人以上の場合は1年10日の休暇を取得できる制度です。改正前は、入社6か月未満の労働者と所定労働日数が週2日以下の労働者は、労使協定を締結している場合に対象外とされていました。
しかし、改正後は入社6か月未満の労働者を対象外とする要件が廃止され、介護休暇を利用できる労働者の範囲が拡大そのため、勤続年数にかかわらず介護休暇を取得しやすくなると言えるでしょう。これらの制度は、2025年4月1日から施行されています。
育児・介護をする従業員のテレワークを努力義務化
2025年4月から、育児や介護のためのテレワーク等の導入が事業主の努力義務として位置づけられました。対象は「3歳未満の子を育てるが育児休業をしていない従業員」および「要介護家族を抱えるが介護休業をしていない従業員」です。テレワーク等には自宅勤務だけでなく、就業規則で定めたサテライトオフィスなどの勤務も含まれ、必ずしもIT業務に限られません。
テレワーク等ができない業務に従事している場合、対象から外すことも可能ですが、性別などによる限定は禁止されています。また、労働者の健康への配慮も求められており、長時間労働の防止や面談の実施なども推奨されています。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 育児休業・介護休業を取得していない従業員 |
| 対象条件 | 3歳未満の子の養育、または要介護家族の介護 |
| 事業主の義務 | テレワーク等を選べる環境整備(努力義務) |
「常時介護を必要とする状態」判断基準の見直し
2025年4月より、「常時介護を必要とする状態」に関する判断基準が改定されました。これは、介護休業制度の対象者をより柔軟に判断できるようにするための見直しです。これまでの基準では、障害児や医療的ケアが必要な子どもなどについて、制度の対象になるかどうかの判断が困難なケースがあるとの指摘がありました。今回の改定により、「常時介護を必要とする状態」の判断基準は2つのいずれかに該当すれば対象となります。
| (1) 項目①~⑫のうち、状態「2」が2つ以上または「3」が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。 (2) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。 |
これらの項目には、座位保持や歩行、排泄、食事、認知・行動、医療的ケアの要否など、日常生活に関する12の観点が含まれています。状態が継続していることが確認されることも前提条件の1つです。

※引用:厚生労働省「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説」 引用日2023/06/26
なお、この判断基準はあくまで目安であり、労働者の休業取得が過度に制限されないよう、事業主には柔軟な運用が求められています。育児・介護休業法の理念に沿い、対象者の個別事情に応じた対応を取ることが重要です。
育児・介護休業法の改正4|育児休業等を理由としたハラスメントの防止強化

2025年の法改正により、育児休業や介護休業などの申出・取得を理由とした不利益取扱いやハラスメントの防止措置が強化されました。これまでも、制度の利用によって解雇や減給、配置転換などの不利益を被ることは禁止されていましたが、今回の改正では対象となる行為や場面がさらに具体化され、保護の対象が拡大されました。
| ・感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式及び卒園式のために子の看護等休暇を申出・取得したこと ・対象家族の介護を必要とする状況に至ったことの申出をしたこと ・妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前の時期に確認された労働者の仕事と育児の両立に関する意向の内容 ・柔軟な働き方を実現するための措置の申出・利用 等 |
また、企業には上司や同僚によるハラスメントを未然に防ぐ措置を講じることが義務付けられました。これには、制度利用を理由とした精神的な圧力や侮辱的発言などを防止する体制整備や研修の実施などが含まれます。
制度の利用をめぐるトラブルを避けるには、事業主側の明確なルール整備と周知、相談窓口の設置などが重要です。ハラスメントのない働きやすい環境づくりが求められています。
育児・介護休業法の改正5|給付制度の拡充

育児・介護休業法の改正により、育児と仕事の両立を経済的にも支援するための給付制度が見直されました。今回は、国が実施する制度として、育児休業中や時短勤務時の給付金が拡充される内容が中心です。企業側に特別な対応は求められていませんが、従業員が安心して制度を利用できるよう、内容を把握しておくことが望まれます。
以下では、具体的な給付制度の変更点を解説します。
育児休業給付の給付率引上げ・出生後休業支援給付の創設
2025年4月より、育児休業に関する給付制度が拡充され、子育て世帯に対する経済的支援が一層手厚くなりました。大きな変更点は、育児休業給付の給付率が最大80%に引き上げられたことと、出生後休業支援給付が創設されたことです。
具体的には、被保険者本人と配偶者の両方が、子の出生後8週間以内にそれぞれ14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間にわたって休業前賃金の13%相当が支給され、従来の育児休業給付とあわせて手取りほぼ100%に相当する給付を受けられるようになりました。

※引用:厚生労働省「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説」 引用日2023/06/26
配偶者が専業主婦(夫)である場合や、ひとり親家庭も対象となるため、幅広い家庭にメリットがあります。これにより、男性の育児参加も含めた「夫婦での育児」の推進が期待されています。
育児時短就業給付の創設
2025年4月より、2歳未満の子どもを養育するために短時間勤務(時短勤務)を選択した被保険者に対して「育児時短就業給付」が支給されるようになりました。これは、育児と仕事の両立を支援するための新たな給付制度です。
育児時短就業を行った月について、その月に支払われた賃金の10%相当額が支給されます。ただし、賃金が時短前と同程度であったり、支給限度額を超えていたりする場合などは、支給対象外となることがあります。また、産前産後・育児・介護休業中や、高年齢雇用継続給付を受けている期間も支給されません。
育児時短就業給付を受けるには、育児休業からの復帰後に時短勤務を開始した場合や、過去2年間に被保険者期間が12か月以上あることなど、一定の要件を満たす必要があります。
支給申請は、原則として事業主が行いますが、被保険者本人が申請することも可能です。育児と就労の柔軟な両立を後押しする重要な制度として注目されています。
育児・介護休業法の改正で事業主に求められる対応

改正育児・介護休業法は2025年4月1日から段階的に施行されるため、事業主は施行日までに必要な対策を講じる必要があります。以下では、事業主が行うべき対応を、2025年4月と2025年10月に分けて説明します。
2025年4月までに必要な対応
2025年4月に施行された内容は多くありました。2025年4月に施行された法改正の内容と、事業主が行うべきだった対応は、以下の通りです。
| 法改正の内容 | 必要な対応 |
| 所定外労働を制限する対象者を小学校就学前に拡大 | ・対象者の確認 ・就業規則の変更 ・所定外労働制限請求書の用意 ・申請フローの見直し |
| 看護休暇の対象を小学校3年生まで・取得事由に入卒園式を追加 | ・対象者の確認 ・就業規則の変更 ・子の看護休暇申出書の用意 |
| 3歳までの子を育てる労働者へのテレワークを努力義務化 | ・対象者の確認 ・就業規則の変更 ・勤怠管理制度や人事評価制度の見直し |
| 育休の取得状況の公表義務を300人超の事業主に拡大 | ・公表する割合の決定・調査 ・公表フローの整備 |
| 行動計画策定時の育休の取得状況の把握・数値目標の設定を義務化 | ・育休取得状況や労働時間状況の把握 ・育休取得状況や労働時間状況の数値目標の設定 |
| 両立支援制度等の個別周知・意向確認を義務化 | ・対象者の確認 ・就業規則の確認 ・個別周知・意向確認書の用意 ・介護休業申出書の用意 ・介護休暇申出書の用意 ・所定外労働制限請求書の用意 ・時間外労働制限請求書の用意 ・深夜業制限請求書の用意 ・介護短時間勤務申出書の用意 ・短時間勤務取扱通知書の用意 |
| 両立支援制度等の情報提供や雇用環境整備を義務化 | ・対象者の確認 ・就業規則の確認 ・両立支援制度等の情報提供 ・両立支援制度等の利用を促す環境整備 |
| 介護休暇で勤続6か月未満の従業員を除外する仕組みを廃止 | ・対象者の確認 ・除外労使協定の締結有無の確認 ・介護休暇申出書の用意 |
| 介護をする従業員のテレワークを努力義務化 | ・対象者の確認 ・就業規則の変更 ・勤怠管理制度や人事評価制度の見直し |
2025年10月までに必要な対応
2025年10月に施行される法改正の内容と、事業主が行うべき対応は、以下の通りです。
| 法改正の内容 | 必要な対応 |
| 柔軟な働き方を実現する措置・個別の周知と意向確認の義務化 | ・対象者の確認 ・実施する措置の選定 ・就業規則の変更 ・育児短時間勤務申出書の用意 ・短時間勤務取扱通知書の用意 ・個別周知・意向確認書の用意 |
| 仕事と育児の両立に関する意向の聴取・配慮の義務化 | ・対象者の確認 ・配慮措置の検討 ・就業規則の変更 ・意向確認書の用意 |
「柔軟な働き方を実現する措置」や「仕事と育児の両立に関する配慮」については、実施内容によっては体制の整備までに時間がかかる場合があるため、会社としてどのような措置・配慮を用意するのか早めに検討しましょう。
まとめ
育児・介護休業法は2024年5月に法改正が行われ、2025年4日1日、2025年10月と段階的に施行されます。育児・介護休業法の改正内容としては「子どもの年齢に応じて柔軟な働き方ができる環境整備」「男性の育休取得状況の把握と公表」「仕事と介護に関する両立支援制度の利用促進」が主なポイントとして挙げられます。
事業主の対応としては、法改正に伴い義務化される内容を理解するのが先決です。そのうえで、就業規則の変更や書類の作成などを行い、施行日を迎えるまでに必要な準備を終わらせるようにしましょう。
関連記事
Related Articles

HSPの”適職”はコレ!「繊細さ」を武器にしたい人に向いている職業
HSP(Highly Sensitive Person)とは、生まれつき感受性が強く刺激に敏感な気質のことです。HS...
HRトレンド
人的資本経営とは?必要な変革・視点と取り組み方を分かり易く解説
人的資本経営は、従業員を「資本」として捉え、その価値を最大化することにより企業価値を中長期的に向上させる経営のアプロ...
HRトレンドエンゲージメント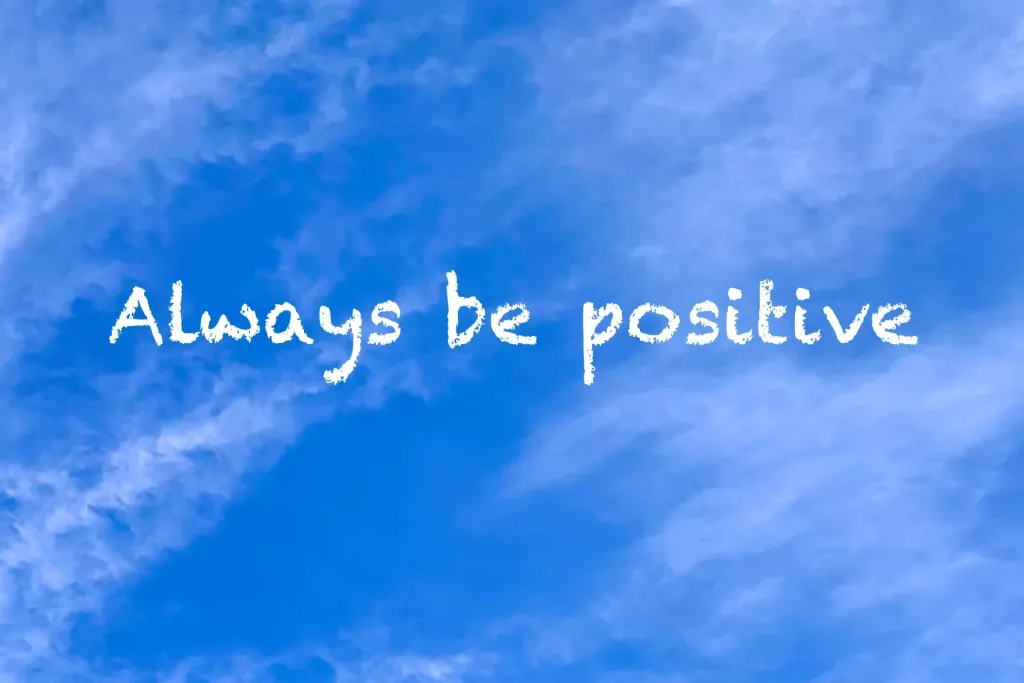
マンガやアニメの名言から学ぶ!仕事や人生に役立つ名セリフを紹介!
マンガやアニメには、ただの娯楽にとどまらず、人生や仕事に役立つ深いメッセージが込められています。キャラクターたちが困...
HRトレンド
心が折れそうな時に寄り添ってくれる【辛い時に救われる言葉10選】
日々の生活の中で、仕事・恋愛・人間関係の悩み、将来の不安などの感情に押しつぶされそうになることはあるでしょう。「もう...
HRトレンド