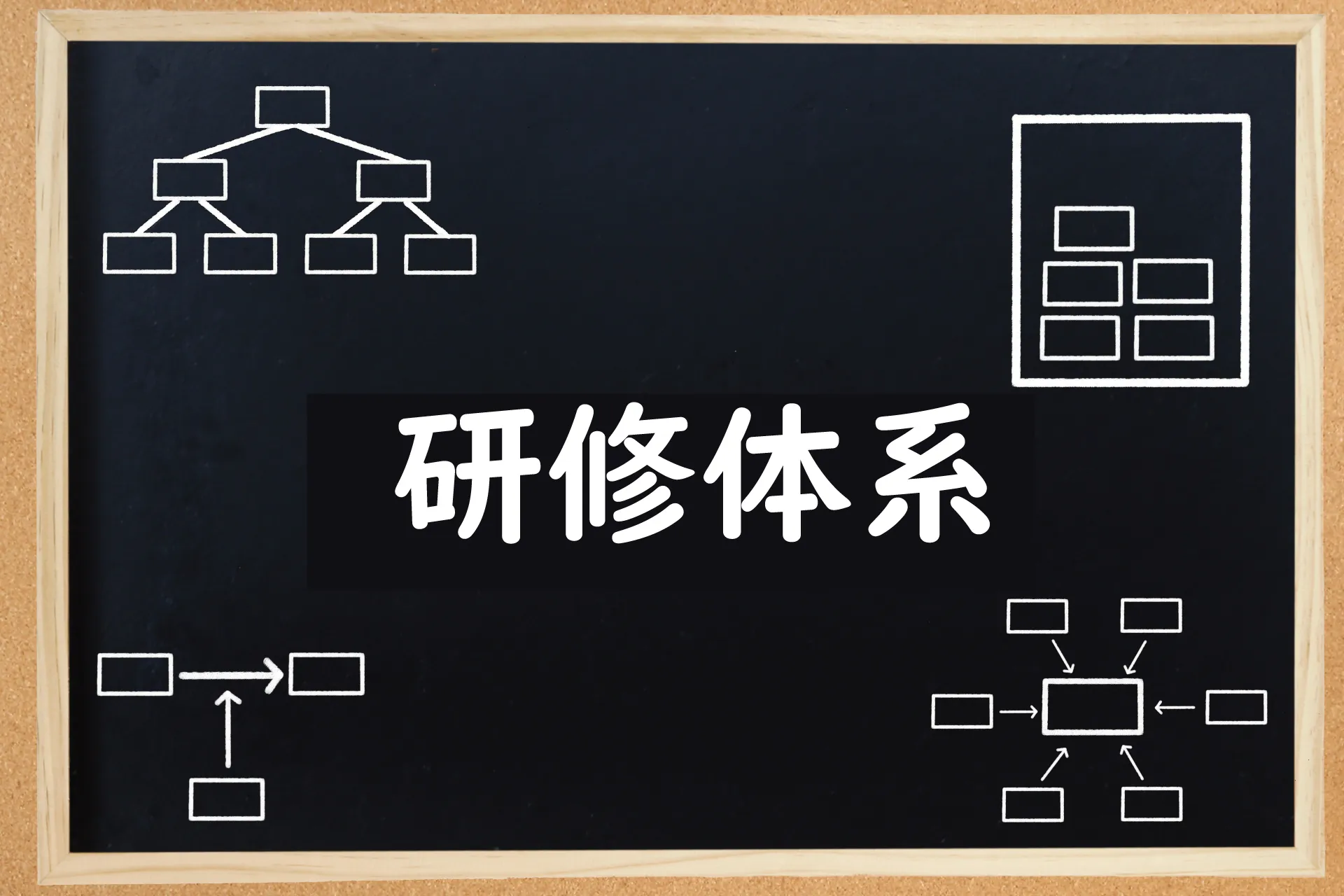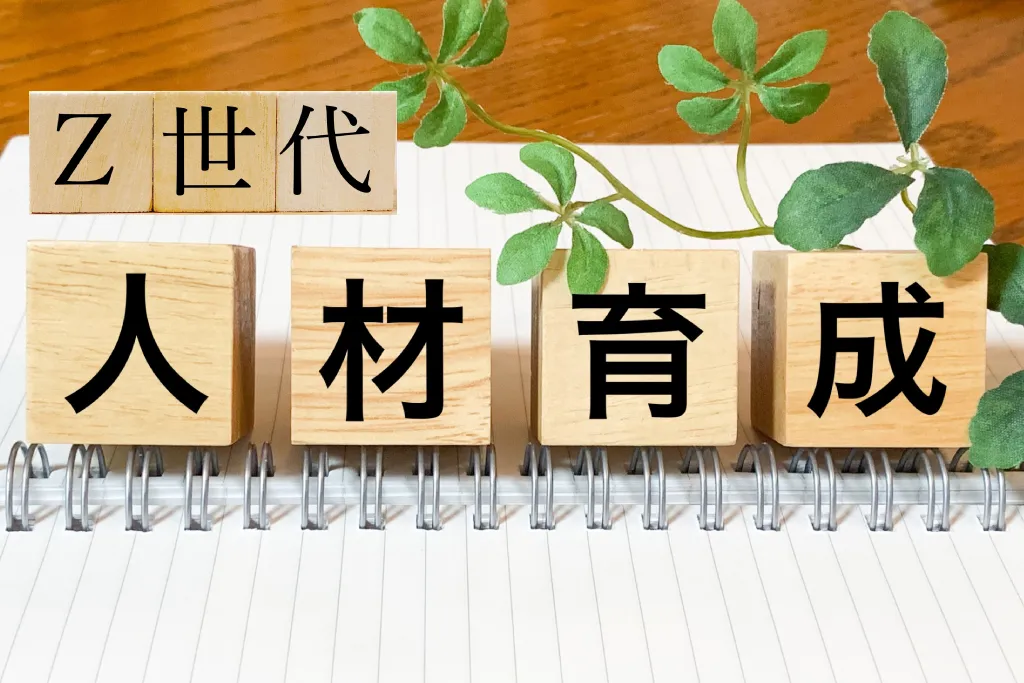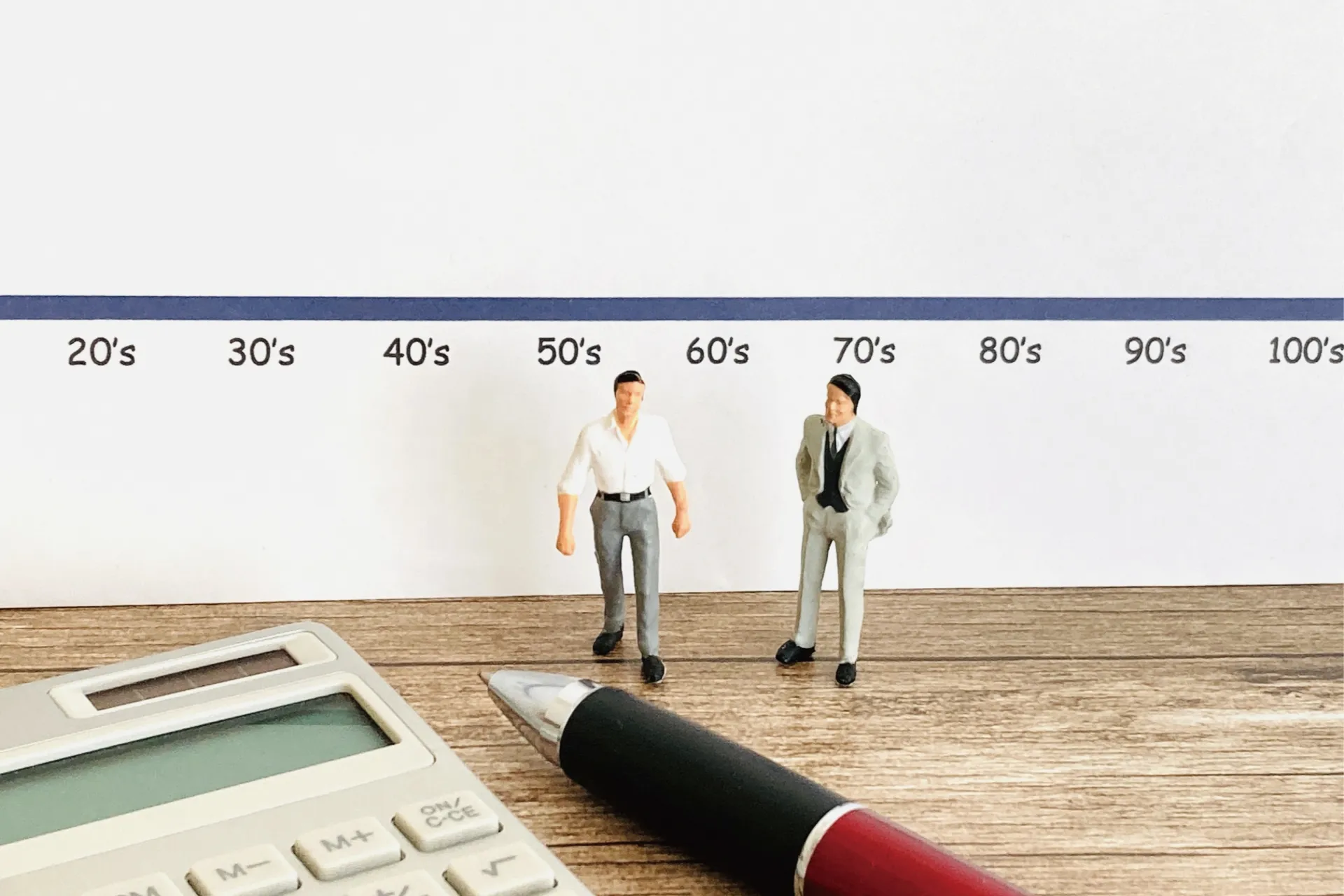- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 【診断問題有】怒りの衝動を鎮める!アンガーマネジメント「6秒ルール」のテクニック
【診断問題有】怒りの衝動を鎮める!アンガーマネジメント「6秒ルール」のテクニック

怒りの感情は誰にでもある自然なものですが、適切に扱わなければ人間関係の悪化や職場環境のトラブルにつながるおそれがあります。現代社会では価値観の多様化や働き方の変化により、ストレスや誤解が怒りの引き金になる場面が増えています。アンガーマネジメントは、怒りの扱い方を学ぶための心理トレーニングです。
当記事では、アンガーマネジメントの基本や実践方法、怒りのタイプ別対処法を丁寧に解説し、今日から実践できるテクニックを紹介します。
目次
Toggle『周囲と良好な関係を築くための アンガーマネジメント研修』について詳しくはこちら
アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手に付き合い、適切に表現・コントロールするための心理トレーニングです。
アンガーマネジメントは1970年代のアメリカで、犯罪者の再犯防止を目的とした矯正プログラムとして始まり、現在では教育や育児、ビジネスの分野にも広く活用されています。怒りを無理に抑えることが目的ではなく、「怒るべき場面では冷静に怒り、怒らなくてよい場面では感情を鎮める」ことを目指す点が特徴です。
怒りに任せた言動は、職場の人間関係や組織全体の雰囲気を悪化させるおそれがあります。そのため、従業員のメンタルヘルス対策や職場の生産性向上の一環として、アンガーマネジメント研修を導入する企業も増加しています。
アンガーマネジメントが重要になった理由
アンガーマネジメントが注目される背景には、働く環境の変化と社会的要請の高まりがあります。
厚生労働省の調査によると、労働者の82.7%が仕事や職業生活において強いストレスを感じており、その主な要因は仕事の失敗や仕事の量に加え、対人関係も含まれます。さらに、テレワークの普及によって対面での意思疎通が減少し、誤解や孤立を招きやすい環境も広がっています。
※出典:厚生労働省「仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項」
また、2022年からは中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務化され、職場での適切なコミュニケーションが強く求められるようになりました。怒りをそのままぶつければ、職場の関係性に悪影響を及ぼす可能性があります。
多様な価値観が共存する現代において、怒りを適切に表現するスキルとしてアンガーマネジメントは不可欠です。
人間の怒りのメカニズム

怒りは単なる衝動的な反応ではなく、心理学的なメカニズムに基づいた感情の1つです。人が怒る背景には、価値観の違いやストレス、身体的・精神的な不調などが複雑に絡み合っています。ここでは、怒りがどのように生まれるのか、そのメカニズムと種類について解説します。
怒りのきっかけとなる価値観のギャップ
怒りが生じる最大の要因は、「価値観のギャップ」です。人はそれぞれ、自分なりの理想や信念、いわゆる「~するべき」というコアビリーフを持っています。たとえば、「上司よりも先に退社してはいけない」「新人は率先して雑務をこなすべき」といった考えがこれにあたります。
こうした価値観が裏切られる場面に出くわしたとき、人は無意識に不快感や違和感を覚え、やがて怒りへと変わります。
大切なのは、自分が信じている価値観が本当にすべての人に共通するものなのかを客観的に見直すことです。他者との違いを認める姿勢を持つ意識によって、怒る必要のない場面に気づく力が養われます。アンガーマネジメントの基本は、自分の怒りのきっかけを知ることにあります。
人間の怒りの種類
怒りにはさまざまな性質があり、心理学では主に「強度」「持続性」「頻度」「攻撃性」の4つに分類されます。自分の怒りの傾向を理解することで、適切な対処法を選ぶための手がかりになります。
| ・強度が高い怒り 一時的に感情が爆発するような状態で、大声を出す・物に当たるといった行動に現れやすい特徴があります。このような怒りは瞬間的に相手や自分自身を傷つける危険性を持ちます。 ・持続性がある怒り 過去の出来事を何度も思い出して怒り続ける傾向を指します。たとえば、以前の評価や人間関係の摩擦が何年経っても怒りとして残る場合です。長期的にメンタルヘルスを蝕む恐れがあるので注意が必要です。 ・頻度が高い怒り 些細なことでもすぐにイライラしてしまい、日常的に怒りを感じてしまうタイプです。この状態が続くと、周囲から「常に怒っている人」という印象を持たれ、信頼関係の構築にも悪影響を及ぼします。 ・攻撃性がある怒り 他人や物、場合によっては自分自身に向かって発散される怒りです。これは最も危険性が高く、パワーハラスメントや自傷行為の原因ともなり得ます。 |
怒りは感情の一部ですが、対処を誤ると重大なトラブルにつながります。まずは自分の怒りの特性を理解することが、適切なマネジメントの第一歩となります。
人間の6つの怒りタイプ

人間の怒りには性格や価値観によって異なる「傾向」があり、怒りの背景には複雑な感情が潜んでいます。下記の「アンガーマネジメント診断」は、いくつかの質問に答えるだけで自分がどのような怒りの特徴を持っているかを把握できるので、ぜひ一度試してみましょう。
・怒りタイプのチェック表
| ・まったくそう思わない:1点 ・そう思わない:2点 ・どちらかと言うとそう思わない:3点 ・どちらかと言うとそう思う:4点 ・そう思う:5点 ・強くそう思う:6点 |
| No. | 設問 |
| Q1 | 世間には尊重すべき規律があり、人はそれに従うべきだ |
| Q2 | ものごとは納得いくまでつきつめたい |
| Q3 | 自分がやっていることは正しいという自信がある |
| Q4 | 人の気持ちを間違って理解していたということがよくある |
| Q5 | 性善説よりも性悪説の方が正しいと思う |
| Q6 | 言いたいことははっきりと主張すべきだ |
| Q7 | たとえ小さな不正でも見逃されるべきではない |
| Q8 | 好き嫌いがはっきりしている方だ |
| Q9 | 周りの人が自分のことを何と言っているのか気になる |
| Q10 | 自分で決めたルールを大事にしている |
| Q11 | 人の言うことをそのまま素直に聞くのが苦手だ |
| Q12 | 後先考えずに行動できるタイプだ |
上記に回答した後、点数を合計し比べることで、怒りタイプを6つに分類できます。
・結果による怒りタイプの分類
| ・Q1+Q7が最大→熱血柴犬(公明正大)タイプ ・Q2+Q8が最大→白黒パンダ(博学多才)タイプ ・Q3+Q9が最大→俺様ライオン(威風堂々)タイプ ・Q4+Q10が最大→頑固ひつじ(外柔内剛)タイプ ・Q5+Q11が最大→慎重うさぎ(用心堅固)タイプ ・Q6+Q12が最大→自由ネコ(天真爛漫)タイプ |
それぞれの動物キャラクターは、怒りの方向性や生じやすい場面を分かりやすく表現しています。ここでは、アンガーマネジメント診断で導かれる6つの怒りのタイプについて詳しく解説します。
熱血柴犬(公明正大)タイプ
熱血柴犬タイプは、正義感が強くルールやモラルを重んじる特徴があり、「こうあるべき」といった信念が強く、それに反する行動を見かけると強く反応してしまいます。たとえば、マナー違反や規律を守らない行動に対しては、たとえ自分に直接関係なくても怒りを感じやすいでしょう。
周囲の秩序を守ろうとする姿勢は評価されますが、自分の価値観を他人に押しつけてしまうとトラブルを招く原因となります。怒る前に「自分が変えられることかどうか」を見極める冷静さが必要です。自分の怒りの範囲を意識し、過剰な介入を避けることがアンガーマネジメントの第一歩となります。
白黒パンダ(博学多才)タイプ
白黒パンダタイプは、完璧主義で何事も白黒はっきりさせたい傾向が強いタイプです。自分にも他人にも厳しく、優柔不断な態度や中途半端な言動に強いストレスを感じやすくなります。仕事や行動において「正解」を求めがちで、グレーゾーンを許容できない面が怒りを生み出す要因となります。
また、自分の基準で他者を評価してしまいがちなので、価値観の違いを受け入れる柔軟性が求められます。「そういう考え方もある」と視点を広げれば、他人への苛立ちを減らせるでしょう。完璧を求める力は強みでもあるため、使いどころを見極めていくことが大切です。
俺様ライオン(威風堂々)タイプ
俺様ライオンタイプは、自信家でリーダーシップを取りたがる親分タイプで、自分の意見や存在が尊重されていないと感じた瞬間に怒りが湧き上がることがあります。また、他人からの評価に敏感なので、思い通りにいかない状況や軽視されたと感じる出来事に強く反応してしまいます。
怒りを抑えるためには、自分の期待や欲求を過剰に相手に投影しすぎていないか、振り返ることが大切です。「尊重されたい」という思いが伝わらない場合もあると理解すれば、感情のコントロールがしやすくなります。
頑固ひつじ(外柔内剛)タイプ
頑固ひつじタイプは、見た目は穏やかで柔和な印象を与えますが、内面には強いこだわりや信念を持っています。一見すると怒りとは無縁のように見えますが、自分の価値観や常識と異なる行動に対して、内心では大きなストレスを感じています。その怒りを抑え続け、ある日突然大爆発してしまうケースも少なくありません。
「普通はこうするべき」といった固定観念が怒りの引き金となることが多いため、自分の常識を他人に押しつけていないかを意識しましょう。また、周囲との違いを許容し、「正しさ」の基準を柔軟に持つことで、心の余裕が生まれやすくなります。
慎重うさぎ(用心堅固)タイプ
慎重うさぎタイプは、何事にも慎重で、物事をじっくりと考えてから行動するタイプです。過去の失敗経験やネガティブな出来事を引きずる傾向があり、「また同じことが起きたらどうしよう」と警戒心を強めてしまいます。このため、不確定な要素や急な変化に対して怒りや不安を抱きやすい傾向があります。
怒りを抑えるには、うまくいったときの経験に目を向けることが効果的です。「例外的に成功したこと」や「人に助けられた経験」を思い出すと、前向きな気持ちで物事に取り組めるようになります。
自由ネコ(天真爛漫)タイプ
自由ネコタイプは、自分の気持ちや考えをストレートに表現できる天真爛漫な性格が特徴です。ルールや制約を嫌い、自由な発想と行動を重視するため、周囲の指示や集団行動に対して強いストレスを感じやすい傾向があります。また、共感力があまり高くない場合があり、自分の意見を押し通そうとしてトラブルの火種になることもあります。
自由ネコタイプの方は、自分の言動が周囲に与える影響に気づき、相手の立場に立って考える力を養うことが大切です。少し立ち止まってから行動する習慣をつけると、自由さを保ちつつ良好な人間関係を築きやすくなります。
アンガーマネジメントを実践するトレーニングのやり方

怒りの感情をコントロールするには、単に我慢するのではなく、段階的に感情を整理し、適切に対処するためのスキルを身につけることが大切です。アンガーマネジメントでは「衝動」「思考」「行動」の3つのステップに分けて感情を整える方法が提唱されています。ここでは、それぞれのステップごとの具体的なトレーニング方法と実践例を紹介します。
衝動のコントロール
怒りを感じた瞬間に反射的な言動をとると、後から大きな後悔につながる可能性があるので、「6秒ルール」を意識するのが大切です。人間は怒りを感じてから理性が働くまでに平均6秒程度かかるといわれているので、反射的な行動を取ってしまわないよう、6秒をやり過ごす方法を身につけましょう。
そのために有効なのが「怒りの温度計」で、「今の怒りは10段階で何点か?」と自問することで、冷静さを取り戻せます。また、深呼吸をする、数字を逆から数えるといった行動も衝動を抑えるきっかけになるでしょう。まずは怒りを感じたら「すぐに動かず、まず止まる」習慣を身につけることが大切です。
思考のコントロール
衝動を抑えた後も、怒りの感情そのものがなくなるわけではありません。感情を整理するステップが「思考のコントロール」です。ここでは、自分の「べき」という思い込みに基づく怒りを、許容の幅で見直す作業を行います。
たとえば「締め切りは絶対に守るべき」という価値観があったとき、提出が数時間遅れた場合を「許せる/まぁ許せる/許せない」の3つで分類します。普段よく怒ってしまうという方は、「まぁ許せる」ゾーンを広げることで、不要な怒りを減らせます。他者の価値観の違いを理解し、柔軟に受け入れる視点を身につける手法です。
行動のコントロール
怒りを感じた出来事がどうしても許容できない場合、最後に必要なのが「行動のコントロール」です。このステップでは、「自分に変えられるか/変えられないか」「重要か/重要ではないか」の2軸で状況を整理します。
たとえば、上司の指導方法に不満を感じた場合、それが自身の業務や成長に大きく影響するのであれば「変えられて重要」な課題です。一方、天候や交通遅延などは「変えられず重要でもない」ため、手放すべき怒りと言えます。
最終的には「自分と周囲にとって長期的に良い行動とは何か?」を基準に行動を選択する力が求められます。
【簡単にできる】怒りの6秒間を乗り切るアンガーマネジメントのテクニック

アンガーマネジメントで大切なのは、怒りのピークといわれる最初の6秒間を乗り切ることです。理性が働き始めるまでのわずかな時間をやり過ごすことで、冷静な判断がしやすくなります。
ここでは、深呼吸以外にも日常で簡単に実践できる4つのテクニックを紹介します。
コーピングマントラ
コーピングマントラとは、怒りを感じたときに自分を落ち着かせる「魔法の言葉」を心の中で繰り返す方法です。たとえば「大丈夫」「たいしたことじゃない」「きっと落ち着ける」といった言葉を、あらかじめ用意しておきます。ペットの名前や好きなフレーズなどでも構いません。
言葉に集中すると、怒りの対象から意識をそらし、感情の高ぶりを抑える効果が期待できます。怒りのピークを迎える前に言葉を唱える習慣を身につけることで、より安定した感情のコントロールが可能です。
カウントバック
カウントバックは、「100から1まで逆に数える」ことで思考を一時的に切り替えるテクニックです。より集中力を要する方法として、「100から7ずつ引いていく」というやり方もあります。
脳は複数のことを同時に処理しにくいという特性を生かした方法で、数えることに意識が向くと、怒りの連鎖的な思考を断ち切りやすくなります。計算に集中することが、冷静さを取り戻す時間稼ぎとなり、衝動的な言動を防ぐ効果が期待できます。
グラウンディング
グラウンディングとは、「今この瞬間」に意識を集中させることで怒りの感情から距離を置く方法です。たとえば、手元のペンやスマートフォンをじっくり観察し、その形状、色、質感、傷の有無まで細かく見つめるといった行動などを指します。
怒りとはまったく関係ない物体に集中することで、思考の流れを切り替え、感情の爆発を避ける時間を確保できます。
タイムアウト
どうしても怒りが収まらないときは、物理的にその場を離れる「タイムアウト」が有効です。会議中であっても「少し席を外します」「一度持ち帰って検討します」といった言葉を添えて場を離れることで、感情をクールダウンさせられます。
冷静さを欠いたままの対応は、関係をこじらせたり、誤解を招いたりする可能性もあるので、無理に続けない選択も大切です。タイムアウトは感情の爆発を防ぐだけでなく、建設的な対話を実現する手段です。
まとめ
アンガーマネジメントは、感情を無理に抑え込むものではなく、「怒るべきときに冷静に怒り、怒る必要のない場面では感情を手放す」ための思考と行動のスキルです。怒りの背景にある価値観や心理状態を理解し、自分の怒りの傾向を把握することで、無用なトラブルを回避できます。
感情との向き合い方は習慣化がカギとなるため、日常の中で小さな実践を積み重ねていくことが大切です。アンガーマネジメントは、家庭・職場・地域など、あらゆる人間関係の中で役立つ技術であり、誰にとっても価値あるスキルと言えるでしょう。
関連記事
Related Articles
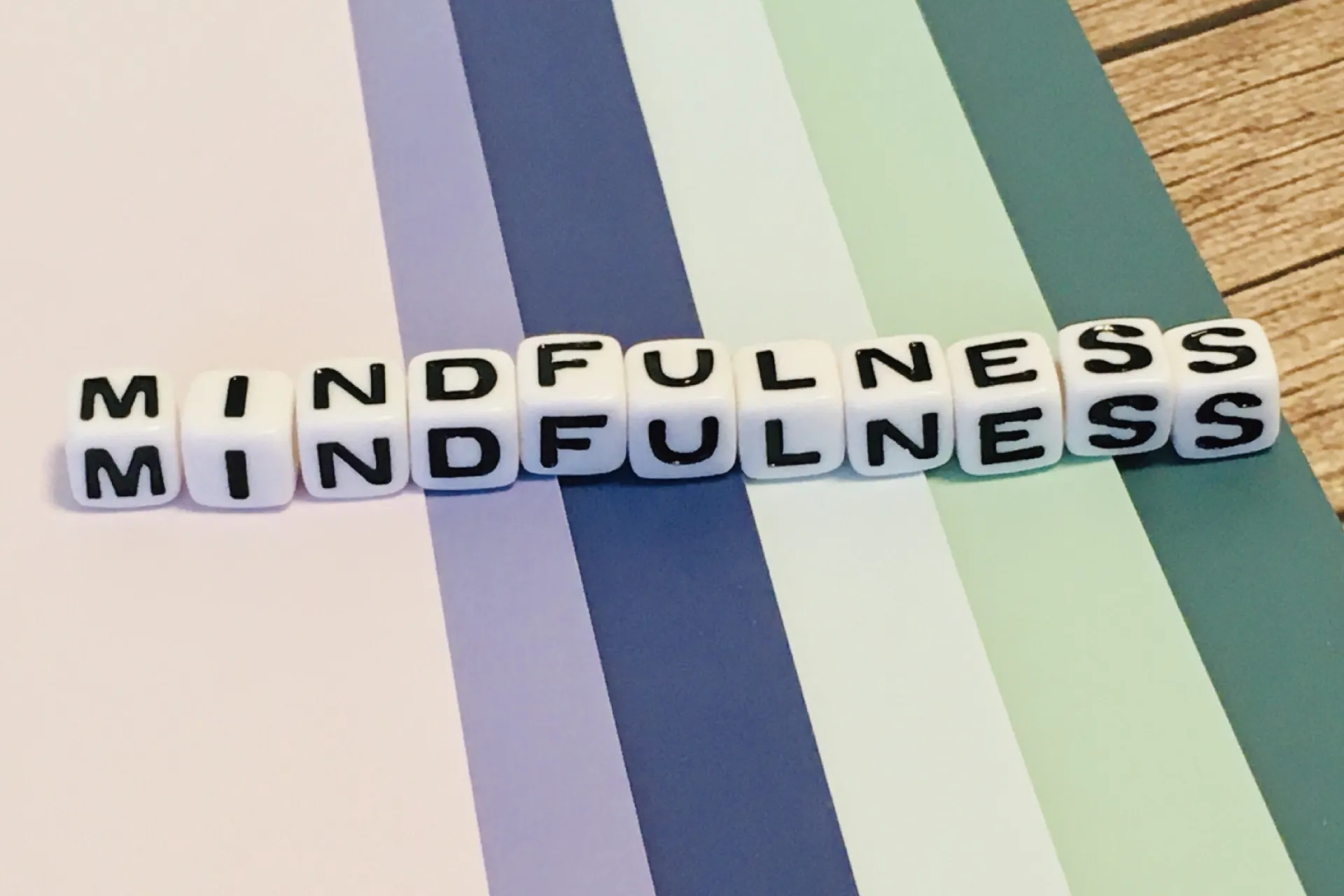
マインドフルネスとは?メリットや注意点、企業の導入事例を紹介
ストレス軽減や集中力の向上につながる手法に「マインドフルネス」があります。マインドフルネスを企業として導入しているケ...
HRトレンド企業研修
失敗しない目標設定のコツは?具体例や目標の立て方・手法を紹介
個々の社員や各チームが設定する目標は、企業の発展にとって重要です。適切な目標を立てれば、自分が今何をすべきかが明確に...
エンゲージメント企業研修