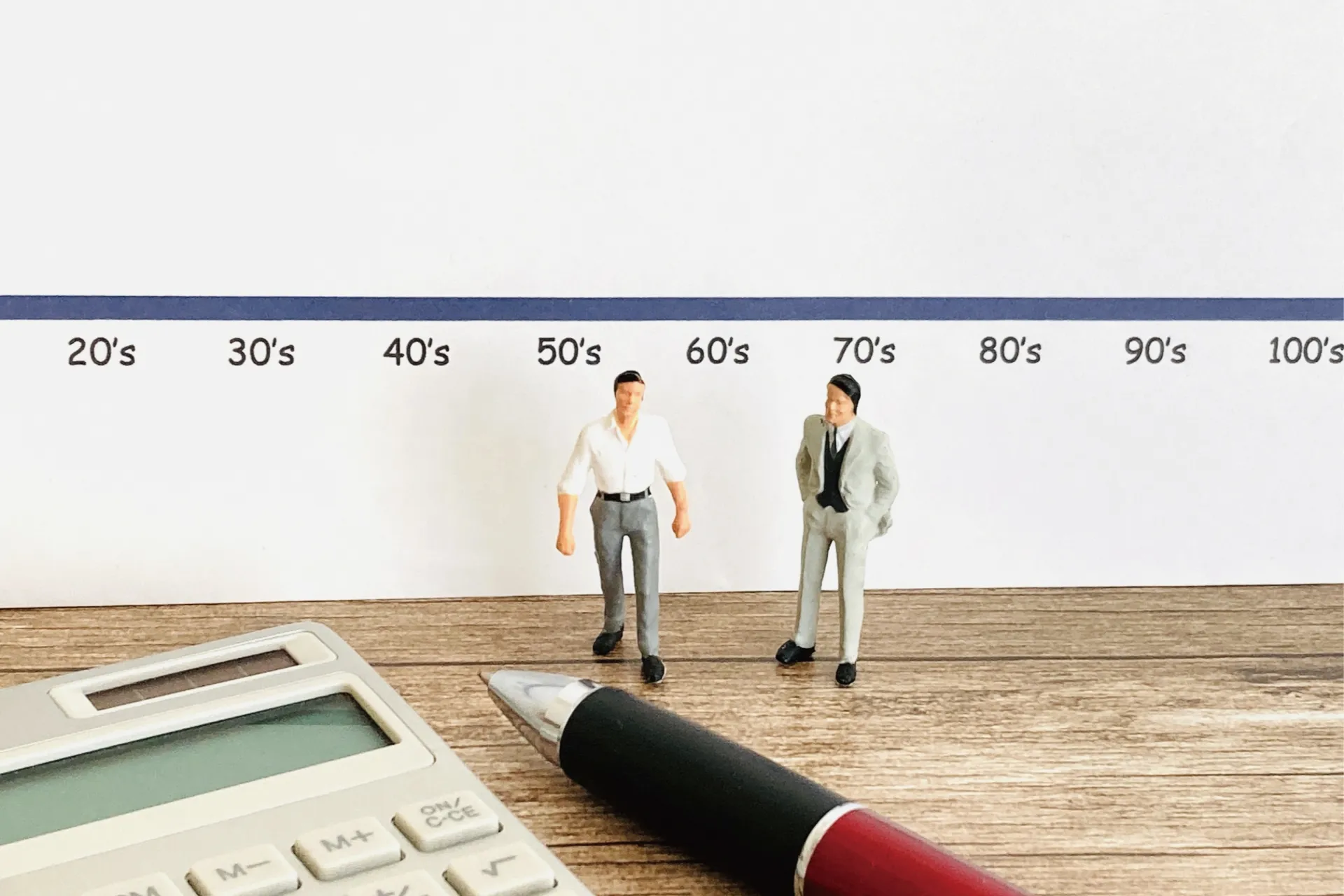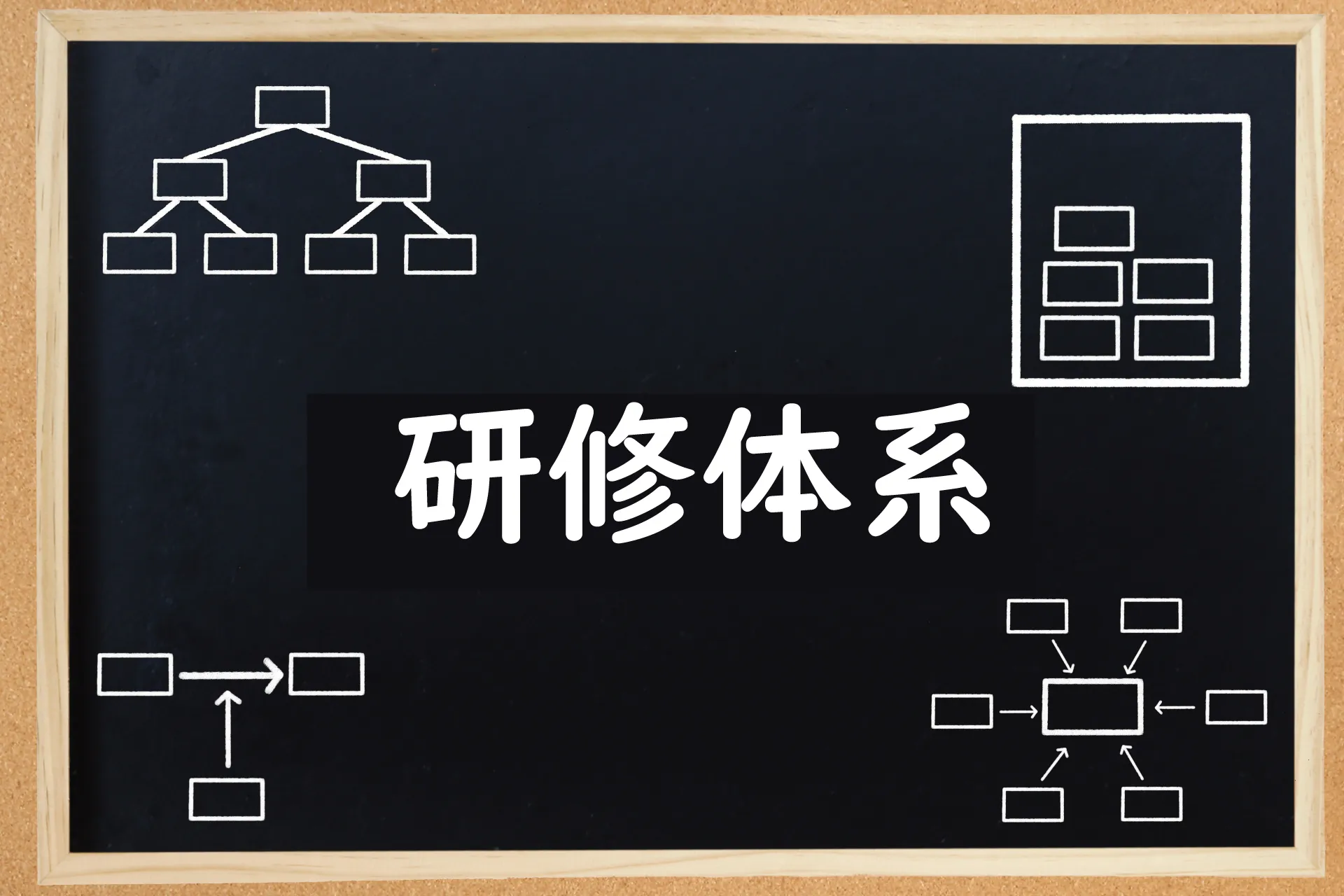- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 心理的安全性を高める研修とは?信頼と対話を生む研修の作り方を解説
心理的安全性を高める研修とは?信頼と対話を生む研修の作り方を解説

現代の職場では、安心して意見を述べられる環境の整備が、成果や創造性に直結すると言われています。そこで注目されているのが「心理的安全性を高める研修」です。「言いたいことが言えない」「上司の顔色が気になる」といった悩みは、誰しもが一度は経験したことがあるでしょう。
心理的安全性の確保は、チームの信頼を育み、生産性やエンゲージメントの向上、イノベーションの促進にも寄与します。当記事では、心理的安全性の基本から、効果的な研修の設計方法、具体的なプログラム内容までを丁寧に解説します。企業経営者の方や、組織づくり・人材育成に取り組んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
Toggle『使える“スキル”としての 心理的安全性研修』について詳しくはこちら
心理的安全性とは

心理的安全性(psychological safety)とは、職場やチームの中で自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して表現できる状態のことを指します。たとえば、上司や同僚に対して意見や質問をした際に、拒絶されたり批判されたりする心配がないと感じられることが心理的安全性の高い状態です。
この概念は、ハーバード大学のエイミー・C・エドモンドソン氏によって1999年に提唱されました。彼女は心理的安全性を「対人関係上でリスクのある言動を取っても安全だとチームで共有されている状態」と定義しています。心理的安全性が確保されている組織では、メンバーが萎縮せずに発言や挑戦ができ、チームの成長やパフォーマンス向上につながります。
心理的安全性を高める研修の目的・メリット

心理的安全性を高める研修(心理的安全性向上研修)には、組織の生産性やチーム力を向上させるためのさまざまな目的があります。ここからは、心理的安全性を高める研修を実施するメリットを紹介します。
生産性を向上する
心理的安全性が高まると、周囲の視線や評価を過度に気にせず、仕事に集中できるようになります。メンバーが自然体でいられることでフロー状態も生まれやすくなり、メンバー同士支え合いながら効率的に業務の遂行が可能です。
フロー状態とは、心理学において夢中になって物事に没頭している精神状態を指し、高い集中力と充実感を伴うものです。メンバーが安心して発言し、仕事に集中できる環境は、挑戦意欲も後押しし、組織として持続的に高いパフォーマンスを発揮できる土台を築けるでしょう。
チーム内で知を共有する
心理的安全性が高い職場では、チーム内での率直な意見交換や情報共有が活発です。メンバーがミスや失敗を恐れずに発言できる環境が整うことで、小さな問題も早期に共有され、改善へのアクションが迅速に取られるようになります。
こうした土台の上に築かれるのが、チーム全体の「学習能力」です。お互いに知識や経験を持ち寄り、よりよいアプローチを模索することで、組織全体として持続的な成長が可能になります。心理的安全性を高めることは、単に安心感を生むだけでなく、知を共有し、学び合う文化を醸成する上でも重要な取り組みです。
イノベーションを促進する
心理的安全性が高くなると、立場に関係なく自由に意見を出し合える雰囲気が醸成されます。その結果、多様な視点や価値観が交わり、斬新なアイデアや新たな商品・サービスの発想が生まれやすくなります。反対に、心理的安全性が低い環境では、「どうせ理解されない」「言っても無駄」といった感情から、アイデアが表に出てこない傾向にあります。
イノベーションを生むには、前向きな提案が歓迎され、誰もが改善意識を持てる安心な環境づくりが欠かせません。心理的安全性の高い状況では、メンバー一人ひとりが積極的に意見を出し合えるため、組織全体の創造力や変化への適応力も高まるでしょう。
エンゲージメントを高める
心理的安全性が高まりとともに、チーム内の信頼関係が深まれば、メンバーは「自分の存在が認められている」と感じる可能性があります。こうした安心感は自己肯定感や自己重要感を育み、自分の能力や特技を生かして仕事に取り組む意欲につながります。
また、不安や悩みを気軽に話せる環境は、ストレスの軽減や孤立の防止、離職率の低下にも役立ちます。仕事へのやりがいや満足感が生まれ、「この職場で働き続けたい」と考える人が増えれば、優秀な人材の定着にも寄与します。
チームの心理的安全性を測定する方法

心理的安全性は抽象的な概念ですが、アンケートによって可視化・定量化することが可能です。ハーバード大学のエイミー・C・エドモンドソン氏は、心理的安全性を測る7つの質問を提唱しています。7つの質問に対して、メンバーに5段階評価で回答してもらうことで、チーム全体の心理的安全性の状態を把握できます。
| 質問内容 |
| (1)チームでミスをしても非難されない |
| (2)問題に自由に意見を言える |
| (3)異なる意見で拒絶されない |
| (4)リスクのあるチャレンジが許容されている |
| (5)助けを求めやすい |
| (6)他人を貶める行動がない |
| (7)自分のスキルが生かされていると感じる |
正確な現状を把握するには、匿名で実施することが望ましく、個人が本音で回答しやすい環境を整えることが重要です。測定結果は、チーム内の信頼関係や課題の見える化に役立ち、今後の改善施策にもつながります。
心理的安全性を高める研修の進め方

心理的安全性を高める研修は、目的設定から効果測定、フォローアップまで段階的に進めることで、よりよい効果が期待できます。以下のようなステップで進めましょう。
今のチームに合わせて目標を設定する
心理的安全性を高める研修では、まず自分たちのチームが現在どの段階にあるのかを見極め、それに応じた目標を設定する必要があります。心理的安全性は「インクルージョン安全性」「学習者安全性」「貢献者安全性」「挑戦者安全性」の4段階で構成されており、段階ごとに求められる支援やアプローチが違います。
| インクルージョン安全性 | 「自分がチームの一員として受け入れられている」と感じられる状態で、発言以前に存在そのものが尊重されます。 |
| 学習者安全性 | 「知らないことを認めていい」「質問や失敗をしても大丈夫」と思える安心感が育まれます。 |
| 貢献者安全性 | 「自分の意見やスキルを生かしてチームに貢献できる」と信じられる状態です。 |
| 挑戦者安全性 | 「現状に疑問を投げかけ、新しいアイデアで変革を試みることが歓迎される」と感じられる環境が整います。 |
たとえば、まだ発言すらためらう段階のチームに対して、挑戦的な意見交換を求めても逆効果です。反対に、貢献や挑戦の意欲が高まっているチームでは、既存の仕組みを見直し、さらなる改善提案を促すことが研修の狙いになります。こうした段階を踏まえて目標を設定する点は、他のビジネススキル研修とは異なる、心理的安全性研修ならではのアプローチです。
研修のターゲット層を選ぶ
心理的安全性を高める研修では、目的に応じて適切な対象層・対象者を選定することが成果に直結します。経営層・管理職層を中心に実施する場合は、リーダーシップや現場での実践を促進しやすく、トップダウンでの展開が可能です。一方、現場社員を含むチームビルディング型の研修は、現場レベルでの信頼関係や対話の土壌を直接育む効果があります。
ただし、研修の参加者がどちらか一方に偏ると、「やらされ感」や「推進力の欠如」が生まれやすいため注意が必要です。一般的な研修と異なり、心理的安全性研修は、組織のあらゆる層を巻き込むことが成功のカギとなります。管理職・従業員・関係部署など、組織の縮図となるようなメンバー構成とし、「ホールシステムアプローチ」を取り入れ、全社的な変革を促す体制が理想です。
研修の手法を決める
心理的安全性を高める研修の効果を最大限に引き出すためには、「知識のインプット」と「体験によるアウトプット」をバランスよく組み合わせることが不可欠です。一般的なビジネス研修では、座学中心やスキルトレーニングに特化することが多い傾向にあります。しかし、心理的安全性の研修では「職場に安心感を作る」という抽象的かつ感覚的なテーマを扱うため、概念の正しい理解と体験的な納得感が求められます。
| インプット | 講義やeラーニングを活用し、「心理的安全性とは何か」「ぬるま湯組織との違いは何か」といった基本知識を明確に伝えます。また、具体例を用いた説明や、質疑応答の時間を設けることで理解を深められます。講義前にeラーニングで予習する「反転学習」も有効な手法です。 |
| アウトプット | ロールプレイングやビジネスゲーム、ワールド・カフェ形式の対話など、実践型・対話型のワークを行います。たとえば上司役と部下役、オブザーバー役に分かれたロールプレイでは、異なる立場からの視点や感情を体験することで、対人関係のリスクを取る難しさと、その支援方法を実感として学べます。ワールド・カフェなどの対話型手法では、日頃感じている不安や課題を言語化し、他者と共有することでチーム内の共通理解が深まります。 |
心理的安全性は知識だけで変わるものではなく、職場での態度や行動の変容につながって初めて意味を持つため、受講者の「気づき→実践」までを見据えた企画が必要です。講義と体験をバランスよく組み合わせることで、研修後の実効性を高められるでしょう。
研修の形式を決める
研修の形式を選ぶ際は、扱うテーマとの相性を考慮しましょう。心理的安全性は「人間関係」や「相手の感情の受け取り方」に深く関わるため、可能であれば対面形式での実施が効果的です。対面形式なら、表情や声のトーン、雰囲気などの非言語コミュニケーションを通じた気づきが得られやすく、受講者同士の信頼関係も築きやすくなります。
全日程の対面実施が難しい場合は、初回と最終回のみ対面にするハイブリッド形式や、同一チームが同じ会議室から参加するオンライン形式にするといった工夫も有効です。また、知識をeラーニングで事前学習し、対面でワークや対話を中心に進めるブレンディッドラーニングもおすすめです。心理的安全性を高める研修では、通常の研修以上に、相互理解と信頼構築を重視した形式選びが求められます。
研修のスケジュールを決める
心理的安全性は一度の研修で即座に変化が生まれるものではなく、組織風土に根差した継続的な取り組みが必要です。そのため、研修スケジュールは短期集中型ではなく、3か月~1年程度の中長期的なプランで設計することが推奨されます。
初期段階は、半日~1日程度の導入研修を実施し、心理的安全性の基本概念や重要性について学びます。その後、実践応用研修やフォローアップ研修を数回に分けて実施し、実際の職場での行動変容を支援します。たとえば、月1回ペースで振り返りや課題の共有を行うと、定着と改善を促す仕組みを構築できます。これにより、受講者の行動変容が定着し、持続的な組織の成長につながります。
他のスキル研修と異なり、心理的安全性を高める研修では「時間をかけて意識と関係性を変えていく」プロセスが重視されるため、スケジュールの柔軟性と持続性がポイントです。研修準備に1~2か月は必要となることから、講師や受講者の予定、予算、カリキュラム全体を考慮した上で、段階的なスケジュール設計を行いましょう。
研修の効果を測定する
心理的安全性を高める研修は、成果が数値化しづらいテーマですが、適切な手法を用いれば効果を可視化できます。その代表的な方法が、エイミー・C・エドモンドソン氏が提唱した心理的安全性を測る7つの質問です。研修の前後で7つの質問に基づいたアンケートを実施し、心理的安全性の変化を定量的に捉えるとよいでしょう。
さらに、1on1やグループインタビューを通じた定性的な評価も併用すると、数値では表れない現場の空気感や行動変容の兆しを掴むことができます。研修参加者の直属の部下やチームメンバーに対するヒアリングも効果的です。
そのほかに、研修の効果を多面的に測る方法として「カークパトリックモデル」の活用も有効です。これはレベル1(受講者の反応)、レベル2(学習成果)、レベル3(行動変容)、レベル4(業務成果)という4段階で研修効果を評価するフレームワークです。
他の研修と異なり、心理的安全性を高める研修は短期的な成果に偏らず、継続的な変化を丁寧に追う姿勢が求められます。効果測定の仕組みを初期段階から組み込み、学びを組織の改善に結びつけることが、研修を真に価値のあるものへと導くでしょう。
研修後のフォローアップを行う
心理的安全性の向上には、一度の研修で終わらせず、継続的なフォローアップが不可欠です。一般的なスキル研修と異なり、心理的安全性は「意識」と「関係性」を扱うため、すぐに効果が現れるものではなく、時間をかけて育む必要があります。
たとえば、研修をシリーズ化して数回に分けて実施する方法や、事後課題を設定して復習や実践を促す方法が有効です。また、定期的なアンケート調査や1on1ミーティングを通じて、現場での心理的安全性の変化を把握・測定できる仕組みを整えることも重要です。
特に1on1では、上司が日常的に部下の不安や意見を引き出す機会を持つことで、研修の学びを現場に浸透させる役割を担えます。多面的なフォロー体制の構築により、研修の効果を持続させ、組織全体の心理的安全性の底上げにつなげられるでしょう。
心理的安全性を高める研修の内容例

心理的安全性を高める研修には、コミュニケーション力や信頼関係を育むための多様なプログラムがあります。ここからは、代表的な研修内容やセミナーの例を紹介します。
心理的安全性研修
心理的安全性研修は、単なる理論理解にとどまらず、現場で活用できるスキルとしての実践力を養うことを目的としたプログラムです。アイ・イーシーの集合研修では、リーダー層や管理職を対象に、対人不安の理解やチームづくりの具体的手法を体系的に学びます。
この研修の特徴は、学術的背景に基づいた正しい理解を深めた上で、ペアワークや個人ワークを通じて「使える行動」に落とし込める構成にあります。表面的な知識習得ではなく、内面と行動の変化を促す工夫が随所に施されており、研修後の実践定着に強くつながる点が、他の研修との大きな違いです。
アサーティブ・コミュニケーション研修
アサーティブ・コミュニケーション研修は、他者と自分の双方を尊重しながら意見を伝えるスキルを習得するプログラムです。アイ・イーシーが提供する本研修では、多様化が進む職場環境で求められる対話力の向上を目指し、アンコンシャスバイアスへの気づきから実践的なアサーション技法までを学びます。
本研修の核となるのは、DESC法(描写・説明・提案・選択)を軸とした対話トレーニングです。リーダー層や中堅社員が感情を抑え込まず、かつ相手に配慮しながら自分の意見を伝えるスキルを磨きます。加えて、アンコンシャスバイアスに気づき、多様な価値観を受容する姿勢を養える構成となっています。
エンゲージメント研修
エンゲージメント研修は、リーダーが部下との信頼関係を築き、組織への愛着やモチベーションを高める手法を学ぶプログラムです。アイ・イーシーの本研修では、心理的安全性や信頼関係を土台に、人材の定着・育成・行動変容につなげる具体的なアプローチを体得します。
本研修では、「信頼残高」や「ストローク理論」などの心理学的な概念を活用して、部下との信頼形成や対話力を高めることを重視しています。目標・評価面談の技術や在宅勤務における注意点など、現場の課題に直結する内容を多く含んでいるのも特徴です。
まとめ
心理的安全性を高める研修は、単なる知識の提供ではなく、職場での信頼性や対話を深める継続的な取り組みです。研修は目的に応じてターゲット層や手法、形式を選び、導入からフォローアップまで段階的に設計することが求められます。
また、効果測定や実践定着を意識することで、学びが行動変容につながり、組織の成長へと結びつきます。心理的安全性は、すべてのビジネスの土台となる重要なテーマです。適切な研修によって安心して意見を交わせる職場づくりを進めましょう。
関連記事
Related Articles

オンボーディングとは?導入目的と方法、成功のポイントを解説
オンボーディングとは、入社した新入社員や中途社員がいち早く仕事に慣れて仕事ができるようにサポートを行うことです。オン...
HRトレンド企業研修