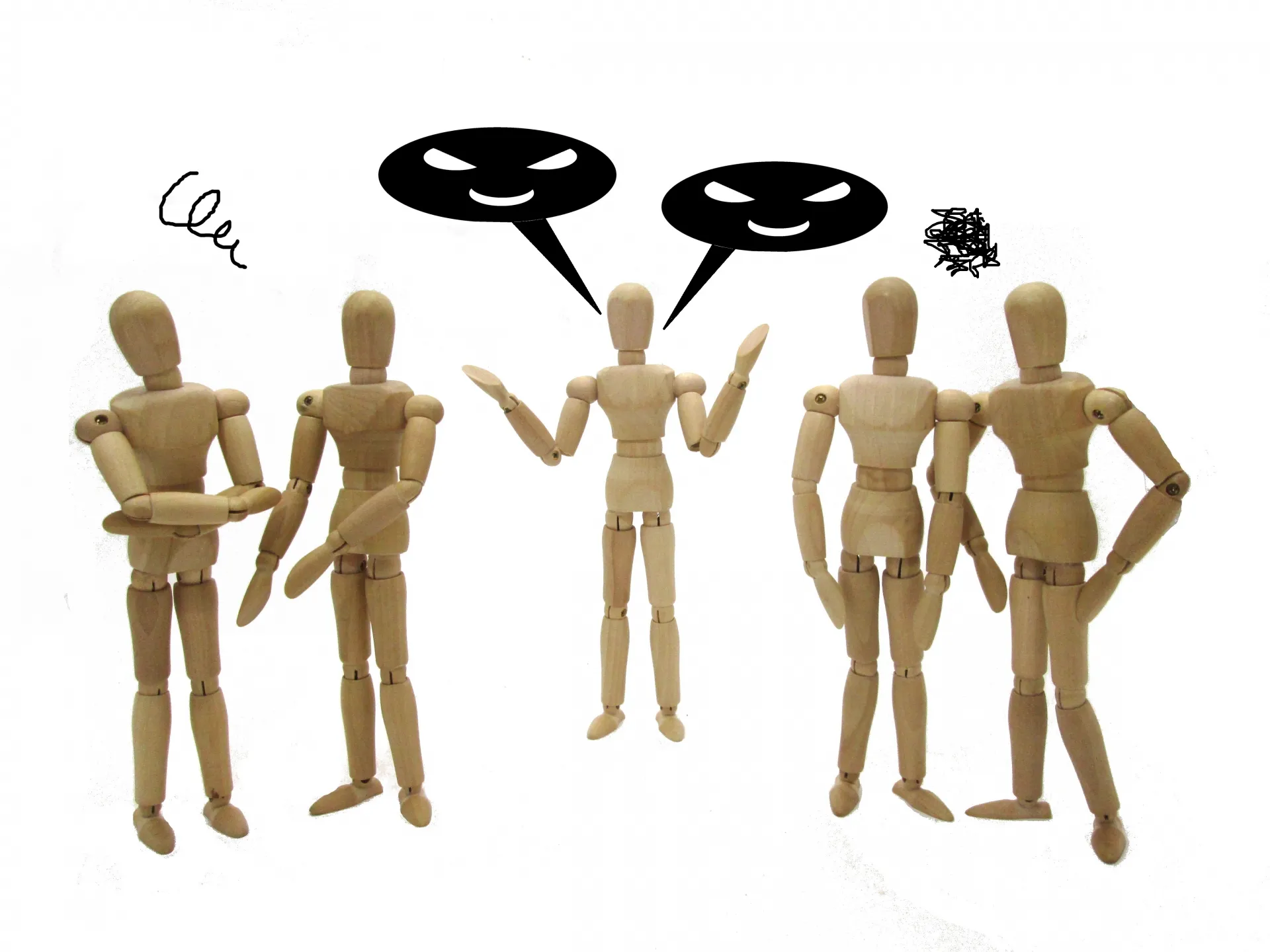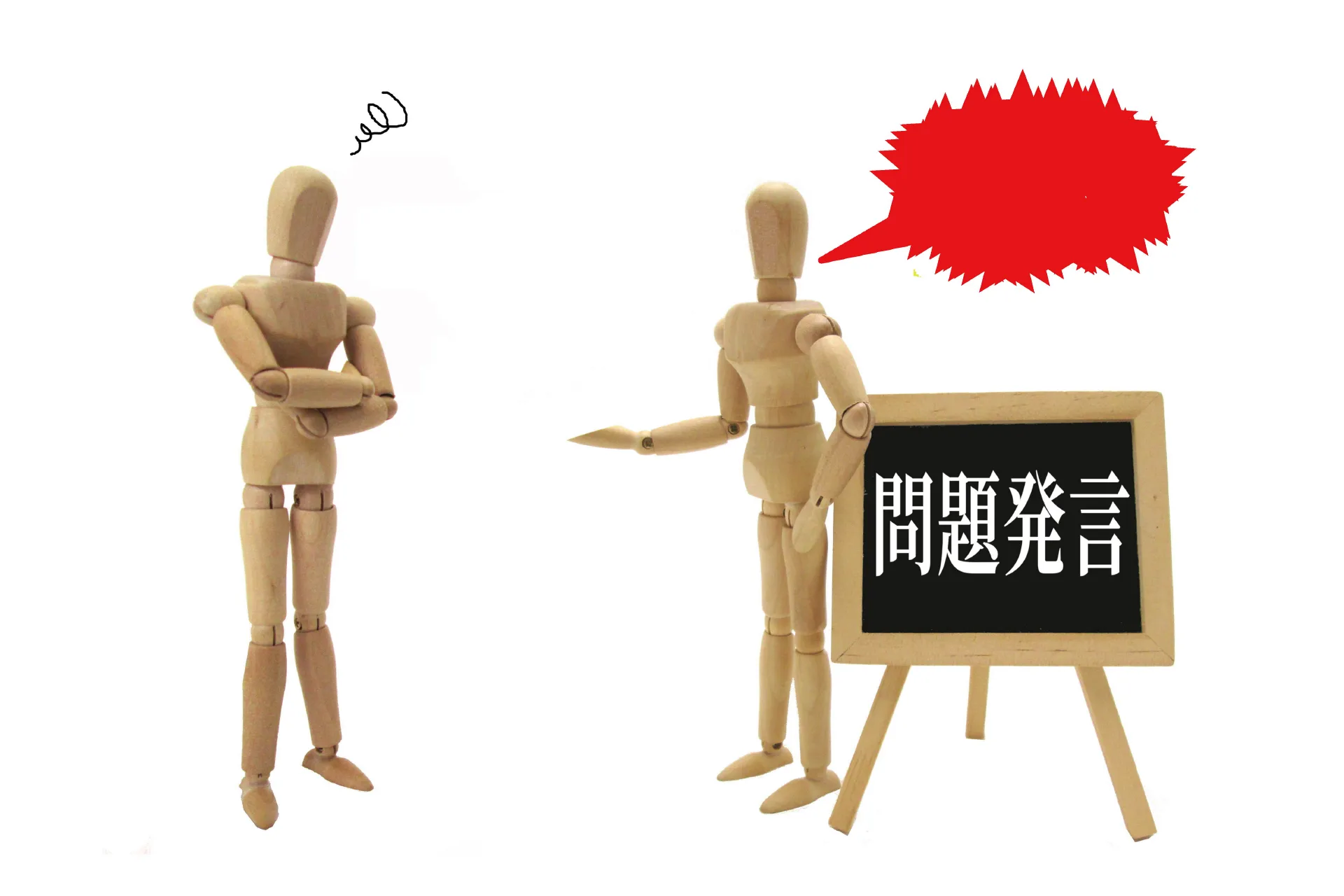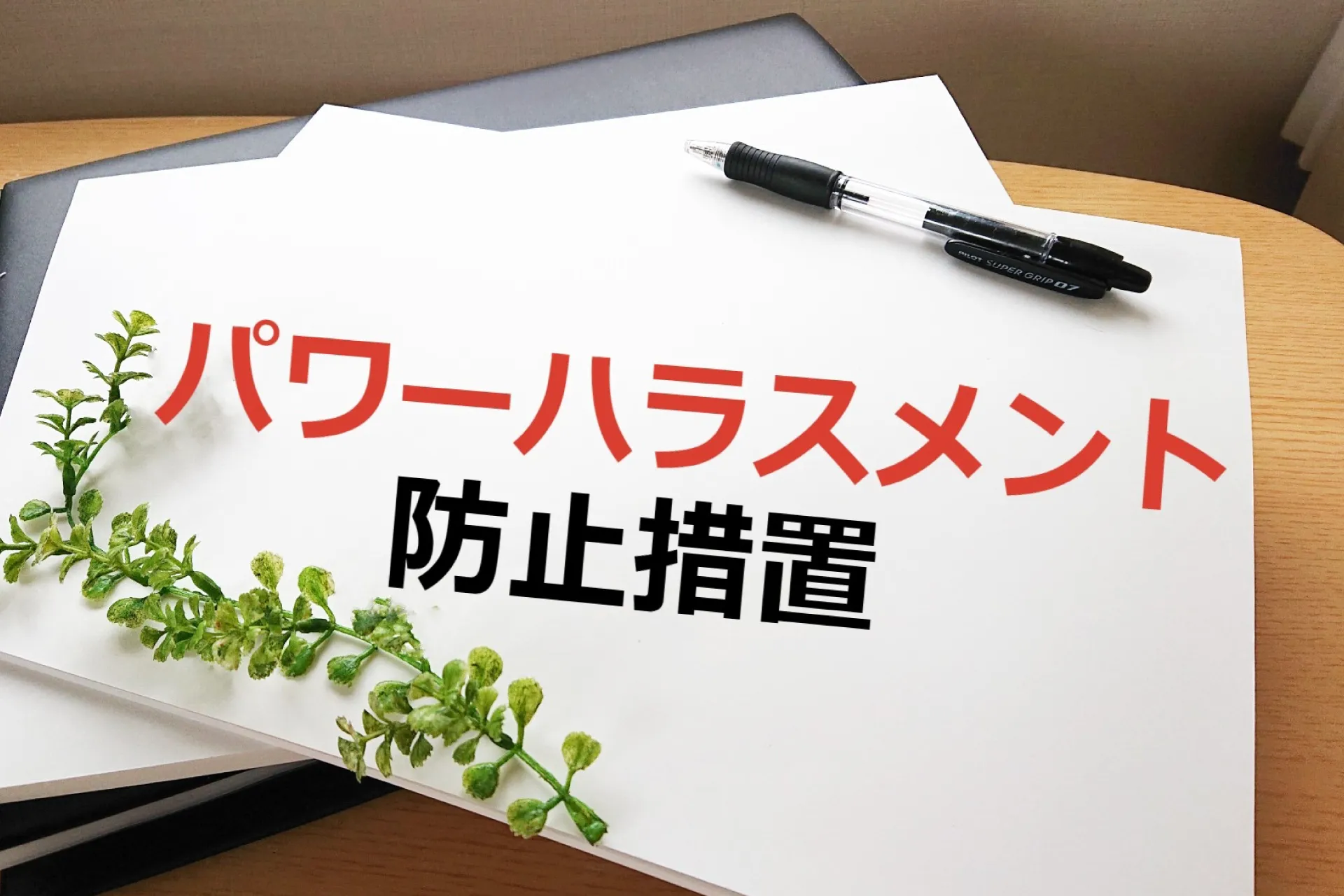- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- ハラスメント
- あなたの指導は大丈夫?パワハラにならないための5つのチェックポイントと解決策
あなたの指導は大丈夫?パワハラにならないための5つのチェックポイントと解決策
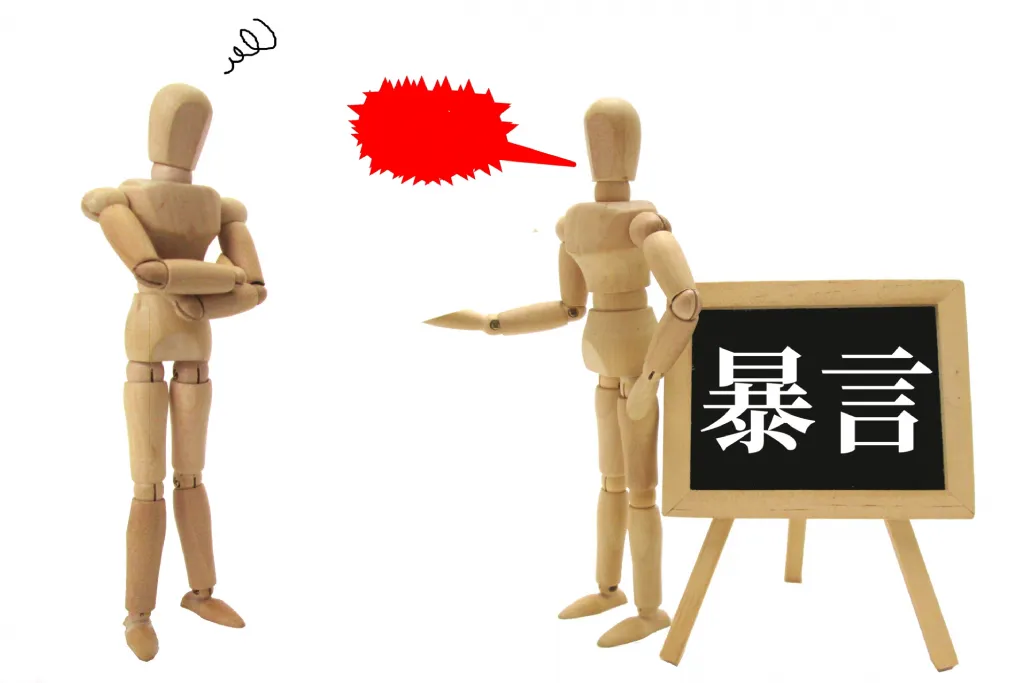
「部下にどう注意すればいいのか分からない」「指導したつもりがパワハラと言われたらどうしよう」と不安を抱える管理職は少なくありません。注意や指導とパワハラの線引きは非常に曖昧で、何が適切で何が行きすぎなのかを判断するのは簡単ではありません。
当記事では、パワハラと指導の違いや実際の判例に基づく判断基準、パワハラを避けながら効果的に指導するポイントを解説します。パワハラの加害者と被害者が生まれるのを防ぎ、適切な指導で部下の成長につなげましょう。
目次
Toggleパワハラと指導の違いとは

職場で部下を注意・指導する場面において、「これはパワハラかもしれない」と不安を抱く管理職は少なくありませんが、適切な指導とパワハラの間には明確な違いが存在します。指導は相手の成長を目的とし、業務上の必要性に基づいて、冷静かつ受容的な態度で行われます。一方、威圧的な態度による相手の人格否定や、業務に無関係かつ私的な攻撃などはパワハラです。
| パワハラ | 指導 | |
| 目的 | ・相手を馬鹿にする、排除する ・自分の目的の達成(自分の思い通りにしたい) | ・相手の成長を促す |
| 業務上の必要性 | ・業務上の必要性がない(個人生活、人格を否定する) ・業務上の必要性があっても不適切な内容や量である | ・仕事上必要性がある ・健全な職場環境を維持するために必要である |
| 態度 | 威圧的、攻撃的、否定的、批判的 | 肯定的、受容的、見守る、自然体 |
| タイミング | ・過去のことを繰り返す ・相手の状況や立場を考えない | ・タイムリーにその場で ・受入れ準備ができているときに |
| 誰の利益か | ・組織や自分の利益を優先する(自分の気持ちや都合が中心) | ・組織にも相手にも利益が得られる |
| 自分の感情 | いらいら、怒り、嘲笑、冷徹、不安、嫌悪感 | 好意、穏やか、きりっとした |
| 結果 | ・部下が萎縮する ・職場がぎすぎすする ・退職者が多くなる | ・部下が責任を持って発言、行動する・職場に活気がある |
とはいえ、パワハラを恐れて注意すべき点を伝えられない状況が続くと、信頼関係の構築や個人の成長を妨げる結果になりかねません。管理職が自信を持って人材育成に取り組むには、指導とパワハラの違いを正しく理解することが必要です。
パワハラとは
職場のパワーハラスメントとは、「優越的な関係を背景とした言動」であり、「業務上必要かつ相当な範囲を超え」「労働者の就業環境が害される」ものです。この3要素すべてを満たす場合にパワーハラスメントと判断されます。たとえば、上司からの暴言や暴力、同僚による無視や隔離、過度な要求や不当な軽視、私生活への過干渉などが代表例です。これらは労働者に精神的・身体的苦痛を与え、職場の環境を悪化させる恐れがあります。
なお、「職場」には、オフィスに限らず出張先や業務中の車内、接待の場なども含まれます。「労働者」は正規・非正規を問わず、パートや派遣社員なども保護の対象です。一方で、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適切な業務指示や指導は、パワーハラスメントには該当しません。
指導とは
指導とは「ある目的・方向に向かって教え導くこと」であり、人材育成においては目の前の課題を解決に導くために必要な考え方や行動の仕方を授ける手法です。上司が部下を指導することにより、部下は知識やスキルを身につけ、徐々にできる業務が増えます。しかし、場当たり的な指示に終始したり、誤った方法で教育したりすると、部下の意欲を奪い、人間関係が損なわれる恐れもあります。
技術や知識の伝達にとどまらず、業務指示の明確化や望ましくない行動の是正も指導に含まれ、これらは職場における成長支援の重要なプロセスです。単なる命令や注意ではなく、相手が自ら成長できるよう、必要な知識やスキルを伝える行為が「指導」に当たります。指導の効果を高めるには、部下が安心して学べる環境を整える必要があります。
注意や指導とパワハラを見分ける判断基準

注意や指導とパワハラの違いは一見分かりにくいものですが、「業務上必要かつ相当な範囲」を超えているかどうかが判断基準の1つとなります。ここでは、注意・指導とパワハラを見分ける判断材料を紹介します。
指導の目的が相手の成長を促すものか
正当な指導であれば、部下の問題点を具体的に指摘し、改善点や再発防止のアクションを示すことで、相手の成長を促そうとする意図があります。たとえば、業務上のミスを指摘し、今後どう改善すべきか一緒に考える行為は正当な指導です。しかし、「相手を不快にさせたい」「ストレスを発散したい」「辞めさせたい」などの不適切な動機がある場合、指導ではなくパワハラに該当する可能性が高くなります。
仮に指導の形式を取っていたとしても、動機が私的な感情や嫌がらせに基づくものであれば、その行為はパワハラとみなされるでしょう。指導の本来の目的は、あくまでも相手の成長や職場全体の改善であることを忘れてはなりません。
業務上必要がある状況や範囲での注意や指導か
業務の遂行や安全確保のために必要な指導は、法律上も正当な行為とみなされます。たとえば、運転中の飲酒や処方箋の取り違えといった人命に関わる重大なミス、問題社員の度重なる遅刻や不法行為などには、厳しい叱責が許容される可能性が高いです。
一方で、初めてのミスや些細な失敗に対して強く叱責する行為、客観的に見てその場で不要なのに感情的に怒鳴るような言動は、業務上必要な範囲を超え、パワハラと判断される恐れがあります。指導の妥当性は、言動の目的や状況、業種や業務の性質を踏まえて総合的に判断することが求められます。
注意や指導の内容が妥当な範囲か
指導目的が部下の成長でも、その方法が常識を逸脱していれば、パワハラに該当する可能性があります。たとえば、「相手を殴る」「物を投げる」「長時間にわたり人前で叱責する」「反省文を書かせ続ける」などの行為は明らかに指導の範囲を超えており、パワハラと判断されやすくなります。性別や年齢などミスと無関係な点を攻撃したり、人格を否定するような言葉を発したりするのも同様です。
反対に、短時間で冷静に問題点を伝え、改善を促すものであれば、適切な指導と評価されやすいでしょう。世間一般の常識や価値観と照らし合わせ、行為の内容が社会通念上妥当かどうかを常に意識することが大切です。
従業員の心身の状態を考慮しているか
健康な従業員には適切とされる言動でも、心身に不調を抱えている相手に対して同様の対応をすれば、パワハラとみなされる可能性があります。たとえば、うつ病の治療中や休職明けの従業員に厳しい叱責を行えば、その影響は重大であり、指導の範囲を超えた精神的苦痛を与える結果となるかもしれません。
また、新入社員や派遣社員など、立場の弱い人への過度な言動もパワハラと判断されやすくなります。企業には従業員の健康を守る「安全配慮義務」があり、精神的なダメージを与えるような言動は指導として正当化されません。
結果として職場がよりよい環境になっているか
注意や指導の正当性を判断する上では、その「結果」にも目を向ける必要があります。適切な指導であれば、注意を受けた従業員が業務改善に前向きに取り組み、より責任を持って行動するなど、職場全体の雰囲気や生産性が向上する効果が期待できます。
一方で、注意を受けた相手が萎縮し、発言や行動を控えるようになったり、退職・休職に追い込まれたりする場合は、職場の心理的安全性が損なわれ、指導ではなくパワハラとみなされる可能性が高まります。指導の目的はあくまで改善と成長の支援であるべきで、その結果として職場にプラスの変化が生まれているかどうかが、対応の適切性を判断する重要な視点となります。
パワハラと指導の境界線が分かる判例

パワハラと指導の違いを正しく理解するにあたって、実際の裁判例は大いに参考になります。ここでは、パワハラと判断された事例・指導と認められた事例をそれぞれ紹介します。
【パワハラとみなされた事例】亀戸労基署長事件
亀戸労基署長事件では、部下への執拗で長時間にわたる叱責が問題となり、最終的にパワハラによる労災と認定されました。従業員Aは長時間の残業に加え、上司から月に2回以上、2時間を超える立ったままの叱責を受けており、肉体的・精神的負担が蓄積します。その結果、持病が悪化し、出血性脳梗塞を発症しました。
一審では「通常の指導の範囲内」と判断されましたが、二審では叱責の頻度・態様が過剰であると認定され、業務起因性が認められました。この判例は、指導の名の下でも執拗で過度な行為はパワハラとされ、企業や上司に重大な責任が問われ得ることを示しています。
※出典:あかるい職場応援団(厚生労働省)「【第62回】 「時間外労働時間だけでなく、上司による叱責も考慮して、業務起因性が認められた事案」 ―亀戸労基署長事件」
【パワハラとみなされた事例】A保険会社上司(損害賠償)事件
A保険会社上司(損害賠償)事件では、上司が部下に送信したメールの内容が問題となり、不法行為として損害賠償が認められました。部下に対する「やる気がないなら会社を辞めるべき」などの退職勧告とも受け取れる文言や、「これ以上当センターに迷惑をかけないで」などの侮辱的な表現が、十数名の同僚にも共有された点が特に問題視されました。
裁判では、一審で指導の目的自体は是認されつつも、二審でメールの表現内容や送信範囲が相当性を欠いており、名誉感情を著しく害するものと判断されます。結果として、上司には5万円の損害賠償が命じられました。この判例は、業務指導の意図があっても、言葉の選び方や伝え方を誤ればパワハラ被害と認定されること、メールの文面や送信先にも配慮が欠かせないことを示しています。
※出典:あかるい職場応援団(厚生労働省)「【第56回】 「上司が送ったメールの内容が侮辱的言辞として、損害賠償請求が認められた事案」 ―A保険会社上司(損害賠償)事件」
【指導とみなされた事例】広島県教員パワハラ事件
広島県教員パワハラ事件では、教諭が校長や教頭から嫌がらせや暴行を受けたと訴え、精神疾患の悪化を理由に損害賠償を求めましたが、裁判所はその主張を退け、指導の範囲内と認定しました。
校長による呼び出しは、教諭が提出を指示された書類を出さなかったことや、休暇簿を様式と異なる形式で記載したこと、卒業式での国歌斉唱時に起立しなかったなどの職務命令違反に対して行われたもので、態様や回数も社会通念上許容される範囲と評価されました。また、教頭が教諭の腕をつかんだ行為についても、教諭が処分告知の場で大声を上げて室外へ出ようとしたため、それを制止する目的で最小限の力を行使したと判断され、暴行とは認められていません。
さらに、教諭が精神疾患を訴えた後は、面談時の同席者を認める、呼び出しを控えるなどの配慮も行われており、安全配慮義務も尽くしていたと評価されました。この判例は、業務上の指導が適切な方法・態度で行われ、相手への合理的配慮がなされていれば、パワハラには該当しないことを示す好例です。
※出典:あかるい職場応援団(厚生労働省)「【第21回】「診断書に基づき原告の要望に配慮」 ― 広島県(教員パワハラ)事件」
【指導とみなされた事例】前田道路事件
前田道路事件では、部下が自殺に至った事案で、上司による叱責がパワハラに当たるかが争点となりました。一審では、上司の発言が社会通念を超えるものであり、不法行為に該当すると判断されましたが、二審の高裁はこれを覆し、上司の行為は指導の範囲内であると認定しました。上司が、日報報告の場や業績検討会で強い口調で叱責したのは、不正経理の是正などを求めて1年以上指導を続けたにもかかわらず改善が見られなかったためです。
高裁はこの経緯を重視し、一定の厳しい指導は正当な業務の範囲内であり、違法とは言えないと判断しました。この判例は、厳しい叱責であっても、その目的や背景が妥当であれば、パワハラとまでは評価されないケースがあることを示しています。ただし、人格を否定するような行為が含まれていれば、違法と認定される可能性がある点には注意が必要です。
パワハラにならない指導を行わせるポイント

パワハラ防止法により、企業にはハラスメント防止対策への取り組みが義務づけられています。適切な部下指導を行わせたい場合は、以下に紹介する事柄を企業側から管理職向けに実践してみましょう。
ハラスメント防止研修でパワハラと指導の違いを理解させる
パワハラを防ぎつつ適切な指導を行うには、まず両者の違いを正しく理解する必要があります。たとえば、大手建設会社B社では「必要な指導までがパワハラと誤解されないようにする」ことを重視し、全社員を対象にしたハラスメント防止研修を継続的に実施しています。特に指導者には、昇格時などのタイミングで専門的な人権研修を実施し、パワハラの境界線を学ばせる工夫をしています。また、研修内容をまとめたハンドブックを全社員に配布するなど、現場での判断力を高める取り組みを行っているのも特徴です。
※出典:あかるい職場応援団(厚生労働省)「【第10回】「必要な指導はしなければならない。だからパワハラ対策。」 ―大手建設会社であるB社」
このようなハラスメント研修を通じて、正当な指導が「パワハラ」と誤解されるのを防ぎ、安心して指導できる職場環境が構築されています。自社でもパワハラ研修を導入し、上司・部下双方の理解を深めたい場合は、ハラスメント予防研修やハラスメント防止研修の活用をご検討ください。
指導を行っている理由を伝えるルールを作る
パワハラと誤解されないためには、なぜその指導を行っているのか、目的や背景を明確に伝える必要があります。指導の際に「目的や背景を明言する」というルールをあらかじめ設けると、上司・部下双方の誤解や摩擦を減らすことができます。
たとえば、遅刻を繰り返す若手社員には「遅刻だよ」とただ指摘するのではなく、「顧客対応に支障が出る」「職場全体の信頼に関わる」などの具体的な理由を伝えることが必要です。さらに、今後の期待や処置も併せて伝えることで、部下は自分に求められている行動を正しく理解できるでしょう。部下の理解力や知識レベルに応じて説明の仕方を工夫し、指導後には内容が伝わったかどうかを確認するプロセスを取り入れるのも有効です。
アンガーマネジメントを身につけさせる
パワハラを未然に防ぐには、「怒りの感情」と上手につき合うスキルも必要です。その手法として注目されているのがアンガーマネジメントです。アンガーマネジメントとは、怒らないことを目的とするのではなく、怒る必要のある場面では冷静かつ適切に伝え、不要な怒りをコントロールする心理トレーニングです。
セイコーエプソン株式会社では、パワハラ防止施策の一環として2015年度よりアンガーマネジメント研修を導入しました。経営層を含む延べ約1.3万人が受講し、社内では「6秒ルール」などの用語が共通言語となり、怒りに流されずに指導を行う意識が浸透しています。怒りの感情を適切に扱うことは、組織内の信頼関係を築き、心理的安全性の高い職場づくりにも貢献します。
コーチングやティーチングを学ばせる
パワハラの防止を図るには、コーチングやティーチングの考え方を学ばせるのも一案です。コーチングは、部下自身が答えを導き出せるようにサポートする手法で、自立性や主体性を育てる効果があります。上司は一方的に正解を伝えるのではなく、問いかけを通じて相手の思考を促し、納得して行動に移せるよう導きます。
一方、ティーチングは知識や経験に基づき、業務の手順やルールを明確に教える方法です。特に新人に基本動作を習得させる場面において有効で、効率的な指導につながります。コーチングやティーチングを状況に応じて使い分けることで、感情的な叱責や押しつけを避け、納得感のある建設的な指導を行えるでしょう。
フィードバックスキルを身につけさせる
フィードバックスキルとは、相手の行動や成果に対して評価や指摘を行い、問題の改善や成長を促すための能力です。上司がフィードバックスキルに基づき指導することで、部下は自身の課題に気づき、納得感を持って行動を改善できるようになるでしょう。
フィードバックをする際は目標と結びつけ、具体的かつ行動可能な内容をタイムリーに伝えることが重要です。一方的な叱責ではなく、相手の状況に寄り添った対話が増えるため、モチベーションや信頼関係の向上にもつながります。結果として、パワハラと誤解されるような不適切な指導が減り、健全な職場環境の形成にもつながるでしょう。
まとめ
パワハラと指導の違いは、目的・態度・タイミングなどの複数の視点から総合的に判断されます。上司がよかれと思って行った注意でも、私的な動機で過激な表現が使われれば、パワハラと認定されるリスクがあります。一方で、配慮を持って適切に行われる指導は、部下の成長や職場の活性化につながる有効なマネジメント手法です。
判断基準や実際の判例、具体的な対策を参考にすれば、パワハラを避けつつ建設的なコミュニケーションが可能になります。今後の指導においては「相手の成長を目的とした関わり方」ができているかを常に意識し、自身の指導スタイルを見直しましょう。
関連記事
Related Articles
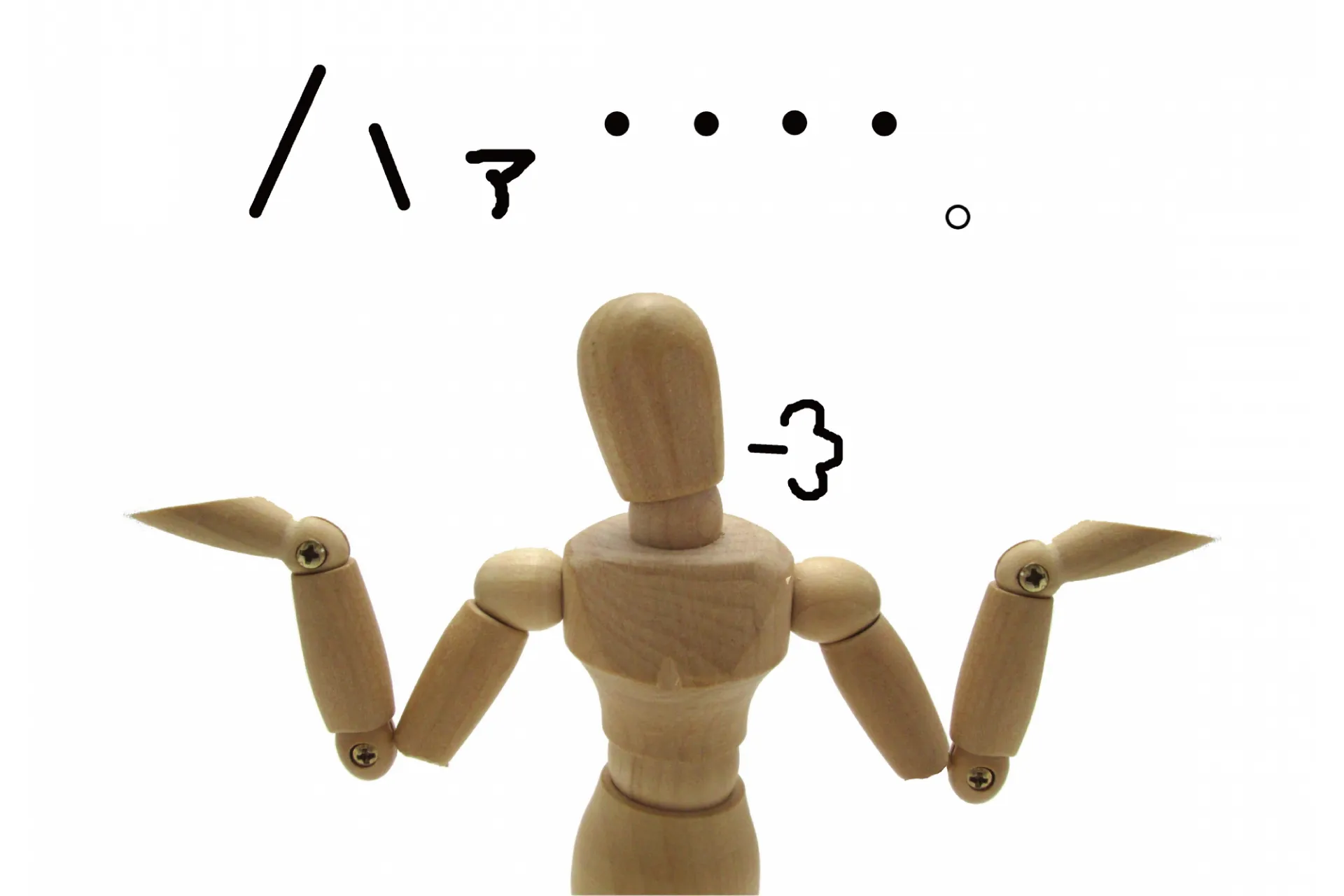
【不機嫌を放置しないで】フキハラの正しい対処法と組織を守る予防策
不機嫌な態度を周囲に振りまき、人間関係や業務に悪影響を与えることをフキハラ(不機嫌ハラスメント)と言います。パワハラ...
ハラスメント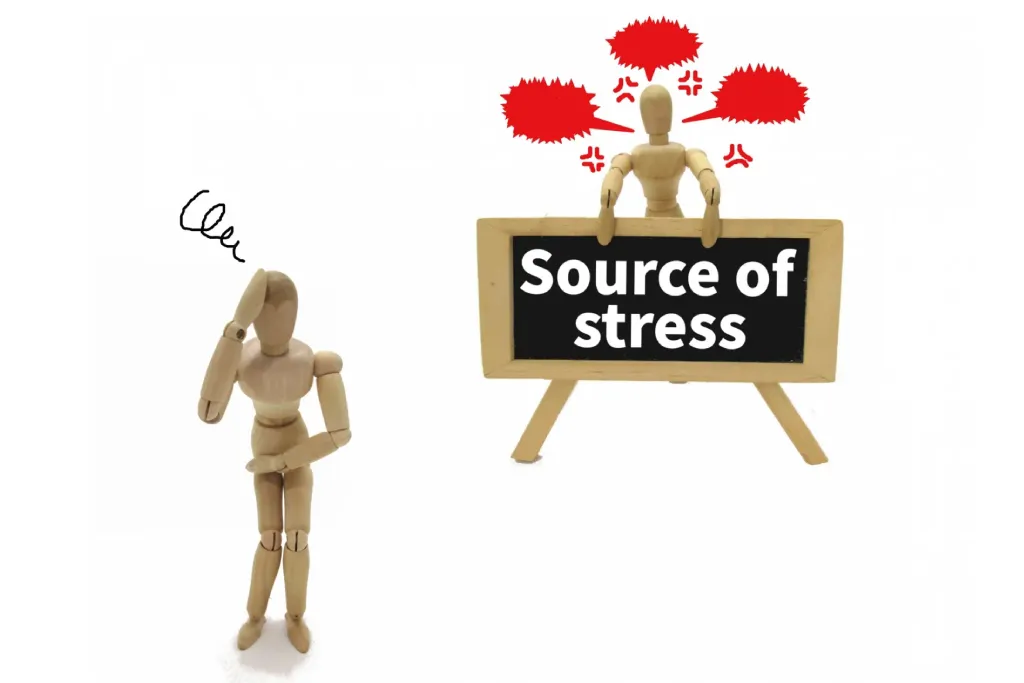
言ってはいけない言葉のパワハラ一覧!パワハラの判例についても解説
言葉によるパワーハラスメント(パワハラ)は、相手の人格や能力を否定する言葉や、仕事や職場からの排除を示唆する言葉、相...
ハラスメント
指導かハラスメントか?線引きに悩む「ハラハラ」の事例と8つの対策
適切な指導まで「ハラスメントだ」と過剰主張する「ハラハラ」について、定義・背景・職場で起きがちな具体例や参考判例、組...
ハラスメント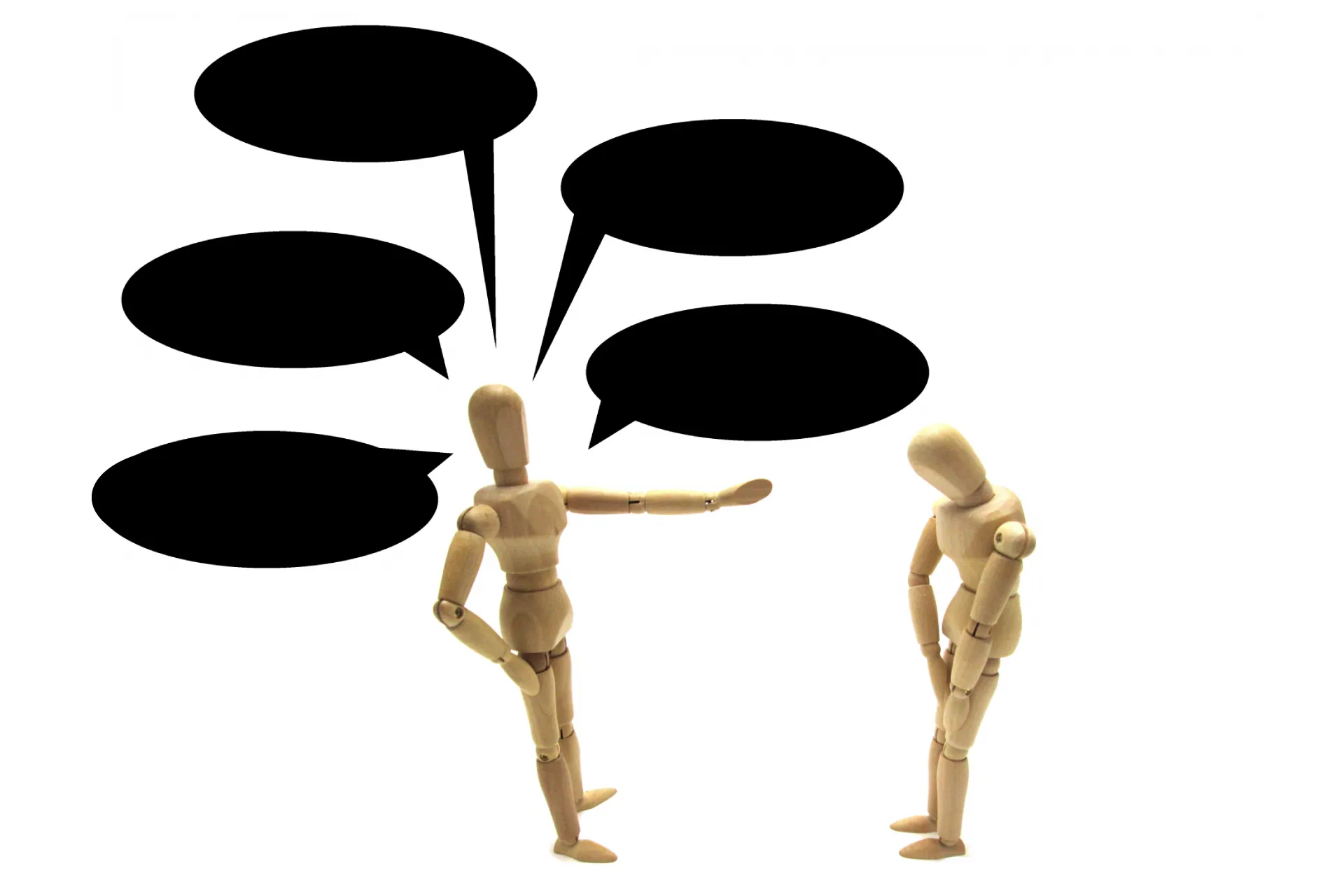
【事例あり】セカンドハラスメントの3つの原因と予防・対処法を解説
セカンドハラスメントとは、ハラスメント被害者が相談・申告した際にさらに精神的苦痛を受ける二次被害のことです。例えば、...
ハラスメント