- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 人の心を動かすプレゼンのコツ21選|資料や構成のこだわりポイントは?
人の心を動かすプレゼンのコツ21選|資料や構成のこだわりポイントは?

この記事は2024.3.11に公開した記事を再編集しています
2025年7月22日更新
プレゼンで人の心をつかみ、商談を成功させたり主張を理解してもらったりするためには、話し方を工夫すると同時に資料作りやプレゼンの構成にも力を入れることが大切です。では、どのような点に注意すれば良いプレゼンができるのでしょうか。
当記事では、良いプレゼンを行なう方法について、構成とプレゼン資料・話し方の3つの観点から詳しく解説します。ビジネスの場で、聞き手を惹きつけるプレゼンを行ないたい方は、ぜひ当記事をご覧ください。
目次
Toggle良いプレゼンテーションとは?

良いプレゼンとは、伝えたい内容がはっきりと相手に伝わるプレゼンです。相手に伝わるプレゼンを作るには、まず何を主張したいのかを整理する必要があります。プレゼンの目的を明確にすると、プレゼンに含むべき情報と不要な情報の切り分けも容易になります。
伝えたい内容がシンプルにまとまっていれば、聞き手は意見や主張を理解しやすくなるでしょう。必要不可欠な情報を網羅しつつ、自分の主張を繰り返し織り込むことにより、「何が言いたいのか分からない」という曖昧さを回避できます。
さらに聞き手の興味をひくためには、場面や相手に合わせた構成も重要です。相手の心を揺さぶるには、巧みな話術が必要に思えるかもしれません。しかし、話術は一朝一夕で身につくものではないため、まずは聞き手の立場に立って、聞き手が理解しやすいプレゼンを準備しましょう。
口頭だけで理解しづらい情報は、スライドや配布資料などを活用して視覚に訴えるのもおすすめです。
分かりやすいプレゼンテーション構成は?

伝わりやすいプレゼンを作るためには、伝える内容を明確にし、適切な順序で話さなければなりません。プレゼンでよく使用される構成には複数の種類があり、それぞれ次のような特徴があります。
| 三段構成 | SDS法 | PREP法 | DESC法 | FABE法 | |
| 流れ | 序論 ↓ 本論 ↓ 結論 | summary (概要) ↓ detail (詳細) ↓ summary (要点) | Point (結論) ↓ Reason (理由) ↓ Example (実例) ↓ Point (結論) | Describe (描写) ↓ Express (表現) ↓ Suggest (提案) ↓ Choose (選択) | Feature (特徴) ↓ Advantage (利点) ↓ Benefit (利益) ↓ Evidence (証拠) |
| 使用場所 | 論文 データ紹介 | ビジネス | 論文 ビジネス 面接 | ビジネス 価格交渉 | ビジネス |
| 特徴 | スタンダードな構成 | 理解しやすい 記憶しやすい | 理解しやすい 説得力がある | 信頼を構築できる | 商品やサービスの特徴や価値を分析できる |
ここでは、表で紹介した伝わりやすいプレゼンの構成方法を解説します。
三段構成
三段構成は、プレゼンで用いられる最もスタンダードな構成です。プレゼンの流れは以下の通りです。
| 1.序論 | イントロダクションとも呼ばれます。聞き手の興味を引くために、インパクトのあるつかみやエピソードを盛り込むのが一般的です。 |
|---|---|
| 2.本論 | ボディとも呼ばれるメインの部分です。エビデンスを織り込みながら伝えたい内容を説明します。 |
| 3.結論 | クロージングとも表現します。全体をまとめ、主張が相手に確実に伝わるよう念押しする部分です。 |
話術や構成が苦手な方でも使いやすいのが三段構成です。三段構成に沿ってプレゼンを練ると、伝わりやすいプレゼンが作れます。
SDS法
SDS法は、シンプルで伝わりやすいのが魅力の構成です。SDS法の構成は以下の通りです。
| 1.Summary(概要) | プレゼンの序盤は、聞き手の集中力が高い時間帯です。SDS法では、冒頭でプレゼンの全体像を簡潔に伝えます。 |
|---|---|
| 2.Details(詳細) | 伝えたい内容や主張を具体的に説明する部分です。 |
| 3.Summary(要点) | まとめや結論として、最も伝えたい内容を繰り返します。 |
プレゼン全体を通して何度も要点が出てくるため、聞き手の理解を深められるのがSDS法を用いるメリットです。理解や記憶が進みやすい構成なので、聞き手のレベルに差がある場面にも効果的です。
PREP法
PREP法は情報をまとめやすく、説得力のあるプレゼンを作りやすい構成法です。三段構成やSDS法より、構成がやや細分化されます。PREP法の構成は、以下の通りです。
| 1.Point(結論) | 冒頭に結論を持ってくるのが、PREP法の特徴です。聞き手にプレゼンの方向性をはっきりと示すことができます。 |
|---|---|
| 2.Reason(理由) | 冒頭で述べた結論にいたる理由を説明します。 |
| 3.Example(事例・具体例) | 事例や具体例を挙げて、結論にいたる理由に信ぴょう性を持たせます。聞き手のイメージを膨らませる部分です。 |
| 4.Point(結論) | 再び結論を述べ、プレゼンを通しての主張を伝えます。 |
プレゼン全体を結論と結論で挟み、聞き手の理解を促すのがPREP法の特徴です。SDS法と似た構成ですが、具体例を挙げる部分を加えることにより、さらに説得力が増します。
DESC法
DESC法は、聞き手の感情や意見を尊重しつつも主張したい場面で使える構成法です。DESC法の構成は、以下の通りです。
| 1.Describe(描写) | 聞き手が抱えている解決すべき問題を明確かつ客観的に提示します。 |
|---|---|
| 2.Express(表現) | 冒頭で提示した課題に対して主観的な意見や感想を述べます。 |
| 3.Suggest(提案) | 状況を打破するための解決策を具体的に提案します。 |
| 4.Choose(選択) | 聞き手が提案を受け入れなかった場合、別の選択肢を提示します。 |
DESC法は聞き手に納得してもらいながら主張を伝えられるのが魅力です。一方で、自分の主張を押し通すのが難しいデメリットもあります。選択肢を増やしすぎると、聞き手に負担をかける場合もあるため注意が必要です。
FABE法
FABE法は、商品やサービスの分析に活用されている方法です。競合との違いを明確にし、自社の商品やサービスを利用した際に顧客が得られる利益を伝えます。情報を分かりやすく整理する手法は、プレゼンのコンセプトを整理する場面でも応用できます。
| 1.Feature(特徴) | 客観的に商品やサービスの特徴を挙げます。機能や仕様などを含めましょう。 |
|---|---|
| 2.Advantage(利点) | 競合と比較した際の商品やサービスの優位点を挙げます。 |
| 3.Benefit(顧客特有の利益) | 自社の商品やサービスを選んだ際に利き手側にどのようなメリットがあるかを考察します。聞き手の顧客層や課題をあらかじめ把握しておくのが重要です。 |
| 4.Evidence(証拠) | 特徴や利点の裏付けとなる証拠や、予想される利益を証明するレポートやデータを提示して、主張にさらに信ぴょう性を持たせます。 |
FABE法は営業やマーケティングなどの分野で活用されています。
プレゼンテーションを成功させるための事前準備のコツ

プレゼンテーションを成功させるには、内容だけでなく準備段階が重要です。ここでは、説得力を高めるための事前準備のポイントを紹介します。
聞き手側のニーズを把握する
プレゼンの内容を作る前に、まず聞き手の立場や関心、知識レベルを把握する必要があります。たとえば、ITサービスの提案を行う場合、相手が技術職か営業職かによって求める情報は異なります。技術職にはシステムの仕様や導入効果を、営業職には顧客メリットや収益性を中心に伝えると効果的です。
また、聞き手の業界や役職、抱えている課題を事前に調べると、プレゼンの内容や表現を相手に合ったものへと調整できます。相手の知識量に配慮しつつ、敬意をもった問いかけをすることで、より良い関係性も築けるでしょう。
ストーリー性のある構成にする
プレゼンで相手の心を動かすには、ストーリー性を意識した構成が効果的です。人は商品そのものではなく、その背景にある「想い」や「体験」に共感して行動を起こす傾向にあります。
たとえば、「新卒で入社してからというもの、失敗の連続で、正直、何度も心が折れそうになりました。それでも『もっと良いものを作りたい』という思いだけは捨てずに、地道に試行錯誤を重ねてきました。その積み重ねが、今回のプロダクトにつながったと感じています」と語ることで、聞き手は自然と引き込まれ、話にリアリティと信頼感を感じるようになります。
プレゼンでは、失敗や挫折、苦労の過程をあえて共有し、そこから得られた学びと展望を描くことで、聞き手の感情を動かし、提案に深く納得してもらえるでしょう。
メッセージの伝え方を決める
プレゼンのメッセージは、聞き手の行動を促す明確な「核」である必要があります。その核を定めた上で、最適な伝え方を選びましょう。伝え方には大きく3つの方法があります。1つ目は、台本を読み上げるスタイルです。内容の正確性は保てますが、感情が伝わりにくく聴衆との視線も合いづらいため、避けるほうがよいでしょう。
2つ目は、話す内容を箇条書きにし、要点だけを見ながら話す方法です。自然な会話ができて伝わりやすいですが、メモに頼りすぎないよう注意しましょう。そして3つ目は、プレゼン内容を一言一句覚え、完全に自分の言葉として話す方法です。伝わる力がもっとも高いですが、入念な準備が必要です。自分のスキルや時間に合わせ、メッセージの伝え方を決めるとよいでしょう。
エピソードトークを用意する
共感を得られるプレゼンには、具体的な体験談やエピソードトークが欠かせません。聞き手がイメージしやすい話は、興味を引きやすく、記憶にも残りやすいという利点があります。
ただし、即興で思い出すのは難しいため、関連するエピソードは日頃からスマートフォンのメモなどにストックするのがおすすめです。伝えたいテーマに合った実体験を織り交ぜることで、説得力が格段に高まるでしょう。
質問を想定して回答を準備する
プレゼン後には、聞き手から質問を受ける場面がほとんどです。想定外の質問に焦ってしまうと、せっかくのプレゼンの印象が薄れてしまい、伝えたい要点が届かなくなる可能性もあります。
そのため、事前に考えられる質問を洗い出し、簡潔に答えられるよう準備しておきましょう。「聞き手の視点で内容を見直す」「本番前に社内で練習を行う」など、聞かれそうな質問の内容を具体的にイメージできるようにすることが大切です。落ち着いた受け答えができれば、信頼感も一層高まります。
リハーサルをする
プレゼンが上手な人ほど、事前に入念なリハーサルを行っています。スライドや資料の準備だけでなく、聞き手の属性や会場の様子を想定し、実際の環境に近い形で練習を重ねるようにしましょう。その際、時間配分の確認やスライド操作の練習などを行うことで、本番の流れを掴めるようになり、自信を持って臨めます。
また、信頼できる相手に聞いてもらいフィードバックを受けることで、自分では気づけなかった改善点にも対応できます。プレゼンは準備がすべてです。リハーサルを重ねることで、気持ちに余裕が生まれ、質の高い発表につながるでしょう。
人前で話すときの体の動きを整える
プレゼンでは、話の内容だけでなく「立ち姿」や「動作」も印象を左右するため、姿勢を正し、動作にメリハリをつけることがポイントです。歩くときはゆっくりと大きく動き、話す場面では落ち着いて立つと、堂々とした印象を与えるとともに、自分自身の緊張も和らぐ効果が期待できます。
また、腕組みや身体を揺らす動作など、緊張からくる無意識のクセは、聴衆に不安を与える要因になります。基本的な姿勢は、おへその前で自然に手を組むスタイルです。全身を使った「落ち着きのある振る舞い」は、プレゼンの説得力を高める土台となります。
プレゼンテーション資料作成のコツ

プレゼンの伝わりやすさは、視覚からの情報にも左右されます。資料を作成する際は、見やすいデザインを心がけるのが重要です。ここでは、見やすい資料を作成するコツを紹介します。
また、資料作成のスキルは研修によっても身につけられます。下記の記事もご参照ください。
読みやすいフォント・文字の大きさを選ぶ
読みやすい資料を作るには、まずフォント選びに注意を払いましょう。ゴシック体は、見やすくシンプルなフォントです。游ゴシックやメイリオなども見やすく、資料にメリハリがつく太字に対応したフォントです。一般的なパソコンに搭載されていないフォントを選ぶと、別の端末でファイルを開いた際に改行やレイアウトが崩れる可能性があります。特殊なフォントは避け、見慣れたフォントを選びましょう。
また、改行の量や行間の広さも重要です。行間が狭いと読みづらくなり、聞き手にストレスを与えます。適度に空白行も織り交ぜて、見やすさを重視した資料作りを心がけましょう。
図やデータをしっかりを入れる
複雑な情報を理解しやすくまとめるには、図解を取り入れるのがおすすめです。適切な図解を入れると、物事の関係や構造、変化などをイメージしやすくなります。資料の文章量が減り、読むストレスを軽減する効果も期待できます。
だらだらと文章を読み上げるより、図を説明する方が聞き手も退屈しません。プレゼンに不慣れな方や話すのが苦手な方は、積極的に図解を活用しましょう。
さらに、数値をまとめたグラフや画像などのデータを織り交ぜると、聞き手の理解を促せます。主張を裏付ける根拠となり、プレゼンへの信頼性を高める効果もあります。
グルーピングを意識する
ひと目見て分かりやすい資料作りには、グルーピングも重要です。グルーピングとは、情報を関係性の近さでまとめて整理することです。グルーピングには、同じグループに属する情報を近い位置に記載したり、グループ名を大きく記載したりするほか、グループごとに線や図形で囲う手法もあります。
線や図形で囲う装飾によってグルーピングする手法は、多用しすぎないよう注意しましょう。装飾が多すぎると、資料が見づらくなります。まずはレイアウトでグルーピングを行なってから、必要最低限の装飾をしましょう。
1スライドは1メッセージにする
情報が多い資料は、聞き手の注意が資料を読むのに向いてしまう原因になります。特にスライドは、情報が増えるとフォントを小さくする必要が生じたり、余白が少なくなったりします。1枚のスライドには1メッセージのみ記載するのを意識して、資料を作成しましょう。
口頭で説明する内容すべてをスライドに記載する必要はありません。すべての情報を記載すると、スライドを読むだけの退屈なプレゼンになるため、スライドは要点をシンプルに記載しましょう。
補足情報や数値データなどの細かい情報は、スライドではなく配布資料に落とし込むのもおすすめです。
使う色は3色に抑える
プレゼン資料に使う色は、ベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3色に抑えるのが基本です。多くの色を使うと一見分かりやすく感じるかもしれませんが、実際には統一感が失われ、視認性も下がってしまいます。
色を3色に絞ることで、情報が整理され、伝えたい内容が自然と際立ちます。配色バランスは「ベース75%:メイン25%:アクセント5%」が黄金比率とされており、見た目のまとまりと印象の強さを両立できます。背景には白やグレーなどの無彩色を用い、強調したいポイントにのみ鮮やかな色を使うと効果的です。
終わりのスライドを準備する
聞き手の印象に残るプレゼンにするためには、プレゼンの最後に「まとめ」や「呼びかけ」を入れたスライドを用意する必要があります。人は話の最後に提示された情報を特に記憶しやすい傾向があります。プレゼン終了時には冒頭の内容の多くを忘れている可能性があるため、最後に要点を再確認することで記憶に定着しやすくなるでしょう。
さらに、聞き手に期待する「次の行動(ネクストアクション)」を具体的に提示することで、行動につながるプレゼンになります。問い合わせ先の情報や特典、聞き手が得られるメリットを盛り込めば、行動喚起の効果も高まります。最後にお礼の言葉を添えることで、プレゼンの締めくくりとして丁寧な印象を与えられるでしょう。
事例を豊富に紹介する
説得力のあるプレゼンにするには、具体的な事例の紹介が欠かせません。事例を通じて「製品やサービスを使うとどのように課題が解決されたのか」を示すことで、聞き手は導入後のイメージを明確に描けるようになります。特に自社と似た業界や規模の成功事例を挙げれば、聞き手の関心や納得感が高まり、稟議や社内共有にも役立つでしょう。
また、複数の事例を用意することで、信頼関係のある顧客が存在する証にもなり、企業全体の信用力向上にもつながります。事例に他のサービスの活用例も盛り込めば、クロスセルのきっかけにもなります。単なる情報提供ではなく、実績に裏打ちされた提案であることを伝えるためにも、事例を積極的に活用しましょう。
プレゼンテーション中の話し方のコツ

構成と資料の適切な作成方法を実践すると、論理的で分かりやすいプレゼンを作れます。さらにプレゼン向きの話し方ができれば、聞き手に良い印象を与えられるだけでなく、プレゼンに説得力が出るでしょう。ここでは、プレゼンでの話し方のコツを紹介します。
笑顔で話す
笑顔でプレゼンをすると、聞き手からは余裕があるように見えます。さらに相手の警戒心をとく効果も期待でき、心理的な距離を縮められる可能性もあります。
笑顔を作るには、意識的に口角を上げるのがおすすめです。緊張すると表情が固くなってしまう方は、自分が笑顔になれるエピソードをプレゼンのつかみに入れて、笑顔を作れるようにするとよいでしょう。
早口になりすぎない
プレゼンでテンポよく話すのは重要ですが、早口になりすぎるのは好ましくありません。必要以上に早口になると、聞き手がついてこられなくなる可能性があるためです。特に口頭での説明を聞きながら資料を照らし合わせる必要がある場面では、聞き手の理解が追いつくスピードで話しましょう。
一方で、終始テンポがゆっくりすぎると聞き手を退屈させる恐れもあります。場面に応じて緩急と抑揚をつけて話すのが、聞き手を飽きさせないコツです。
スライドを読み上げない
スライドに記載している情報を読み上げるだけでは、魅力的なプレゼンになりません。手元の原稿には、言い忘れてはいけない各スライドの要旨や、スライド間を自然につなげる言葉を記載しましょう。自然な語り口で展開するプレゼンは、主張が伝わりやすく、聞き手にストレスを与えません。
必要に応じてスライドにはない補足情報や体験談などの具体的なエピソードを盛り込むと、聞き手の興味を引くことができます。
つなぎ言葉に注意する
論理が飛躍したり、情報がぶつ切りになったりするのを防ぐため、プレゼンでは適切な接続詞を使用しましょう。接続詞には、順接や逆接、付加、対比などさまざまな種類があります。プレゼン相手によっては文語で用いるような固い接続詞ではなく、「すると」や「でも」のような柔らかい口語の接続詞を使っても構いません。
「えー」や「あのー」などのフィラーと呼ばれる無意味なつなぎ言葉を使うのは避けましょう。聞き苦しいだけでなく、話し慣れていない印象を与えます。
ジェスチャーを使う
ジェスチャーを取り入れるのも、聞き手の興味を引く手段の1つです。会議室のような広さでのプレゼンであれば、仰々しいジェスチャーは必要ありません。数字が出てきた際に指で表したり、大きさを両手で示したりするのも、ジェスチャーの1種です。言葉だけでなくジェスチャーという視覚的なメッセージが加わることにより、さらに聞き手の理解が深まります。
ジェスチャーに慣れていない方は、取り入れやすい簡単なジェスチャーをあらかじめ考えておき、手元の原稿にメモしておくのがおすすめです。
アイスブレイクを挟む
プレゼンはしばしば緊張感のある空気で行なわれます。場の空気を和らげるとともに、自分の緊張もほぐすことができるのがアイスブレイクです。アイスブレイクとは、プレゼンや会議の前に自己紹介や雑談を挟んだりするなど、雰囲気を和ますために行なうコミュニケーションです。距離によっては聞き手に質問を投げかけ、コミュニケーションを図る方法もあります。
聞き手を笑わせようとする必要はないので、お互いへの理解を深められるような話題をチョイスしましょう。政治や宗教などのセンシティブな話題やネガティブな話題は、アイスブレイクに不向きです。
堂々と話す
話す姿勢が悪いと、内容をどれほど練ったとしても心を揺さぶるプレゼンにはなりません。堂々と話しているように見せるためにも、話している間は両足で立ち、背筋を伸ばします。
特に体の重心を左右に移動させる癖がある方は、天井から糸で吊られているような意識で立ちましょう。上半身が小刻みに揺れると、落ち着きがなく見え、自信がないように受け取られる可能性があります。
さらに、聞き手を見渡してアイコンタクトを図るのも、堂々としているように見せるテクニックの1つです。
プレゼンテーションの資料を作る流れ

効果的なプレゼン資料を作成するには、明確な目的と流れをもとに、段階を踏んで情報を整理・構成することが必要です。以下に、基本的な5つのステップを紹介します。
| 1. プレゼンの流れを決める |
| まずは、プレゼンの目的とそれに合う構成を明確にしましょう。たとえば、提案型のプレゼンでは「結論→問題提起→解決策→信頼性→行動提案」といった流れが基本です。どのような順序で話せば相手に伝わるかを考えることが出発点です。 |
| 2. 必要な情報を洗い出す |
| プレゼンの主旨に沿って伝えるべき情報を箇条書きで整理します。この段階では情報の取捨選択が大切です。相手にとって不要な情報を削り、必要な要素だけを抽出することで、資料の無駄を省けます。 |
| 3. 情報をテキストで整理する |
| 洗い出した情報を短く・分かりやすく文章化します。同時に、どの情報をスライドに書き、どこを話で補足するかも決めておきましょう。文字を詰め込みすぎず、「1スライド1メッセージ」を意識することが大切です。 |
| 4. スライドの構成を考える |
| 全体の流れをもとに、各情報をどの順番・形式で配置するかを設計します。各パートに必要なスライド枚数を見積もり、プレゼン全体のボリュームやテンポを把握しましょう。 |
| 5. スライドを作成する |
| スライドを作る際は、視認性と統一感を重視しましょう。グラフや図、写真などの視覚的要素を活用して、情報を整理します。伝えたいポイントを目立たせ、聞き手が考えずに理解できるような設計を心がけてください。 |
このような手順を踏むことで、プレゼン資料は単なる情報の羅列ではなく、相手に伝わる「説得力のある資料」へと仕上がります。
プレゼンテーションを成功させるためには?

プレゼンを成功させるには、十分な準備と練習が重要です。自信を持ってプレゼンができるようになるまでには経験を積む必要もあります。小規模なプレゼンを積極的に行ない、経験をどんどん積みましょう。最後にプレゼン成功のコツを場面別で紹介します。
<プレゼン前>
事前に本番と同じ状況を作って練習しましょう。1人で練習する際は、動画を撮影して見直すのがおすすめです。スムーズに話せるようになったら、協力してくれる人を募って、リハーサルを行ないます。理解しづらい部分をフィードバックしてもらい、場合によっては資料も修正します。話し方や目線の配り方など、話術に関しても意見を求めましょう。
<プレゼン中>
プレゼンに不慣れな間は、緊張する方がほとんどです。緊張で手元やスライドだけに目線がいくと、聞き手の感情に訴えることはできません。まずは頷いたりメモを取ったりして好意的に聞いてくれている方を探しましょう。好意的に聞いてくれる方を見つけられると、緊張が和らぎ、落ち着いて話せるようになります。反応が良い方を中心に、他の方にも目線を配ると、自信を持って話しているように見えます。
プレゼンの機会が頻繁にない方は、経験を積むのが難しいかもしれません。プレゼンのスキルを上げるには、講座を受講する方法もあります。詳しくは、下記のページもご参照ください。
まとめ
良いプレゼンを行ないたい場合は、主張内容を明確にし、聞き手にとって理解しやすい構成にする必要があります。構成には「三段構成」や「SDS法」などさまざまな種類があるため、プレゼンの目的に応じて使い分けます。
また、見やすい資料作りと聞き手を惹きつける話し方も重要です。自信をもってプレゼンを行なうためにはある程度の経験が必要なので、プレゼン前に練習をしたり、研修を実施したりして、プレゼンスキルを高めましょう。
関連記事
Related Articles
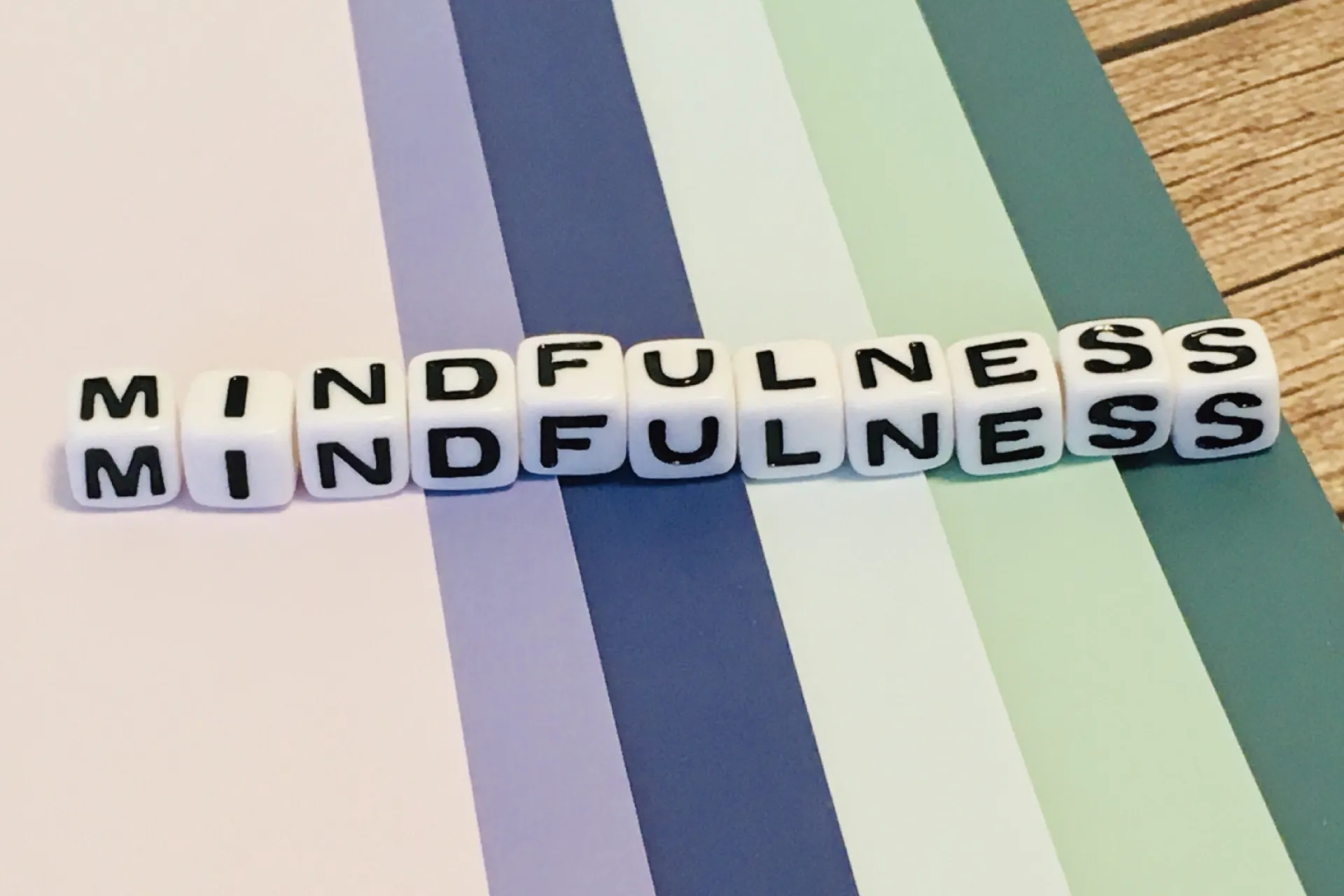
マインドフルネスとは?メリットや注意点、企業の導入事例を紹介
ストレス軽減や集中力の向上につながる手法に「マインドフルネス」があります。マインドフルネスを企業として導入しているケ...
HRトレンド企業研修
ストレングスファインダーで分かる34の資質|企業の活用事例も解説
ストレングスファインダーは、エンゲージメントのレベルや仕事の生産性の向上、他社理解の促進など、さまざまな利点をもたら...
HRトレンド企業研修
ファシリテーターとは?役割と求められるスキル・うまくなるコツを解説
ファシリテーターは参加者一人ひとりの意見を尊重し、安心して発言できる環境を作りつつ、多様な意見を効果的に引き出して活...
HRトレンド企業研修









