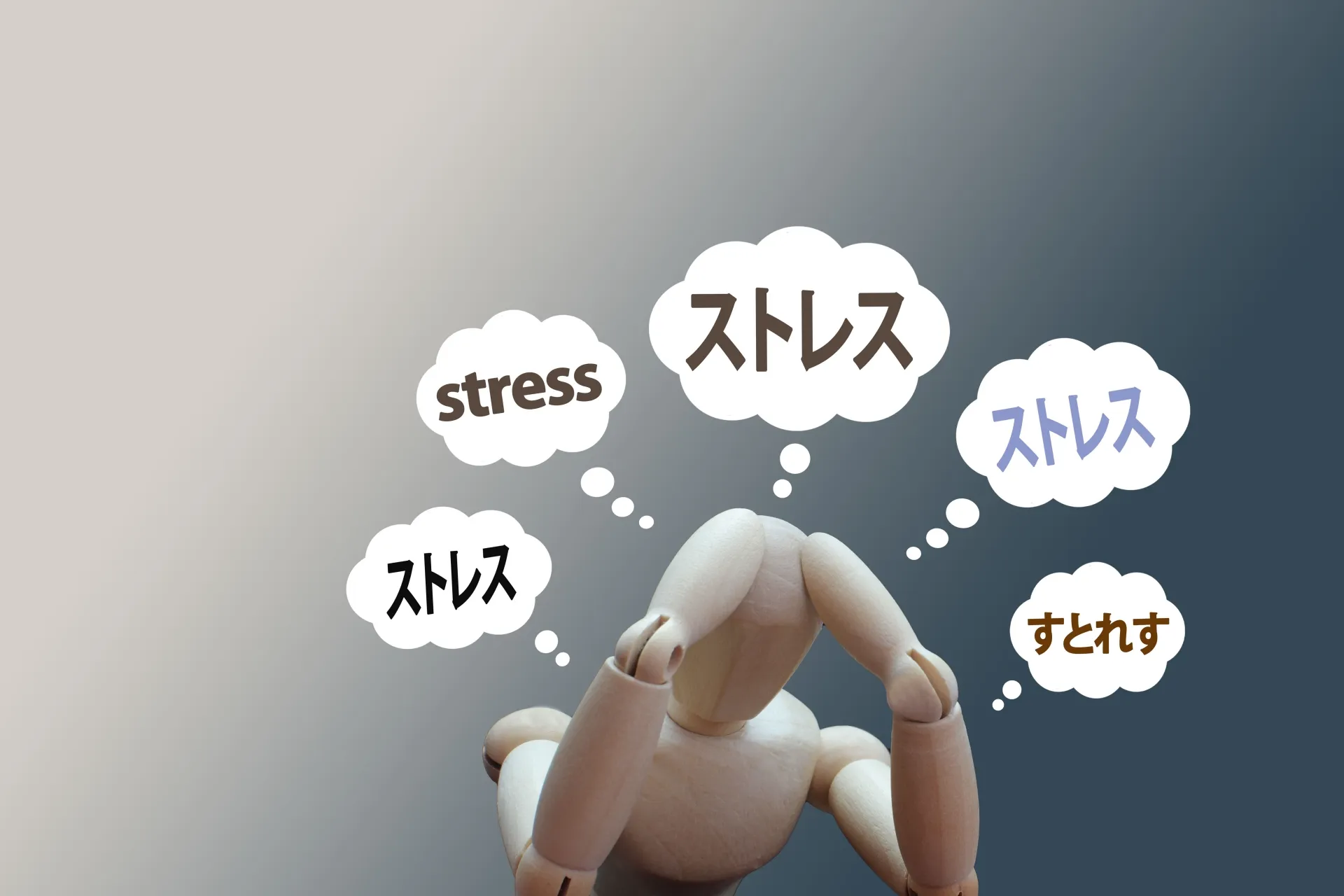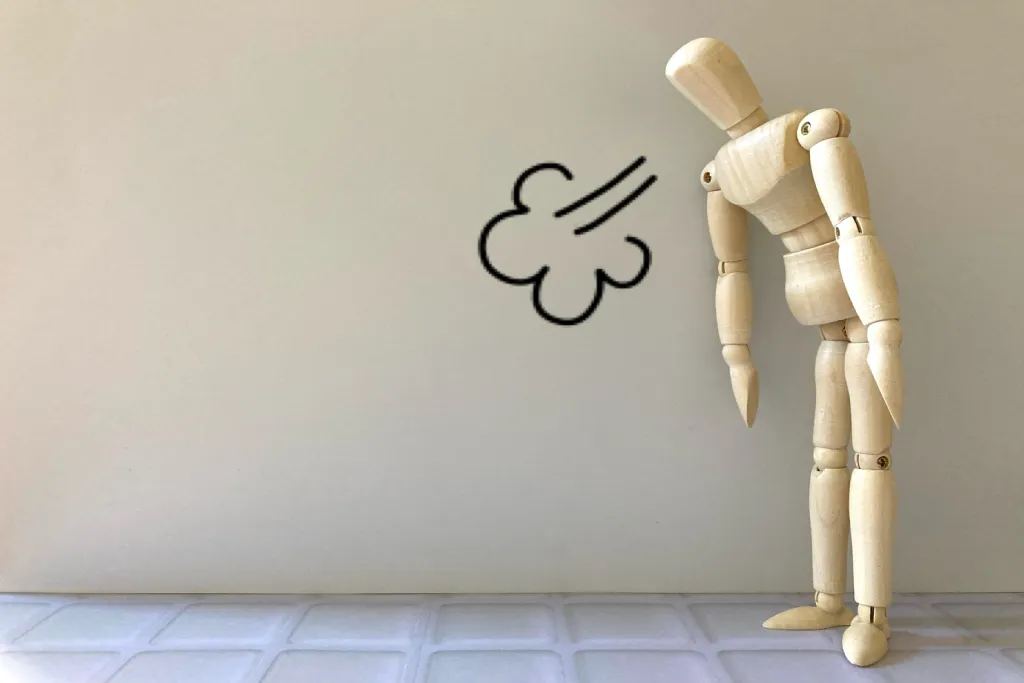- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- ハラスメント
- パワハラ防止法とは?罰則や企業がやるべき措置を事例付きで解説
パワハラ防止法とは?罰則や企業がやるべき措置を事例付きで解説
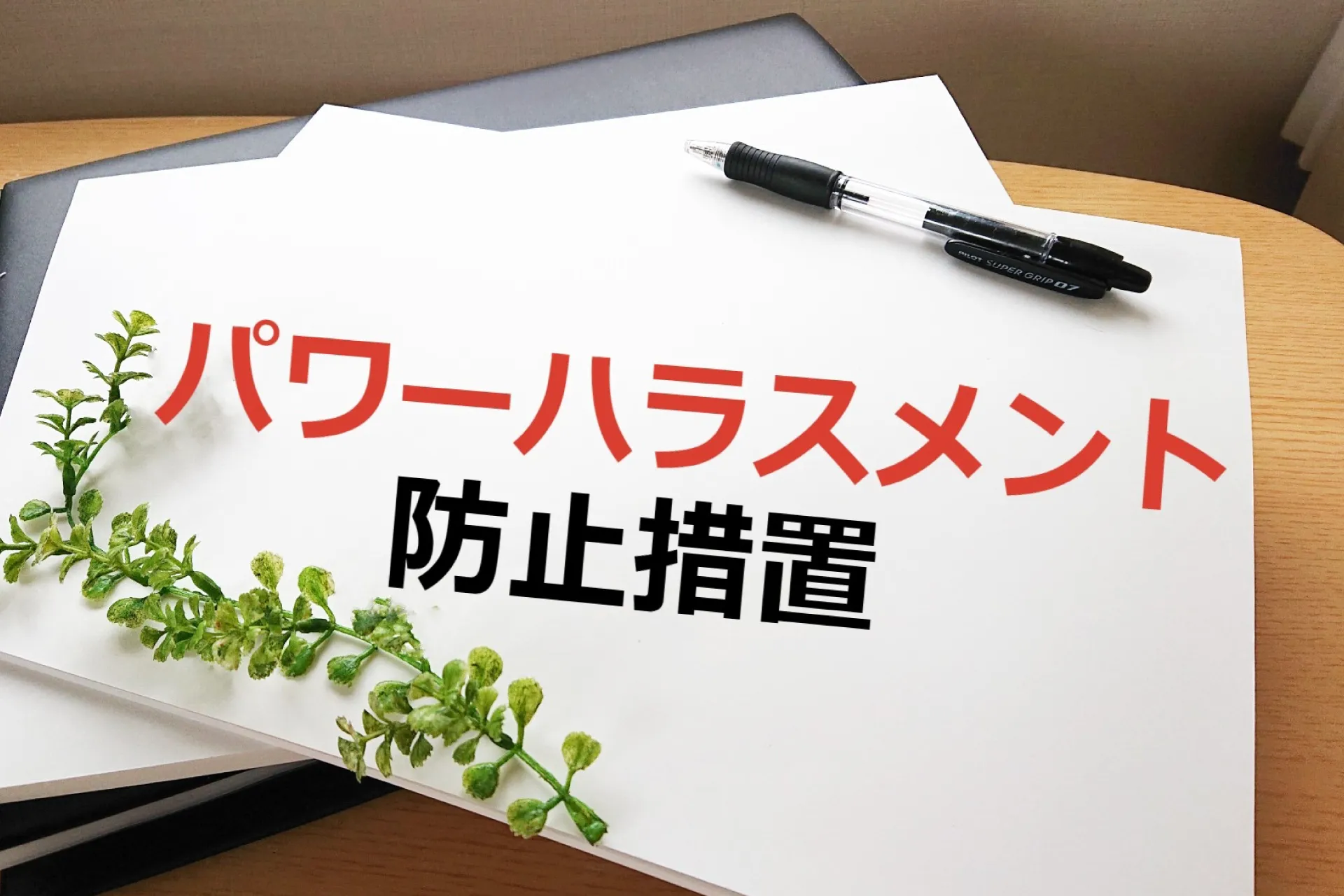
職場内でのパワハラは、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、組織としての生産性や職場環境に深刻な影響を及ぼします。そのため、国は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、通称パワハラ防止法を制定しました。企業は従業員にハラスメントについて周知・啓発し、パワハラを防ぐ必要があります。
この記事では、パワハラ防止法の概要や罰則、企業が取るべき措置、およびパワハラ防止に成功した事例について解説します。
目次
Toggleパワハラ防止法とは

パワハラ防止法とは、パワーハラスメント防止に向けて、企業に対して雇用管理上必要な措置を義務付ける法律です。「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」という正式名称を持ちます。
「労働施策総合推進法」という略称が使われるケースも少なくありません。現在のパワハラ防止法は、2019年5月に以前の「労働施策総合推進法」が改正される形で成立しました。
パワハラ防止法が制定された背景
パワハラという言葉は、株式会社クオレ・シー・キューブが作った和製英語です。「パワハラ」という概念の誕生は、職務上の地位を利用した威圧的な態度や嫌がらせなどに悩んでいた社員が、「声をあげやすい環境づくり」に貢献しました。パワハラが社会で顕在化し、問題の重要性が認識されたことで、2011年には厚生労働省を中心にパワハラ予防・解決に向けた取組についての議論が始まっています。
さらに、2019年には国際労働機関(ILO)でハラスメント禁止条約が採択され、初めて国際レベルで「職場でのセクハラ・パワハラ行為を禁止する」内容が示されました。この流れやパワハラ相談件数の増加を受け、日本でも2019年に、パワハラ防止法が制定されました。
下表は、パワハラ防止法制定前の2020年のパワハラ対策実施率を示したものです。
●パワハラ防止法制定前のパワハラ対策実施率(%)
| 従業員規模 | 全体 | 99人以下 | 100~299人 | 300~999人 | 1000人以上 |
| 事業主によるハラスメント対策への取組姿勢を明確に示す発信 | 60.6 | 51.0 | 53.5 | 65.9 | 79.0 |
| ハラスメントの内容や対策方針の明確化・周知 | 83.1 | 71.0 | 81.6 | 90.9 | 95.9 |
| 行為者への対処方針の規定・周知 | 69.8 | 55.2 | 65.7 | 78.8 | 88.7 |
| 相談窓口の設置と周知 | 78.6 | 55.4 | 80.0 | 93.3 | 98.1 |
| 相談窓口担当者向けのマニュアル作成・研修等 | 42.1 | 22.7 | 33.1 | 53.1 | 72.5 |
| プライバシー保護措置の実施・周知 | 48.5 | 24.2 | 42.1 | 62.8 | 79.8 |
| 不利益取り扱いを禁じることの規定・周知 | 60.6 | 36.6 | 53.0 | 76.4 | 87.5 |
| ハラスメントについて従業員が理解を深めるための取組 | 45.3 | 28.6 | 37.1 | 54.2 | 73.3 |
※出典:厚生労働省「令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査」
従業員規模「全体」の結果を見ると、複数の項目で実施率が50%を下回っています。また、従業員規模の小さな会社と大きな会社では、各対策の実施率に大きな差が見られます。
一方、下表は、パワハラ防止法制定後の2023年のパワハラ対策実施率を示したものです。
●パワハラ防止法制定後のパワハラ対策実施率(%)
| 従業員規模 | 全体 | 99人以下 | 100~299人 | 300~999人 | 1000人以上 |
| 事業主によるハラスメント対策への取組姿勢を明確に示す発信 | 65.7 | 56.8 | 61.5 | 68.6 | 76.5 |
| 経営幹部がハラスメントに対する関心と理解を深めるための周知・啓発 | 55.7 | 46.4 | 52.8 | 58.9 | 64.9 |
| ハラスメントの内容や対策方針の明確化・周知 | 82.6 | 67.4 | 80.6 | 85.9 | 92.2 |
| 行為者への対処方針の規定・周知 | 72.2 | 55.8 | 69.9 | 78.0 | 84.5 |
| 相談窓口の設置と周知 | 86.0 | 68.2 | 88.1 | 92.0 | 95.2 |
| 相談窓口担当者向けのマニュアル作成・研修等 | 47.8 | 26.9 | 44.3 | 54.7 | 65.7 |
| プライバシー保護措置の実施・周知 | 55.9 | 31.4 | 52.2 | 59.3 | 75.4 |
| 不利益取り扱いを禁じることの規定・周知 | 67.8 | 45.2 | 64.0 | 75.6 | 86.2 |
※出典:厚生労働省「令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査」
完全に項目が同じではないことから、単純に比較はできないものの、従業員規模「全体」については、「相談窓口担当者向けのマニュアル作成・研修等」以外で実施率50%を上回る結果が得られました。また、従業員規模「299人以下」の会社では、相談窓口の設置やプライバシー保護措置などの複数項目で2020年よりも実施率が大きく向上しています。
パワハラ防止法の対象者・対象企業
現在のパワハラ防止法は、全労働者・全企業が対象です。全労働者とは、事業主が雇用するすべての労働者を指しており、パートタイム労働者や契約社員といった非正規雇用労働者も含まれます。さらに、自社が雇用する労働者だけではなく、取引先などの他の事業者が雇用する労働者・求職者もパワハラ防止法の対象です。
2020年6月の法律施行当初には、大企業のみにパワハラ防止措置義務が適用されましたが、2022年4月に中小企業まで適用範囲が拡大されています。したがって、すべての企業がパワハラ防止法に沿った対策を求められます。
パワハラ防止法で禁じられるパワハラの定義
パワハラ防止法で禁じられるパワハラの定義は、以下の通りです。
| 優越的な関係を背景とした言動 | 業務上の地位や人間関係における優越性を背景に行われる言動を指します。同僚または部下による言動であっても、以下のような例はパワハラに該当します。 ・当該言動を行う者が業務上必要な知識や経験を有しており、当該者の協力がなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの ・集団による行為で、抵抗または拒絶することが困難であるもの |
| 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 | 社会通念に照らし、明らかに当該事業主の業務上必要性がない、または態度が相当でない言動のことです。該当する言動の例は、以下の通りです。 ・業務上明らかに必要性のない言動 ・業務の目的を大きく逸脱した言動 ・業務を遂行する手段として不適当な言動 ・当該行為の回数、行為者の数など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動 |
| 労働者の就業環境が害されるもの | 当該労働者が就業する上で、次のような看過できない程度の支障が生じるものを指します。 例えば、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じるものなどが該当します。 |
パワハラ防止法に罰則はある?

現行のパワハラ防止法に罰則は設けられておらず、事業主が直接処罰される訳ではありません。ただし、行政指導に従わない場合は、自社ホームページにパワハラ防止法違反があった旨を掲載しなければなりません。また、厚生労働省のWebサイトで企業名が公表されるなどのペナルティもあるため注意が必要です。
近年は、コンプライアンスの遵守が企業イメージに大きく影響するようになりました。社名が公表されると、世間に対して「パワハラ防止や法規則への対応力がない」というネガティブなイメージを与えてしまいます。
SNSでの情報拡散・炎上を経て、企業ブランドに対する評価が急落するリスクも否定できません。企業やブランドに対するネガティブな印象が、販路拡大・採用といった事業活動に悪影響を及ぼす危険性も理解しておく必要があります。
パワハラ防止のために企業が講じるべき4つの措置と10の対策

パワハラ防止法では、パワハラ防止に向けて、企業が講じるべき4つの措置が定められています。企業が取り組むべき措置は、以下の通りです。
| ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ・相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備 ・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ・そのほか併せて講ずべき措置 |
また、上記の措置に関する具体的な取組例として、10の対策を紹介します。
ハラスメントについて周知・啓発する
職場におけるハラスメントの内容、及びハラスメントを許さない旨の方針や規則を就業規則などにおいて明確にした上で、全労働者に対して周知・啓発を行います。パワハラ被害防止を徹底するためには、すべての労働者にパワハラ防止対策に向けた社内規則の存在を認識してもらう必要があります。また、定期的な周知・啓発により、ハラスメントの発生原因や対策の必要性について理解を促すのも大切です。
具体的な周知方法としては、社内報やパンフレット・リーフレットといった媒体の活用が挙げられます。研修や講習を通して、パワハラ防止に関する周知・啓発を行うのも1つの方法です。妊娠・出産、育児・介護休業などに関するハラスメントへの対応を実施する際は、利用可能な制度についても周知しましょう。
十分な周知がなされていないと、パワハラ加害者が企業を訴えた場合は企業側が裁判で不利になる点に注意してください。例として、長門市の消防長が暴行や暴言、セクハラ、脅迫を繰り返した結果懲戒処分を受けたことを不満として市を訴えた事例があります。当該事例では、ハラスメントに対する周知が不十分であったという理由で、市が地裁・高裁の双方で敗訴しました。最高裁にて市側が勝訴したものの、ハラスメントについての周知や啓発・研修を行うことは組織を守ることにもつながると言えるでしょう。
ハラスメントを行った者への厳正な対処を伝える
職場でハラスメントを行った者については、厳正な対処をとる旨の方針と対処法を明確にし、すべての労働者に伝えておく必要があります。対処の方針や具体的な処分内容をあらかじめ就業規則・服務規律などの社内規則の中で規定し、社内で共有しておきましょう。加えて、どのような行為がパワハラに該当するのかも明記しておきます。
懲戒規定を明確に設けていない場合、行為者に対して適切な対処が行えず、パワハラ対策が思うように進まない可能性があります。「どのようなハラスメント行為が、どのような処分につながるのか」を労働者にルールとして認識してもらうことで、パワハラを未然に防ぐのが重要です。
相談窓口を設置して周知する
ハラスメント行為に関する相談や苦情があった場合に、適切に対応できる窓口の設置と周知も必須です。しかし、ただ形式的に窓口を設置しているだけでは、法律に基づく有効な措置・対策として認められないため注意しましょう。
ハラスメント相談窓口の設置を定期的に周知するとともに、労働者が利用しやすい相談体制を整えるのも大切です。労働者の中には、社内相談窓口の利用に抵抗を感じる人も少なくありません。自分の相談内容がパワハラ行為者に伝わったり、人事考課や異動などに不利益を与えたりするのではないか、という不安・不信感が拭えないためです。
従業員側に相談窓口への不満や不信感がある場合は、委託型の外部相談窓口を設置し、労働者が会社を通さずに専門相談員に相談できる体制を整えるのも有効です。企業内部で相談窓口を設置する場合も、プライバシー侵害や報復行為、業務上の不利益に対する心配がない旨を丁寧に説明して安心感を持ってもらう必要があります。
相談に対して適切な対応ができる仕組みを作る
相談に適切に対応するために、相談の受付だけではなく、事実関係の確認が必要になるケースもあります。担当部署や職員の役割を明確にし、スムーズに対応できる仕組みを確立するのが重要です。
相談担当者には、相談者の心身の状況やハラスメント行為の受け止めや認識に配慮して、広く相談に対応する力が求められます。研修・講習などを活用して、相談担当者のスキルアップをサポートするのも1つの方法です。
会社として適切な相談対応に失敗すると、訴訟などの大きな紛争に発展するリスクも考えられます。実際に、消費者金融会社で上司から受けたパワハラの相談に真摯に対応しなかったことで、最終的に当該上司と会社に対して損害賠償請求が認められた事例もあります。
※出典:厚生労働省 あかるい職場応援団「【第17回】「上司から受けたパワハラを理由とした損害賠償請求」 ― 日本ファンド(パワハラ)事件」
事実関係を素早く正確に確認する
パワハラ行為などについての訴えがあった場合に、事実関係を素早く正確に確認するのも、企業に求められる重要な義務です。調査義務に違反した場合は、損害賠償請求の対象になり得るため、注意が必要です。
例えば、厚生労働省のサイトに掲載されたハラスメントの裁判事例として、セクハラの訴えについて被害者の上司が加害者の意見だけを信じて問題にしなかったというものがあります。上司と加害者は個人的に仲が良かったため、拙速かつ一方的に被害者の訴えを退けたことが問題になりました。後ほど社内の労働組合に被害者が訴え出たことで、加害者の証言が嘘であると分かり、加害者およびその上司は降格処分となりました。
※出典:厚生労働省 あかるい職場応援団「【第8回】「ハラスメント相談対応について」 ― 新聞輸送事件」
上司や同僚による調査は、人間関係などの事情が反映されて正確な結果が得られない可能性があるため、望ましくありません。
正確に情報を確認する手順として、はじめに相談担当者・人事担当者・法務担当者といった複数人で調査チームを作り、相談者のヒアリングを行う必要があります。続いて、相談者の了承を得て加害者にヒアリングを行い、双方の言い分が食い違っている場合は第三者への確認を実施します。目撃者や関係者といった第三者からヒアリングを行う際も、被害者と加害者から承諾を得るなどの配慮が必須です。
被害者に向けて適正な配慮をする
パワハラが生じた事実が確認できた場合は、被害者の気持ちに寄り添い、適切な配慮を行う必要があります。適切な配慮措置の例としては、被害者と加害者の関係改善に向けた援助やメンタル不調に関する相談対応、労働条件上の不利益の回復などが挙げられます。
また、会社がパワハラ行為者に行った処分について、被害者がなかなか納得できないケースも少なくありません。被害者が前を向けるように、処分決定に関与していない相談担当・同僚などが精神的なサポートを行うのが大切です。さらに、該当ハラスメントの解決後に新たな問題が生じていないか、所属部署や総務部門が連携をとって被害者の職場環境を注視する必要があります。
加害者に向けて適正な措置を行う
パワハラが生じた事実が確認できた場合は、加害者に対して、速やかに適切な措置を行う必要があります。業務規則などの定めに基づき、加害者に懲戒処分などを実施する際は、事実関係の調査を経て正確な情報を把握しておくのが重要です。具体的な処分内容は、調査で把握した内容やパワハラ行為の証拠をもとに、慎重に検討します。
適正な処分を選択するには、パワハラ内容だけではなく、常習性・被害程度・加害者の反省の有無といった複数要素を考慮するのが大切です。特に、パワハラ加害者の行為が継続しているケースでは、緊急的な措置が求められます。
適切に証拠を確認した上で処分を行っていれば、たとえパワハラ加害者が会社を訴えた場合でも退けられます。例として、ハラスメント加害者と加害者をかばった上司が、降格を不満に感じて会社を訴えた裁判では、企業側が適切に調査をしており、適切な措置がされているとして加害者が敗訴しています。
再発防止措置を実施する
パワハラが生じた事実が確認できた場合は、改めてハラスメントについて周知・啓発を行うなどの再発防止措置を実施します。調査を経てパワハラが生じた事実が確認できなかったケースにおいても、同様の措置が必要です。
再発防止策の例としては、パワハラ行為者に対する研修実施や職場環境改善のための取組などが挙げられます。再発防止研修については、なるべく外部のセミナーや研修を活用し、社内の対象者同士が顔を合わせなくて済むように配慮しましょう。
パワハラ行為の背景には、労働環境への不満・ストレスなどが潜んでいる場合も少なくありません。コミュニケーション・人間関係の希薄化、長時間労働といった問題が見られる場合は改善を行い、パワハラ事案が発生しにくい環境を整備するのが大切です。
当事者のプライバシーを守る
パワハラ行為に関する相談への対応や、事後の対応に当たっては、加害者も含めた当事者のプライバシーを守る措置が求められます。プライバシー保護の措置を行っている旨を労働者に周知し、相談しやすい環境を構築しておくのが大切です。
また、「守秘義務の徹底」をはじめ、プライバシー保護に必要な事項は事前にマニュアルなどに定めておく必要があります。さらに、相談担当者や職場管理者向けに、プライバシー保護に関する研修を実施するのも1つの方法です。プライバシーを守り、当事者と担当者が信頼関係を築くことで、速やかな解決につながる場合もあります。
相談や協力した者に不利益がある取り扱いをしない
企業には、パワハラ行為の相談や問題解決に協力した者に不利益がある取り扱いをしない旨を定め、労働者に対して周知・啓発する義務があります。不利益がある取り扱いの具体例は、以下の通りです。
| ・解雇 ・減給 ・降格処分 ・退職や労働契約内容変更の強要 ・昇進や昇格に不利な評価 ・経験や技能が発揮できない部門への配置転換命令など |
上記を防ぐ取組としては、ハラスメント相談や調査協力が原因で不利益な取り扱いをされない旨を就業規則などに定め、労働者に周知・啓発するのが有効です。また、パンフレットをはじめとする資料を用いて周知・啓発を継続することで、パワハラ相談や調査協力への心理的ハードルの低下につながる効果も期待できます。
パワハラ防止に成功した企業が行った対策事例

厚生労働省のパワハラ対策の好事例集では、パワハラ防止の手本となるような事例・体験談が掲載されています。事例集の中からパワハラ防止の成功事例を紹介するため、パワハラが起きにくい職場環境づくりの参考にしてください。
3年間ハラスメント発生ゼロに成功したS社
大手運輸会社グループ企業の一員であるS社は、業績が伸び悩んだ時期に、社員の20%程度を占める女性の活躍に期待を寄せました。社長発のプロジェクト開始当初には、業績回復や働きやすい職場について、女性労働者の意見を吸い上げる会議を何度も開催した実績があります。
女性を中心に改革が進む中で、パワハラ防止に関する周知や全社員を対象とした年2回の研修などが実施された結果、S社は深刻なハラスメントの発生防止に成功しました。「ハラスメントをなくす」アプローチではなく、職場改革の結果としてハラスメント防止が実現できた、特徴的な事例です。
コミュニケーション改善研修でハラスメントを予防したW社
W社は、主にクライアントの職場に開発エンジニアを常駐させる形で、相手方と一体となったIT開発を行う企業です。従業員の最も大切な2つの軸「自立」と「相互支援」を社内に浸透させる過程で、W社トップによる「あらゆるハラスメントを排除する」というメッセージが明確に示されました。
「感情」の伝達を意識して「お互いを受け止める」訓練を主体とした、コミュニケーション改善研修を取り入れることで、ハラスメント予防を目指した事例です。
継続的な研修でハラスメントを未然に防いだZ社
愛知県で運輸業を営むZ社は、世間的にハラスメントへの関心が高まる中、カウンセラーから研修実施を勧められたのを契機に対策へと乗り出しました。最初に取り組んだのは、管理職を対象としたハラスメント防止研修の実施です。
また、就業規定を見直す形でパワハラ防止規定を作成し、ハラスメントの定義や解決までの流れを明確化しました。小冊子配布を通じた周知・啓発や研修を継続した結果、管理職からは「言い方に気をつけるようになった」という意見も聞かれ、ハラスメント防止につながっています。
まとめ
パワハラ防止法の対象企業は従業員規模の大小にかかわらないため、相談窓口の整備や周知啓発に向けた取り組みをすぐに行う必要があります。
パワハラ防止法の遵守は、企業のコンプライアンス強化やリスクマネジメントのみならず、人材確保やブランド価値向上においても重要な課題となっています。従業員が安心して働ける環境は、離職率の低減や新たな発想の創出といったプラスの効果をもたらすためです。
企業規模や業種を問わず、ハラスメントの根本的な予防策を打ち出し、従業員一人ひとりが意欲的に働ける職場づくりを進めることが、これからの企業経営に欠かせません。
関連記事
Related Articles

ハラスメントの種類を徹底解説!3大ハラスメントや企業側の対処法も
この記事は2023.9.20に公開した記事を再編集しています2025年1月29日更新 ハラスメントは、他人に対する嫌...
ハラスメント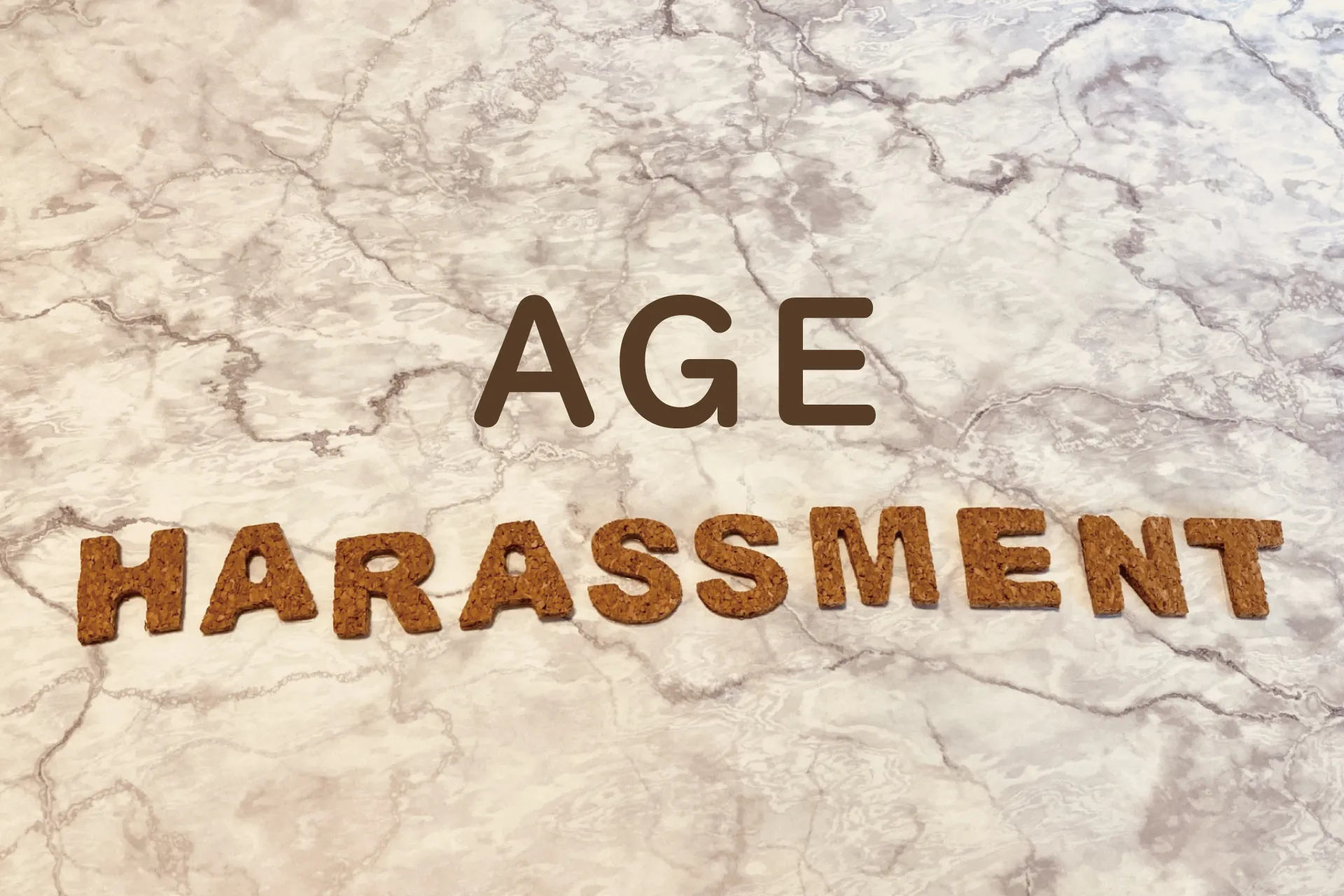
何気ない言葉もハラスメントかも?|エイジハラスメントにあたる事例を紹介
事業主によるハラスメント対策が義務化される中、ハラスメントにあたる事例について注目が集まっています。上の立場の人から...
ハラスメント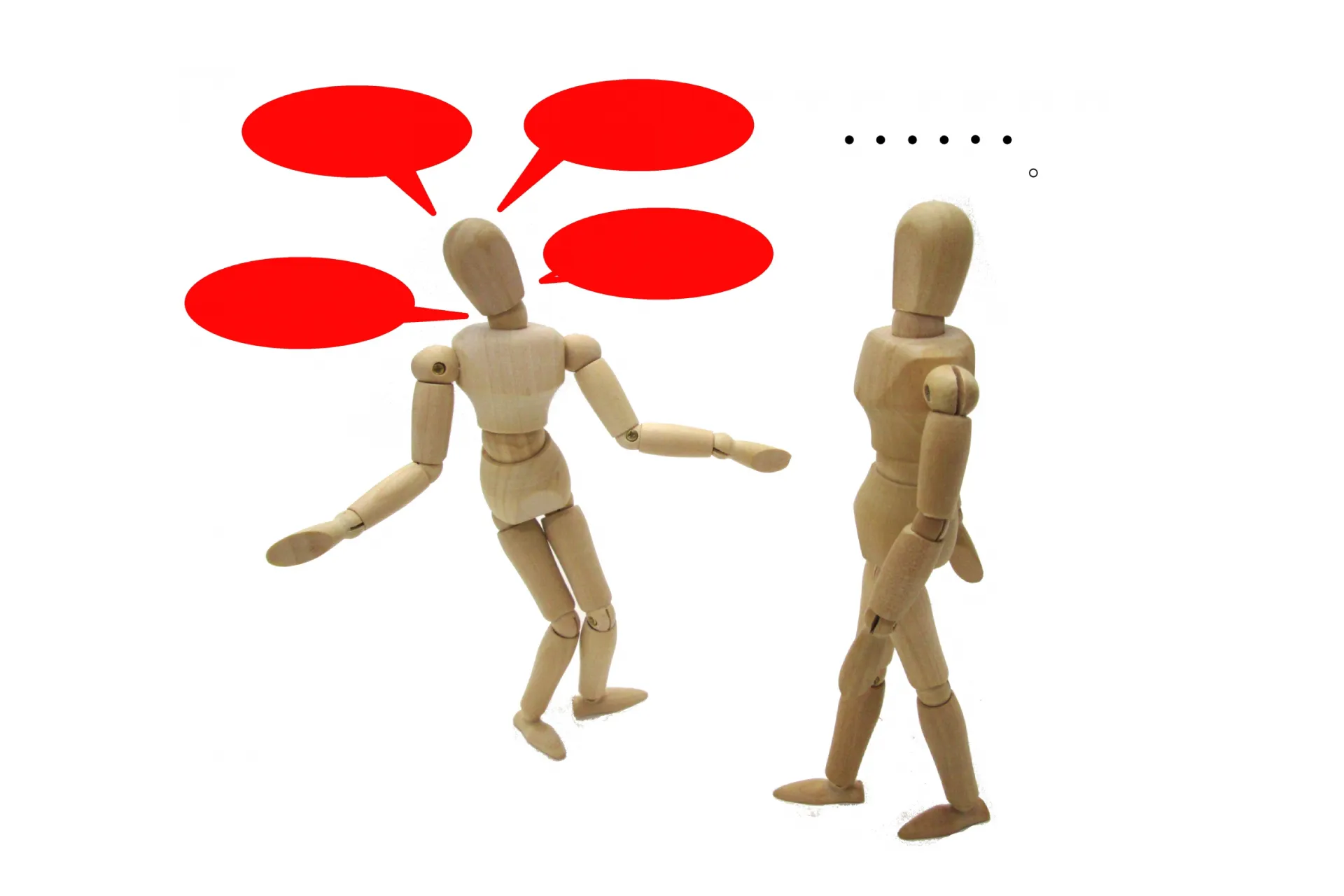
知らないと損する!セクハラする人の10の特徴と心理・対処法も解説
職場でのセクハラは、働く環境や従業員のメンタルヘルスに深刻な影響を与える問題です。セクハラをする人には特定の性格や行...
ハラスメント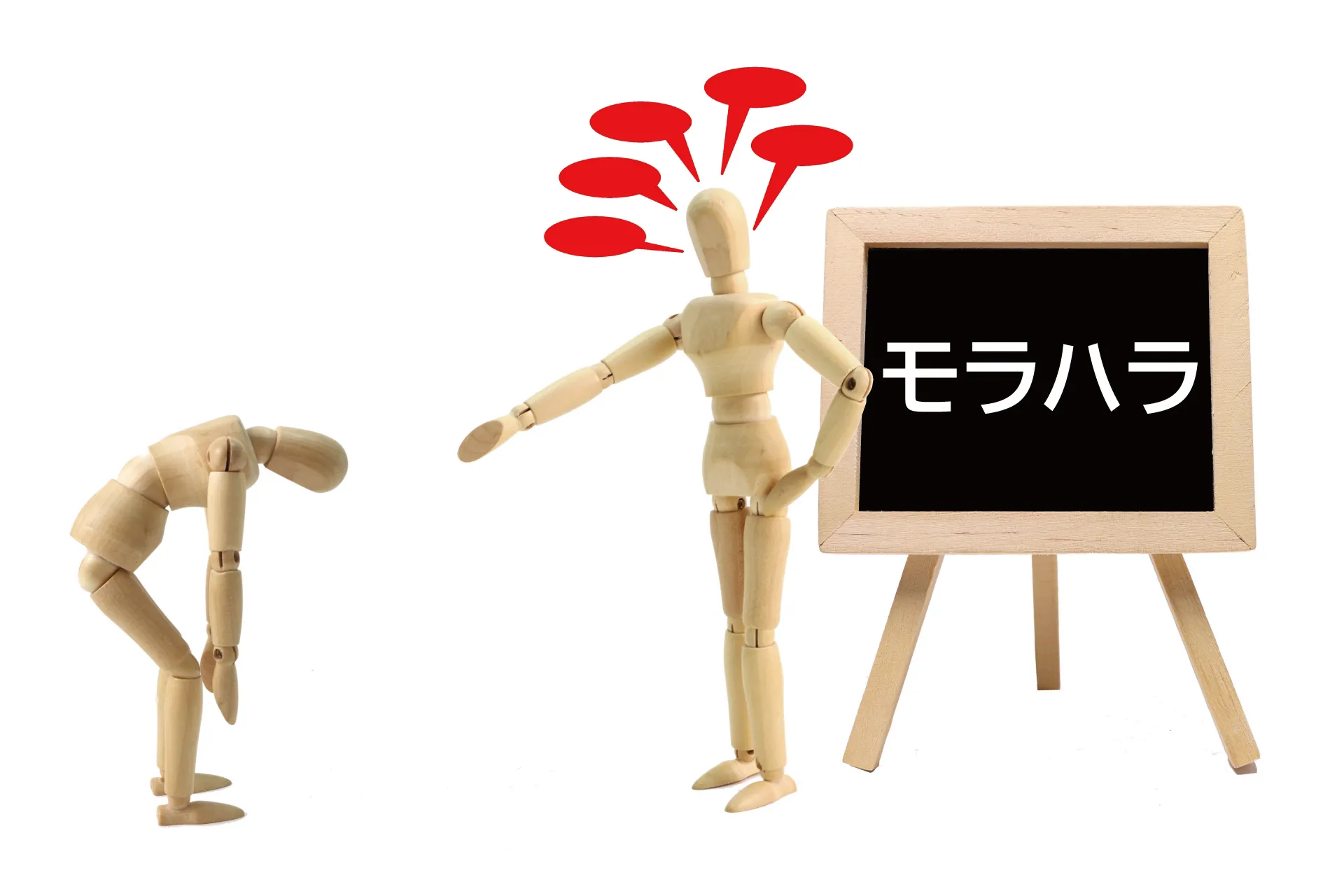
こんな人には要注意!職場のモラハラ上司の特徴と有効な6つの対処法
モラルハラスメント(モラハラ)は道徳や倫理に反する嫌がらせ行為のことで、言葉や態度による精神的な攻撃が該当します。上...
ハラスメント