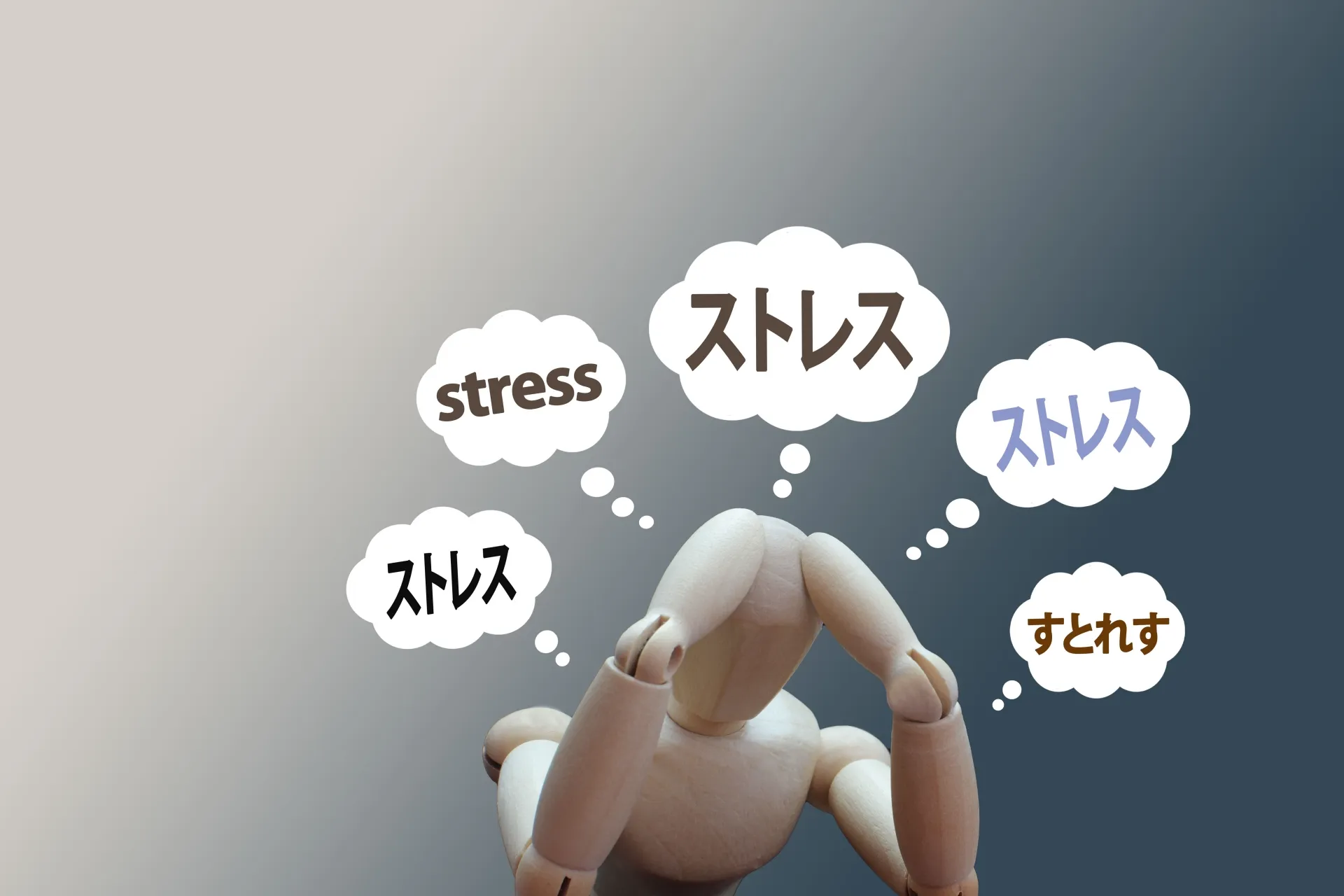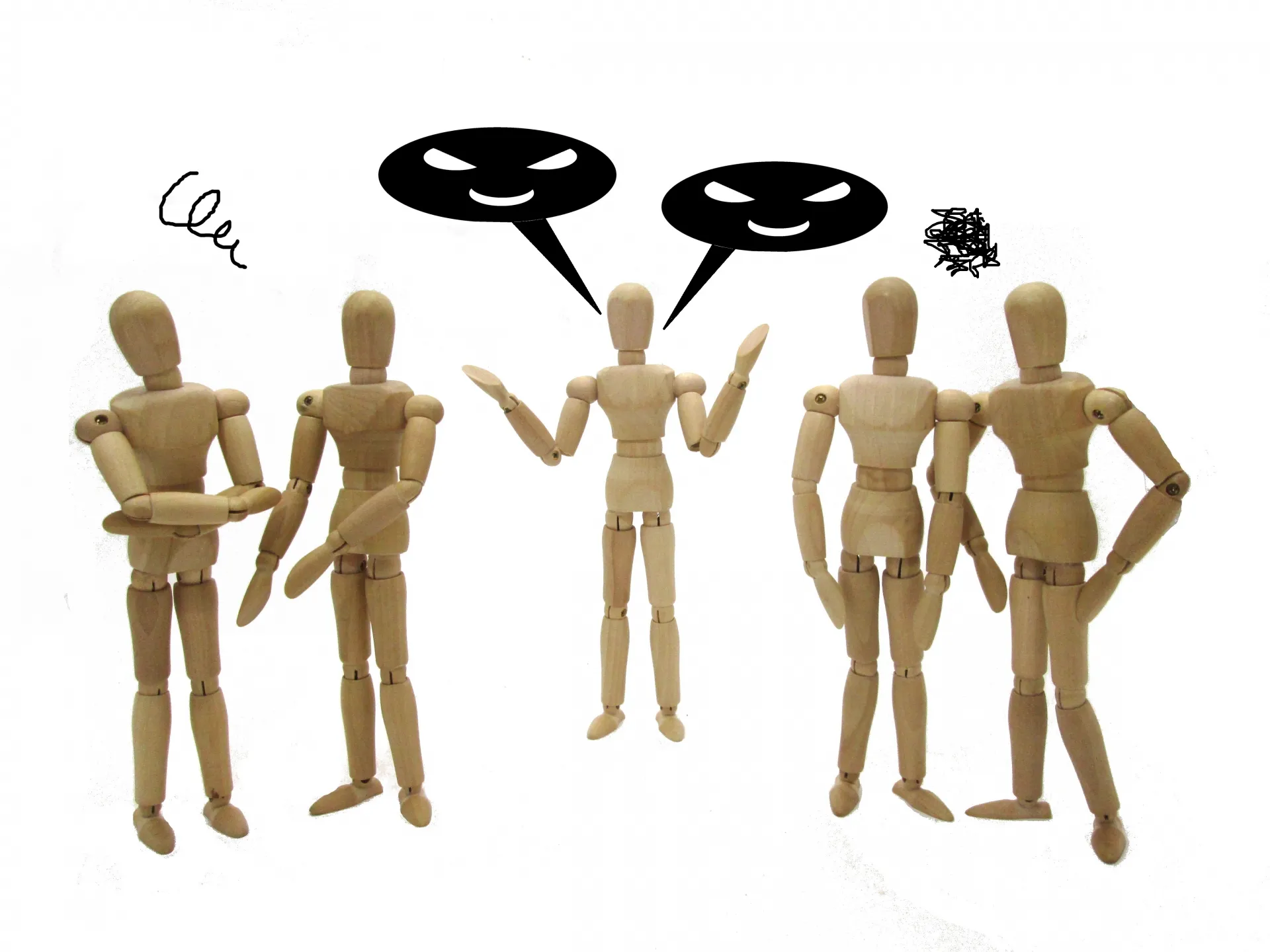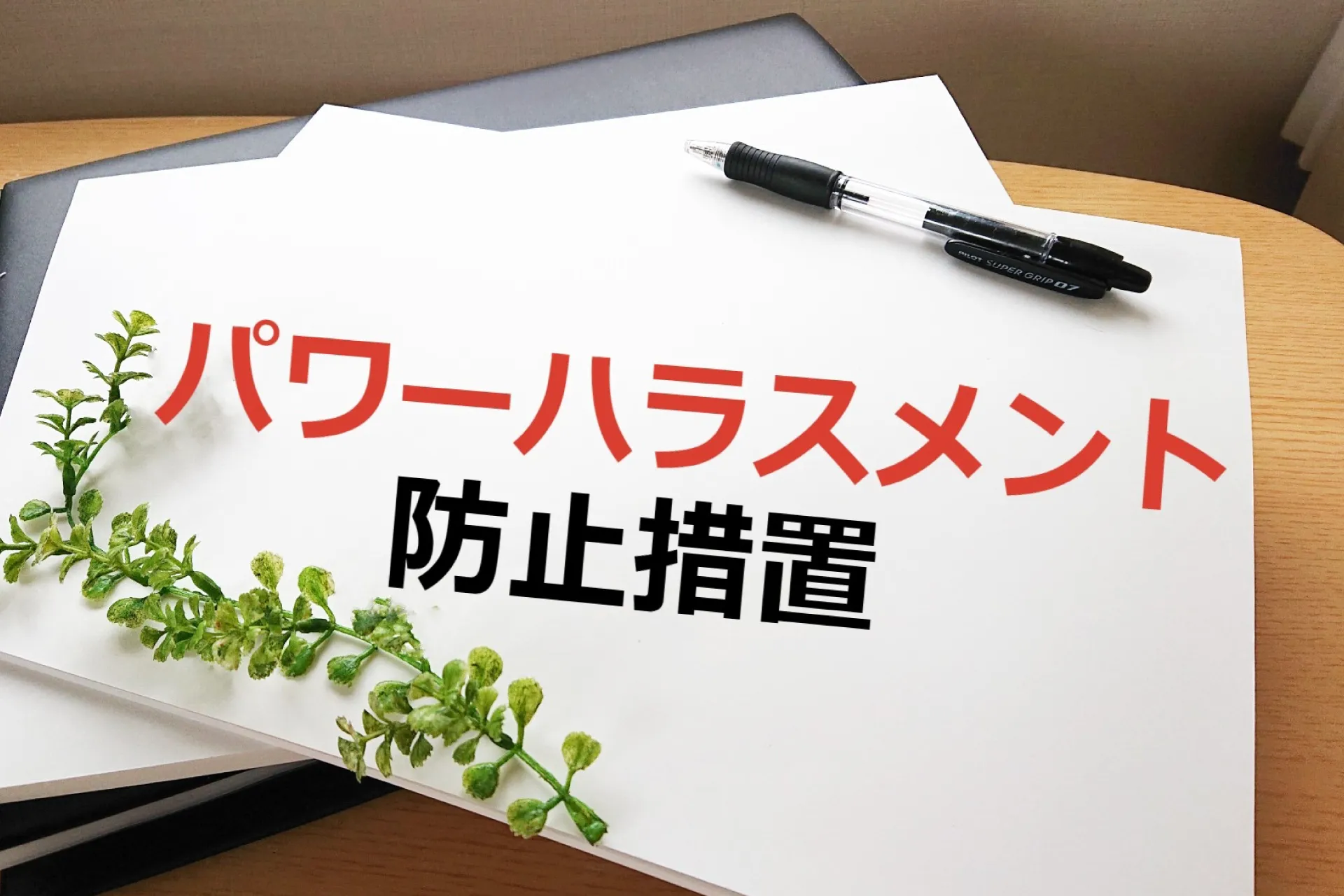- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- ハラスメント
- パワハラに当たらない事例とは?グレーゾーンや対策ポイントを解説
パワハラに当たらない事例とは?グレーゾーンや対策ポイントを解説

パワハラの境界線を明確にすることは、職場の健全な運営に欠かせません。特に、指導や注意がどこまで業務上正当で、どこからがハラスメントに当たるのかを理解しておくことで、無用な誤解を避けることができます。
この記事では、パワハラと認定される言動の具体例から、パワハラに当たらないケースやその判断基準について解説します。さらに、パワハラ防止のためのポイントも取り上げているので、社員が安心して働ける職場を作りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
Toggle『法的事例から学ぶ 管理・監督者向けハラスメント防止研修』について詳しくはこちら
パワハラとは

パワハラとは、職場内での地位や立場を利用し、部下や後輩などに過剰な要求や暴言、暴力などを行うことです。
ハラスメントは被害者の主観に基づいて判断されることが多いものの、客観的にパワハラが認められるには、パワハラの3要件を満たす必要があります。パワハラの3要件は、次の通りです。
| ・優越的な関係を背景とした言動 ・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 ・就業環境が害される言動 |
3要件を満たさない場合、「パワハラの被害を受けた」という訴えがあっても、パワハラが成立しません。
パワハラに当たる言動の6つの類型
パワハラに当たるとされる言動は、大きく6つのタイプに分類されています。パワハラの6つの類型は次の通りです。
| 身体的な攻撃 | 殴る・蹴るといった暴力行為 |
|---|---|
| 精神的な攻撃 | 同僚の前や他の人が見るメールなどでの罵倒 必要以上に長時間の叱責 など |
| 過大な要求 | 相手の能力に見合わない、難しい仕事や膨大な仕事を与える行為 |
| 過小な要求 | 相手の能力に見合わない、スキルを要しない簡単な仕事のみを与える行為 |
| 人間関係からの切り離し | 特定の人を、正常な人間関係を築けないように切り離す行為 物理的に1人だけ別室に移す・職場で無視する・飲み会や送別会に呼ばない など |
| 個の侵害 | 交際相手や家族などについて執拗に聞いたり悪口を言ったりして、プライベートを侵害する行為 |
上記のような行為が蔓延する職場では、直接の被害者だけでなく職場環境そのものが悪化し、周囲の社員の業務妨害にも発展する可能性があります。
職場でのパワハラに当たらない言動【グレーゾーンはどこ?】

被害者がパワハラであると感じる可能性があっても、実際にはパワハラに当たらないケースも少なくありません。ここでは、どのような言動であればパワハラに当たらないかを、パワハラ3要件に着目して解説します。パワハラに当たる言動・当たらない言動を把握し、多くの人が安心して働ける職場づくりを目指しましょう。
誤って相手にけがさせる
誤って相手にけがをさせるケースは、会社での立場や役職などにかかわらず、いつでも誰にでも起きうるでしょう。単なる事故であれば、優越的な関係を背景としていない上、業務上必要かつ相当な範囲を超えておらず、行為によって労働者の就業環境が害されないため、パワハラには当たりません。意図的に相手にけがをさせた場合はパワハラです。
例えば、工場での作業中に機械の操作を誤り、部下がけがをした場合はパワハラになりません。一方で、部下を脅そうとして意図的に操作をした結果相手にけがをさせた場合はパワハラになります。また、労災が起きやすいと分かっていたにもかかわらず改善せず、部下に命じて作業をさせた結果相手がけがをした場合は、パワハラとみなされやすいグレーゾーンです。
ただし、職場で事故や労働災害が頻発しているのであれば、パワハラとは別に職場環境を早急に改善する必要があります。
会社のルールを守らない人に注意する
会社のルールを守らない人を注意する行為は指導に当たり、業務上必要と見なされます。上司が部下を注意する場合は優越的関係ではあるものの、ルール違反を指摘するのは業務上必要な行為です。また、注意されても就業環境が害されるわけではないため、パワハラには当たりません。
例えば、遅刻を何度も行う課員を課長が呼び出して、常識的な範囲で注意と指導をし、「行動を改めないなら評価に影響する」と伝えるならパワハラではありません。
ただし、不必要に長く叱る・暴力を振るう・脅迫と受け取られる叱り方をするといった行為が見られる場合は、パワハラと見なされます。長時間の叱責や暴力、脅迫は業務上不適切かつ優越的な関係を利用した行動であり、労働者の就業環境が害される恐れがあるためです。
「遅刻を反省するまで部屋から出さない」と言い、休憩もなく丸1日別室に閉じ込めて叱責するならパワハラです。また、部下の態度に腹を立てて殴ったり、物を投げつけたり、「殺すぞ」など明らかに指導から逸脱した言動をしたりしたならパワハラになります。
「きちんとしろ!」などという気持ちを込めて肩をたたくなどの行為も、相手の受け取り方によってはパワハラと扱われる可能性もあるグレーゾーンのため、避けるのが無難です。
業務上必要な高いレベルの業務を任せる
会社では、部下や後輩を育成する目的で高いレベルの業務を任せる場合があります。業務の割り振りは上司や先輩に与えられた職権によるため、優越的な関係による行為と見なされます。
ただし、育成は業務上必要であり、部下や後輩に高いレベルの業務を任せてもパワハラには当たりません。業務の遂行にあたって上司や先輩から適切な指導やサポートを受けられれば、労働者の就業環境の侵害にも当たらないでしょう。
ただし、単純に自分の仕事を押し付ける行為や、1人で対応できない量の業務を与える行為はパワハラです。また、たとえ育成目的でも達成不能なほどのノルマを与えたり、異常な難易度の業務を行わせたりした場合は、グレーゾーンではあるもののパワハラ扱いされる可能性が高くなります。適切にサポートすることに加えて、本人が自己申告で「このレベルはまだ難しい」と言える環境を作る、など意思表示しやすい形をとるのがベターでしょう。
育成や面談のため個室で指導をする
育成・面談目的から個室で指導するのは、指導する側の優越的な立場を背景とした行為です。また、部下や後輩が個人面談の必要を感じていなかったり、指導の意図を納得していなかったりする場合は、就業環境が害されているとも解釈できます。
目的が社員の育成や目標設定などの面談であれば、業務上必要であると考えられ、パワハラではないと見なされます。ただし、指導にあたって人間関係を切り離す目的で個室から出さない・育成とは無関係な叱責を行う、といった行動が見られる場合は、パワハラです。
例えば、期末目標を達成できておらず、やる気が見られない部下に向けて短時間個室で指導と注意をするのはパワハラではありません。
一方で、育成や研修のためと称して別室での業務を命じ、達成するまではチームの飲み会に呼ばない、などの行為はパワハラになります。ほかにも、「期末目標を達成できなかった反省文を毎日5000字書け」など、明らかに指導から逸脱した業務命令をするのはパワハラです。別室で1人だけ業務を行わせるのは、人間関係の切り離しにつながり、パワハラとみなされるグレーゾーンのため、長時間にわたって隔離するような行為は避けましょう。
パワハラと認定されなかった裁判例

被害者がパワハラを訴えたものの、裁判の結果パワハラと認定されなかった事例もあります。ここでは、パワハラに認定されなかった裁判の事例を紹介します。
| ボーダフォン(ジェイホン)事件 |
| うつ病にかかっていた労働者が、会社から異動を命じられた後に自殺にいたった事件です。背景としては、保守センターと技術センターの責任者が退職するにあたって、当該労働者が2つのセンターの責任者を兼任する形での異動を会社側が命じました。しかし、労働者は負担が大きすぎるとしてこれを拒否、会社側の責任者が叱責した結果、自殺にいたっています。 労働者は家族に「暴言を受けた」「過剰な要求を受けた」と伝えており、自殺の背景としてパワハラを疑った遺族が訴えを起こしました。 裁判にあたっては、会社は異動の際に業務量や業務内容を確認した上で、当該労働者でも十分にこなせると判断していたこと、サポートについても伝えていたことが明らかになりました。また、うつ病の罹患と会社の行為に関連性はないと判断された結果、会社側の命令は適切だったとして、パワハラ認定はされませんでした。 |
| 社会福祉法人県民厚生会事件 |
| デイサービスセンターのセンター長であった労働者が、上司である理事からのパワハラによって適応障害に陥ったとして法人を訴えた事件です。事件の背景としては、理事が労働者に向けて、利用者数が伸び悩んでいることを理由にチラシ配りをさせるほか、助成金の不正受給を行うよう命じたために心身に不調が起きたという事情があります。 裁判では理事の言動が注目され、理事の言動そのものは職務遂行目的で行われ、内容も不当でないと判断されました。不正行為そのものは認められましたが、労働者への嫌がらせのため不正行為を行ったものではないとして、パワハラ認定はされませんでした。 なお、原告の適応障害自体は、業務による症状であると労災認定がなされています。 |
パワハラがあるように見えるケースや、疾患が労災認定されているケースであっても、上司や先輩の行動が不当と認められない場合はパワハラと認定されません。
パワハラにならないためにチェックしたい対策ポイント

正当な行為であっても、相手や周囲の人にパワハラを疑われる場合があります。パワハラにならないようにコミュニケーションを取るには、次のような点をチェックしましょう。
| ・感情的に叱っていないか ・人前で叱責していないか ・相手の人格を否定する発言をしていないか ・部下や後輩の成長につながる内容を伝えられているか |
パワハラ防止には、アンガーマネジメントを意識しましょう。腹が立つことがあっても、頭の中で数字を数えたり深呼吸したりして自分をクールダウンさせるだけで、行きすぎた言動を抑えやすくなります。
相手に話す際には、よくない点や一方的な指示だけでなく、話している理由や現状の問題点などを明確に伝えると、相手に話の内容が伝わりやすくなります。相手がどのように理解したかをヒアリングするのも、話す側の意図を正確に伝えるには有効です。
相手の立場になって考えるのが苦手な人は、パワハラにつながる言動をしやすい傾向があります。特に上司と部下、先輩と後輩では大きく立場が異なるため、相手の立場になるのは難しいでしょう。相手の立場を理解するには、自分の言動を振り返って「同じことをされたらどう感じるか」を落ち着いて考えてみるのが大切です。
また、新人や年次が浅い社員は基本的に知識や経験が少なく、上司や先輩の知識レベルで話す内容が理解できないケースもあります。部下や後輩がすぐに自分と同じレベルになるのは難しいと考え、相手の知識やスキルのレベルを探り、適切な言葉選びや説明を行いましょう。
『言ってはいけない言葉のパワハラ一覧!パワハラの判例についても解説』について詳しくはこちら
『法的事例から学ぶ 管理・監督者向けハラスメント防止研修』について詳しくはこちら
まとめ
パワハラの有無を判断するには、法律や裁判例に基づく客観的な基準が重要です。しかしながら、主観的には業務上の指導や注意と思える場合でも、客観的に見ればパワハラとなるケースも少なくありません。研修などで自分を客観視する訓練をして、特に指導を担当する従業員が相手の気持ちを理解できるようにするのが大切です。
指導内容を具体的に説明し、相手の理解を確認するプロセスを取り入れることで、健全なコミュニケーションを実現できます。さらに、アンガーマネジメントを身に着けてもらえば、感情に左右される言動を防ぐことが可能です。お互いの立場を尊重し合い、働きやすい職場づくりを目指しましょう。
関連記事
Related Articles
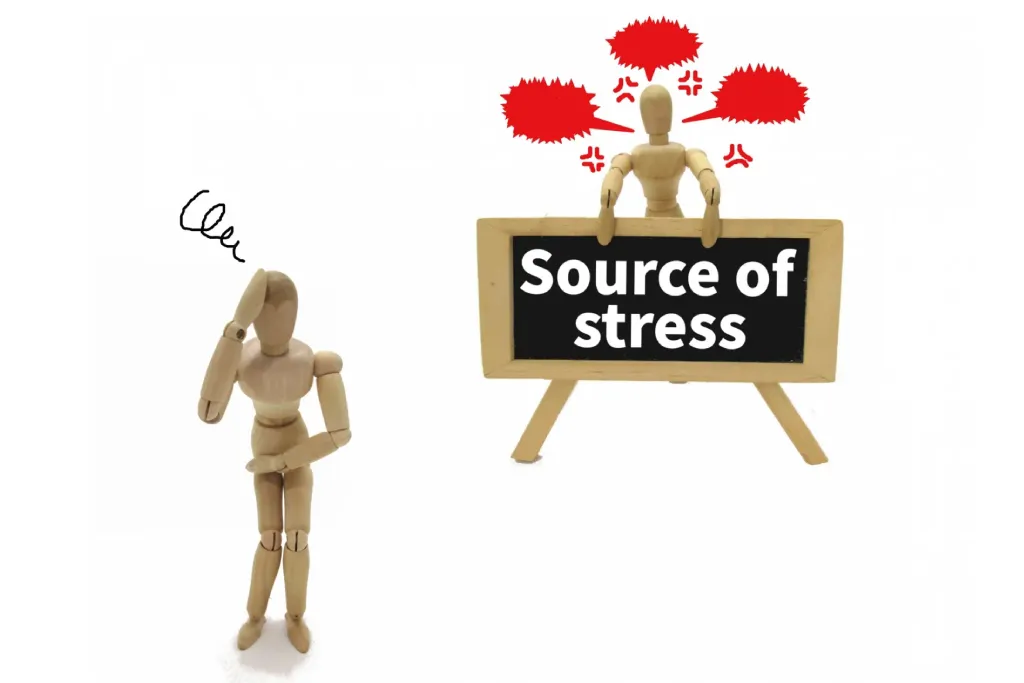
言ってはいけない言葉のパワハラ一覧!パワハラの判例についても解説
言葉によるパワーハラスメント(パワハラ)は、相手の人格や能力を否定する言葉や、仕事や職場からの排除を示唆する言葉、相...
ハラスメント
加害者・被害者になる前に!パワハラチェックリストの設問や項目を紹介
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)は、加害者・被害者ともに自覚がないまま進行するケースが少なくありません。近年は...
ハラスメント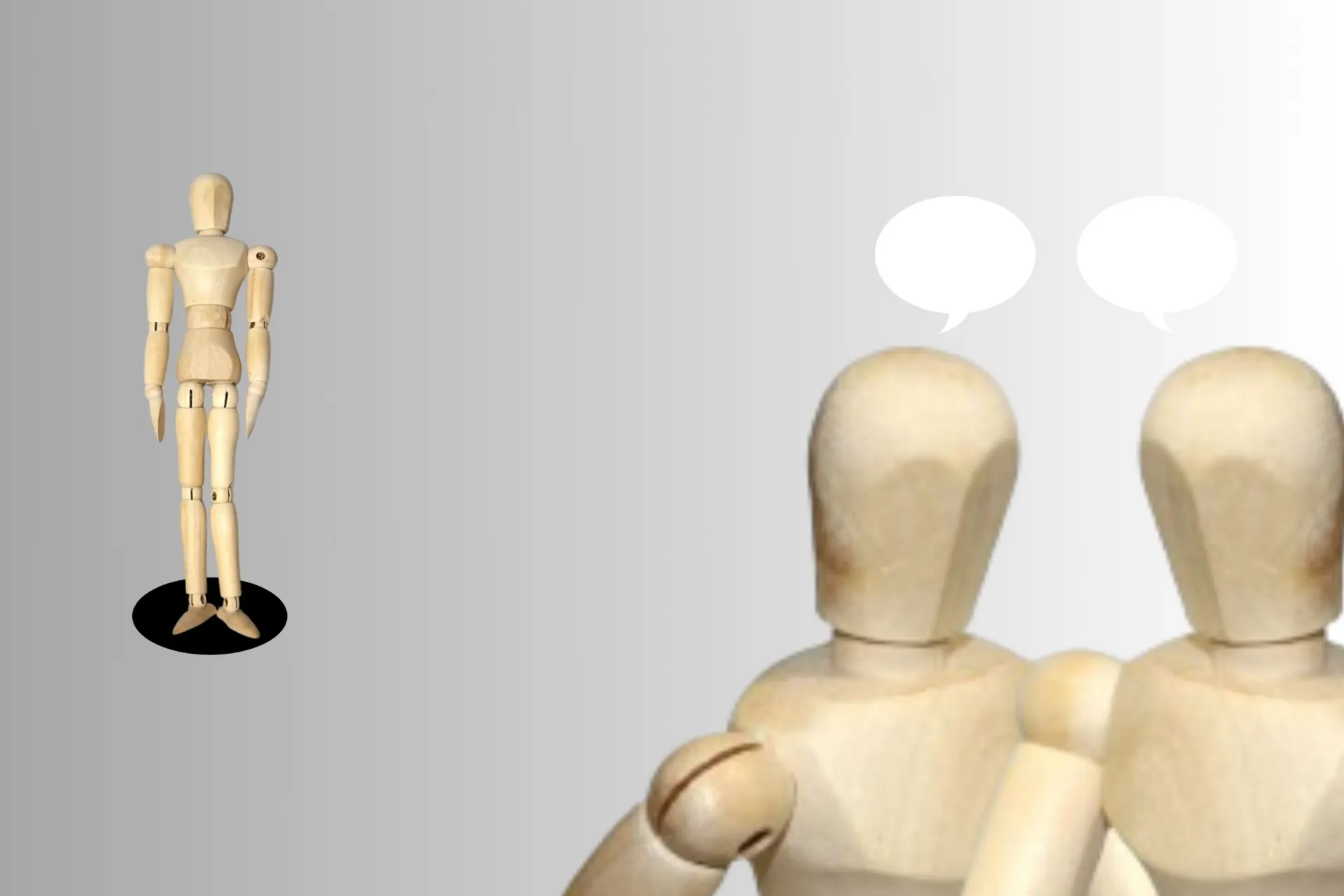
優しさがハラスメントに?ホワイトハラスメントの意味と具体例を解説
パワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)など、近年はさまざまなハラスメントに注目が集まる中...
ハラスメント