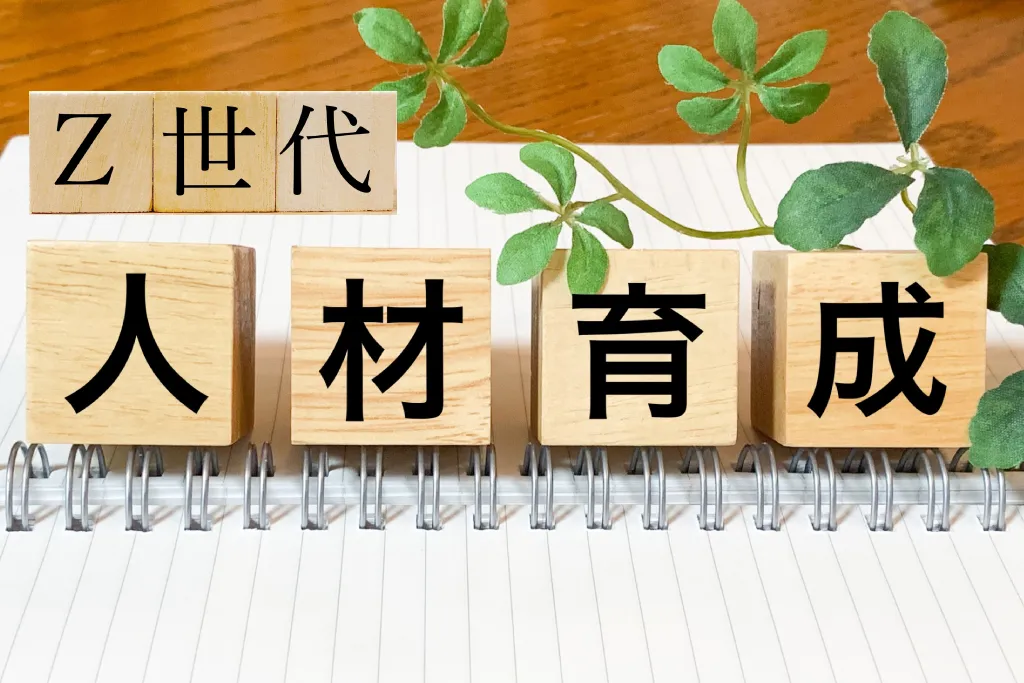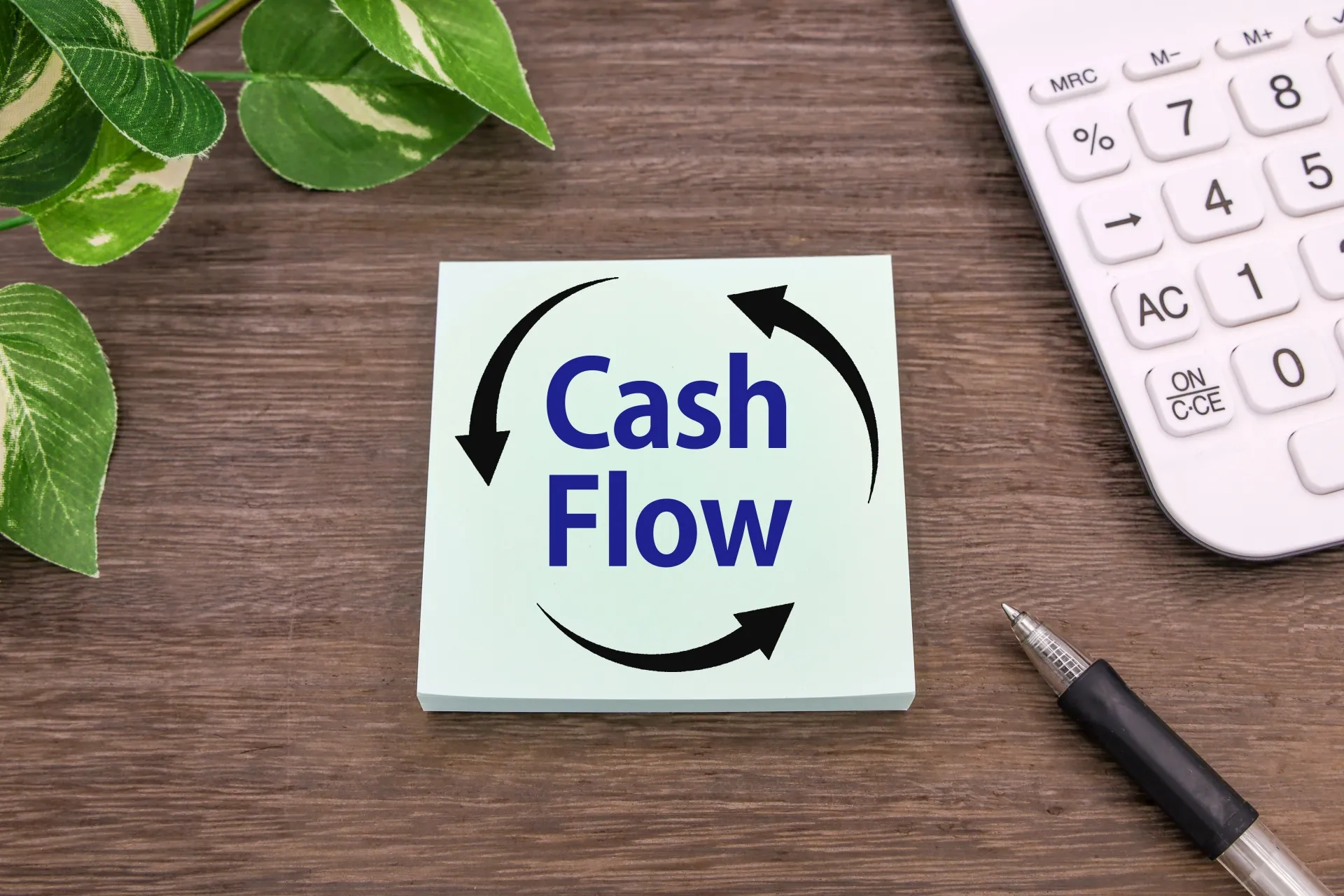- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 研修講師を選ぶポイント10箇条!失敗しない講師選定ガイド
研修講師を選ぶポイント10箇条!失敗しない講師選定ガイド

新人研修や管理職研修など、企業研修にはさまざまな種類がありますが、その成否は「講師選び」にかかっていると言っても過言ではありません。しかし、「有名講師に頼めば安心」「費用は高いほど研修教育効果がある」と思い込んでいると、現場の課題とずれた研修になる恐れがあります。
この記事では、社内講師・社外講師の違いや、それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、失敗しない研修講師選定のポイントを解説します。自社の成長に直結する研修を実現したい経営者や人事担当者・教育担当者の方は、ぜひご一読ください。
目次
Toggle研修講師とは?

研修講師とは、企業や団体が実施する社員研修やセミナーにおいて、受講者の成長と業務スキルの向上を支援する専門家です。単に知識を教えるだけでなく、研修プログラムの設計から教材作成、進行、理解度の確認、アウトプット支援まで、学びのプロセス全体に関わります。講師の力量や人間性は、研修の効果を大きく左右します。
研修講師の種類

研修講師には、社内の社員が務める「社内講師(内部講師)」と、外部から招く「社外講師(外部講師)」があります。ここでは、それぞれの特徴や選び方のポイントを解説します。
社内講師
社内講師とは、自社の社員や管理職、経営層が講師を務める形態です。企業理念や行動指針、業務ルールなど、自社固有の情報を伝える研修テーマに適しており、研修の内製化によってノウハウの蓄積やコストの削減にもつながります。
たとえば、新入社員研修や業務マニュアルの共有・企業文化の浸透を目的とした研修では、社内講師の活用が効果的です。ただし、専門的な知識や体系的なビジネススキルを伝えるには限界もあるため、研修内容や目的に応じた使い分けが重要です。
社外講師
社外講師とは、企業や団体が外部から招へいする専門の研修講師のことです。多くの場合、豊富な指導経験と専門分野に関する知識を持ち、さまざまな業界や企業での実績を生かして研修を行います。
社外講師は、社内講師では補いきれない分野や、より客観的な視点が求められるテーマにも対応できるのが特徴です。たとえば、最先端のビジネストレンドやスキルに関する研修、資格取得を伴う分野、MBA的な知見が必要な内容などに適しています。管理職層の研修では、社外講師ならではの視点や異業種の事例を通じて、新たな気付きを与える効果も期待できます。
『ビジネス基礎力の筆頭!ロジカルシンキング研修』について詳しくはこちら
社内講師のメリット・デメリット

社内講師は、自社の社員が研修を担うことで、現場に即した教育を実現できる点が特徴です。実際の業務経験をもとに内容を構成できるため、受講者にとって実践的で納得感のある学びが期待できます。一方で、講師の育成や業務負担などの課題も存在します。
| メリット | ・自社の実情に即した研修内容にできる ・研修後のアフターフォローがしやすい ・スケジュールや場所の変更に柔軟に対応できる ・外部委託に比べてコストを削減できる ・講師自身のスキル整理・成長にもつながる |
| デメリット | ・研修資料作成など、担当者に大きな業務負担がかかる ・講師と受講者の関係性により本音を言いにくい場合がある ・候補者が見つかりにくく、質にばらつきが出やすい ・外部委託に比べて新鮮味や客観性に欠ける場合がある |
たとえば、キヤノン株式会社では、社内講師を養成・育成する仕組みを整え、約8割の研修を内製化しています。現場の事例共有や継続的なフォロー体制、講師同士のブラッシュアップの機会を通じて、質の高い研修を社内で実現しています。
社外講師のメリット・デメリット

社外講師は、豊富な知識と経験を持つプロフェッショナルとして、社内では得がたい視点やスキルを提供してくれる存在です。高い専門性を持ち、研修の質や参加者のモチベーションにも好影響を与えますが、費用や社内事情への理解度など、注意すべき点もあります。
| メリット | ・最新の知識やトレンドを取り入れた内容を提供してくれる ・社内にない視点や専門スキルを学べる ・社外の立場から、忖度なく課題を指摘できる ・講師の経験談が社員の気付きを促す可能性がある ・講義の準備や資料作成などの負担を軽減できる |
| デメリット | ・社内事情を理解していないと、内容が実情に合わない場合がある ・講師とのスケジュール調整や内容のすり合わせに手間がかかる ・講師によって研修の質にばらつきがある ・講演料や交通費などのコストがかさむ |
たとえば、三井住友海上火災保険株式会社では、社員の自律的な学習を重視し、社外講師の力を活用した多様な研修プログラムを展開しています。オンラインでの受講やオープンカレッジ機能により、全国の社員が柔軟に学べる仕組みを整えました。講師の質の高さと運営の効率性を両立させることで、多様なニーズに応える人材育成を実現しています。
研修講師を選ぶ前に確認したい項目

研修講師を選定する前に、自社の課題や研修の目的をあらかじめ明確にする必要があります。ここでは、講師選びを成功させるために押さえておきたい事前の確認項目を解説します。
社内で抱えている課題を洗い出す
社内のコミュニケーション不足や情報管理意識の低さなど、まず自社が抱えている課題を正確に把握しましょう。組織によって、直面している課題は異なります。
課題を洗い出した上で優先順位を付けて整理することで、研修の目的が明確になり、講師や研修内容の選定もスムーズに進められます。課題の可視化には、社員アンケートや既存研修の振り返りなどが有効です。
研修の目的を決めて正しく理解する
目的が曖昧なままでは、研修の効果が発揮されにくく、講師選びや内容設計も迷走します。また、経営層と現場の課題意識がずれていると、研修の意義が伝わらず、効果も半減しかねません。
企画担当者だけでなく、受講者・上司・経営層など関係者全員が目的を共有することで、研修への納得感が高まり、受講者のモチベーションも向上します。たとえば、新入社員なら社会人意識の定着、中堅社員なら視野拡大、管理職ならマネジメント力強化など、階層に応じた具体的なゴール設定が求められます。
講師を社内・社外から呼ぶのか決める
社内講師と社外講師の選択の基準となるのは、研修の目的や内容、自社にあるノウハウの有無です。企業の理念や社内ルール、業務プロセスなど、社内に十分な知識や経験があるテーマは、社員による社内講師のほうが実情に即した指導ができ、費用も抑えられます。
一方で、自社にノウハウがないテーマや、業界トレンド・外部の視点が必要なテーマは、社外講師を選ぶことで高い専門性や新たな価値観を取り入れられます。また、社外研修は意識改革や視野拡大など、受講者に刺激を与える機会としても有用です。研修の種類や目的、受講者の特性に応じて最適な講師を選定し、必要に応じて外部の力を活用すると、研修効果を最大化できるでしょう。
外部から研修講師を呼ぶ場合は研修会社を選ぶ
研修の目的や、講義形式やワークショップ形式など希望のスタイルを明確にしたら、それに合うプログラムを提供している研修会社を絞り込みましょう。研修プロデュース会社なら手厚いサポートが期待でき、専門会社なら高い専門性に基づくサービスを受けられます。
実績や講師の質・プロフィール、カリキュラムの柔軟性、アフターフォロー体制などを確認し、総合的に判断することが大切です。また、研修サービスの費用が予算内か、研修コンテンツのカスタマイズが可能かも事前にチェックしましょう。
『ゼロに近づける!ヒューマンエラー防止研修』について詳しくはこちら
社内の研修講師を選ぶポイント

社内講師を選ぶ際は、研修内容に対する知識やスキルだけでなく、受講者との関係性や伝える力も重要な要素です。ここでは、社内講師選定時に確認すべきポイントを解説します。
研修内容に対するノウハウや専門知識があるか
社内講師がテーマに関する実務的なノウハウや専門知識を有していると、自身の経験談を交えて説明できるため、研修内容への納得感や理解度が高まります。受講者から質問があった際には、正確かつ具体的に回答できるでしょう。
社内講師には、自社の業務フローや文化を熟知しているからこそ伝えられるリアルな視点が求められます。資格の有無にこだわる必要はありませんが、対象となる分野での実績や経験を持ち、分かりやすく伝える力があるかを事前に確認しましょう。現場や上司からの推薦や過去の業務成果も参考にしながら、テーマに適した人材を選ぶことが、効果的な研修につながります。
コミュニケーションスキルがあるか
研修はただ講師が一方的に話すのではなく、受講者との対話や反応のキャッチボールを通じて進めるものです。そのため、受講者の表情や反応から理解度を読み取り、話し方や進行を柔軟に調整する力が求められます。また、社内講師が親しみやすく、明るく分かりやすい話し方をすることで、受講者の興味関心や集中力を高める効果も期待できます。
豊富な専門知識があっても、高圧的な態度や聞き取りづらい話し方では受講者が萎縮し、研修の効果は半減します。受講者が安心して質問や意見を述べられる雰囲気をつくれることも、コミュニケーション能力の一部です。知識と人柄の両面で、スムーズに意思疎通ができる人材を選びましょう。
受講者との距離感が近いか
受講者が研修内容をしっかり理解し、自らの業務に生かせるようになるには、社内講師が受講者の目線に立って丁寧に指導する必要があります。講師が受講者の立場を理解し、悩みや課題に共感できる存在であれば、受講者も安心して質問や意見を出しやすくなります。
特に、自分と同じ部署や近いポジションで働いた経験のある社内講師なら、現場の状況を踏まえたアドバイスや実践的な知見を共有でき、受講者の納得感や信頼感も向上します。結果として、研修へのモチベーションが高まり、学んだ内容の定着にもつながるでしょう。
社外の研修講師を選ぶポイント

社外講師を選ぶ際は、専門性や実績だけでなく、自社との相性や柔軟な対応力も重要視することが求められます。ここでは、社外講師を選定する上で確認すべきポイントを解説します。
分野において最新の動向に詳しいか
ビジネス環境は日々変化しており、研修内容が現場の実情にマッチしていなければ、受講者の学びは一過性で終わる恐れがあります。特にITやマーケティングなど変化の早い分野では、業界トレンドを正確に捉えた内容が求められます。
研修講師の経歴や活動実績、書籍・コラムの執筆、セミナー登壇歴などを確認し、知識のアップデートに積極的かを見極めましょう。本当に成果のある研修を行うには、受講者にとって「今現場で求められる知識」を得られる研修講師が理想です。
スムーズなコミュニケーションが取れるか
研修講師と依頼側の担当者との事前のやり取りの中で、円滑に意思疎通が図れる場合は高い研修効果が期待できます。研修は一方的な講義ではなく、受講者との対話や質疑応答によって進行します。
そのため、こちらの質問に的確に答え、要望を丁寧に汲み取ってくれるか、打ち合わせ段階から研修講師の傾聴力や柔軟性を確認しましょう。実際の研修現場を見学できる機会があれば、参加者とのやり取りや場の雰囲気づくりにも注目することでも、コミュニケーション能力の高さを測れます。
専門用語を多用せず説明が分かりやすいか
研修講師が難解な専門用語や略語を多用すると、受講者が内容に付いていけず、学びの効果が低下します。打ち合わせの際や、可能であれば模擬講義・過去のセミナー動画などを確認し、難しい言葉を平易な表現に言い換える力があるかをチェックしましょう。
また、受講者の理解度に合わせて説明のスピードや話し方を変えられる柔軟性もポイントです。専門的な知識があるだけでなく、それを伝える技術に長けていると、優れた研修講師と言えるでしょう。
具体例を挙げて解説してくれるか
実力のある研修講師は、理論だけでなく具体的なエピソードを交えて解説し、受講者の理解を深めます。実務に直結する内容の場合、現場で起こり得るシチュエーションや他社の事例も一緒に説明することで、受講者は自分事として捉えやすくなり、研修内容の定着率も向上します。
話が抽象的すぎると、研修後に「何を実践すればよいか」が不明確になりがちです。過去の講義内容に、具体的なストーリーや講師自身の現場経験に基づく話が含まれているかを確認しましょう。
研修内容を柔軟にアレンジできるか
研修講師が自社のニーズに応じて研修内容を柔軟にカスタマイズしてくれるかも重視すべきポイントの1つです。企業ごとに業種・文化・人材課題は異なるため、パッケージ化された内容をそのまま当てはめるだけでは研修の効果は限定的になります。
事前打ち合わせの際に、課題や背景を丁寧にヒアリングし、適切な提案ができる研修講師であるかを見極めることは大切です。企業側の要望に寄り添える研修講師は、当日も受講者の反応に応じて話題を切り替えたり、想定外の質問にも柔軟に回答したりしてくれるでしょう。
企業の風土や雰囲気に合っているか
どれだけ知識や実績を持っていても、研修講師が企業の風土や雰囲気に合わなければ、受講者に響かない恐れがあります。たとえば、形式張った進行が苦手な企業風土に、堅い口調の研修講師が登壇すると、受講者の集中力が続かず、研修効果は上がりません。
反対に、自由度の高い企業文化が根付いているなら、カジュアルな語り口や双方向のやり取りが得意な研修講師がフィットすることもあります。研修会社が複数の講師候補を提案してくれる場合は、実際に話して企業文化に合いそうな人材を選びましょう。
失敗経験を語れるか
受講者の共感を得られる研修講師は、成功談だけでなく失敗経験を語れる力も持つ傾向にあります。たとえば、研修講師が過去の苦労や試行錯誤を正直に語る中で、「自分も頑張ってみよう」と受講者が背中を押されることは少なくありません。
成功した方法論はもちろん、つまずいた経験や乗り越えた過去も語れる研修講師は、現場での実感や共感を生み、行動変容のきっかけをつくります。表面的なテクニックに終始するのではなく、人間味のある語り口で受講者の心を動かせるかどうかが、プロの講師としての真価と言えるでしょう。
研修が終わった後の対応・注意点

研修は実行して終わりではありません。研修後の振り返りやフォローが、着実な定着と成果につながります。ここでは、研修後に行うべき対応や注意点について解説します。
研修目的の達成度を確認する
研修が終わったら「受講者の満足度」「知識やスキルの理解・習得度」「業務への行動変化」「業績面の変化」という4つの視点で、当初設定した目的がどの程度達成されたかを必ず評価しましょう。
満足度や行動変化についてはアンケート調査、理解度は確認テストなどで測定できます。一方で、業績面での変化は時間がかかるため、研修の影響が現れる場面を長期的に観察する必要があります。定量・定性の両面から成果を評価すると、次回以降の研修改善にもつながります。
受講者からの声を収集する
研修終了後のタイミングで、「役立った点」「改善してほしい点」「講師の印象」なども含めて、受講者からの感想や意見をアンケートなどで収集しましょう。
満足度や内容の理解度だけでなく、改善点や講師についても尋ねることで、研修全体の質を客観的に評価できます。回答は集計・分析した上で、次回の講師選定やプログラム改善に反映させるとより効果的です。
研修講師へのフィードバックを行う
研修講師に受講者のアンケート結果や研修中の様子を共有することで、講師側も内容の改善や進行の工夫につなげることができます。研修講師にとっては自分の研修の成果を知る機会となり、より質の高い指導へのモチベーションになります。
また、受講者の反応だけでなく、企業としての要望や今後の方向性も伝えることで、次回以降の研修がより自社に合う内容になります。優秀な講師に次回も依頼したいと考えるなら、研修終了後のフィードバックは講師と企業の双方にとって価値のあるやり取りとなるでしょう。
まとめ
研修の成果を最大限に引き出すには、目的や課題を明確にした上で、講師選定を丁寧に行うことが必要です。社内講師は実務に即した内容を伝えられる一方、社外講師は最新トレンドや客観的な視点を提供できます。どちらにもメリット・デメリットがあるため、研修の目的と照らし合わせて適切な研修講師を選びましょう。
選定時は専門知識の有無だけでなく、受講者との相性や柔軟な対応力なども確認ポイントです。研修後には受講者の声や成果を分析し、講師へのフィードバックを欠かさず行うことで、次回以降の研修の質を高められるでしょう。
関連記事
Related Articles

【アイスブレイク鉄板ネタ9選】ビジネスですぐ使える事例を徹底解説
アイスブレイクとは、会議や研修、ワークショップなどの開始前に短い時間で行うアクティビティです。参加者同士の親睦を深め...
HRトレンド企業研修
なぜIQよりもEQが重要なのか|人生を幸福に導く心の知能指数の高め方
ビジネスでは、知能指数を示すIQだけでなく、EQも必要だと言われています。心の知能指数を表すEQが高い人は、自身の感...
HRトレンド企業研修