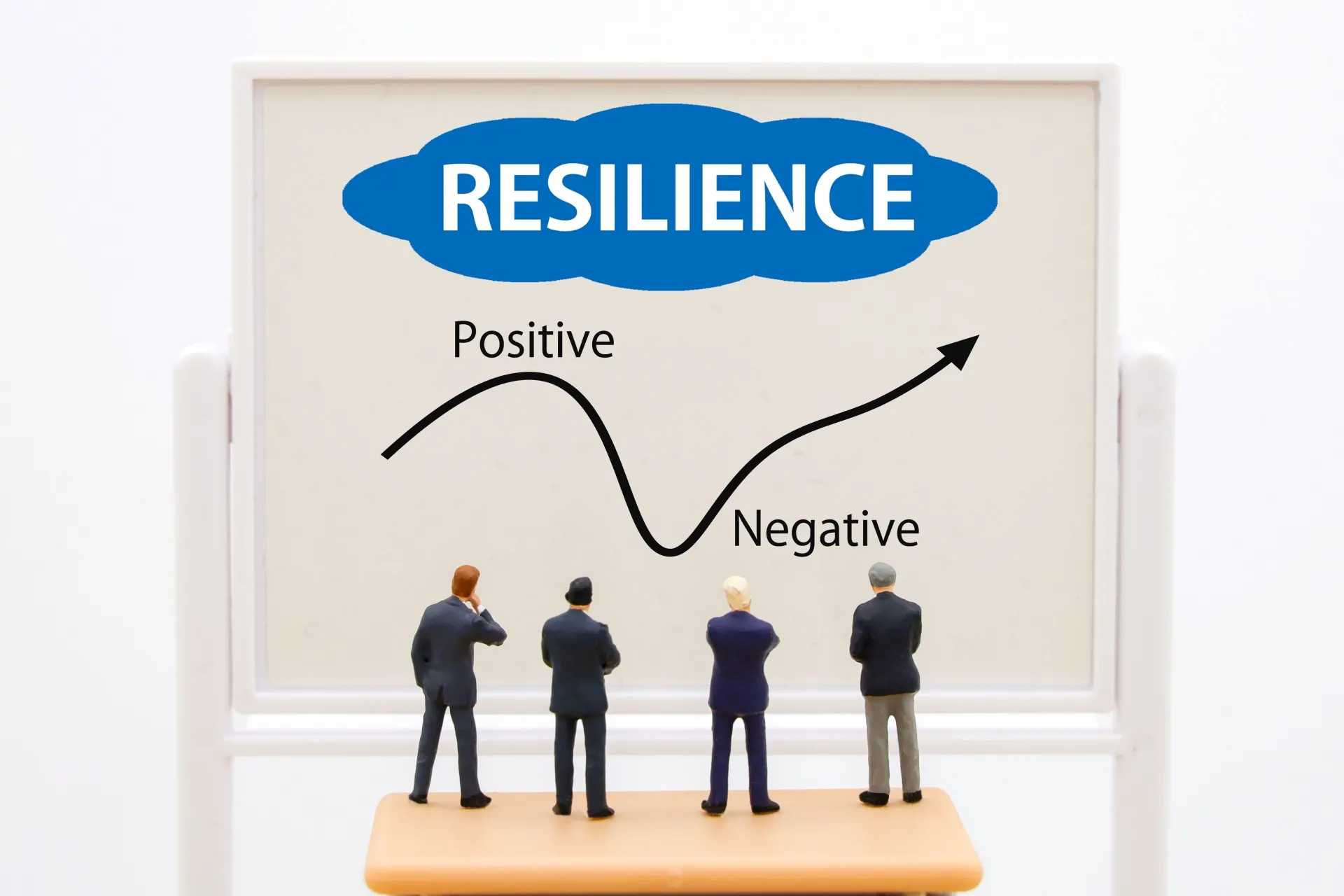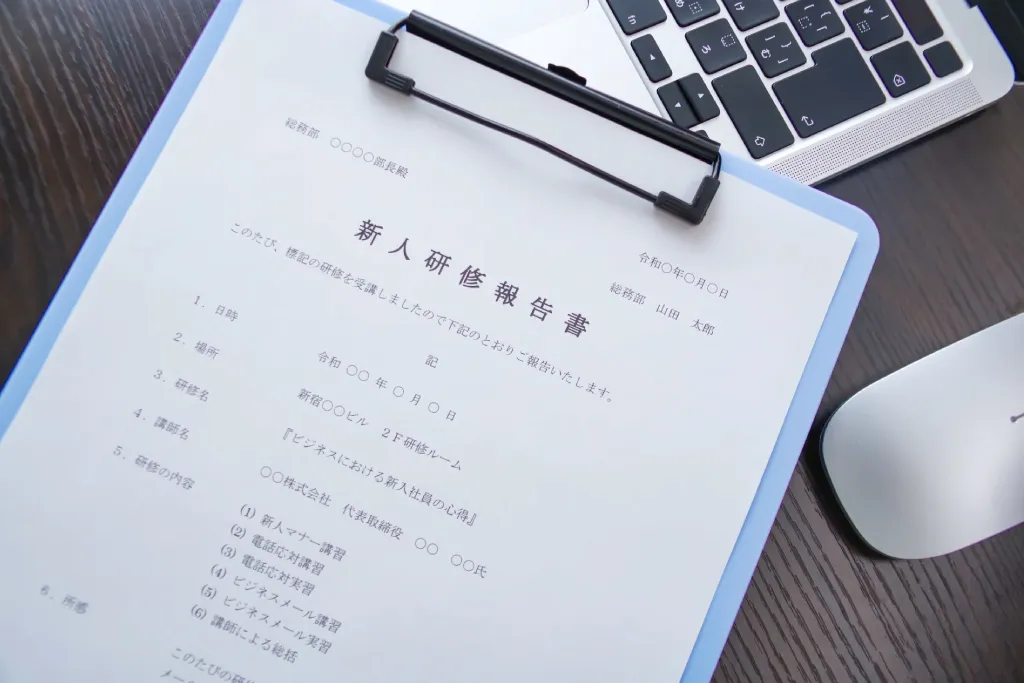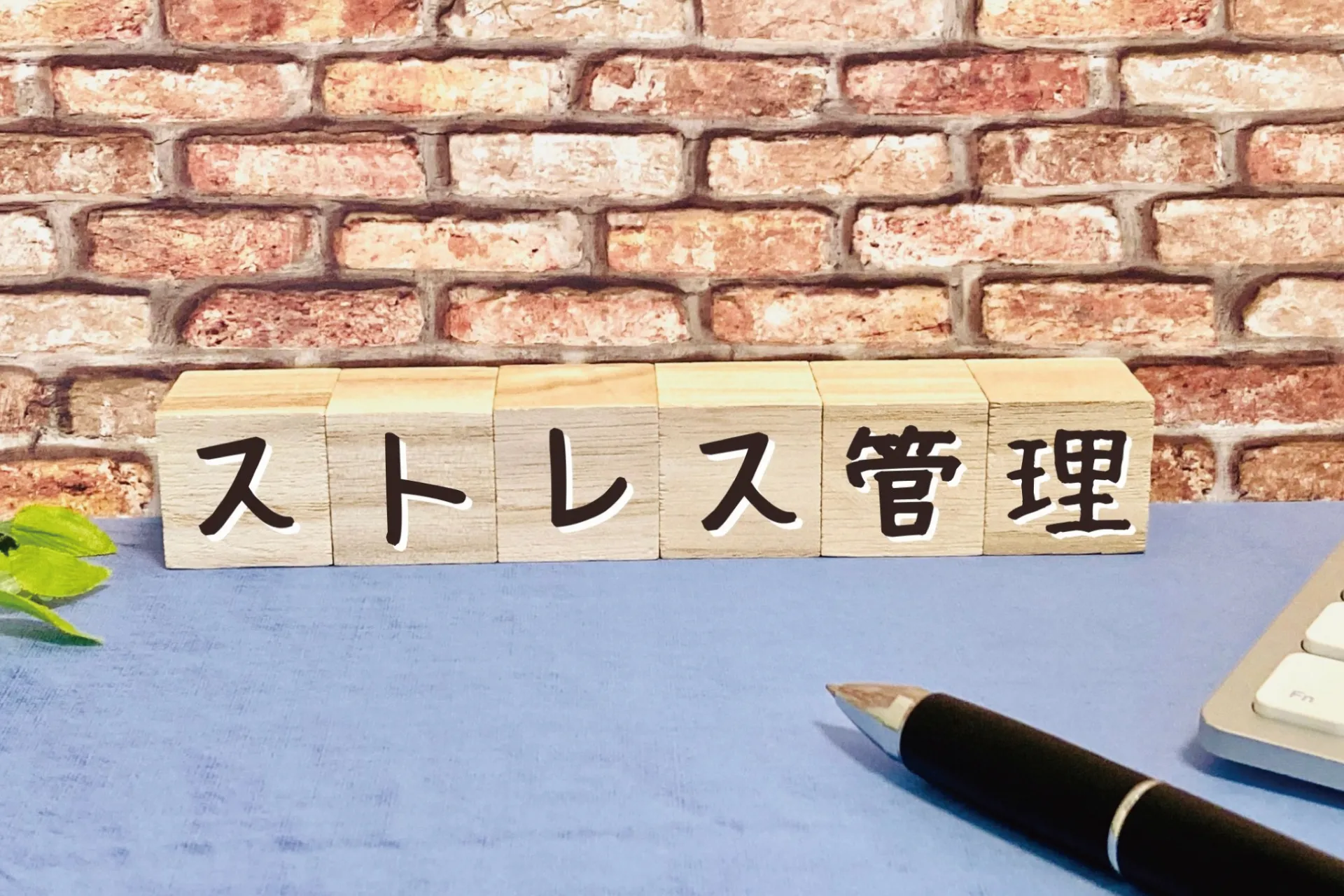- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 行動経済学とは?ビジネスで活用できる理論13個を具体例付きで紹介
行動経済学とは?ビジネスで活用できる理論13個を具体例付きで紹介
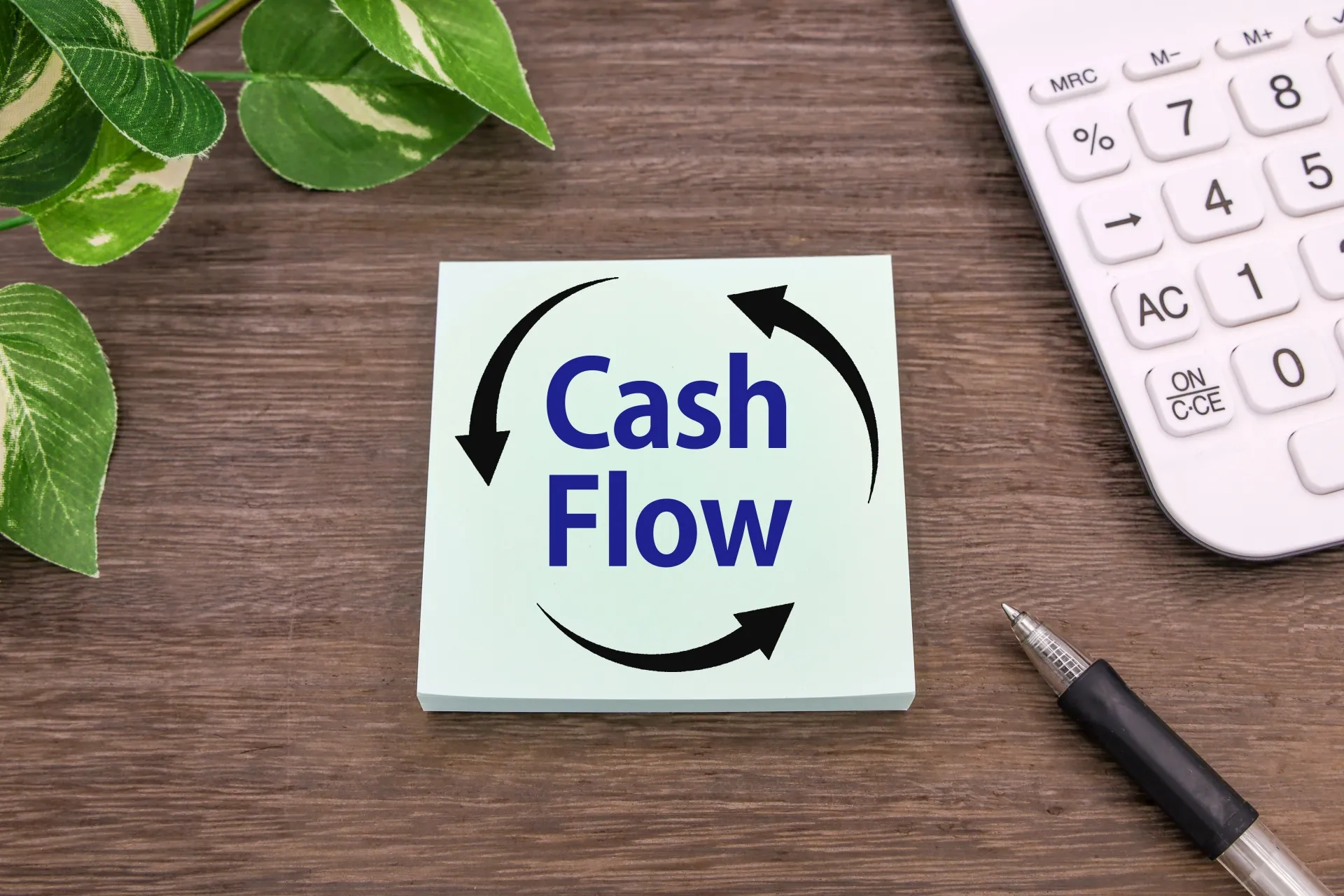
行動経済学は、人間がどのようにして意思決定をして、どのように行動を起こすのか、という視点に基づいて、人間の経済活動を研究する学問です。従来の経済学では、人々は常に理性を使って最良の選択をするものだと考えられていました。対して、行動経済学では人間がしばしば感情や直感に基づいて非合理的な判断を下すという点に着目し、人間の経済活動をモデル化します。
この記事では、行動経済学の主要な理論と、ビジネスでの活用方法について具体的な例を交えて紹介します。
目次
Toggle行動経済学とは

行動経済学とは、人間の行動特性に基づいて経済活動モデルを考える、心理学と経済学を融合させた学問です。人間が合理的に考えないという前提のもと、人間の行動心理に合わせて傾向を予測し、経済活動をモデル化します。
1979年および1984年に経済学者であるダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーが発表した2本の論文からスタートした行動経済学は、経済を考える上で必ず押さえるべき理論です。カーネマンとトヴェルスキーはこれら2本の論文でノーベル経済学賞を受賞しています。
行動経済学のベースとなったのは、人間の認知機能です。人間は、直感的に物事を判断する「システム1」と、熟慮して物事を判断する「システム2」の2つを持ちます。通常、人間は日常生活でシステム1を働かせています。とっさの判断を行うシステム1は、危険を避け、普段の生活をスムーズに送るのに必要です。しかし、本来システム2を働かせるべき熟慮のときにも、とっさに働いたシステム1に影響され、人間は「よく考えれば非合理的」な選択肢に飛びついてしまいます。
行動経済学は人間の非合理的な行動や心理効果を考慮して人間の行動パターンを考えるため、企業経営やマーケティング、人事などさまざまなビジネスシーンで活用できます。
行動経済学と経済学の違い
従来の経済学と行動経済学の違いは、人間の非合理性を想定しているか否かという点にあります。
従来の経済学では、「人間は常に合理的な選択をし、利益を最大化する」という考え方が基本です。この前提のもと、経済学者は「ホモ・エコノミカス(エコン、経済人)」という理想的な存在を設定し、理論を組み立ててきました。
エコンは一瞬で100%合理的に物事を考え、完全に合理的行動をとります。一見してばかばかしいことであっても、「そうするのが合理的だから」行動に踏み切る存在です。例えば、糖尿病リスクが高くなる甘いものを好んで人々が食べるのは、従来の経済学では「そのうち安価かつ簡単な糖尿病の治療薬が出る」と想定しているためだと説明されます。
一方で、現実の社会は従来の経済学モデルでは説明のつかない非合理的行動であふれています。甘いものの食べすぎはよくないと分かっていても、人間はついケーキやアイスクリームを口にしてしまうものです。特に、疲れているときにケーキの甘い香りが漂って来たり、夏の暑い盛りにアイスクリームが売られていると、つい買ってしまいます。
人間が状況や感情に左右され、必ずしも合理的な選択をしないことを理解し、背後にある心理的メカニズムを探るのが行動経済学です。
行動経済学では、人間が感情や直感、心理的な影響に基づいて意思決定を行うことを重視します。消費者は気分や雰囲気によって商品を選んだり、思いついて即決で購入したりするという前提で、どのような行動を人間が取りやすいのかに焦点を当て、理論を構築します。
行動経済学と心理学の違い
行動経済学は心理学の要素を持つ一方で、心理学とは異なる学問です。
行動経済学と心理学は、どちらも人間の行動を研究する学問ですが、そのアプローチや焦点においていくつかの違いがあります。心理学は、個人の心情や行動、言動を深く理解し、心の仕組みや精神的なプロセスを探る学問です。心理学の範囲は非常に広く、人間の精神的な反応や行動を多面的に解明することを目指します。
一方で、行動経済学は、経済的な意思決定に焦点を当て、特に人間がどのようにして非合理的な選択をするのか、背後にある心理的要因を解明します。経済学的な理論を基盤にしつつ、心理学の知見を活用して、実際の経済活動における人間の行動をより現実的に説明しようとする学問です。行動経済学は、経済活動における意思決定のメカニズムを理解し、それをビジネス戦略に応用することを目的としています。
行動経済学は、心理学のうち行動心理学や社会心理学、認知心理学などの狭い分野の考え方を経済学に応用した学問である、と言えるでしょう。
行動経済学と人事・マーケティング部門の関係
行動経済学の考え方は、ビジネス分野の中でも、特に人事部門やマーケティング部門で役立ちます。
人事領域では、人材の採用や評価制度、報酬体系の設計に行動経済学の知見が活用されています。就職や昇進の選考にあたって、非合理的な判断につながるシステム1の働きを抑え、熟慮するシステム2を使って考えるのは、公平な人事活動で必須です。ほかにも、従業員のモチベーションを高めるためには、福利厚生や報酬の改善をいつ、どういった形で伝えるべきか、といった場面でも行動経済学を活用できます。
マーケティング領域では、消費者の心理的バイアスや感情的要因を踏まえて、商品やサービスをどのように魅力的に提示するかを考える際に行動経済学が使われます。価格設定や見せ方を工夫すれば、人間がシステム1を働かせて、直感的に魅力を感じる販促戦略を立てることが可能です。行動経済学は、同じ商品、同じ情報を扱っても、消費者に与える印象をがらりと変えられるヒントになります。
行動経済学の理論を応用することで、消費者や従業員の心理や行動をより的確に理解し、効率的かつ効果的な戦略を打ち立てることが可能です。行動経済学を学ぶのは、ビジネスパーソンにもとても重要と言えます。
ビジネスで活用できる行動経済学理論の例

ビジネスで活用できる行動経済学理論は、極めて多種多様です。以下では行動経済学理論の中でも特に有名な13種類について解説します。
また、ビジネスでどのように活用できるのか、具体例も合わせて解説します。
アンカリング効果
アンカリング効果とは、最初に提示された情報や数字を基準(アンカー)として、その後の判断や意思決定が無意識に引きずられてしまう現象のことです。錨を海に下ろすと船が限られた範囲でしか動けなくなるように、最初に示される情報が強い影響力を持ち、後から登場する情報の相対評価がゆがんでしまいます。
例えば、1000万円のスポーツカーのオプションが15万円でも安く感じる一方、10万円のパソコンのオプションが15万円だと必要かどうか悩んでしまう場合、アンカリング効果の影響下にあります。
アンカリング効果は、ビジネス分野では、主に価格戦略で活用される理論です。例えば、お客様に複数の見積もりを出す場合、初めに高価格のプランを提示し、次に少し安いプランを提示すると「割安に感じる」心理が働き、契約に結びつきやすくなります。
ほかにも、人事分野では部下のモチベーションアップのためにアンカリング効果が使われます。例えば、「普段なら3営業日かかる仕事」などの形で事前に基準値を示した上で、「4営業日でできないか」と伝えると、ただ「4営業日でやってほしい」と伝えるよりも余裕を感じながら仕事に取り組めます。
おとり効果
おとり効果とは、選択肢が2つしかない場合に迷っていた消費者が、3つ目の「明らかに劣る(もしくは不必要に高い)選択肢」を提示されることで、特定の商品へ誘導されやすくなる現象のことです。
例えば「高価格・高機能な商品A」と「低価格・低機能な商品B」で悩んでいるときに、Aよりも割高で、かつBよりも中途半端な商品Cが登場すると、消費者は「Cは選ばない」と判断しやすくなり、結果的にAを選ぶ可能性が高まります。
ビジネスでは、松竹梅の3プランを提示する形で、おとり効果がよく使われます。例えば、月2000円の松プラン、月3000円の竹プランしかない場合、価格重視の顧客は松プランを選ぶケースが多いでしょう。しかし、ここに月5000円と高額で、あまり竹プランと変わりない梅プランが追加されると、竹プランを程よくお得に感じ、竹を選ぶ消費者が増えます。
ただし、あまりにもおとり感が強すぎるプランを作ると不信な印象を与えるリスクもあるため、バランスの取れた設計が重要です。
現在志向バイアス
現在志向バイアスとは、将来に得られる大きなメリットよりも、今手に入る小さなメリットを過剰に高く評価してしまう認知バイアスのことです。1年間貯金を積み立てれば、利子がさらに上乗せされると分かっているにもかかわらず、貯金に回さずにお金を使ってしまうのが、現在志向バイアスの例です。
人事分野では、現在志向バイアスが発生しやすいため注意が必要です。目先の採用ノルマを達成するために採用基準を下げる、すぐに欲しい人数を確保してしまう、といった行動に出る場合、現在志向バイアスにとらわれている可能性があります。長期的視点で優秀な人材を見極めたり、改善策にコストを投資したりするほうが大きなリターンを得られると意識し、冷静に選択肢を比較検討することが重要です。
現状維持バイアス
現状維持バイアスとは、現状を変えることに対して抵抗を感じ、変化を避けて現状を維持しようとする心理的傾向のことです。既知の状況に安心感を覚えるため、変化に伴うリスクや不確実性を避けたくなる人間のあり方が、現状維持バイアスを生みます。
例えば、新しいルールや仕組みを導入することに対して「今のやり方でうまくいっているから変更する必要はない」と拒否する姿勢がある従業員は、現状維持バイアスにとらわれています。
現状維持バイアスをマーケティングに取り入れたのが、「初月無料」「初回無料」などをうたうサブスクリプションサービスです。一度利用を始めてメリットを受けてしまうと、顧客は変更するのに不安を感じ、解約を先延ばしにして続ける可能性が高まります。また、契約時にデフォルトのプランを選ぶ必要があり、変更手続きを自分で行う必要がある形にすると、変更の手間を避けて現状のまま契約を続けやすくなります。
サンクコスト効果
サンクコスト効果とは、過去にかけた費用を取り戻したいという心理が働き、結果として非合理的な判断をしてしまう現象です。合理的な意思決定では、将来の利益とリスクのみを考慮すべきですが、人間は過去の投資を惜しんでしまうため、その費用を回収しようと行動を続けることがあります。結果、無駄な投資をして、さらに傷口を広げてしまいます。
有名なサンクコスト効果の例がコンコルドです。コンコルドは燃費の悪さや収容定員の問題が指摘されていたにもかかわらず、すでに巨額の投資が行われていたため、開発を中止せずに運行を開始し、最終的には巨額の赤字を生む結果となりました。この事例から、サンクコスト効果のことをコンコルド効果と呼ぶときもあります。
マーケティングにおける「一定期間の契約を続けた場合の特典」は、サンクコスト効果を使って顧客を離脱させないための代表的な施策です。例えば、「1年間契約を続ければ別商品をプレゼント」などの施策は、離脱した場合投資が無駄になると感じるため、顧客が1年間商品を購入し続けたくなる狙いで行われます。
単純接触効果(ザイオンス効果)
単純接触効果とは、繰り返し接触することで、人や物に対する好感度や評価が高まる心理的現象を指す言葉です。1968年にポーランド出身の心理学者ロバート・ザイオンスによって発表されたため、ザイオンス効果とも呼ばれます。
基本的に、人間は新しいものや未知のものに対して警戒心を持つ生き物です。しかし、同じものに繰り返し触れることで、警戒心が薄れ、好意的な感情が生まれるのを逆手にとって、単純接触効果はマーケティングに使われています。
典型的な単純接触効果の例が、広告です。テレビCMやWeb広告、SNSで定期的に同じ広告を繰り返せば、消費者の関心を高め、購買行動に繋げることができます。また、過去に訪れたサイトの情報をもとに、ユーザーに再度広告を表示するリターゲティング広告や、ユーザーに定期的にメールで情報を配信するメールマーケティングも、単純接触効果を狙って行われる施策です。
ほかにも、営業活動において、顧客のところに粘り強く通うと単純接触効果が生まれ、顧客が好意的になる可能性もあります。ただし、単純接触効果には限界があり、10回以上接触するとかえって嫌われる可能性が高まるとされています。また、もし接触がネガティブなイメージを与える場合、接触回数が増えることでかえって嫌われてしまうため、注意が必要です。
認知的不協和
認知的不協和とは、個人が持っている2つの矛盾する考えや信念が引き起こす不快感を指す言葉です。矛盾する考えをどちらも持っている人間は、精神的に不安定な状態になり、矛盾を解消するために、自分に都合の良いように考えを変えたり、行動を正当化したりします。
認知的不協和は、マーケティングにも大きな影響を与えます。消費者が感じる矛盾を解消する方法を提供すると、購買意欲を高めたり、顧客のリピーター化を促進したりできます。
例えば、消費者が商品を購入した後に不安や後悔を感じないように、購入後に適切なアフターフォローを提供するのは、認知的不協和を解消する施策です。商品の使い方をアドバイスするメールマガジンを送ったり、満足度の高い他の顧客のレビューを紹介したりすることで、「商品をうまく使えないのは、商品の質が悪いからだ」と思われずに済むでしょう。
一方で、認知的不協和を利用して、消費者の注意を引き付けるキャッチコピーを作成するケースもあります。例えば、「食べて痩せる」というキャッチコピーは、「たくさん食べたいけど痩せたい」という消費者の認知的不協和を解消し、消費者の共感を生むことにつながります。
バーナム効果
バーナム効果とは、本来であれば誰にでも当てはまりそうな曖昧で一般的な表現を「これは自分だけに当てはまる」と感じてしまう心理現象のことです。たとえば占いで、「あなたは気配りがうまい一方で、物事に夢中になると周りが見えなくなる時もあります」など、一見して性格を言い当てているような一般論を思わず信じてしまうのが、バーナム効果の例です。
マーケティングにおいては、「従業員の育成に不満や不安を感じていませんか?」など、多くの企業に起こる課題を提示するキャッチコピーがバーナム効果を利用しています。相手は「まさに自社の問題にぴったり」と思い、話を真剣に聞いてくれる可能性が高まるでしょう。
ハロー効果
ハロー効果とは、ある対象を評価する際に、目立つ特徴や印象に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる現象のことです。例えば、ある人が非常に魅力的であると感じると、その人の他の特徴や行動も無意識に良く評価してしまうことがハロー効果です。反対に、第一印象で悪い印象を受けた場合、他の良い特徴も見逃しがちになります。
ハロー効果は、面接や人事評価の場面で強く現れます。一流大学を卒業している学生がビジネスパーソンとして優れていると評価してしまうケースや、服装が乱れている学生を能力まで低く評価してしまうケースが、ハロー効果の典型例です。
人事評価にハロー効果によるバイアスをかけないよう、面接や面談の際には評価基準を明確にし、一貫性を持たせることが重要です。例えば、評価する項目ごとに具体的な基準を設け、それに基づいて評価を行うことで、偏った評価を防げます。
バンドワゴン効果
バンドワゴン効果とは、「多くの人が選んでいる」という現象が、さらにその対象に対する支持を増やす心理的な効果です。流行に乗る、人気のある商品を購入する、政治的に優勢な候補者に投票するなどの行動は典型的なバンドワゴン効果の例です。
バンドワゴン効果が活用されるシーンが、SNSマーケティングです。InstagramやX(旧Twitter)などでフォロワーが多いアカウントが商品・サービスを紹介すると、「皆が選んでいるから自分も選びたい」という思いを高められます。
また、広告にもバンドワゴン効果がよく使われます。例えば、「顧客満足度No.1」「業界最高」などの表現を購買データや成功事例とともに客観的に示すことで、バンドワゴン効果による購買促進を狙うことが可能です。
フレーミング効果
フレーミング効果とは、同じ情報でも提示の仕方や表現方法によって反応が変わる心理的現象のことです。例えば、同じ商品について「90%の人が効果を実感しています」と「10%の人は効果を実感していません」と表現を変えると、どちらも同じ内容を伝えているのに、前者はポジティブに、後者はネガティブに受け取られます。
マーケティングにおいて、フレーミング効果は消費者の意思決定に大きな影響を与えるため、戦略的に活用される現象です。例えば、健康や生活の質を向上する商品の場合、「購入者の95%が使ってよかったと感じています」と言った形で、ポジティブな部分を強調する表現が使われます。一方で、予防やリスク回避を目的としている商品の場合、「40%の方が健康に不安を感じています」などの形で、ネガティブな部分を強調するのが効果的です。
プロスペクト理論
プロスペクト理論は行動経済学の柱となる理論で、簡単に言えば「人間は得をするよりも、損をするほうを恐れる(損失回避)」「人間は低い確率を過大評価し、高い確率を過小評価する(確率の無視)」という考え方です。
例えば、「コインを10回投げて、表が出たら100円をもらえる」ゲームと、「コインを10回投げて、表が出たら200円もらえるが、裏が出たら100円取られるゲーム」があると、人は前者を選びたくなります。後者のほうが貰える金額の期待値が高くても、損失を避けたいという心理が働くためです。
日常の例としては、墜落を怖がって航空機に乗りたがらない人の心理が挙げられます。例えいくら確率が低いと理屈の上では分かっていても、「わずかな確率で墜落する」可能性を過大評価してしまうプロスペクト理論が働いていると言えます。
プロスペクト理論は、マーケティングにも大きな影響を与えている考え方です。例えば、期間限定セールはプロスペクト理論の損失回避に基づいて、顧客に「今買わないと損をする」という心理を働かせ、即決を促す施策です。また、「●名にプレゼントが当たる」といったキャンペーンは、たとえ低い確率でも「当たるかもしれない」という過大評価を顧客が起こすため、購買につながります。
保有効果(エンダウメント効果)
保有効果とは、人が自分の所有物に対して、客観的な価値以上に高い価値を見出す心理現象です。例えば、自分が住んでいる家の評価額を過剰に高く見積もるのは、保有効果が働いているためです。保有効果は損失回避、現状維持バイアス、単純接触効果の3つが影響していると考えられています。所有物を手放すことは、心理的に「損失」ととらえられ、現状維持ができなくなる不快な体験です。さらに、長く触れているものに人間は愛着を感じるため、3つの心理的効果が複合して、物を手放すのに苦痛を感じることで保有効果は発生します。
保有効果は主にマーケティングや営業活動に活用されている理論です。例えば、車の試乗などの実体験を無料で提供する販売手法は保有効果を与える目的で行われます。一時的にせよ車を保有することで愛着を持ち、顧客は車の購入に踏み切りやすくなります。
また、消費者に商品を購入してもらう際に返品・返金保証を設けるケースも、保有効果の活用例です。保証が商品購入のハードルを下げる一方で、実際には保有効果によって返品・返金に踏み切りたいと思いづらくなります。
行動経済学理論を活用する際の注意点

残念ながら、行動経済学理論には、心理学と同様に一部再現性に問題がある理論が存在する状況です。これは、人間の心が影響を受ける要素が極めて多様な現代社会で、すべての影響を与える要素を排除して、公平な条件で実験をするのが容易でないためだと考えられています。
行動経済学を「こういった傾向がある」という大まかなガイドラインにとらえ、「この状況では人間は必ずこうする」と考えると、施策はうまく行きません。
例として、行動経済学理論で多くの注目を集めていたナッジ理論が挙げられます。ナッジ理論とは、行動経済学に基づいてちょっとした気付きを与え、無意識的に行動変容を促す取り組みです。多くの人々がローコストで誰かの行動を変えられるとされていたナッジ理論を魅力的に感じました。しかし、現在ではナッジ理論は当初考えられていたよりもはるかに効果が小さいと判明しています。
また、行動経済学は人間心理を使い、誰かを誘導する形でも悪用できるため、国は景品表示法を適宜改正するなどの形で対応しています。行動経済学を利用する側も、倫理観を持って行動する必要があります。
したがって、マーケティングやビジネス戦略に応用する際には、以下の注意点を押さえておくのが大切です。
| ・理論に頼りすぎない 行動経済学は効果的な理論である一方で、すべての状況に対して万能な解決策を提供するわけではありません。また、ビジネスにおいて理論のみに過度に依存し、消費者への配慮を行わないことは、コンプライアンス上や倫理的な問題を引き起こす可能性もあります。例えば、消費者の心理的バイアスを悪用し、意図的に不利益を被らせるような戦略は、法的に問題となるだけでなく、企業の信用にも影響を与えるため避けるべきです。 ・一時的だけでなく継続的に観察する 行動経済学を活用した戦略やキャンペーンは、しばしば一時的に成功を収めることがあります。しかし、長期的に効果を持つかどうかは別問題です。理論に基づく施策がすぐに効果を発揮したとしても、それが継続的な成果をもたらすかどうかを確認するためには、長期的なデータの収集と分析が必要です。また、行動経済学理論を採用する場合でも、内容に再現性があるのか慎重に見極めるようにしましょう。 ・顧客体験の質を高めることを目的とする 行動経済学をマーケティングに活用する際は、最終的には顧客にとって価値のある体験を提供することが企業の成功につながります。例えば、顧客が自分で選んだ商品に対して感情的に満足できるような選択肢を提供すれば、顧客との信頼関係を構築できます。反対に、消費者を不誠実な方法で誘導するやり方は、ブランドのイメージを傷つけ、長期的には企業にとって不利益をもたらすでしょう。 |
まとめ
行動経済学の理論には、マーケティングや人事、会社経営などのビジネス分野で応用できる、企業の戦略に役立つ理論が豊富にあります。しかし、行動経済学を活用する際には、効果が短期的なものにとどまらないよう、長期的な視点で顧客との関係を築くことが大切です。短期的な利益を追求するあまり、消費者を不誠実な方法で誘導してしまうと、信頼を失い、企業にとって逆効果を生む可能性があります。
また、理論に頼りすぎず、実際の市場環境や消費者の反応を定期的に観察し、柔軟に戦略を見直すことが求められます。
関連記事
Related Articles

厚労省推奨!管理職の「必須スキル」ラインケアで職場と部下が劇的に変わる秘訣とは?
ラインケアとは、職場における管理職が中心となって行うメンタルヘルス対策です。当記事では、ラインケアの定義や必要性、厚...
企業研修
人の心を動かすプレゼンのコツ21選|資料や構成のこだわりポイントは?
プレゼンで人の心をつかみ、商談を成功させたり主張を理解してもらったりするためには、話し方を工夫すると同時に資料作りや...
企業研修
ファシリテーターとは?役割と求められるスキル・うまくなるコツを解説
ファシリテーターは参加者一人ひとりの意見を尊重し、安心して発言できる環境を作りつつ、多様な意見を効果的に引き出して活...
HRトレンド企業研修