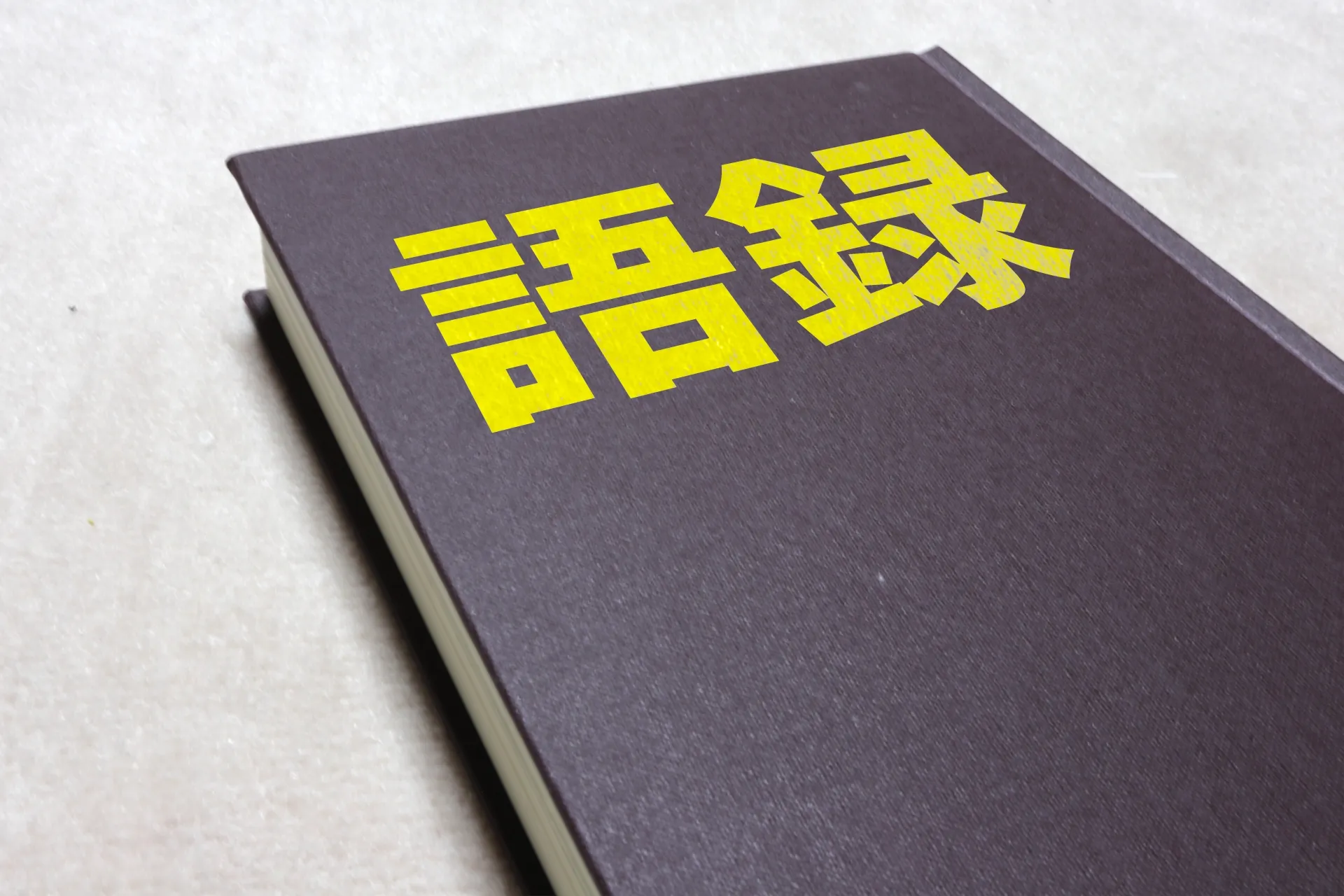- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- HRトレンド
- 仕事ができない人の10の特徴と口癖5つ|原因や対策方法を解説
仕事ができない人の10の特徴と口癖5つ|原因や対策方法を解説

職場で「仕事ができない」と評価される従業員には、ある程度決まった特徴や口癖があります。しかし、仕事ができない人が生まれるのは、単に個人の能力不足だけが要因とは限りません。業務を効率よく進めるためのスキルやタスク管理のコツを身につけられない、あるいはコミュニケーション体制そのものに問題があるなど、さまざまな職場環境の問題が潜む可能性があります。
この記事では、仕事ができない人に共通する特徴や口癖、および仕事ができない人が生まれる原因と対策方法を解説します。
目次
Toggle仕事ができない人の特徴とは

仕事ができない人とは、さまざまな要因によって業務で求められる成果を達成できず、周囲に迷惑をかけるようなミスも多く、かつ改善スピードも遅い人のことです。
仕事ができない人は、同じような特徴を持つケースが多くあります。以下では、仕事ができない人の共通点を10個紹介します。
タスク管理ができない
仕事ができない人に共通する特徴として、タスクやスケジュール管理能力の不足があります。
タスク管理ができない人は、日常業務において自分が抱えている業務の全体像を把握することが苦手です。自分がいつまでに何をすべきかが分からず、締め切りギリギリになって慌てて作業を始めたり、期限を守れずに周囲に迷惑をかけたりすることがあります。
タスクを抱え込んだまま放置すると、本人だけでなくチーム全体の進捗にも悪影響を及ぼすでしょう。
報告・連絡・相談をしない
報告・連絡・相談(報連相)が苦手な人は、トラブルや課題が発生した際に適切なタイミングで上司や同僚に伝えません。問題を1人で抱え込み、自力で解決を試みた結果、問題が深刻化するケースが多く見られます。例えば、顧客からクレームが出た場合上司に報告せずに現場だけで解決を図ろうとする、などは仕事ができない人の典型的な行動です。
ほかにも、業務の進捗状況を報告しないのも、仕事ができない人の特徴です。上司や同僚が状況を把握できず、フォローが困難になったり、周囲が不必要な対応を強いられたりすることも多くなります。
レスポンスが遅い
メールやチャット、口頭での問い合わせに対して返答をしないのも、仕事ができない人の特徴です。「後で対応しよう」と先延ばしにして忘れてしまう、あるいは重要度を見極められずに対応が後回しになるケースがよくあります。
また、返信を求められた際に即答できず、何度も催促されてようやく対応するような行動を取る傾向も、レスポンスが遅い人にはありがちです。情報共有や意思決定が遅れ、チーム内でのコミュニケーションに支障をきたすと、業務の停滞を招いてしまいます。
さらに、顧客の問い合わせやクレームになかなか答えない場合、顧客からの信頼を失い、契約解除や顧客離れに至るリスクもあります。
同じようなミスを繰り返す
仕事ができない人は、以前の失敗から学ぶことが苦手で、同じ誤りを何度も繰り返しがちです。
よくある特徴が、指摘された問題をメモや記録に残さないところです。記憶だけに頼って仕事を行うため、注意すべき点を忘れて何度も同じようなミスを繰り返します。周囲のサポートや指摘にもかかわらず、同じ行動を繰り返すため、組織内での信頼が低下し、周囲の負担ばかり増やします。
加えて、同じようなミスを繰り返すタイプの仕事ができない人は、手順書やマニュアルを軽視し、自己流で仕事を進める傾向がある点も問題です。正しい手順を守らずにミスをすると、結果として労災や事故が起きることもあり、会社に大きな損害を与えます。
責任感が薄く他責的な態度をとる
仕事ができない人の中には、業務で問題が発生した際に自分のミスを素直に認めず、周囲の人や環境のせいにする人もいます。自分の失敗について、同僚や上司の指示が不十分だったこと、あるいは業務環境が整っていないことを理由として挙げ、自分自身の改善点を見つめようとしません。
また、仕事に対しての責任感が希薄なため、途中で仕事を放置したり、他人任せにしたりする行動が見られます。
他責性が高いと反省や改善が遅れるため、周囲のサポートや指摘にもかかわらず同じ行動を繰り返し、任せられる仕事の範囲も狭くなります。結果として周囲の士気を下げ、職場の雰囲気にも悪影響を及ぼしがちです。
作業の優先順位をつけない
仕事を進める際に緊急度や重要度を考慮せず、目についた仕事や得意な仕事から手をつけてしまう、優先順位の付け方が下手な仕事ができない人もいます。周囲からの急な依頼や新たなタスクに対しても、既存業務とのバランスを取ることができず、結果的にすべての業務が中途半端になります。
特に、急ぎの仕事よりも自分が楽な仕事から取り組み、期日が近づくにつれて慌てて本来優先すべき作業を片付けようとするタイプは、業務上問題を起こしがちです。得意ではない作業を急いでやるため、本来持っている能力よりクオリティの低い成果物ができ、結果として仕事ができない人と見なされます。
仕事に取り掛かるまでのスピードが遅い
ぐずぐずといつまでも仕事に取り掛からないのも、仕事ができない人によくある特徴です。取り掛かるスピードが遅い人には、慎重すぎるタイプと怠けているタイプの2種類がいます。
慎重すぎるタイプの人は、業務を開始する前に余計な準備や確認を繰り返し、実際の作業に入るまでに多くの時間を浪費します。完璧主義や不安から、必要以上に手順を再確認したり、細かな情報を集めたりして、中々行動を起こせません。このタイプにはタイムマネジメントが苦手で、「いつまでにできているべきか」という意識が希薄な人もいます。
怠けているタイプは優先順位を付けるのが下手なタイプを併発しているケースが多くあります。このタイプは、やるべき仕事があっても「後でやろう」と考えて先延ばしし、他の重要度の低い作業や雑務に逃げてしまいがちです。結果、いつまでも成果が上がらず、仕事ができない人と周囲に見られてしまいます。
指導を聞かない
プライドが高く、上司や先輩から指導されても素直に受け入れられない人は、入社時には十分な能力があっても、やがて仕事ができない人になりがちです。指導中に自分の意見や反論を繰り返したり、指摘された内容を「分かっています」と軽視したりすると、成長が遅れやすくなります。
ミスに対するフィードバックを受け入れられない、自己流の仕事のやり方を変えない、といった特徴があると、改善すべき点が改善されません。周囲も指導や協力をしなくなるため、成長がますます遅れ、仕事ができない人になります。
消極的で指示待ちが多い
消極的で指示待ちが多く、自分から行動を起こそうとしないタイプの人も、仕事ができなくなりやすい傾向があります。常に誰かの指示や助言を待ち、自分の判断で行動することを避ける人は、仕事を自分で進められません。
わずかな判断や小さな決定でも上司に確認を求めたり、指示がない限りは仕事を進めようとしなかったりすると、業務は停滞し、周囲も都度指示するために時間を取られます。
また、与えられた業務以外に何か問題が起きても、自発的に解決策を模索せず、指示待ち人間としてふるまう従業員がいると、問題の解決が遅れます。結果として周囲の負担が大きくなり、仕事ができない人と扱われるでしょう。
何事もネガティブにとらえる傾向がある
過度にネガティブな人は、周囲のモチベーションを下げるため、仕事ができない人となりがちです。業務上の小さな失敗や困難を必要以上に重く受け止め、自己否定的な考えに陥ると、周囲は指導や改善策を伝えても効果が薄いように感じてしまいます。
また、「自分にはできない」「失敗するに違いない」と否定的な言葉を口に出したり、周囲にネガティブな影響を与える発言を繰り返したりするのも問題です。加えて、ポジティブな評価や励ましを受けても、「たまたま運が良かっただけ」と否定的に捉え、自信やモチベーションを低下させることがあります。
周囲は仕事を新たに与えても落ち込み、褒めても落ち込むためどう扱ってよいのか分からず、腫れ物に触るように接するしかなくなります。結果、業務が円滑に進みづらくなるでしょう。
仕事ができない人によくある口癖

仕事ができない人には、決まった口癖があり、周囲に悪い印象を与えやすくなります。HR部門の担当者や管理職の方は、以下のような口癖がある部下に対しては特に注意して指導を行う必要があると言えます。
「でも」「だって」
「でも」「だって」を頻繁に口にするのは、相手の意見や指摘を素直に受け入れず、自分の行動やミスを正当化しようとする可能性が高い人です。上司からミスを指摘された際、「でも、時間がなかったから」「だって、〇〇さんが言ったから」と反論し、自らの責任を回避する傾向があります。
強い他責性やプライドを持っており、指導しても改善が遅れるリスクが高いと言えます。
「後でやります」「忙しい」
「後でやります」や「忙しい」を口癖にする人は、タスク管理や仕事の優先順位をつけるのが苦手な可能性があります。新しい仕事を依頼されるとすぐに「今忙しいので後でやります」と返答し、結局対応が遅れている場合は要注意です。
本当に忙しいわけでなくても忙しさを過度にアピールして仕事を回避しようとしているケースや、締め切りギリギリに仕事をした結果無駄に忙しくなっているケースがあります。自己管理ができない結果、余裕のある仕事量でも多忙になっていないかチェックが必要でしょう。
「指示されていません」「知りませんでした」
「指示されていません」「知りませんでした」が口癖の人は、主体性や責任感に問題があるケースが多いです。トラブルが発生した際、「そんな指示は受けていません」「知りませんでした」と発言し、自ら積極的に情報を収集しなかったことや、責任を持って動かなかったことを棚上げします。
指示や指導をする側のモチベーションを低下させる可能性も高いため、指導側のケアも必要になります。
「やったことがありません」「難しいです」
「やったことがありません」「難しいです」を口癖にする人は、新しい仕事や挑戦に対して消極的な傾向があります。「やったことがないのでできません」「難しいので無理です」と業務をすぐに断ろうとするため、本人はなかなか成長しません。
さらに、積極的に仕事をしないことから周囲の負担も増えがちです。
「~~のせい」「〇〇さんに言われた通り」
「~~のせい」「〇〇さんに言われた通り」という口癖は、自己の責任を回避し、失敗を他者や環境のせいにする人に多く見られます。業務でミスが起きた際に「〇〇さんの指示通りにやっただけ」「環境が悪かったから」と他責的な発言をすると、責任をかぶせられた側はモチベーションが下がります。
チームの信頼関係を悪化させる原因になるだけでなく、本人が自分を顧みて改善する機会も少なくなる言葉です。
仕事ができない人が生まれる原因

仕事ができない人が生まれるのは、一見して本人の性格が原因のように見えます。しかし、実際は職場環境に何らかの問題が隠れており、結果として本来発揮されるべきポテンシャルを人材が発揮できていない可能性もあります。
職場環境という視点からチェックしたい、仕事ができない人が生まれる原因は以下の通りです。
自己認識に歪みがある
仕事ができない人が生まれる原因として、自己認識に歪みがある場合が挙げられます。周囲が感じる自身の課題や足りない能力を正しく捉えられず、自分を過大評価、あるいは過小評価してしまった結果、プライドが肥大化したり、過度にネガティブになったりします。
特に「自分はできる」と思い込んでいる場合には、周囲の助言や評価が耳に入らなくなり、同じミスを繰り返すため危険です。
社員に自己認識の歪みが生まれている場合、客観的なフィードバックを受ける機会が不足している可能性があります。特にモデルケースとなるべき者が周りにおらず、自己流の成長をした場合、自己認識が狂いやすいです。
したがって、職場の各従業員に向けて、業務においてどういった人材が理想的なのかを明確にし、客観的な評価尺度を可視化するのが大切です。また、フィードバックや評価制度を設けて、定期的に自分の強みや弱みを見直す機会を与えるのも効果的です。
スキルが足りていない
スキル不足は、業務の遅れや品質の低下を招き、周囲から「仕事ができない」と評価される要因の1つです。
従業員のスキル不足は、本人に問題があるケースだけでなく、職場環境に問題があるケースも多い問題です。必要な教育や指導が行き届かない職場環境は、従業員の成長の機会を逃してしまいます。また、昨今の業務は専門性が高まっているため、基礎的なスキルアップの機会がない状況を放置すると、組織全体の業務効率に悪影響を及ぼす可能性があります。
周囲のサポートや会社としての育成体制が不十分だと、いつまでもスキル不足を解消できず、仕事ができない人を生産する職場が生まれます。
職場の評価制度に問題がある
評価制度が不透明だったり、公平性や妥当性に欠けていたりすると、「自分は正当に評価されていない」と感じる社員が増え、仕事へのモチベーションが下がりやすくなります。
例えば、明確な評価基準がないまま結果のみで判断される、努力が見えにくいプロセスが評価に反映されないなどの状況では、社員が組織への不信感を抱きやすいでしょう。また、評価者の主観や人間関係が影響していると疑われると、実際に優秀な社員でも評価に納得できず離職を考えるケースが増えます。
加えて、適切な評価を受けていないと、これ以上評価が下がらないよう責任を回避したり、消極的な態度を取ったりしやすくなるのも問題です。
結果として、人材の流出や職場全体の生産性低下につながるため、評価制度の見直しと適切なフィードバックを行う仕組みづくりが重要です。
職場の心理的安全性に問題がある
職場の心理的安全性が低いと、社員はミスや疑問を素直に共有できなくなり、自分の意見を言うことに大きな不安を抱きがちです。「こんなことを言ったら無知だと思われるのではないか」「反対意見を出したら邪魔だと扱われるのではないか」などの恐れから、チームメンバーが口をつぐんでしまう状況が生まれます。
結果、消極的で指示待ちの姿勢や、報連相の遅れ、他責的な態度につながります。
さらに、失敗や相談を許さない空気感の中では、社員が自ら学んで成長する機会を失いやすいのも問題です。「無能だと思われたくない」「ネガティブだと見なされたくない」という意識が強いと、必要なサポートを求めることも避けてしまい、スキル不足や仕事へのモチベーション低下が生まれます。
心理的安全性を高めるためには、チームや職場のコミュニケーションを活発化させ、相互の信頼関係を築くことが重要です。以下のポイントを押さえて、心理的安全性の高い職場を作りましょう。
| ● メンバーで話す機会を増やす ● 協力を重視する ● ポジティブな思考を意識する ● 評価の仕方を見直す ● さまざまな価値観を尊重する |
心理的安全性の高い職場を作る方法については、以下の記事もぜひ参考にしてください。
メンタルヘルスが損なわれている
メンタルヘルスが損なわれている状態では、集中力や判断力が低下し、普段は難なくこなせていた業務でもミスが増えたり作業効率が落ちたりすることがあります。特に、長時間労働の横行や行きすぎた成果至上主義など、ストレスが蓄積されやすい職場では、うつ病などの精神疾患を発症するリスクが高まります。職場環境が厳しく、失敗を叱責されるばかりでフォローが不十分な場合には、さらに追い詰められやすいでしょう。
たとえ病名がつかなくても慢性的な疲労や心理的な負荷が続く状況は、心身の不調につながり、業務へのモチベーションやパフォーマンスを大きく損ないます。過度なストレスが対人関係の余裕を失わせ、従業員間でパワハラやセクハラと言った問題行動を発生させる恐れもあります。
従業員が休職や退職を余儀なくされる可能性もあるため、従業員には休息し、ストレスを解消する方法を教えるのが大切です。また、管理職に従業員のメンタルヘルスについて知識を持たせて、心身の不調を速やかに察知するのも重要です。
『マインドフルネスとは?メリットや注意点、企業の導入事例を紹介』についてより詳しくはこちら
仕事ができない人への対策・指導方法

仕事ができない人を仕事ができる人に変えるためには、いくつかのポイントを押さえて職場環境を改善し、対策や指導を行うことが大切です。
以下では、仕事ができる従業員を作るための対策方法を解説します。
今のキャリアに必要な基本スキルを身に着けさせる
従業員にスキル不足を感じた場合、研修や指導をする仕組みを作り、キャリアの段階に応じて必要となる基本的なスキルを身に着けてもらうのが重要です。
新人であれば、報連相をはじめとするコミュニケーションスキルやタスク・時間管理の方法を指導し、業務の流れを理解しながら着実に成果を出せる土台を作りましょう。一方、中堅社員や管理職の場合は、問題解決力やリーダーシップなど、より高度な能力を養うことが求められます。
また、従業員にキャリアデザインを行わせるのも、スキル不足の改善につながります。キャリアデザインとは、各従業員が自分の将来像を具体化し、実現するためのキャリアを自ら設計することです。自分で将来を決定し、目指すキャリアにどのようなスキルが必要になるのか自分で考えるため、自発的にスキルアップができるようになります。
適材適所の人材配置をする
従業員が「仕事ができない人」になるのは、人材が適切に配置されていない可能性があります。本来は適性のない業務に従業員を就かせていた結果、モチベーションが低下したり、スキル不足になったりすることを防ぐためにも、適材適所の人材配置を心がけましょう。
人材配置は、従業員個々のスキルや経験だけでなく、性格や志向、キャリアビジョンなどの情報を正しく把握した上で行うことが重要です。求める業務内容や組織目標に合ったポジションへ配置すれば、本人のモチベーションとパフォーマンスを最大限に引き出せます。
配置後も効果測定を行い、成果が出ているか、チームや本人の満足度はどうかを定期的に確認しましょう。改善点があれば、異動や育成プランの再検討を通じて調整していくことが大切です。
フィードバックを増やす
上司や指導役がフィードバックの回数を増やすと、客観的に自分の状況を判断しやすくなり、仕事ができない人の現状改善につながります。
良い点をきちんと評価されると、従業員は自己肯定感ややる気を高めやすくなり、消極的なスタンスが改善する可能性も上がります。また、コミュニケーションの機会が増えることで、上司は部下の気持ちや得意分野、悩みなどを把握しやすくなり、適切なサポートが可能です。お互いが学び合う土壌が整うと、職場も心理的安全性も改善します。
フィードバックにあたっては改善すべき点だけを突きつけるのではなく、「どうすれば良くなるか」をともに考える姿勢は、上司と部下の信頼関係を深める上でも大切です。上手にフィードバックするやり方を、特に管理職や指導役に身に着けさせるとよいでしょう。
メンター制度を取り入れる
メンター制度とは、経験やスキルを持った先輩社員が、より経験の浅い社員の相談役を担い、定期的に面談を実施しながら精神的なサポートや助言を行う人材育成の仕組みです。指導する側をメンター、指導される側をメンティと呼びます。
メンター制度により、メンティは悩みや不安を打ち明けられる存在を確保できます。また、メンターも後輩を指導するプロセスを通してコミュニケーション能力やマネジメント力を磨け、スキルアップが可能です。
メンター制度を取り入れると、経験の浅い社員はロールモデルとなる相手を得られるため、自分の現状が客観的に分かり、どのように成長すればよいか判断できます。また、自分の思いをメンターに打ち明けられ、過度にネガティブになったり消極的になったりするリスクを減らせるでしょう。
スキルアップする機会を増やす
スキルアップの機会を増やすことで、仕事ができないと評価されてしまう人でも着実に成長できる可能性が高まります。特に、研修制度の導入は、本人の意欲次第で不足しているスキルを補強し、仕事ができない人を減らすのに有効です。
業務に必要な知識を学ぶ研修や、オンライン講座、社内勉強会などを定期的に開催すれば、社員は自分の業務に直結したスキルを効率的に習得できるでしょう。
また、リスキリング制度を整備するのもよいでしょう。リスキリングとは、企業にとって重要度が高いスキルを新たに従業員に学んでもらう制度のことです。従業員にとっては新しい分野や技術に挑戦する機会になり、組織としても中長期的な変化に備える土台づくりに役立ちます。
職場から認められ、スキルアップのためのリソースを積極的に与えられると、「自分は成長を期待されている」という実感が芽生え、仕事への意欲が高まりやすくなります。結果として、個々の業務効率や生産性が上がるだけでなく、チーム全体の士気向上や離職率の低下にもつながるでしょう。
まとめ
仕事ができない人が多く生まれる職場は、個人だけでなく職場環境に問題がある可能性が高いと言えます。タスク管理やスキル育成の不足、評価制度の不透明さ、心理的安全性の欠如など複合的な要因が、従業員を仕事ができない人に変えている恐れがあります。
研修制度の充実や適材適所の配置、定期的なフィードバックの実施などを通じて、仕事ができない人を作らない職場環境を作ることが大切です。職場環境を改善すれば、職場全体の生産性向上や離職率の低下も期待できるため、組織内の課題を洗い出し、取り組みやすい部分から改善策をスタートさせましょう。
関連記事
Related Articles

アクティブラーニングとは?主体的な人材を育てる手法を事例で解説
生徒が受動的に教育されるのではなく、能動的に考えて自主的に学ぶよう促すアクティブラーニングは、学校教育以上にビジネス...
HRトレンドエンゲージメント
逆境こそチャンス!人生やビジネスを切り開く英語の名言・格言13選
逆境を乗り越えてきた偉人たちの英語の名言を紹介します。ビジネスに役立つ言葉から人生を前向きに導く格言、心に響く一言ま...
HRトレンド
ノンバーバルコミュニケーションとは?具体例から重要性や効果を解説
ビジネスシーンで日々行われているコミュニケーションには、言葉だけでなく表情や身振り手振り、声のトーンなど、多くの非言...
HRトレンド
社員の意識を統一!滝のように目標や戦略が伝わるカスケードダウンとは?
カスケードダウンは、会社の目標や戦略を経営層から社員に浸透させるのに有効な方法の1つです。会社として安定的な成長を目...
HRトレンド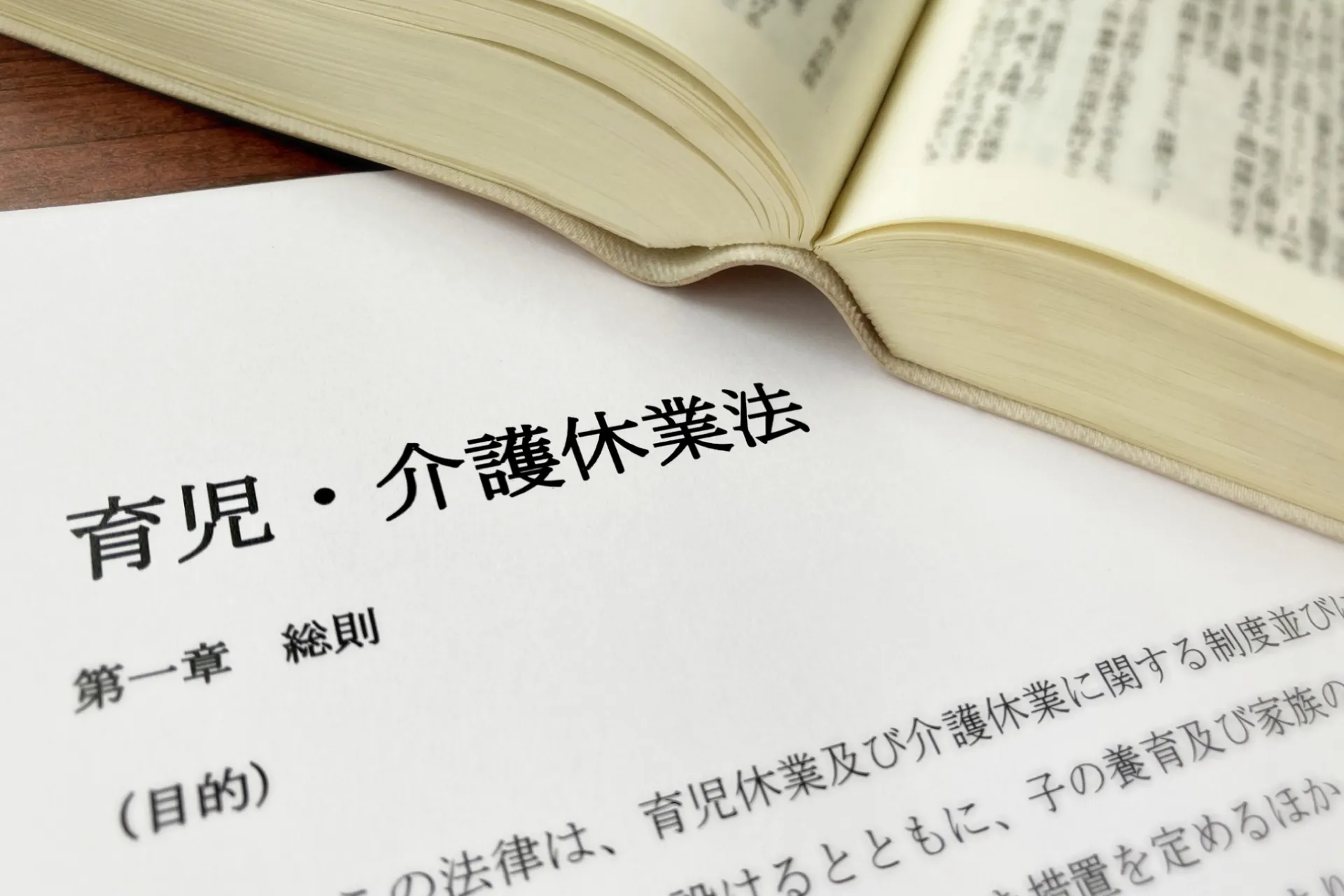
【2025年10月】育児・介護休業法が改正!いつから対応が必要か徹底解説
2025年10月から段階的に施行される改正育児・介護休業法について、具体的な変更内容やポイント、事業主に必要な対応を...
HRトレンド