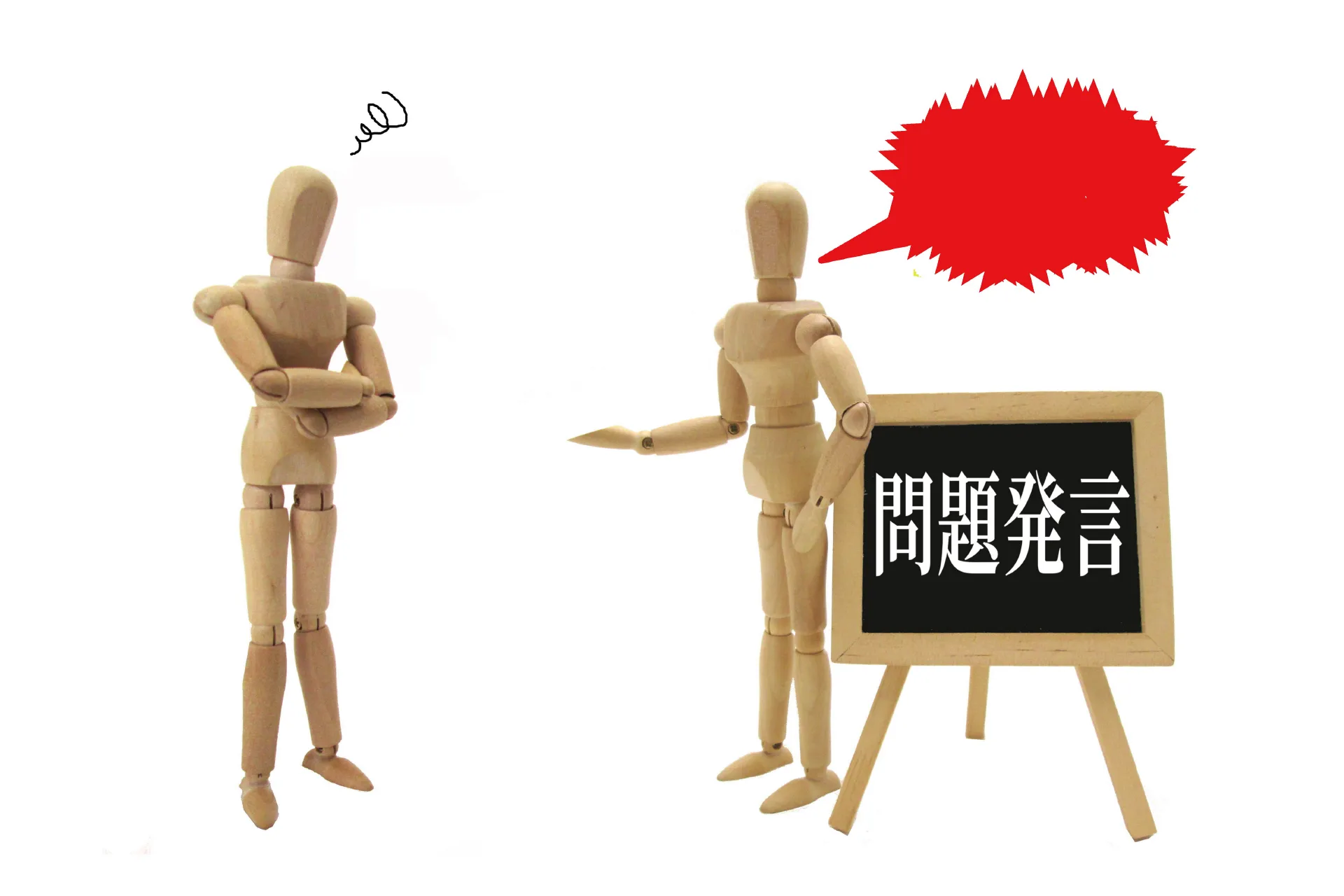- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- ハラスメント
- ため息は不機嫌ハラスメントになる?職場への影響・対策方法を解説
ため息は不機嫌ハラスメントになる?職場への影響・対策方法を解説
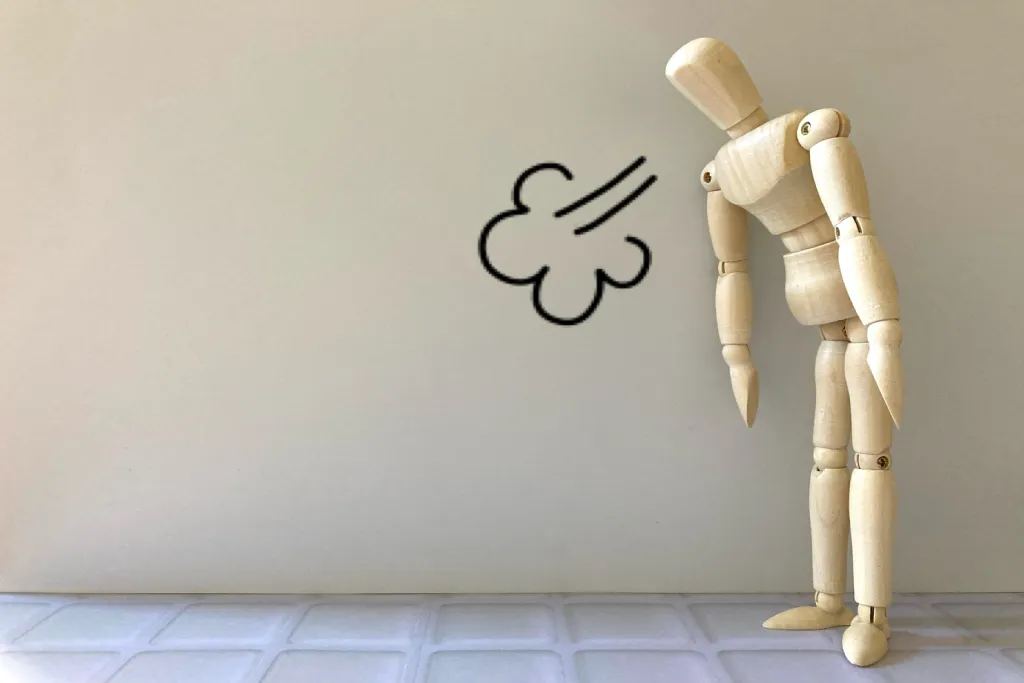
職場で何気なく聞こえる「ため息」は、周囲への圧力や不快感を与え、いわゆる「ハラスメント」として近年問題視されるケースが増えています。こうした威圧的な態度は「不機嫌ハラスメント(通称:フキハラ)」と呼ばれ、意図的に機嫌の悪さをアピールすることで、同僚や部下の精神的な負担を増やす行為とされます。
当記事では、どのようなため息がフキハラとされるのか、企業や職場に与える影響、また具体的な対策方法について詳しく解説します。
目次
Toggleため息はハラスメントになる?

職場での何気ない「ため息」も、状況や頻度によってはハラスメントと見なされることがあります。特に、ため息をつくことで周囲に不機嫌さをアピールし、威圧感や精神的な圧力を与える行為は「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」と呼ばれ、問題視されつつあります。
フキハラは、立場の強い方が部下などに向けて不機嫌さを示すと、相手は「自分に非があるのかもしれない」と自信を失い、心理的ストレスを抱える原因になります。たとえ明確な言動がなくても、繰り返されるため息や舌打ちなどが威圧的に感じられる場合、職場環境の悪化につながる可能性があります。
不機嫌ハラスメント(フキハラ)とは?
不機嫌ハラスメントとは、ため息や舌打ち、無言の威圧など、不機嫌な態度で周囲に不快感やプレッシャーを与える行為を指します。言葉にせずとも精神的な圧力となる場合があり、加害者に自覚がないケースも少なくありません。
職場で上司が部下に対して行えばパワハラに該当することがあり、同僚間や家庭内で起きた場合はモラハラとみなされることもあります。何気ない態度が、人間関係や職場の雰囲気を大きく損なうリスクをはらんでいます。
フキハラになるため息・フキハラにならないため息

すべてのため息がフキハラになるわけではありません。自然な呼気として出る場合もあれば、相手に不快感を与える意図がある場合もあります。ここでは、フキハラとされるため息と、そうでないため息の違いについて解説します。
ストレス解消のために自然と出るため息
ため息は、緊張状態にある心身を落ち着けるために生じる自然な生理反応です。ストレスや疲労がたまっているとき、人は無意識のうちに深いため息をつくことで交感神経の高ぶりを抑えようとします。このようなため息は、自分の状態を整える目的であり、他人に向けた威圧的な意図は基本的にないため、通常はフキハラには該当しないとされています。
ただし、頻繁すぎたり、特定の場面で繰り返されたりすると、周囲から誤解を招く可能性もあるため、状況には注意が必要です。
周囲に不機嫌であることを伝えるため息
部下の報告に対して、舌打ちを交えてわざとらしいため息をつくような、自分の不満や苛立ちを相手に示す態度は、威圧感を与え、精神的な負担をかけることになります。相手に不快感やプレッシャーを与えるために意図的につくため息は、フキハラに該当する可能性が高い行為です。
たとえ言葉での指摘がなくても、ため息という行動を通じて感情を押しつけるのは、職場の信頼関係やモチベーションを損なう原因になります。こうした行為は、パワハラやモラハラの一形態とみなされる場合もあるため、注意が必要です。
フキハラが企業・職場に与える影響

ため息などの不機嫌な態度によるハラスメントは、見過ごされがちですが、職場環境に深刻な悪影響を与える可能性があります。フキハラが常態化すると、職場の雰囲気が悪くなるだけでなく、社員のモチベーションや定着率、生産性の低下にもつながりかねません。ここでは、フキハラが職場にもたらす具体的な影響について解説します。
職場の雰囲気を悪化させる
不機嫌な態度やため息といった行動が職場で繰り返されると、周囲は常に相手の機嫌をうかがいながら行動せざるを得なくなります。このような心理的な圧迫感は、オープンなコミュニケーションを阻害し、報連相が滞る要因にもなり得ます。
また、ネガティブな雰囲気が蔓延すれば、新しいアイデアが出にくくなったり、周囲の活気が失われたりすることもあります。継続的なフキハラは職場の信頼関係を壊し、組織全体の風通しを悪くする要因となるため、重大な問題として捉える必要があります。
離職率を高める
フキハラによって精神的ストレスを感じる環境が続くと、社員は「この職場に居続けたくない」と考えるようになります。特に、上司など立場が強い人から日常的に不機嫌な態度を取られ続ければ、自分の評価やキャリアに対する不安も重なり、職場への信頼感を失ってしまうでしょう。結果として早期退職や転職を決断するケースが増え、優秀な人材の流出につながるリスクもあります。
残された社員にもフキハラの影響は及び、組織全体の定着率が下がる悪循環が生まれます。
生産性を低下させる
フキハラが蔓延する職場では、業務に対する集中力や士気が著しく低下します。社員は「また不機嫌な態度を取られるのでは」と萎縮してしまい、報告や相談をためらうようになります。その結果、業務の遅延やミスの発生、判断の先送りなどが起こりやすくなり、チーム全体のパフォーマンスが落ちてしまいます。
フキハラによるストレスが心身に蓄積すれば、休職者の発生や体調不良による欠勤にもつながり、さらに組織の機能低下を招きます。生産性の維持には、良好な人間関係と安心して働ける環境が大切です。
職場におけるフキハラ対策

フキハラは見過ごされがちなハラスメントですが、放置すると職場環境に深刻な悪影響を及ぼします。組織として早期に気づき、適切な対策を講じることが重要です。以下では、加害者への対応方法や組織的な対処策について紹介します。
本人に対して丁寧に指導を行う
フキハラを改善するには、本人への丁寧な指導が大切です。まずは事実確認を行い、どのような言動が周囲に悪影響を及ぼしているかを具体的に伝え、自覚を促します。不機嫌な態度によって周囲が萎縮したり、業務に支障が出ていたりすると客観的に伝えることで、改善意識を持たせましょう。また、本人に過度なストレスや業務負担がないかを確認し、必要に応じて環境調整を行うこともポイントです。
愛知県のQ社では、役員が現場で管理職の言動を日常的にチェックし、不適切な指導があればその場で注意しています。繰り返し指摘することで、本人も言い方の問題に気づき、行動が改善されました。現場密着型の姿勢が、ハラスメントの芽を早期に摘むことにつながっています。
配置転換を通じて環境を変える
フキハラの背景にある人間関係の摩擦や業務上のストレスが大きい場合は、配置転換によって環境を変えることが有効です。加害者・被害者の直接的な接触を避けることで心理的負担が軽減され、職場環境の改善につながることがあります。ただし、配置転換は根本的な解決ではなく、異動先でも同様の行動が繰り返されるおそれもあるため、受け入れ先の理解と体制整備が必要です。
大阪府のZ社では、事案ごとに事実認定委員会を設けて対応を進め、懲戒の要否は社長が決裁します。再発防止のため、相談者の意向を踏まえて注意指導や懲戒処分を行うほか、必要に応じて配置転換も実施しています。また、相談者へは経過報告を行い、対応内容への理解と納得を得るよう努めています。
業務の指示系統やフローを見直す
業務の指示が曖昧だったり、複雑なフローで進められていたりすると、従業員にストレスを与え、不機嫌な態度につながる場合があります。こうした状況を防ぐには、指示系統や業務フローを明確に整備することが重要です。業務の割り振りや報告経路を見直すことで、無用な混乱や感情のすれ違いを回避できます。また、全体の業務が見える仕組みを導入し、風通しのよいコミュニケーションを促す体制づくりも求められます。
愛知県のS社では、まず風通しの良い環境づくりとして、女性社員が自発的に立ち上げた「チームひまわり」が、社内コミュニケーションの活性化に取り組んでいます。感謝を伝える「ありがとうのお届け便」や社内報の発行を通じて、職場の人間関係が良好になり、パワハラの相談件数がゼロになりました。会社側も就業規則でハラスメント防止を明文化し、風通しのよい職場づくりに取り組んでいます。
まとめ
職場でのため息は、状況や頻度によってハラスメントになり得ます。特に上司が部下に対して不機嫌さを示すため息や舌打ちは「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」と呼ばれ、パワハラの一形態とされることがあります。
ストレス解消のための自然なため息は問題ありませんが、相手に威圧感や精神的圧力を与える意図的なため息は職場環境を悪化させ、離職率上昇や生産性低下を招きます。対策として、本人への丁寧な指導、配置転換、業務フローの見直しなどが有効とされています。
関連記事
Related Articles
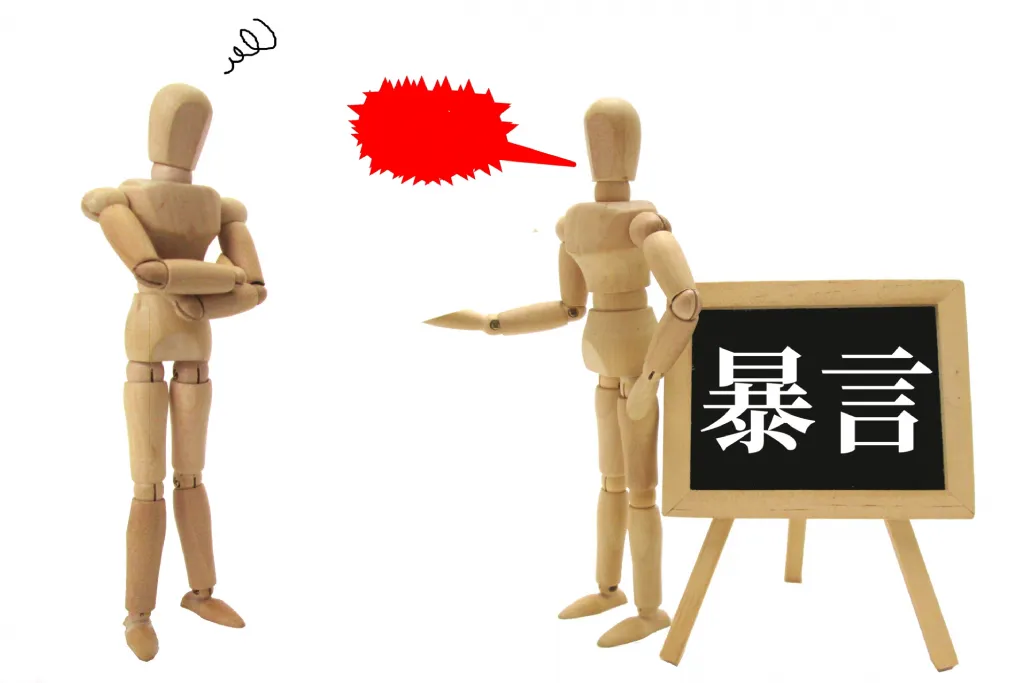
あなたの指導は大丈夫?パワハラにならないための5つのチェックポイントと解決策
部下への指導が「パワハラ」にならないためには、目的や態度、伝え方に注意が必要です。パワハラと指導の違いや見極め方、具...
ハラスメント
職場におけるモラハラとは?言動の例や加害者の特徴・対策方法を解説
モラハラは、倫理や道徳に反した精神的な嫌がらせを指し、身体的暴力を伴わずに言葉や態度で相手の尊厳を傷つける行為です。...
ハラスメント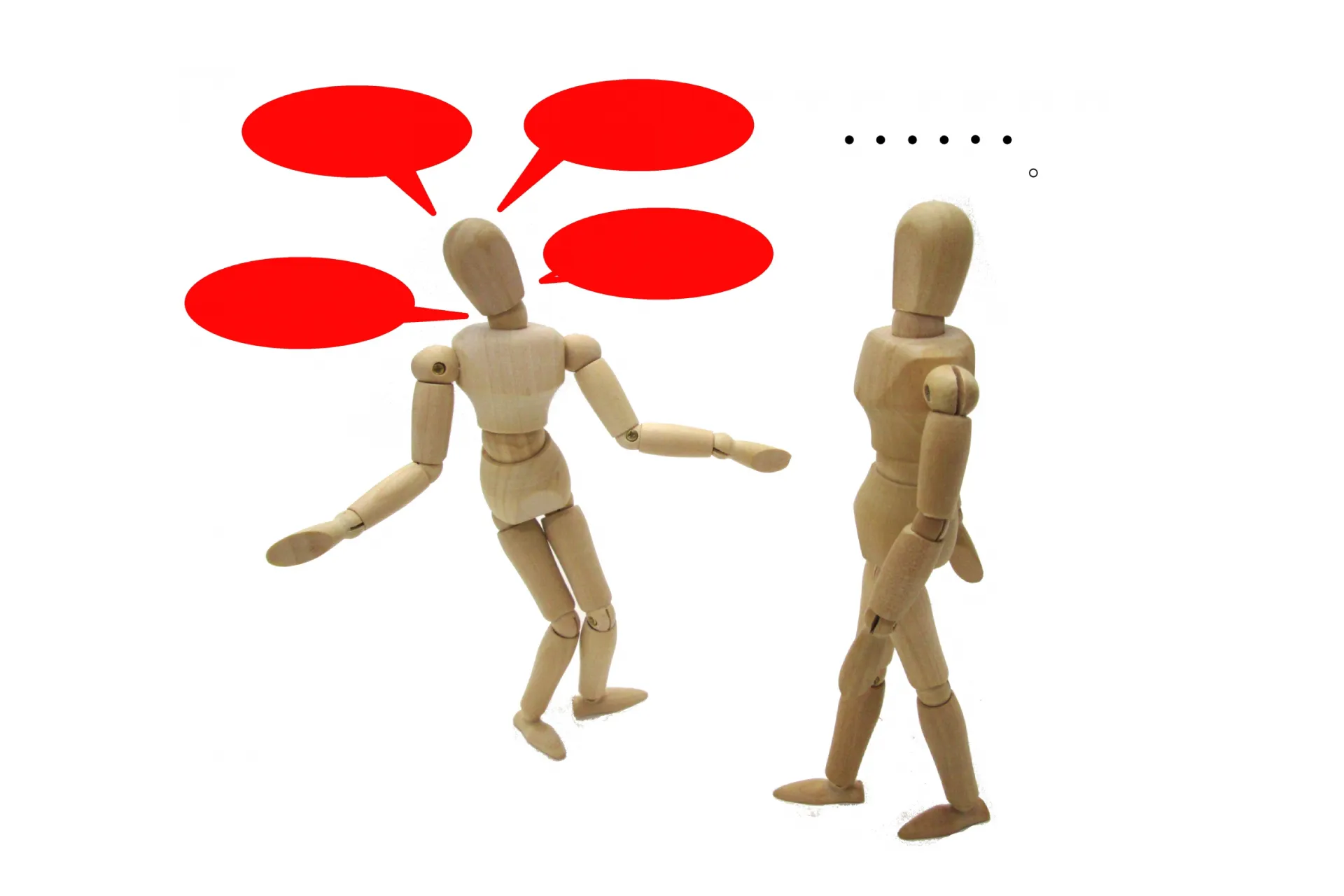
知らないと損する!セクハラする人の10の特徴と心理・対処法も解説
職場でのセクハラは、働く環境や従業員のメンタルヘルスに深刻な影響を与える問題です。セクハラをする人には特定の性格や行...
ハラスメント
加害者・被害者になる前に!パワハラチェックリストの設問や項目を紹介
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)は、加害者・被害者ともに自覚がないまま進行するケースが少なくありません。近年は...
ハラスメント