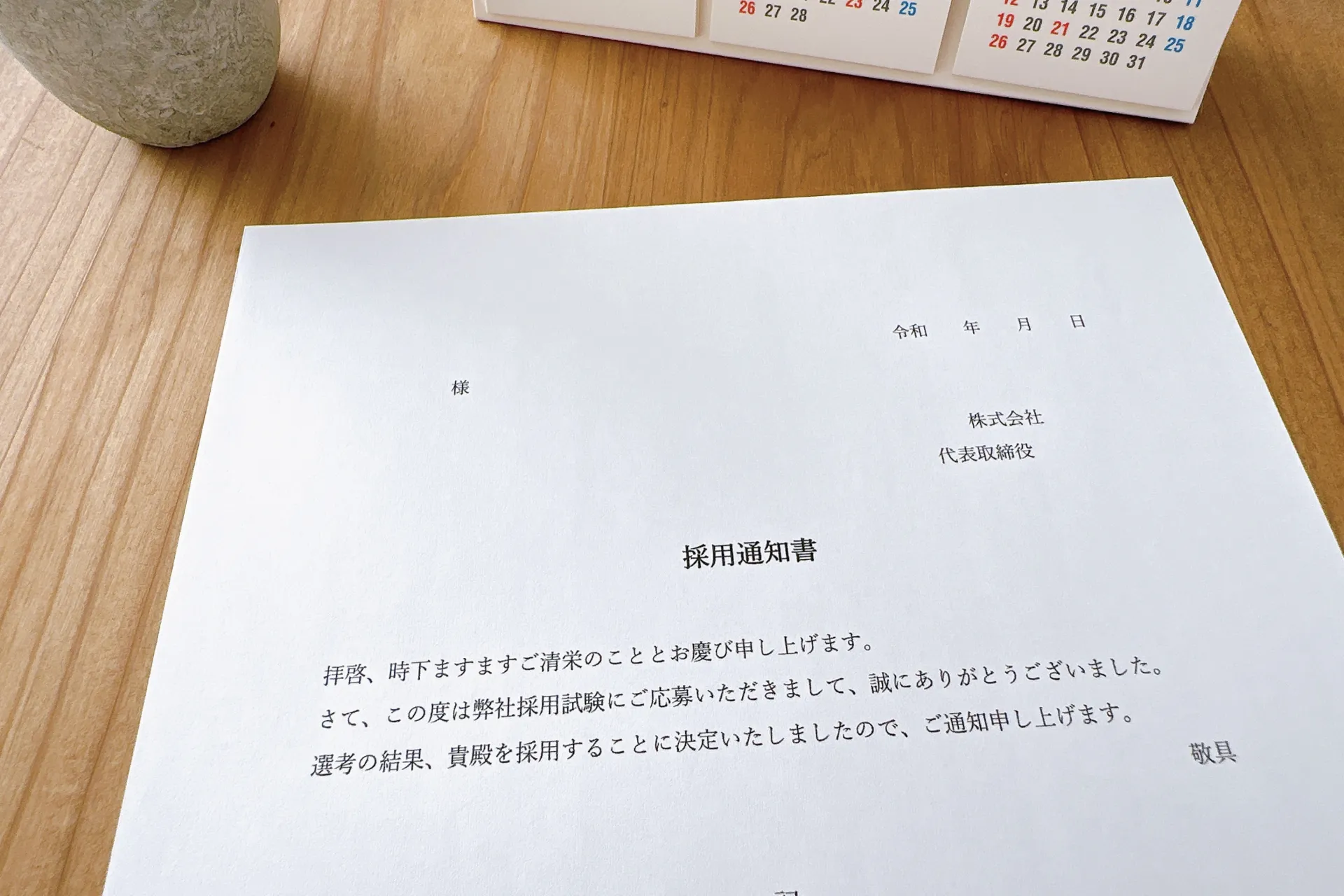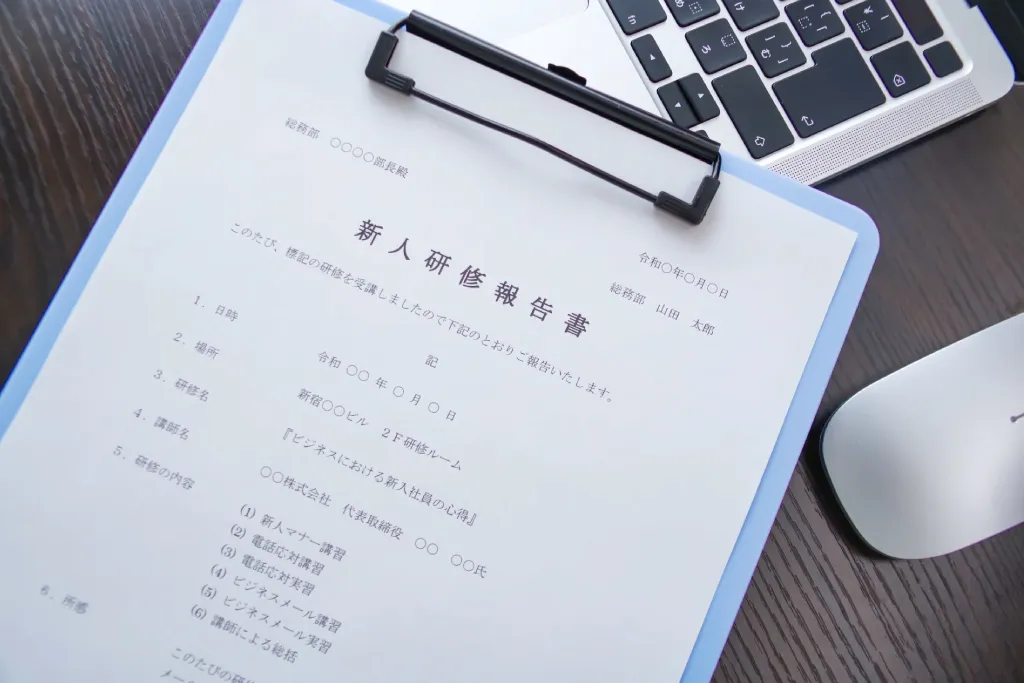- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 現場の「なぜ?」を解消!ヒューマンエラーが起きない職場を作る10の具体的な対策
現場の「なぜ?」を解消!ヒューマンエラーが起きない職場を作る10の具体的な対策
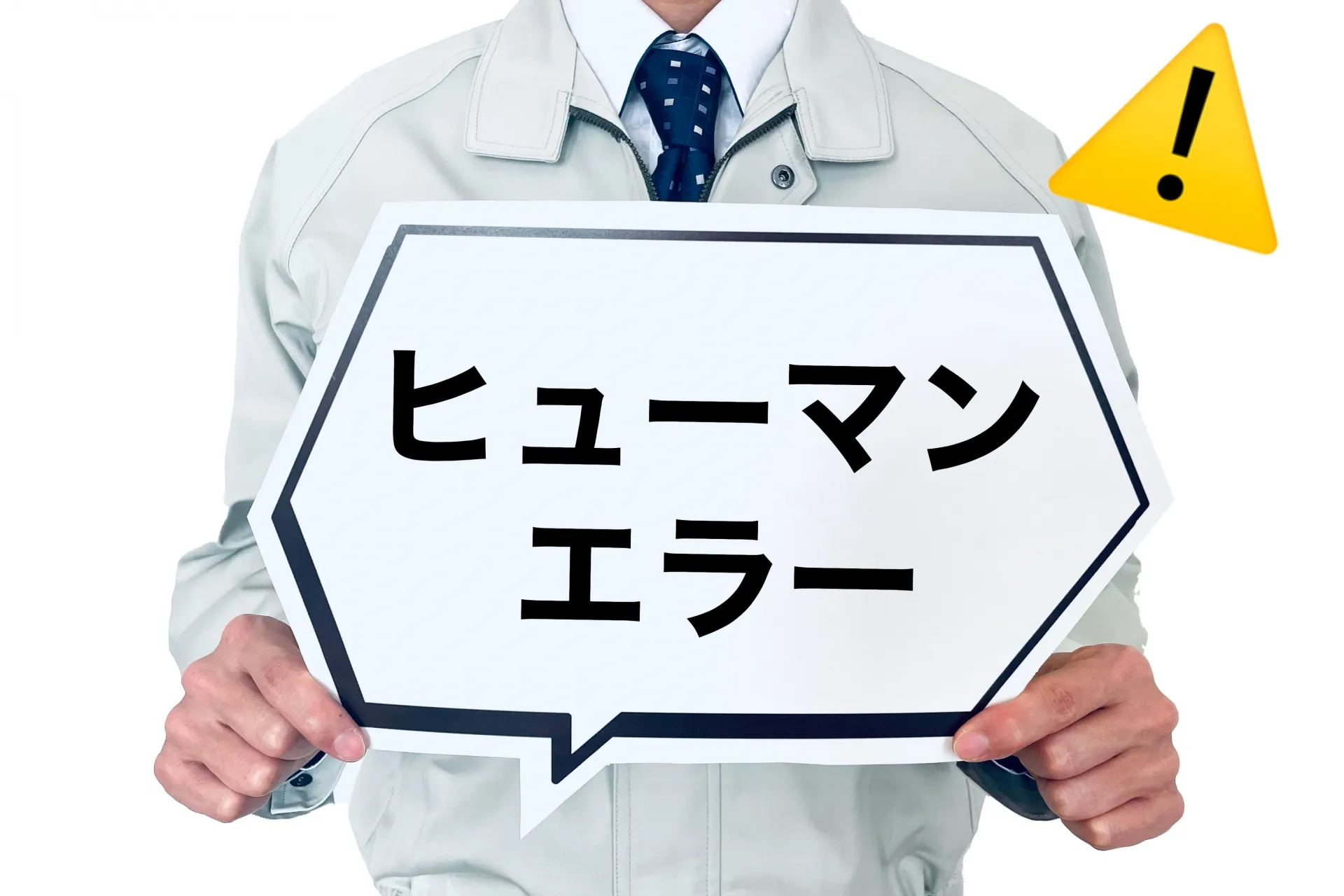
この記事は2024.12.2に公開した記事を再編集しています
2025年9月1日更新
人間が作業をするときに、つい・うっかり正しい手順を守らなかったり、多忙などの理由からあえて手順を飛ばしたりすると発生するのがヒューマンエラーです。ヒューマンエラーが発生しても、ちょっとしたヒヤリハットで済む場合もあります。しかし、会社に数百億円規模の大損害を発生させる大事故の原因にもなるため、業務フローを作るにあたってはヒューマンエラーが起きづらい仕組みを考えるのが重要です。
この記事では、ヒューマンエラーの種類や起きる理由、重大な事故事例、およびヒューマンエラーを防ぐための対策について解説します。
目次
Toggle「失敗から学び、予防策を考える ヒューマンエラー防止研修」について詳しくはこちら
「ヒューマンエラーのメカニズム100講座」について詳しくはこちら
ヒューマンエラーとは

ヒューマンエラーとは、ある事柄に対する行動をする中で、確認不足や思い込みによって引き起こされるミスのことを指しています。ヒューマンエラーによる損害の規模は、リカバリが効く程度から、企業の経営に大きなダメージを及ぼすような事故の原因までさまざまです。ミスの発生を未然に防ぐためにもヒューマンエラーの詳細を把握し、対策を講じたり、現状の職場環境の改善に取り組んだりするのが大切です。
ここでは、ヒューマンエラーの種類について解説します。
ヒューマンエラーの種類
ヒューマンエラーには大きく分けて、「ついつい・うっかり」と「あえて」の2種類が存在します。
| ついつい・うっかり | 意図的ではないヒューマンエラーです。業務内容や手順を正しく覚えていない「記憶エラー」と呼ばれるミスのほか、思い込みから誤った判断をする「判断エラー」などが該当します。 |
| あえて | 決まりごとを守らない行為や、手抜き作業によって発生するヒューマンエラーです。業務に慣れたことを理由に手順を省いたり、確認を怠ったりして発生する意図的なミスが該当します。 |
2種類のヒューマンエラーの内、どちらが発生しやすいかは職場環境や現場の状況により異なります。それぞれに対する効果的な対策も場面によって異なるため、ヒューマンエラーが発生した際はその状況や原因を適切に把握するのが重要です。
ヒューマンエラーが起きる原因

ヒューマンエラーは、心理状態や環境要因、業務慣習などさまざまな要因が複雑に絡み合って発生します。業務効率化を目指すときには、エラーの根本的な発生原因を特定し、それに応じた対策を講じることが欠かせません。
ここでは、ビジネス現場でよく見られる12の要因について解説します。
不慣れ
業務に不慣れな段階では、基本的な作業手順やルールの理解が浅く、ヒューマンエラーが発生しやすい状態にあります。新入社員や異動直後の社員など、まだ現場の流れに十分に適応できていない人は特に注意が必要です。
たとえば、新しいシステムの操作方法を十分に習得しないまま使用すると、入力ミスや手順漏れが生じる可能性があります。これは業務全体の品質にも影響を及ぼしかねません。
思い込み
思い込みによる判断ミスは、うっかり見落とされがちなヒューマンエラーの要因です。人は過去の経験や先入観に基づいて判断する傾向があり、「以前もこうだったから今回も同じだろう」といった決めつけがミスを誘発します。
特に、マニュアルが変更された場合や、顧客の要望が通常と異なる場合などには注意が必要です。変化に気づかず従来のやり方を踏襲することで、重大なエラーを引き起こすことがあります。
不注意・確認不足
注意力が散漫な状態で業務を行うと、小さな確認ミスが重大なトラブルにつながることがあります。発注書の桁数ミスや日付の入力間違いなどは、業務の流れ全体を狂わせる要因になり得ます。
特に単純作業を長時間行う状況や、複数の業務を同時に抱えている状況では注意力が低下しがちです。集中力が途切れることで、作業の中で本来必要な確認を飛ばしてしまうケースも見られます。
油断
業務に慣れたタイミングで起こりやすいヒューマンエラーが油断です。長年同じ業務に携わっていると、「この程度なら安全手順を逸脱しても問題ないだろう」「いつもと同じだから確認は不要」といった過信が生まれやすくなります。
油断によるミスは、前兆として基本的な手順や確認作業の省略が現れるのが特徴です。作業をショートカットする行動が習慣化すると、小さな見落としや判断ミスが蓄積し、ある日大きな事故やクレームにつながることがあります。
知識・経験不足
業務に必要な知識や経験が不足している場合、判断ミスや対応の遅れが発生しやすくなります。特に、入社間もない社員や異動直後の担当者は、知識不足により業務内容を理解しきれていないことや、経験不足によりとっさの判断を誤ることが多く、ミスを引き起こすリスクが高い特徴があります。
なお、知識・経験不足は本人の問題とされがちですが、教育体制が不十分な場合も根本原因の1つです。
集団欠陥
集団欠陥とは、組織や職場全体の文化や慣習によって、誤った行動が常態化してしまう現象を指します。たとえば、「この業務はいつも確認しなくても問題なかった」「皆がやっているから大丈夫」といった意識が職場に蔓延すると、個人の意識だけでは是正が難しくなります。
結果として、重大なエラーが発生しても「誰の責任でもない」状態になりやすく、業務改善も遅れがちです。
注意不足・集中力の低下
注意力が散漫になった状態や集中力が切れたときには、些細な確認ミスや見落としが発生しやすくなります。特に終業間際の時間帯は、脳のパフォーマンスが低下し、判断や処理能力に影響が出やすくなります。
また、視覚や聴覚への刺激が多い、騒音や温度の不快感が強いなどの不適切な環境は、集中力を保つのを難しくするヒューマンエラーの原因の1つです。
手順の省略
業務効率化を目的とした手順の省略が、結果として重大なヒューマンエラーにつながるケースもあります。特に納期に追われている場合や、業務が煩雑化している場面では、確認や検証、記録などの工程が後回しにされがちです。
しかし、省略された手順の中には、エラーを防ぐための重要なプロセスが含まれていることも多く、小さな見落としが後になって大きな損失へとつながる可能性があります。
連絡不足
連絡不足による情報の伝達ミスは、業務の抜け漏れや手戻りを引き起こす原因の1つです。たとえば、口頭の伝言だけで重要な情報を共有した場合、聞き間違いや記憶違いが発生する可能性があり、作業に大きな支障をきたします。
また、複数の部署が関与するプロジェクトでは、進捗状況や変更点を情報共有しきれず、認識のズレによるトラブルが起こりやすくなります。特にシフト勤務やテレワークのように、対面でのやり取りが限られる環境では注意が必要です。
過集中
過集中とは、特定の作業に意識が向きすぎた結果、周囲への注意が行き届かなくなる状態のことです。一見すると集中力が高いことはプラスのように感じられますが、ほかのタスクを忘れてしまったり、緊急の指示に反応できなかったりと、業務全体のバランスを崩す要因になり得ます。
特に、納期が迫っていたり、重要なプロジェクトに関与していたりする場合には、当人も気づかぬうちに過集中に陥っていることがあるでしょう。結果、ほかの業務やチームメンバーとの連携が希薄になり、エラーが発生します。
パニック・トラブル
突発的なトラブルや緊急事態に直面したとき、人は冷静さを失いやすくなります。特に慌ただしい職場や、プレッシャーがかかる状況では、普段できている判断や操作ができなくなり、ヒューマンエラーを引き起こします。
システムエラー発生時に操作を誤る、顧客対応中に想定外の要求がきて混乱する、といった場面は、ヒューマンエラーの原因です。パニック状態では、正確な情報処理や選択が困難になり、エラーが連鎖的に拡大する恐れがあります。
疲労・ストレス
長時間労働やプレッシャーの強い業務環境は、身体的・精神的な疲労やストレスを蓄積させ、集中力や判断力の低下を招きます。特に疲労が慢性化している場合、自覚がないままエラーを繰り返す恐れがあります。
また、ハラスメントが横行している職場では、業務以外の要因でストレスがたまるため、ヒューマンエラーが多発しがちです。些細な指示ミスや報告漏れが繰り返されるようであれば、背景に心理的負荷が潜んでいる可能性も考えられます。
「パワハラとは?定義や6つの分類・事例・防止方法などを簡単に解説」について詳しくはこちら
「セクハラとは?職場におけるセクハラの種類・定義・予防法などを紹介」について詳しくはこちら
「職場におけるモラハラとは?言動の例や加害者の特徴・対策方法を解説」について詳しくはこちら
ヒューマンエラーを起こしやすい人の特徴

ヒューマンエラーは小規模なものから大規模なものまでさまざまな形で現れます。特に分かりやすいヒューマンエラーによる被害が、労災です。
厚生労働省の調査では、労災の発生はU字を書く形で起こっています。
■男女別の労働災害発生率(死傷年の千人率)

※引用:厚生労働省「令和5年 高年齢労働者の労働災害発生状況」 引用日2025/06/16
19歳以下の若手と55~59歳のベテランはほぼ同等の労災発生率であり、60代からは若手と労災発生率が逆転します。新人とベテランの双方に注意しなければ、今後社会の高齢化が進む中でヒューマンエラーによるリスクは高まっていくと言えるでしょう。
特に労災を起こしやすい人の特徴は、以下の通りです。
| ・新卒で入社したばかりの若い社員 入社直後の新入社員は、知識や経験が乏しく、業務の全体像や判断基準を十分に理解できていないことが多いため、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。また、「報告・連絡・相談」の重要性を十分に認識できていないことから、ミスが顕在化する前に周囲へ共有されず、エラーが拡大してしまうケースもあります。 ・加齢によりとっさの判断力が低下している高齢の社員 加齢によって認知機能や判断力、反応速度が低下してくると、突発的な対応が必要な場面でヒューマンエラーが発生しやすくなります。さらに、長年の経験により業務に対する自信がある従業員は、油断や過信からヒューマンエラーを起こしやすいため注意が必要です。 ・心身の不調により注意力が低下している社員 心身に不調を抱えている社員は、通常時よりも集中力・注意力・記憶力が低下しやすく、ヒューマンエラーが生じやすくなります。身体的な疲労や病気にくわえ、メンタルヘルスの不調によっても業務の質は大きく左右されます。 ・多忙すぎる、あるいはマルチタスクが必要な状況で働く社員 業務量が過度に多かったり、常に複数のタスクを並行して処理しなければならなかったりする状況では、注意が分散され、エラーが発生しやすくなります。たと えば、電話対応中に重要なメールを見落とす、複数の案件の納期を取り違えるなどのミスが考えられます。 |
ヒューマンエラーが起こりやすい職場の特徴
ヒューマンエラーは、個々人の特性やスキル不足が原因で起こると考えられがちです。しかし、ヒューマンエラーを防ぐために重要なのは、何よりも職場環境の改善です。
以下のような特徴がある職場は、特にヒューマンエラーの温床となりやすいため、早急に改善の必要があります。
| 失敗を個人の責任に転嫁する風潮がある |
| ミスやトラブルが発生した際に、個人の責任を過度に追及する文化がある職場では、ヒューマンエラーの再発リスクが高まります。このような組織では、問題の根本原因を明らかにするよりも、誰がミスをしたかという点に注目が集まりがちです。結果、当事者が萎縮し、ミスの報告をためらう空気が醸成されます。また、過失を隠す行動や、仲間内でのかばい合いが常態化すると、教訓が共有されず、同様のエラーが繰り返される温床になります。 |
| 失敗を共有する仕組みがない |
| ヒューマンエラーを防ぐためには、過去のミスやヒヤリハットの情報を全体で共有し、次のリスクに備える取り組みが欠かせません。しかし、その仕組みが整っていない職場では、同じようなエラーが繰り返される傾向にあります。 特に、失敗を報告することが評価に影響すると捉えられている環境では、ミスの隠蔽や曖昧な報告が常態化しやすくなります。また、報告されても内容がうやむやにされ、共有・活用につながらない場合も多く見受けられます。 |
| 定められた安全な手順が実作業では実現できない |
| 現場では、安全性や正確性を確保するための手順が整備されているにもかかわらず、実際には標準化されたはずの手順通りに業務を進められないというケースが少なくありません。 例えば、スケジュールの過密さや人員の不足、作業スペースの制約などが原因で確認作業を行う時間が確保されていなかったり、専用のチェック機器が現場に配置されていなかったりする状況では、安全手順は理想論として片付けられてしまいます。このような職場では、ルールの形骸化が進み、ヒューマンエラーが起きやすくなります。 |
| コミュニケーション不全が起きている |
| 情報伝達の不備や相互理解の欠如は、ヒューマンエラーの大きな要因です。上司からの指示が曖昧だったり、担当者間での申し送りが徹底されていなかったりすると、業務内容に齟齬が生じ、結果としてミスにつながるでしょう。 また、職場における上下関係や部門間の壁が強く、タコツボ化が発生していると、必要な情報が届かないまま判断を迫られる状況が発生します。このような環境では、確認や相談のハードルが高く、独断による行動が増えるため、リスクが拡大します。 |
ヒューマンエラーが続いた例として、マシュー・サイド『失敗の科学』には、アメリカでは年間40万人以上が医療過誤で死亡していると書かれています。これは、毎日2機航空機が墜落事故を起こしている状況に匹敵する死者数です。
これほどの医療過誤が起きる原因として、医療従事者が厳重な処罰を避けるために、自分が起こしたミスを共有せず隠す傾向がある点が指摘されています。また、同様に大事故が起きた際に大規模な死者が出る航空業界と比較して、医療事故による失敗を共有する仕組みがなく、専門性が高いために業種ごとに壁が高くコミュニケーション不全が起こりやすい点も、医療事故の原因です。
また、国内の事例では、東海村原発事故もヒューマンエラーの結果起きた大事故です。東海村では国で決められた安全マニュアルを守らず、効率化のために放射性物質をバケツで混ぜた結果、死者および多数の被爆者を発生させる放射能漏れが起こりました。大事故の原因は、現場の業務の手間が多く、大変だったために効率化しようとしたという単純なものでした。現場の担当者はほとんど放射性物質の取り扱い方について知らされておらず、さらに取り扱い方を知っていた上層部はずさんなチェック体制でマニュアル変更を許容していたとされています。
ヒューマンエラーが起こりやすい環境を放置すると、膨大な死者を出す過誤や、歴史に残る凄惨な事故が起こりうることがここからも分かります。
ヒューマンエラーが原因で起きた重大な事故の事例2つ

ヒューマンエラーはどのような企業でも起こりうる事象です。小さなミスや事故、失敗で終わるケースもありますが、多額の損害を出すなど企業に深刻な状況を招く場合もゼロではありません。
ここでは、実際に発生したヒューマンエラーによる重大な事故の事例を2つ紹介します。
みずほ証券:ジェイコム株誤発注事件
みずほ証券の担当者が、株式数と価格の数値を誤って入力したことにより発生した事件です。本来は「1株を610,000円」で売るつもりが、「610,000株を1円」として登録してしまいました。登録時に警告文は出ていたものの、担当者は「よくあること」と無視し、データ入力ミスに気づかないまま誤発注を完了させています。
誤発注に気付いた後、直ちに取り消し作業を試みたものの、処理中は取り消しできないプログラムになっていました。結果的に取り消しは失敗し株価が急落、みずほ証券は約400億円の損失を招く事態に陥ったと言われています。
頻出する警告を「いつもと同じ」と判断し発生したこの誤発注は、みずほ証券の財務面に大きなダメージを与えています。くわえて、株式市場にも大きな影響を与えたとされる事件です。
JR西日本:のぞみ34号重大インシデント事件
JR西日本が運行する新幹線のぞみで発生したのが、「のぞみ34号重大インシデント事件」です。インシデントとは、何らかのトラブルにより大きな事故が引き起こされる一歩手前の状況を指しています。
2017年に新幹線のぞみが博多から東京に向けて走行している最中に、異音・異臭が確認されました。しかし、直ちに点検されることはなく、しばらく走行したのち名古屋駅で運行停止となっています。名古屋駅で床下点検が行われた結果、台車に亀裂が入っている事態が発覚しました。幸い走行中に台車が破断する状況には至らなかったものの、運行停止の判断がさらに遅れていれば被害者が出ていた可能性のある事件です。
当時の関係者は下記のように認識していたとの話があり、思い込みや伝達ミスがあったことが把握できます。
| ・ 異音と異臭が関連していると思わなかった ・ ほかの担当者によって確認済みと判断し走行を続けた |
ヒューマンエラーは自社だけではなく、顧客も巻き込む可能性もある存在です。事前に工夫や対策を講じ、ヒューマンエラーを発生させない環境を整えましょう。
【具体例あり】ヒューマンエラーを防ぐための対策10選

ヒューマンエラーを完全に防ぐのは困難ですが、事前の対策により重大な事故を未然に防ぐ工夫をするのは可能です。
ここでは、ヒューマンエラーを防ぐのに有効な対策を10種類紹介します。
ヒヤリハットを見逃さない
ヒヤリハットとは、作業中にヒヤリとしたりハッとしたりする危ない状況が起きたものの、大きなミスには至らなかった出来事のことです。
ヒヤリハットを放置した場合、重大な事故につながる問題を見落とす可能性があります。有名な例が、「同じ人間が起こした330件の事故のうち、1件の重大事故に対して、29件の軽い事故と300件のヒヤリハットが起きている」というハインリッヒの法則です。
そのため、ヒヤリハットが起きた際は「ミスに至らなくてよかった」と安心して終わらせず、自身が体験した出来事を作業者間で共有するのが大切です。些細な体験でも報告し共有し合える環境を整えると、同じミスが起きないように都度対策ができます。
フールプルーフを導入する
フールプルーフとは、人による誤操作を防ぐ機械や設備、システムの設計を指しています。誤った操作や特定の操作を検知すると、自動で警告したり機能を制限したりするため、ミスをしようとしてもできない、またはミスを最小限にとどめる仕組みづくりが可能です。
たとえば、機械を扱う場面が多い製造業では、誤操作による手の挟み込みや場合によっては切断に至るような危険性が存在しています。大きなケガや事故につながる可能性が考えられる現場では、フールプルーフは特に安全性の向上に貢献する設計です。そのため、フールプルーフは企業の作業環境だけではなく、日常生活に用いる設備などにも採用されています。
指さし確認などで注意喚起をする
指差し確認はアナログで簡単にできるチェック方法ですが、ミス発生防止に役立つ対策の1つです。製造業をはじめとする多くの業界で取り入れられています。
指差し確認で得られる効果は、下記の通りです。
| ・ より集中して対象物を確認する ・ 焦りによる確認漏れの防止 ・ 意識レベルの向上を促す |
指差し確認は、単調に行ってもミス発生防止の効果を得られません。対象物をしっかりと見て指差すのにくわえ、名称などを呼称するとより意識を向けられ、ヒューマンエラーの防止ができます。
マニュアルを整備する
定期的に更新されているマニュアルは、思い込みやうっかり、確認漏れなどのあらゆるミスを防ぐのに役立ちます。
マニュアル整備をする際は、下記のポイントを意識しましょう。
| ・ 業務の目標やゴールを明確に記載する ・ 古い手順と新しい手順の違いを記載する ・ 手順は書き連ねず1つの工程ごとに区切るなど、視認性を高める ・ 具体例を記載し、確認の重要性などを記載する |
マニュアルは、特に複雑な作業をする際に役立つ存在です。イラストや図、写真を挿入するほか、可能であれば動画なども活用すると、作業に不慣れな人でも理解しやすくなります。
より簡潔な業務フローに見直す
複雑な業務フローは分かりづらく、作業に慣れるまでに時間がかかります。ミスを招く原因になるほか生産性の低下にもつながるため、複雑な業務フローは簡潔になるように内容を見直しましょう。
たとえば、誰が・いつ・どのタイミングで何を実行するのか不明瞭な記載や、用語が統一されていない内容は、そもそも理解するのに時間を要します。間違って理解してしまい、勘違いによるミスを誘発する可能性も考えられる状況です。そのため、担当者以外の誰が見てもスムーズに作業の流れが掴めるように、業務フローはシンプルに仕上げましょう。
業務を自動化する
複雑な作業がなくパターン化しやすい業務は、自動化すると人による手作業を減らしミスの発生防止を図れます。
自動化できるとされる主な業務は、下記の通りです。
| 経理 | 仕訳や伝票入力・入出金管理 |
| 人事・総務 | 勤務時間管理・報告書作成 |
| 倉庫 | 検品・発注・在庫管理 |
| 営業 | 営業メール送信・見積書作成 |
業務を自動化すると、誤った設定をしない限り入力ミスや漏れを防げます。品質向上につながるだけではなく複数人による確認も不要となり、業務効率の向上にも期待できます。
チェックリストを作る
チェックリストを活用すると作業の抜けがないか、また正しく作業が実行されているか「見える化」ができます。記憶に頼って作業を完了させるよりも、作業一つひとつを明確に捉えてチェックできるためミスの発生防止に効果的です。複数人が関わる作業でも、人によって認識違いが起きたり品質が変わったりする状況を防げます。
チェックリストは、可能であれば電子化するのがおすすめです。紙に書き出す手間を省いてデータ管理できるほか、メールなどの活用により複数の作業者への共有が楽になります。
ただし、ヒューマンエラーが発生したからと言ってチェック回数やチェック項目を増やすと、一つひとつの項目をしっかりとチェックできなくなり、効果が薄れます。不要なチェック項目はできるだけ減らし、最低限見るべきところだけを複数の異なる視点から確認するリストにするのが大切です。
発生したヒューマンエラーについて共有する
同じミスを繰り返さないためにも、発生したヒューマンエラーは作業者間で共有するのが大切です。共有によって業務フローに見直せる点はないか、ミスが起きやすい手順はないかなどの、作業の改善点を見つけるのに役立ちます。ほかの作業で同じようなミスが起こる可能性を考慮するのにも役立つため、ヒューマンエラーを欠かさず共有できる環境づくりを意識しましょう。
発生したヒューマンエラーは、過去の失敗事例として記録するのがおすすめです。対策や改善点も併せて記録すると、今後の経営に生かせるヒントになる可能性があります。
危険予知訓練を行う
危険予知訓練とは、作業内に潜むミスを誘発する事柄や、事故を引き起こす可能性のある危険な要因を発見・解決する力を高める訓練です。5~6人を1つのチームとして編成し、実際の作業や話し合いによる訓練を実施します。
訓練では、イラストや動画なども活用されるのが特徴です。チームで同じ状況を把握し、どのような危険点があるか発見・確認と絞り込みを行います。続いて、危険点の解決に向けた意見を出し合い、対策を実践に移せるように目標設定することで、ヒューマンエラーへの認識を高めます。
ヒューマンエラー研修・教育を行う
ヒューマンエラー研修を実施すれば、人為的ミスが発生する原因の理解や予防、対策を身につけられます。ヒューマンエラーが発生するメカニズムを我がこととして認識・理解することで、致命的なミスを避けるための環境づくりに役立つでしょう。
研修・教育は、社内でマニュアルやプログラムを作成し実施する方法と、外部講師に依頼する方法が存在します。ヒューマンエラーに対する全体的な知識の学習や、より特化した教育機会を得たい場合には外部講師への依頼がおすすめです。
ヒューマンエラーが起きづらい職場環境の作り方

ヒューマンエラーを防ぐには、職場環境の改善も重要です。主に下記に挙げる2点に着目し、自社の職場環境を見直しましょう。
| ・心理的安全性の確保 心理的安全性とは、組織の中で周囲の影響を受けず、安心して自分の意見を発言できる状態のことです。自分の気持ちや物事への考え方が少数派の意見であったとしても、拒絶や罰せられることがないと確信して発言できるため、本音での話し合いがしやすくなります。反対に心理的安全性がない職場では、自分の発言や行動による失敗や否定される状況を恐れるあまりミスが誘発される可能性が高く、注意が必要です。 ・長時間労働の防止 長時間労働によって疲労が蓄積すると、それ以上の負担が長続きしないように人間の脳は小休止を取ろうとします。自然と労力を抑えて行動するように力が制限されるため注意力が落ち、見落としや見逃しが発生しやすくなります。 |
心理的安全性があり長時間労働がない職場は、心身ともに負担が少ないと言える環境です。ミスが少ない職場を目指すのであれば心理的安全性が保たれており、かつ長時間労働がない環境を整えられるよう意識しましょう。
企業によるヒューマンエラー対策の事例

適切なヒューマンエラー対策を実行できれば、ミスを誘発しにくい環境を整えるのに役立ちます。どのような対策が自社に効果的か判断に迷う場合は、他社の事例を参考にするのがおすすめです。
ここでは、ヒューマンエラーを効果的に防いでいる3つの企業の事例を紹介します。
トヨタ自動車
トヨタ自動車は、異常が生じたら機械が自動で停止したり、ランプで知らせたりする機能を活用して「ポカヨケ」と呼ばれるヒューマンエラー対策を行っています。部品の締め忘れなどのチェックも、機械に任せて人の手作業を減らすことで、不良品の発生防止を図っています。こうしたヒューマンエラーを抑止する方法は、「ニンベンのついた『自働化』」と呼ばれており、人が機械の見張りをする必要をなくす目的でグループ創始者の豊田佐吉が考案したものです。
また、トヨタ自動車には失敗を財産として扱い、失敗を認めやすい環境にするルール「失敗は見える所に置け」があります。ミスが発生しても自分だけで解決しようとせず、言い出しやすくなる環境が整うため、周囲の助けを得やすくなります。
一の湯
老舗旅館の一の湯は、IoTシステムの導入により、特にヒューマンエラーが多かった温泉施設の制御設備の操作ミスへの対策を行い、顧客サービスの品質向上を図っています。
導入しているのは、従業員によるバルブ開閉の操作記録が残っていないと、自動的に担当者に通知が届くシステムです。システムのチェックと通知によって操作漏れが把握できるため、水道費・光熱費の無駄や、お客様への温泉提供の遅れを未然に防げるようになりました。
富士フイルムテクノプロダクツ
富士フイルムテクノプロダクツは、医療機器の製造を担っている企業です。1つのミスが機器の不良を引き起こし、誤診につながる可能性も考えられるため正確な製造が欠かせません。
厳しい規格を設けてはいるものの、より正確な機器の製造を目指すため、トラブル発生時には自動的に作業が停止するシステムを活用しています。たとえば、ネジを締める順番が間違っていれば速やかにミスが検知される仕組みです。ミスが発生したまま作業が進むのを防げるため、そもそも「間違えられない」環境が作られています。
まとめ
ちょっとしたヒューマンエラーでも、放置されているうちに重大な事故に発展する可能性もあります。何かしらのヒューマンエラーが発生した場合は共有し、フールプルーフの導入や指差し確認、業務フローの簡素化・自動化を取り入れる形でマニュアルを更新しましょう。また、チェックリストを導入するのも有効です。ただし、確認に手間がかかりすぎる非効率的なチェックリストはかえってチェックを飛ばすヒューマンエラーのもとになるため、簡素化を心がけてください。
対策方法を浸透させるためにも、危険予知訓練やヒューマンエラー研修・教育を導入し、それぞれの従業員にヒューマンエラーを減らす意識を持たせましょう。
関連記事
Related Articles

2030年に必要な未来のスキルも解説|社会人に必須のビジネススキル一覧
ビジネススキルは、仕事を効率的に、かつ効果的に遂行するために必要なスキルです。社会人として昇給や昇格を目指す場合にビ...
企業研修
【アイスブレイク鉄板ネタ9選】ビジネスですぐ使える事例を徹底解説
アイスブレイクとは、会議や研修、ワークショップなどの開始前に短い時間で行うアクティビティです。参加者同士の親睦を深め...
HRトレンド企業研修