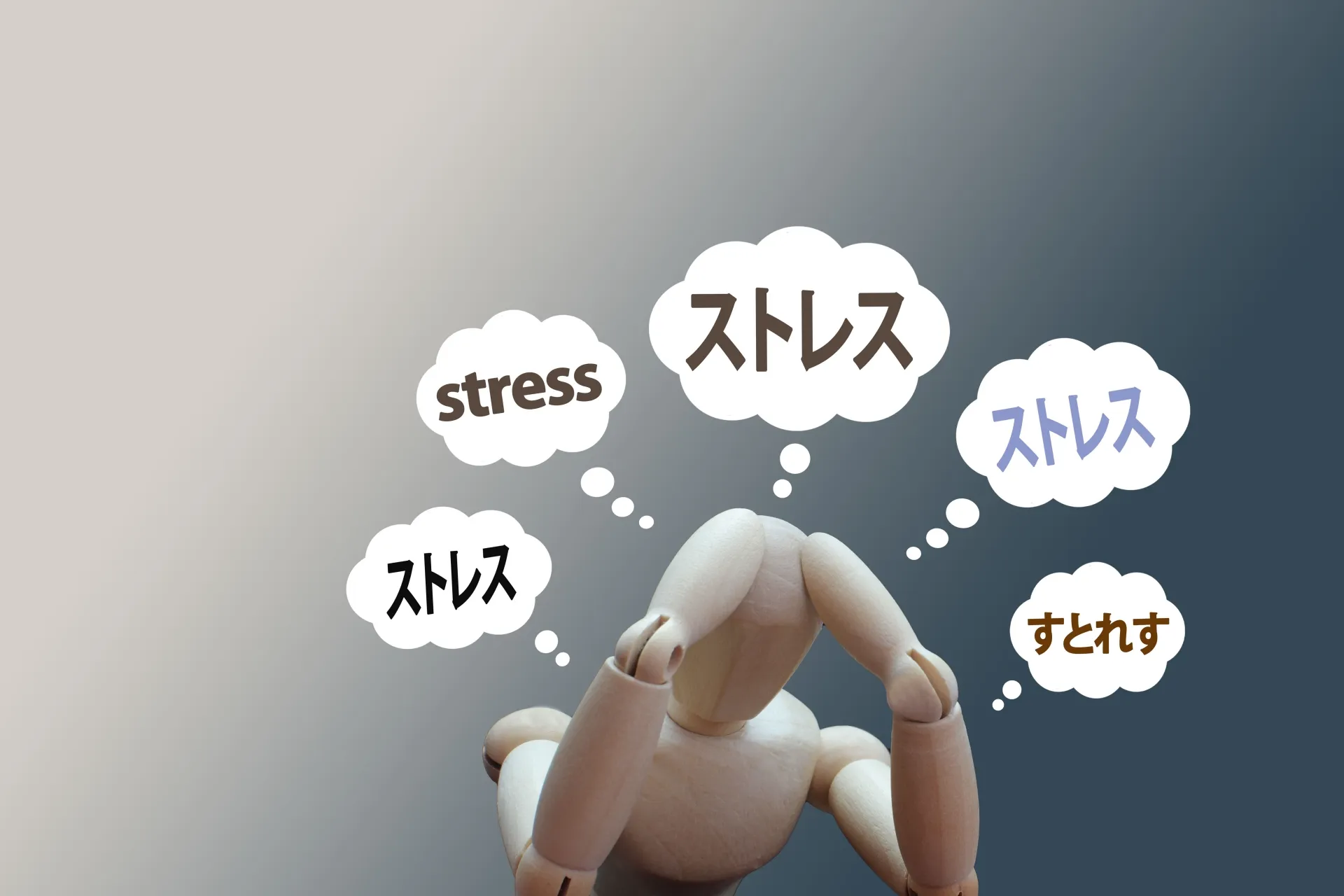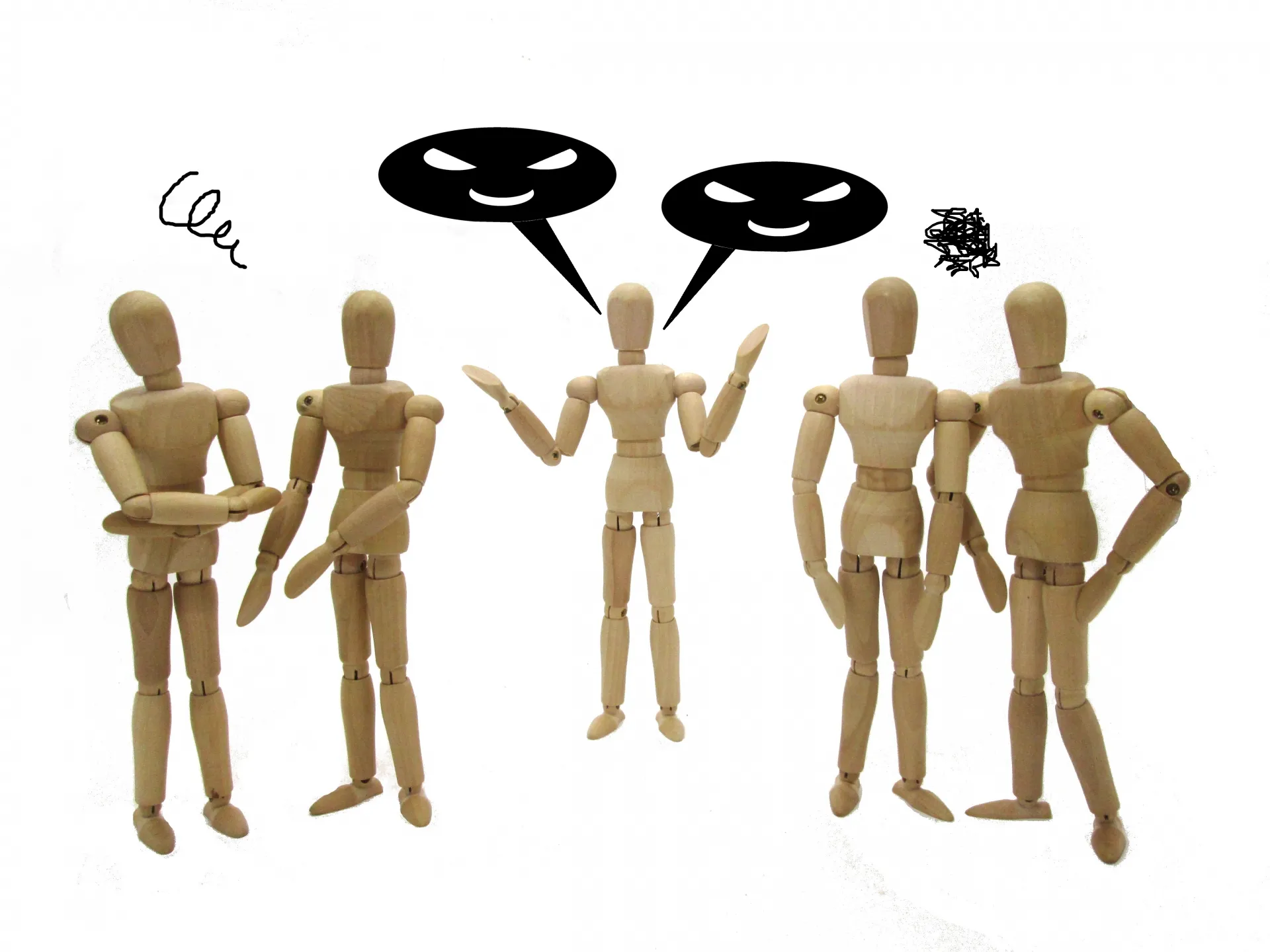- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- ハラスメント
- パワハラされやすい人の8つの特徴とは?自分を守る対処法を伝授
パワハラされやすい人の8つの特徴とは?自分を守る対処法を伝授

職場でパワハラの被害を受ける人には、ある共通した傾向が見られます。真面目で反論しない人や、自信がなさそうに見える人は、加害者にとって“攻撃しやすい”存在と見なされやすく、標的にされるリスクが高まります。
一方、加害者側にも共通する特徴があり、完璧主義や感情的な性格など、一定のパターンが見受けられます。また、コミュニケーション不足や人手不足といった職場環境も、パワハラの温床となることがあります。
本記事では、パワハラされやすい人と加害者に共通する特徴、パワハラが起きやすい職場の特徴、パワハラを避けるために個人ができる対処法などを詳しく解説します。
目次
Toggle『最低限の知識と対処法を身につける ハラスメント予防研修』について詳しくはこちら
パワハラされやすい人に見られる特徴8つ

パワハラの被害に遭いやすい人には、一定の共通点が存在します。特に、性格や行動の傾向、人間関係の築き方などが影響し、無意識のうちに加害者から標的にされてしまうケースも少なくありません。自分では当たり前だと思っている態度や言動が、職場での立場を不利にする要因となることもあります。
ここでは、パワハラされやすい人に見られる代表的な特徴を8つ紹介します。
真面目で上司に逆らわない
真面目で上司に対して従順な人は、職場では信頼されやすく、一定の評価を受けることも多い傾向があります。しかし、どんな理不尽な言動に対しても反論せず受け入れてしまう態度が、「何をしても大丈夫な相手」と認識される原因になることがあります。
パワハラ加害者は、反撃や抵抗のリスクがないと感じる相手に対して攻撃的な態度を取りやすいため、真面目で逆らわない人はその対象になりやすい傾向があります。過剰な責任を引き受けてしまうことで結果的にミスや負担が生じ、さらに攻撃される悪循環に陥ることもあるため注意が必要です。
良くも悪くも正直な性格である
正直にものを言うことは、誠実さや信頼感につながる長所ですが、職場環境によっては摩擦の原因になることもあります。たとえば、思ったことをそのまま口にする人や、上司に対してお世辞を言わないタイプの人は、「配慮に欠ける」「生意気だ」と受け取られることがあります。
パワハラを行う人物は、自尊心が傷つけられたと感じたときに攻撃的な反応を示すことがあり、相手の意図とは無関係に敵意を抱く場合があります。正直さそのものが悪いわけではありませんが、相手の立場や状況に配慮した伝え方を意識しないと、思わぬトラブルにつながることがあります。
コミュニケーションが得意でない
報告・連絡・相談といった基本的なコミュニケーションが十分に行えていないと、職場での信頼関係が築きにくくなります。上司や同僚と必要な意思疎通が取れていない場合、進捗や問題点の共有が遅れ、結果としてトラブルや誤解を招くことがあります。適切な意思疎通が取れない状況が続くと、「何を考えているか分からない」「周囲との連携がとれていない」といった否定的な評価につながり、攻撃の対象になりやすくなります。
加えて、相談できる相手が少なく孤立していると、外部からのサポートも得られにくく、パワハラのリスクが高まる点も見逃せません。
仕事を覚えるのが苦手である
業務の習得には個人差があるものの、仕事を覚えるのが遅いと見なされると、職場では厳しい視線が向けられることがあります。特に、パワハラ気質の強い人物は、自分の基準で他者の能力を測る傾向があるため、思うように成長しない相手に苛立ちを感じやすくなります。
こうした加害者は、過去の自身の経験を顧みず、現時点での結果だけをもとに相手を責める傾向にあります。結果的に、覚えが悪いことを理由に過剰な叱責や人格否定が行われるリスクが高まってしまうでしょう。仕事の習得には焦らず丁寧な支援が必要ですが、それが行われない職場環境ではパワハラの温床となり得ます。
マイペースな振る舞いが見られる
自分のペースを大切にして行動することは、一定の独立性や主体性を示す一方で、集団での協調が重視される職場では誤解を招く場合があります。たとえば、周囲が忙しくしているときに定時で帰ったり、暗黙の了解とされているルールに従わなかったりする場合、周囲の不満を引き起こすことがあります。
マイペースな行動が職場の空気とズレて見えると、「協調性がない」「わがまま」といった評価を受けやすくなり、パワハラの対象になりやすくなるリスクがあります。実際には悪意がないとしても誤解によって孤立しやすく、標的にされる可能性が高くなります。
仕事のミスが多い
業務上のミスは誰にでも起こり得ることですが、頻度が多い場合は「能力が低い」と見なされ、過度に厳しい指導や叱責を受ける原因になることがあります。特にパワハラを行う人物は、ミスを口実にして感情的な言動を正当化しようとする傾向があり、相手の人格を否定するような言葉や態度をとることもあります。
本人に改善の意思があっても、意思が十分に認識されないと、状況が悪化しやすくなります。ときには、同じミスを繰り返さないよう努力している姿勢すら無視され、攻撃の材料として利用されてしまうこともあります。
自分に自信がないように見える
自信のなさは、言動や態度にあらわれやすく、それが職場での評価や対応に影響を与えることがあります。たとえば、話すときに目を合わせない、指示に対して消極的な態度をとるといった行動が、「頼りない」「弱々しい」と受け取られやすくなります。消極的な印象を与える人は、パワハラを行う人物から「反論してこない」と見なされ、支配の対象にされやすくなります。
また、困っているときに助けを求めることが難しい傾向もあり、問題が表面化しづらいまま深刻化するケースも少なくありません。
嫉妬されやすい要素が多い
容姿や学歴、業務スキルなどが際立っていると、周囲の嫉妬を招きやすくなります。特に、目立つ存在であることが加害者の自尊心を刺激し、「気に入らない」「生意気」といった否定的な感情につながる場合があります。本人に悪意や過剰な自己主張がなくても、評価される場面が多いこと自体が反感の対象になることがあるのです。
また、プライベートでの充実ぶりを話題にするなど、意図しない言動が嫉妬心を煽り、パワハラのきっかけとなることもあります。環境や人間関係によっては、目立つことで不利益を被るケースもあるため、慎重な言動が求められる場面もあります。
パワハラの加害者になりやすい人の特徴5つ

パワハラの加害者には、職場の立場や役職だけでなく、性格や思考パターンにも共通する傾向が見られます。中でも注意が必要なのは、次の5つの特徴を持つタイプです。それぞれの特徴を具体的に解説します。
完璧主義者である
完璧主義の人は、自他に厳しく、仕事のミスや遅れを強く咎める傾向があります。部下に対しても自分と同じレベルの完成度を求め、細かな点まで過剰に口出しすることが多くなります。過剰な口出しが続いた結果、部下の自主性が奪われたり、精神的なプレッシャーを過剰に与えたりする場面が生じやすく、パワハラと受け取られる恐れがあります。
完璧主義が悪いわけではなく、完璧主義を他者に押し付けすぎると職場の人間関係を悪化させる要因となります。
感情的な振る舞いがよく見られる
感情の起伏が激しい人は、状況に応じた適切な対処が難しく、職場での対人関係にも悪影響を及ぼします。特に、怒りや苛立ちを抑えられずに大声を出す、威圧的な言葉を使うといった行動は、部下に対する明確なハラスメントにつながります。
相手のちょっとした行動を敵意と解釈し、過剰に反応してしまうこともあり、ターゲットとなった部下の心身に大きな負荷をかけるケースも少なくありません。
自分の優秀さを誇示するくせがある
自分の能力や実績を誇示したがる人は、周囲を見下すような態度を取りがちです。自尊心を誇示するタイプは、他者の評価よりも自分の評価を最優先に考え、部下の手柄を横取りしたり、他人の失敗を過剰に非難して自身の優位性を強調したりする傾向があります。
また、業務の目的よりも自分が目立つことを重視し、部下を単なる実績づくりの道具とみなすケースもあります。自分しか見えていない行動は、職場内での信頼関係を損ない、威圧的な態度や無責任な振る舞いがパワハラと見なされる原因となります。
責任感が欠けている
責任感が乏しく、失敗や問題を他人のせいにするタイプも、パワハラを起こしやすい要注意人物です。自分の業務上のミスを部下になすりつけたり、業務上のトラブルが発生した際に真っ先に部下を責めたりする姿勢は、信頼関係を損ない、精神的圧力を与える原因になります。
また、部下の事情や負荷を無視して無理な業務を押し付けるといった行為も、結果的にハラスメントとなる場合があります。
独善的で支配欲が強い
自分の価値観や考え方が絶対であると信じ込み、他者の意見を聞き入れない独善的な性格は、支配的な振る舞いにつながりやすい特徴です。自分の指示に従わない部下を攻撃したり、必要以上に統制したりすることで、部下の自由な行動や発言を抑圧します。
部下の行動や発言を抑圧する姿勢は、部下の心理的安全性を著しく損なうため、パワハラとして指摘されることも多く、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼします。
パワハラが起きやすい職場の特徴

パワハラが発生しやすい職場には、いくつかの共通した特徴があります。以下に代表的な要因を挙げ、それぞれについて解説します。
| ■コミュニケーションが足りていない 日常的な報連相が不十分な職場では、誤解や不信感が生まれやすく、業務上のトラブルが起きやすくなります。対話が少ない環境では指導と攻撃の境界が曖昧になり、指示に対して過剰な叱責が行われることがあります。 ■人手不足で業務負担が大きい、業績が低下している 常に人手が足りない状態や業績不振が続いていると、職場全体に余裕がなくなります。責任の押しつけ合いや感情的な指導が起こりやすくなり、ストレスが他者への攻撃としてあわられるケースも見られます。 ■ノルマが過度に厳しい 目標達成を強く求める環境では数値の達成が最優先となり、人間関係や働き方への配慮が軽視されがちです。プレッシャーの中で、部下に対して過剰な言動が正当化される危険性があります。 ■失敗が許されない 一度のミスでも強い叱責や責任追及が行われる風土では、心理的安全性が失われ、萎縮や対人トラブルの温床となります。ミスに対する寛容さがない職場は、長期的にみて人材が定着しにくくなります。 |
特に、上下関係が厳しく「昔ながらのやり方」に固執する旧態依然とした職場や、属人的な働き方に依存している環境では、パワハラが起きやすい土壌が形成されやすい点に注意が必要です。
パワハラされにくくなるために個人ができる対処法

パワハラは組織全体の問題である一方で、個人の振る舞いや対人関係の築き方によって、被害を受けにくくすることも可能です。明確な意思表示や日常的な人間関係の工夫など、日頃の意識がリスクの軽減につながる場合があります。
以下では、職場でパワハラの対象にされにくくなるために、個人が実践できる行動や心構えを4つ紹介します。
職場で味方を増やす
パワハラを防ぐためには、職場内で信頼できる人間関係を築くことが重要です。特定の人とだけ関係を深めるのではなく、広く浅くでもよいので複数の人と会話やあいさつを交わすよう心がけると、周囲からの支援を得やすくなります。
孤立している人ほど標的にされやすく、助けを求めたときに誰も状況を把握していないという事態に陥る可能性もあります。上司だけでなく、その上の立場の人や他部署のメンバーと交流を持つことも、いざというときの防御策となります。
毅然とした態度をとる
パワハラを行う人は、自分にとって抵抗しにくい相手を選ぶ傾向があります。表情や姿勢、言葉遣いなどで自信を持っている印象を与えることは、攻撃の抑止につながります。無理な要求や理不尽な指示を受けた場合は、「それはできません」「理由があるのでお受けできません」と、丁寧かつ明確に断る意思を示すことが大切です。
すべてを受け入れてしまうと際限なく要求がエスカレートする可能性があるため、自分の限界を伝える習慣を身につけることが予防策になります。
仕事の能力を高める
業務遂行能力を高めることは、職場での信頼を得るだけでなく、パワハラの標的になりにくくする効果も期待できます。仕事での成果が安定すれば、不当な叱責の口実を与えることが減り、加害者側も攻撃の理由を見つけにくくなります。
また、仕事への集中は精神的にも前向きな影響を与え、余計な不安やストレスを軽減することにもつながります。日々の業務の見直しや、スキルアップのための資格取得などを通じて、実力を高めることは長期的な自衛手段となります。
自慢や自己アピールをしすぎない
優れた実績やスキルは評価されるべき資質ですが、必要以上に誇示すると、周囲の反感や嫉妬を招く原因になることがあります。特に職場では、協調性が重視される場面も多いため、自己主張が過度になると「でしゃばっている」といった否定的な印象を持たれやすくなります。
あくまでも成果は行動で示し、言葉による過度なアピールは避ける姿勢が無難です。人間関係を円滑に保つことも、パワハラを回避する重要な要素であるといえます。
自分がパワハラのターゲットになったときの対処法

もし自分が職場でパワハラの標的になっていると感じた場合、我慢を重ねるだけでは状況が悪化するおそれがあります。精神的・身体的な健康を守るためには、早めに適切な行動をとることが重要です。以下では、パワハラに直面した際に実践したい具体的な対処法を紹介します。
パワハラの証拠を残す
パワハラ被害を訴える際には、客観的な証拠が非常に重要です。音声やメール、メモなどの記録があると、被害の深刻さや継続性を第三者にも正確に伝えやすくなります。たとえば、暴言や不当な指示の録音、日々の出来事を詳細に記した日記、診断書などが挙げられます。
証拠がなければ、たとえ事実があっても主観的な訴えとして扱われるリスクがあるため、証拠収集は早期に始めましょう。将来的に労働基準監督署や裁判所に相談する際にも大きな支えとなります。
社内外の相談窓口に相談する
証拠が集まったら、社内の人事部やコンプライアンス窓口、または労働組合に相談して対応を求めましょう。社内に信頼できる窓口がない場合や、相談による不利益を懸念する場合は、外部の公的機関を頼るのも有効です。
たとえば、「総合労働相談コーナー」(厚生労働省)や「みんなの人権110番」(法務省)は無料で相談を受け付けており、法的な視点からのアドバイスも期待できます。専門機関に相談することで、状況を客観的に整理し、今後の行動方針を明確にする手助けとなるでしょう。
転職する
相談しても状況が改善しない、あるいは職場全体にパワハラを許容する風土がある場合は、転職を検討するのも現実的な選択肢です。被害が長期化すれば、心身の健康が損なわれ、仕事だけでなく私生活にも大きな影響を及ぼします。
近年は「ハラスメント対策」に積極的な企業も増えており、より良い職場環境を求めて再出発することは決して後ろ向きな選択ではありません。自分の尊厳と健康を守るためにも、必要であれば速やかに新たな職場を探す行動を始めることが大切です。
企業がやるべきパワハラの対策方法

2022年4月の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、すべての企業にパワハラ防止措置が義務づけられました。加えて、一部自治体ではパワハラ防止条例も施行されており、企業には体制整備が求められています。企業が講じるべき主な対策は以下の通りです。
| ・パワハラを許さない方針の明文化と社内への周知 ・内部・外部の相談窓口の設置 ・相談者のプライバシー保護と不利益取り扱いの禁止 ・行為者・被害者への適切な対応と再発防止策の実施 |
社内のパワハラ対策には、管理職や従業員向けの研修制度を整備し、パワハラに関する知識を深めることも大切です。以下では、パワハラ対策のより詳しい内容や実際の対策事例などを紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
『企業が取り組むべきパワハラ対策とは?他社の対策事例も紹介』について詳しくはこちら
まとめ
パワハラは、被害者側の性格や立ち居振る舞いだけでなく、加害者の思考傾向や職場全体の風土によっても生じやすくなります。真面目で反論しない人、コミュニケーションが苦手な人はターゲットにされやすく、一方で加害者には完璧主義や感情の起伏が激しいといった特徴が見られます。
パワハラを避けるには、社内で信頼できる人間関係を築くこと、毅然とした態度で接すること、仕事の能力向上も有効です。万一被害に遭った際には、証拠を残し、社内外の相談窓口に相談し、必要に応じて転職も選択肢に含め、自身の心身の健康と尊厳を守りましょう。企業にもパワハラ防止体制の構築が求められており、個人と組織の両面での対応が重要です。
関連記事
Related Articles
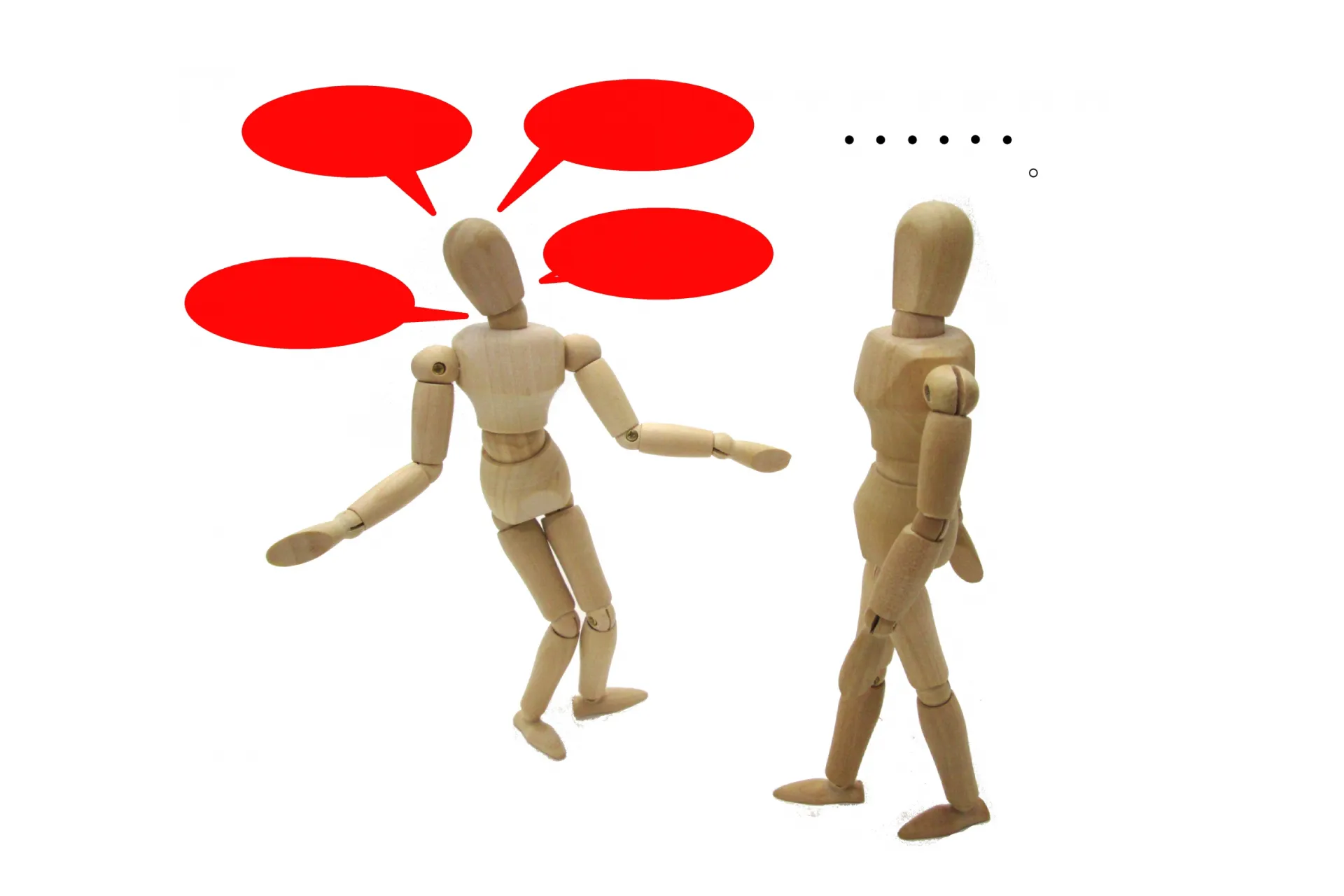
知らないと損する!セクハラする人の10の特徴と心理・対処法も解説
職場でのセクハラは、働く環境や従業員のメンタルヘルスに深刻な影響を与える問題です。セクハラをする人には特定の性格や行...
ハラスメント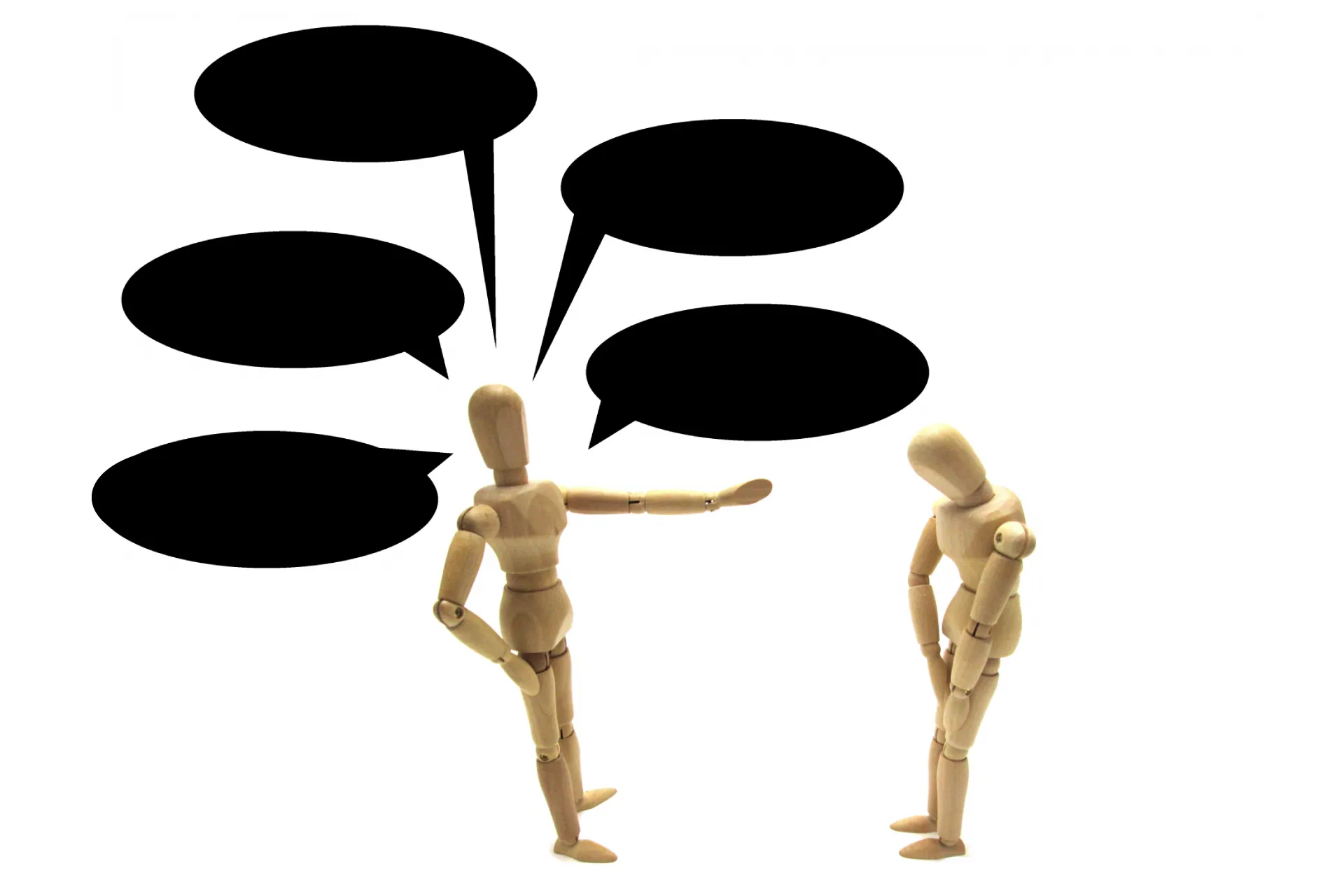
【事例あり】セカンドハラスメントの3つの原因と予防・対処法を解説
セカンドハラスメントとは、ハラスメント被害者が相談・申告した際にさらに精神的苦痛を受ける二次被害のことです。例えば、...
ハラスメント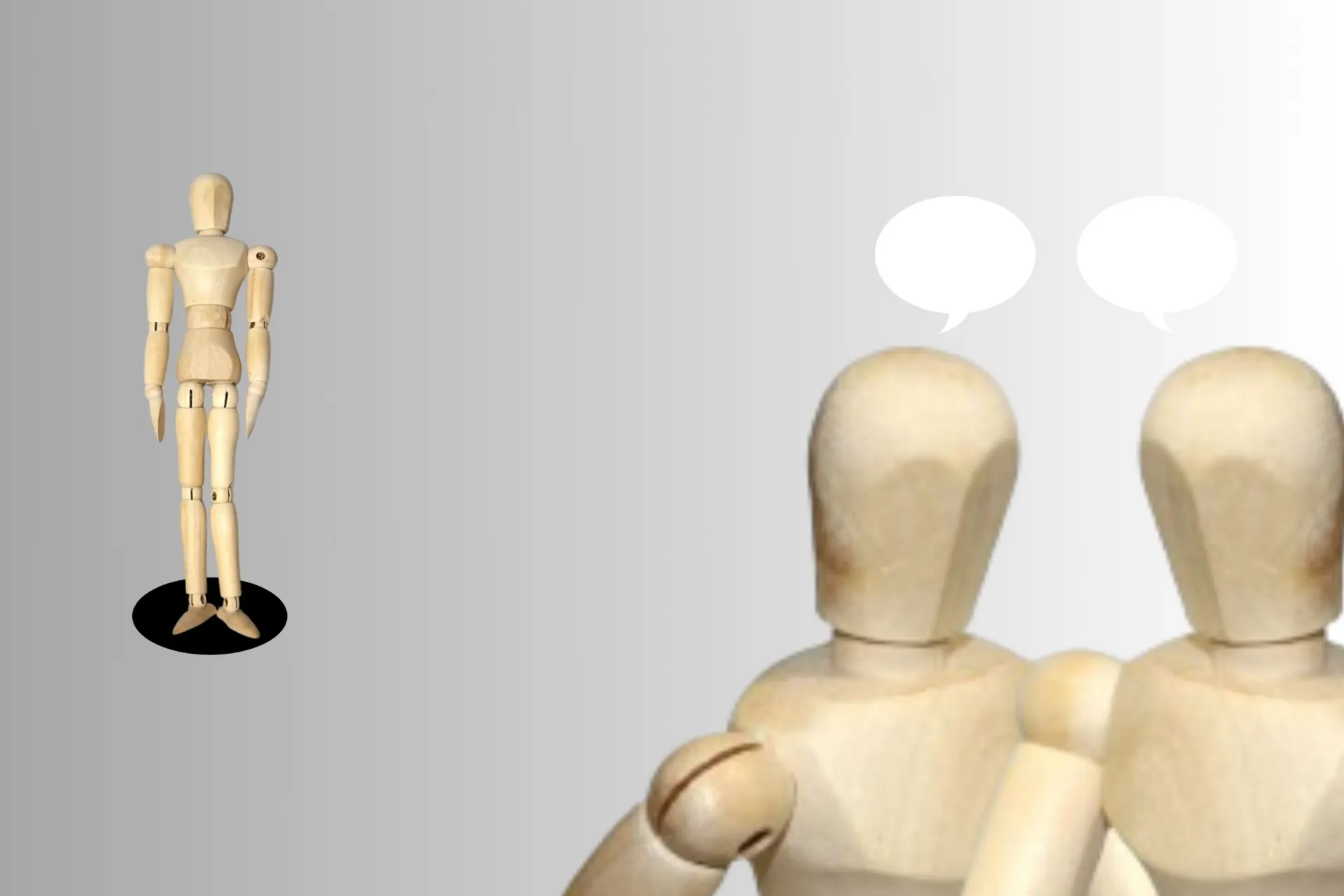
優しさがハラスメントに?ホワイトハラスメントの意味と具体例を解説
パワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)など、近年はさまざまなハラスメントに注目が集まる中...
ハラスメント
無意識のスメハラが職場を壊す?適切な伝え方のポイント・対策を解説
当記事では、スメハラ(スメルハラスメント)とは何かという点を解説した上で、スメハラの具体例や日頃からできる対策、相手...
ハラスメント
加害者・被害者になる前に!パワハラチェックリストの設問や項目を紹介
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)は、加害者・被害者ともに自覚がないまま進行するケースが少なくありません。近年は...
ハラスメント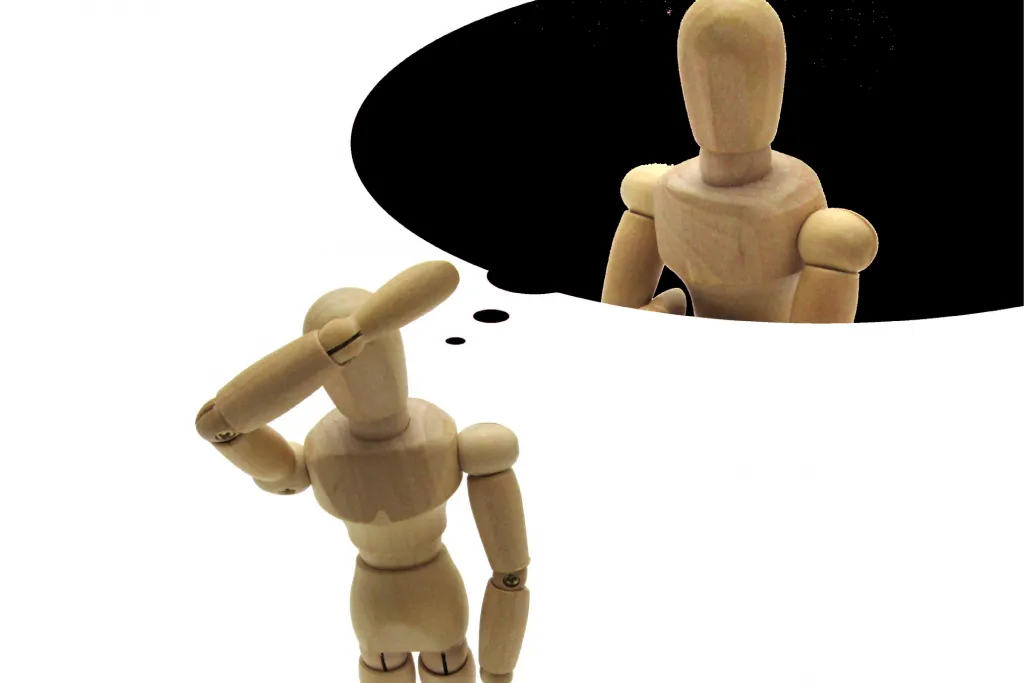
貴社の職場は大丈夫?コミュニケーションハラスメントの具体的事例と今すぐできる対策
コミュニケーションハラスメントの定義や具体例、発生原因、防止対策を解説します。コミュハラの基礎知識を理解し、健全な職...
ハラスメント