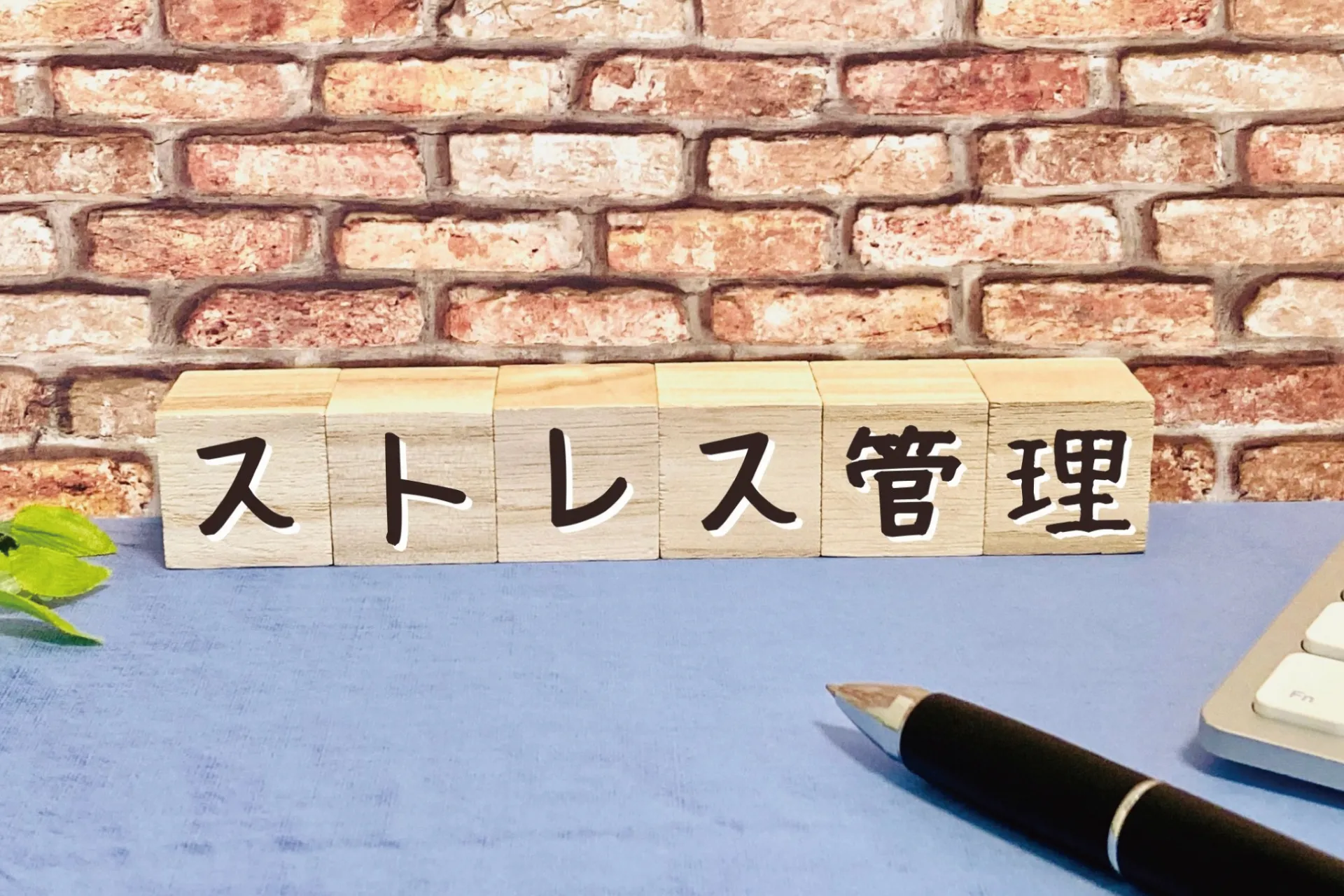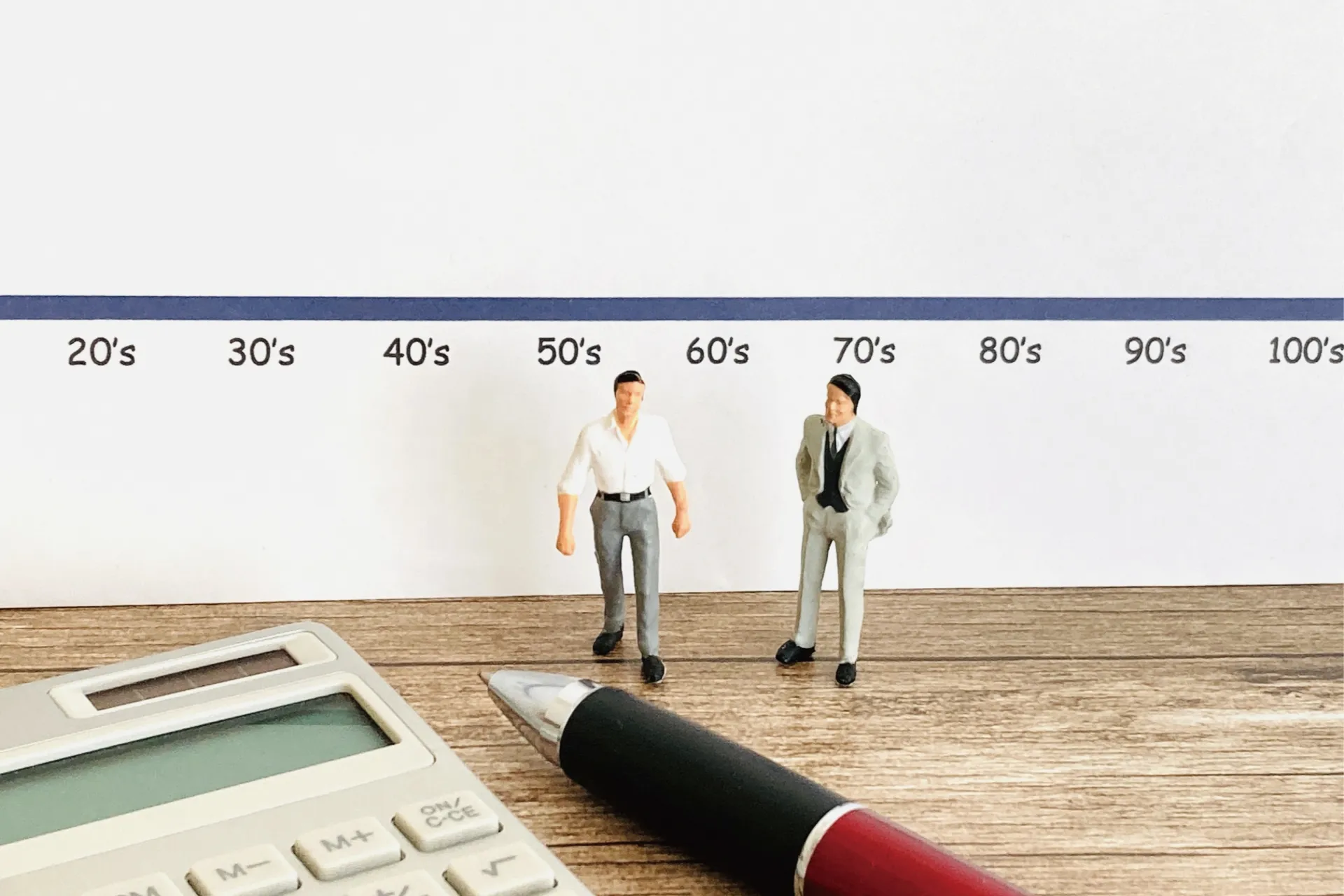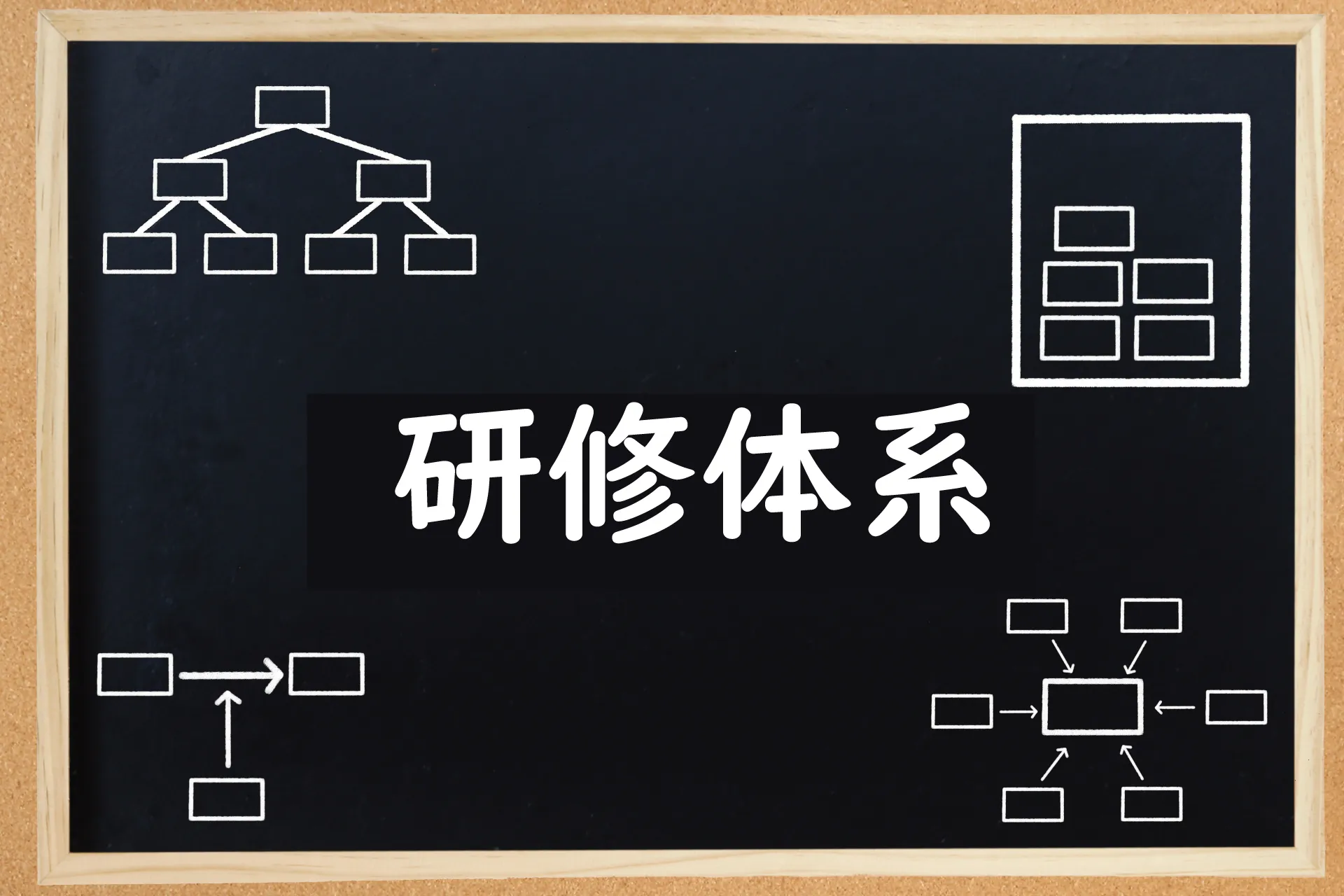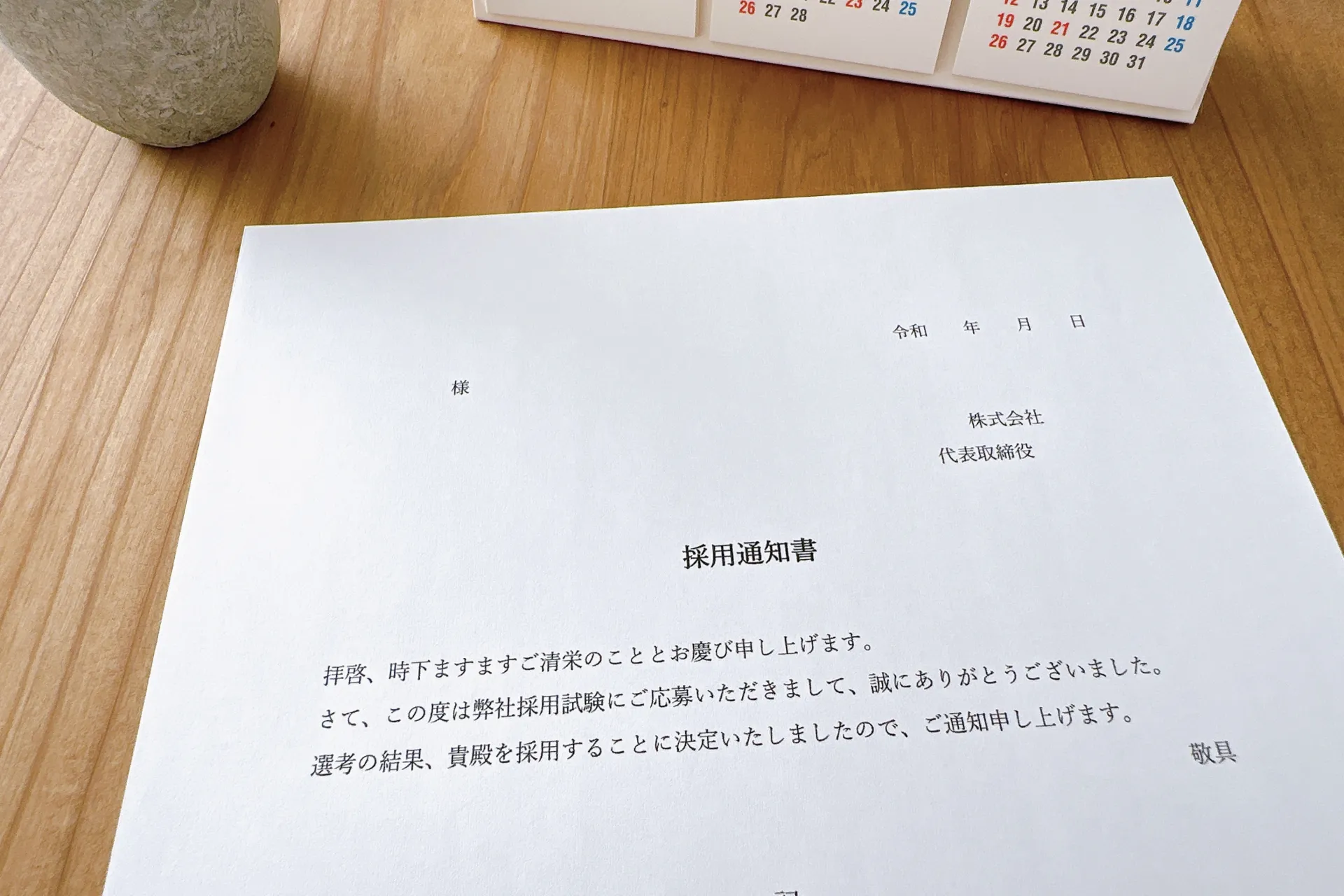- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- タイムパフォーマンスとは?メリット・重視するZ世代の特徴も解説
タイムパフォーマンスとは?メリット・重視するZ世代の特徴も解説

この記事は2024.1.29に公開した記事を再編集しています
2025年8月4日更新
IT技術の発達やデジタルコンテンツの増加により大量の情報が氾濫する中で、特にZ世代の若者にはタイムパフォーマンス(タイパ)という概念が重視されています。また、企業にとっても日本企業の生産性がOECD加入国の中でも下位にある現状、業務のタイムパフォーマンス向上が必要です。
この記事では、主にZ世代がタイムパフォーマンスを重視する理由やタイムパフォーマンスの重要性、職場のタイムパフォーマンスを向上するメリットを解説します。事例付きでタイムパフォーマンスを向上する方法も伝えるため、HR担当者の方はぜひご一読ください。
目次
Toggleタイムパフォーマンスとは

タイムパフォーマンス(タイパ・タムパ)とは、「時間対効果」を意味する言葉で、時間に対してどれだけの効果があるかを示します。この概念は、費用対効果を表すコストパフォーマンス(コスパ)から派生しました。
もともとは限られた時間内で効率よく仕事をこなす、能率の概念として使われ始めた言葉です。現在では「時間内に得られる成果の多寡」を評価する言葉としても広く使われています。
短時間で多くの情報や成果を得られることを、タイムパフォーマンスが高いと表現します。反対に、長い時間や多くの労力を費やしても得るものが少なければ、タイムパフォーマンスが低い状態です。
多様なコンテンツや情報が溢れる現代では、効率よく必要な情報にアクセスする必要性が増しており、この概念は特に若い世代において重視されています。
コスパ・スぺパとの意味の違い
タイムパフォーマンスと似た言葉にコストパフォーマンス(コスパ)・スペースパフォーマンス(スペパ)がありますが、それぞれ異なる要素に着目した効率の評価基準です。
| タイムパフォーマンス (タイパ) | コストパフォーマンス (コスパ) | スペースパフォーマンス (スペパ) |
| かけた時間に対して、得られた効果(時間対効果) | かけたお金に対して、得られた効果(費用対効果) | 限られた空間を効率よく使うことで、得られた効果(空間対効果) |
タイパは時間の使い方、コスパはお金の使い方、スペパは空間の使い方をそれぞれ評価する指標です。たとえば、コスパではよい商品をより安く購入すること、スペパでは狭いスペースを最大限に活用することが評価されます。
これらは相互に影響を及ぼし合うケースも少なくありません。スペパを考えてスティック型の掃除機を選んだら、何度も充電する羽目になってタイパが落ちた、といった具合です。反対に、スペパのために1台で何役もこなす家電に切り替えたら、1か所で用事が済み、タイパが向上するといった場合もあります。
タイパが高い仕事の進め方は時間を効率的に使えますが、それがコストや空間の効率によい影響があるかは別の問題です。
「タイムパフォーマンスが高い」消費活動の具体例
Z世代が意識する「タイパ(タイムパフォーマンス)」という消費スタイルは、映像コンテンツの視聴方法から日常生活のサービス利用に至るまで、短時間で成果を得られる手段が選ばれる傾向にあります。代表的なタイパ消費の例を、以下の表にまとめました。
| 動画のながら視聴(81.3%) | 動画を見ながら料理やSNSなど別の作業を同時進行する視聴スタイル。時間を無駄にしたくないという意識から、高い割合で取り入れられている。 |
| 動画のスキップ視聴(51.5%) | 興味のある場面や必要な情報だけを選んで視聴し、それ以外のシーンは飛ばす。効率よく本題にたどり着ける点が特徴。 |
| 動画の倍速視聴(48.6%) | 再生速度を上げて短時間で動画の内容を把握する視聴方法。通常の2倍速や1.5倍速がよく使われる。テンポよく情報を得たいZ世代に支持されている。 |
| ネタバレ消費(44.3%) | コンテンツを視聴・購買する前に、あらすじや結末を把握しておくスタイル。内容を把握した上で、安心して視聴したいニーズに応える形。 |
| 完全栄養食 | 栄養バランスが整った食品を手軽に摂取できる。調理や準備の手間を省きたい人にとって、食事時間の短縮に有効。 |
| ネットスーパー | スマホやPCで食材や日用品を注文し、自宅に配送してもらうサービス。買い物にかかる時間や移動を削減できる点がタイパ消費と合致。 |
※出典:SHIBUYA109 lab.「Z世代の映像コンテンツの楽しみ方に関する意識調査」
上記の括弧内の百分率は「Z世代の映像コンテンツの楽しみ方に関する意識調査」に基づくデータです。Z世代は日常生活においても時間効率を最大化する方法を積極的に選び取っており、企業側もこの消費傾向に即したサービス設計が求められています。
タイムパフォーマンスがビジネスシーンで重要になった理由

近年、ビジネスシーンにおいても、タイムパフォーマンスが注目されるようになっています。Z世代の社会進出やIT・デジタルコンテンツの発展、人手不足や働き方改革など、要因はさまざまです。
以下では、タイムパフォーマンスがビジネスシーンで重要になった3つの理由を解説します。
Z世代のタイムパフォーマンス意識の高まり
新入社員として会社に入ってくるZ世代にとって、タイムパフォーマンスは重要な指標となっています。Z世代は、デジタルツールやインターネットが身近にある環境で育ち、「デジタルネイティブ」と呼ばれるようになりました。彼らは、大量の情報の中から効率的に有益な情報を選び取るスキルに長けています。
そのため、仕事においても最小の労力で最大の成果を得ること、すなわちタイムパフォーマンスを意識する傾向が強く見られます。消費者庁の調査でも、特に20代の若者のうち約6割がタイムパフォーマンスを重視しており、ほかの世代に比べてもタイムパフォーマンスを重視する割合が多いという特徴が示されました。
※出典:消費者庁「令和4年度消費者意識基本調査」の結果について」
Z世代のこの傾向は、企業が若手の人材を確保し、離職防止に努める上で考慮すべき点と言えるでしょう。
IT技術の発達やデジタルコンテンツの増加
近年、スマートフォンやパソコンの普及により、情報収集が以前にも増して迅速になりました。インターネット上に無数の情報が存在する中、必要な情報を効率的に探し出すスキルが求められるようになっています。
また、SNSの普及により、移動時間やわずかな休憩時間でも容易にコンテンツを消費できるようになりました。短時間で楽しめるショート動画の人気が高まるのは、効率的に情報を得たいというユーザーのニーズが反映されている証拠です。
デジタル技術の進化によって情報の取得速度は向上し、人々がより効率的に情報を得る方法を模索し始めています。これがビジネスにおいてもタイムパフォーマンスが重視される理由の1つと言えるでしょう。
人手不足・働き方改革に伴う生産性向上の重要化
人手不足の深刻化と働き方改革が進む現代において、企業側には「同じ時間でどれだけのパフォーマンスを出せるか」という観点から生産性の向上が求められています。
労働者の価値観も変化し、短時間で成果を出して余剰時間を生み出し、キャリアアップやプライベートの充実に活用したいと考える人が増えています。今後社会の高齢化がますます進む中、限られた労働力で生産性を高めるには、仕事の効率化が欠かせません。
特に日本は時間あたりの労働生産性がOECD加盟38か国中27位と低い状態にあり、国際競争力を高めるためにもタイムパフォーマンスの向上が不可欠です。
ビジネスでタイムパフォーマンスを意識するメリット

ビジネスの現場でも、限られた時間で成果を最大化する「タイムパフォーマンス(タイパ)」の重要性が高まっています。タイパを意識した働き方は、業務効率や生産性の向上だけでなく、従業員の満足度向上にもつながります。
以下では、時間管理や生産性の観点に加え、ワークライフバランスの実現や若手人材への訴求力など、企業がタイパを意識することで得られる具体的なメリットを解説します。
時間を効率的に使える
タイムパフォーマンスを意識することで、限られた時間を最大限に活用し、無駄を省いた働き方が実現しやすくなります。ビジネスの現場では時間そのものが貴重な経営資源であり、特に人手不足が深刻化する企業においては限られた人的リソースをどう使うかが成果に直結します。業務を短時間で効率的に完了できれば、その分、自身のスキルアップや新しい取り組みに充てる余裕が生まれます。
また、タイパを意識することで日々の業務改善にも目が向くようになり、チーム全体の生産性向上にも波及する可能性があります。時間を効率的に使うという意識は、忙しい現代のビジネスパーソンにとって不可欠な考え方と言えるでしょう。
生産性を高められる
タイムパフォーマンスを意識することは、個人や組織の生産性向上に直結します。限られた時間の中で成果を最大化するためには、業務の優先順位を見極め、必要な作業に集中する姿勢が必要です。自分の行動に対する時間配分を見直すことで、不要な作業の削減や業務プロセスの効率化が促進されます。同じ労働時間でもより高いアウトプットを実現できるようになるでしょう。
また、業務の生産性が高まれば、浮いた時間を企画立案や戦略的業務など、より付加価値の高い仕事に充てることが可能です。
ワークライフバランスを実現しやすくなる
タイムパフォーマンスを意識した働き方は、ワークライフバランスの向上にもつながります。業務の時間管理が徹底され、限られた時間で成果を出せるようになることで、長時間労働や残業を抑えることが可能になります。仕事を効率よく終えられれば自分の時間を家族との時間や趣味、休息などに振り分ける余裕が生まれるため、生活全体の質が高まり、心身の健康維持にも好影響をもたらすでしょう。
また、柔軟な働き方を推進する企業においては、テレワークやフレックスタイム制といった制度との相性も良く、より多様なライフスタイルに対応できる職場環境の整備が進みます。
若手人材やZ世代にアピールできる
タイムパフォーマンスを重視する企業姿勢は、Z世代を中心とした若手人材にとって魅力的に映ります。限られた時間を有効に使い、効率よく成果を出す価値観は、Z世代の行動様式と親和性が高いためです。
デジタルネイティブであるZ世代は、動画の倍速視聴や効率的な情報収集を日常的に行っており、働く上でも無駄を避ける傾向が強く見られます。そのため、タイパに配慮した業務設計や柔軟な働き方を導入している企業には自然と関心が集まります。
人手不足が深刻化する中で、若手からの支持を得ることは企業にとって重要な課題です。タイパを意識した職場づくりはZ世代からの共感や定着にもつながりやすく、人材確保と育成の面でも有効と言えるでしょう。
ビジネスでタイムパフォーマンスを意識するデメリット

タイムパフォーマンスを意識する働き方には多くの利点がありますが、一方で注意すべき側面も存在します。時間効率ばかりを追い求めることで、仕事の質や働く人の心身に悪影響が及ぶ可能性も否定できません。
以下では、タイパ重視の働き方が抱えるデメリットについて、4つ解説します。
過程を軽視しがちになる
タイムパフォーマンスを過度に意識した働き方では、結果を出すことが最優先され、業務の背景やプロセスの重要性が軽視されやすくなります。たとえば、業務改善の提案を求められた際に結論だけを急いでしまい、現場の実態や課題の構造を深く理解しないまま対策を打ってしまうケースが挙げられます。
プロセスには、試行錯誤を通じた学びや、他者との対話によって生まれる新たな発想など、成果だけでは得られない価値があります。タイパを優先しすぎると、プロセスを踏む中での学習や発見などの気づきを取りこぼしやすくなり、組織全体としての成長機会を損なうおそれもあります。
特にチーム業務では、プロセス共有が疎かになると認識のズレや責任範囲の不明確さが生じ、結果的に非効率なやり直しやミスを招く原因にもなりかねません。効率と過程のバランスを意識することが重要です。
短期的な成果に偏りやすくなる
タイムパフォーマンスを重視するあまり、短期的な成果ばかりを追い求める姿勢が強まると、中長期的な視点が損なわれるおそれがあります。たとえば、トラブル対応において一時的な対症療法に終始してしまい、根本原因の分析や再発防止策がなおざりにされると、同様の問題が繰り返される可能性があります。
また、目先の効率だけを優先することで、本来時間をかけて丁寧に行うべき業務プロセスが軽視され、品質や信頼性の低下につながることもあります。営業活動においても、早期の成果に集中するあまり、長期的な関係構築が必要な顧客へのアプローチが後回しになるケースも考えられます。
企業として持続的に成長していくには、短期と長期のバランスを取る視点が重要です。タイパを意識することは重要であるものの、目的や状況に応じて柔軟に判断する姿勢が求められます。
従業員への負荷が増加しやすくなる
タイムパフォーマンスを意識した働き方は一見合理的に思えますが、職場での過度な効率追求は、従業員に見えない負荷を与える場合があります。限られた時間内で成果を出すことが常態化すると、ミスを恐れて気が休まらない、余裕のない状態が続くなど、精神的なプレッシャーが蓄積します。限られた時間内で成果を出すことが常態化すると、ミスを恐れて気が休まらない、余裕のない状態が続くなど、精神的なプレッシャーが蓄積します。
たとえば、会議の短縮や業務の高速処理が続く環境では、発言の機会を逃したり、判断を急ぎすぎて誤認識が発生したりすることがあります。細部への確認や丁寧な対話が後回しになると、信頼関係の構築やチームワークにも支障が出るおそれがあります。
タイパを追求する風土が「常に急ぐことが正しい」という無言の圧力を生み出すと、心身の健康を損ねるリスクが高まります。効率と健全な労働環境のバランスを保つ視点が必要です。
創造性や柔軟性が損なわれる可能性がある
業務における創造性や柔軟性は、必ずしも効率的なプロセスの中で生まれるとは限りません。むしろ、遠回りに見えるような試行錯誤や雑談、余白の時間から新しい発想が生まれることも少なくありません。
タイムパフォーマンスを優先する働き方が定着しすぎると、「無駄」と見なされがちな過程が排除され、発想の幅や視点の転換が起こりにくくなります。たとえば、商品企画やアイデア出しの場で即答を求められると、意見の多様性や深掘りが妨げられ、画一的な提案にとどまりがちです。
短期的な効率だけでは測れない価値もあることを踏まえ、余裕のある時間設定や柔軟な働き方を許容することが、創造性を守る上で重要となります。タイパと自由な思考の両立には、意識的な環境設計が求められます。
タイムパフォーマンスを重視するZ世代前後の社員の特徴

現代の職場において、特にZ世代を中心とした若手社員にタイムパフォーマンス重視の傾向が見られます。Z世代の特徴を理解することは、職場の生産性向上や効率的なチームワークを促進する上で重要です。
以下では、タイムパフォーマンスを重視する社員の行動パターンを4つ解説します。
ハイブリッドワークを好む
タイムパフォーマンスを重視するZ世代は、場所を問わず働きやすいハイブリッドワークやワーケーション制度の利用を好みます。
コロナ禍に学生時代を過ごしたZ世代は、オンラインでのコミュニケーションに慣れた世代です。出社するのに時間やコストをかけずとも、Webのツールや各種システムを活用すれば十分に成果が出せ、プライベートの時間も確保できると考えます。
同時に、対面でのコミュニケーションの重要性も理解しているのがこの世代の特徴です。人間関係の構築やスキルアップなどに必要だと判断できれば、オフィスでの作業も厭いません。
そのため、オンラインとオフラインを適切に組み合わせたハイブリッドワークスタイルが彼らにとって最適です。仕事の効率化と精神的な安心感の両方を得ることができ、Z世代の成長にもプラスに働きます。
残業を好まない
Z世代の社員にとって、残業は働く環境を選ぶ重要な判断基準の1つです。残業が少ない職場を好む背景としては、プライベートの時間を確保することや、働き方の健全さを重視する考え方が挙げられるでしょう。Z世代の社員は、決められた労働時間内で効率よく仕事を終え、残った時間は趣味や自己研鑽、副業などに充てたいと考えます。
また、旧来の仕事観、特に「上司より先に帰らない」「残業時間が長いほど頑張っている」といった、仕事や能力には直結しない考え方に対しては否定的です。契約時間の範囲を超えた働きを求められるのは、「無駄」「理不尽」と捉える傾向にあります。
仕事の優先順位をつけて働く
ワーク・ライフ・バランスを重視するZ世代の社員は、仕事に費やす時間を最小限に抑えたいという意識が強めです。そのため、仕事の優先順位をつけて、効率的に仕事を進めようとする傾向が見られます。たとえば、仕事の重要度や緊急度を基に優先度を決め、スケジュールを立てて時間配分を考える、効率化のツールやサービスを活用するなどです。
また、Z世代は仕事の成果を重視する傾向があり、成果に直結する仕事を優先します。スケジュール管理を徹底するだけでなく、できない仕事は断るといった姿勢は、成果を出しながら私生活も大切にする現代の働き方を象徴しています。
まず正解を欲しがる
現代の若者世代、特にZ世代は、まず正解を知った上で行動するのを好みます。具体的な指針やサポートを求めており、「とりあえずやってみて」や「自分で考えて」といった曖昧な指示にはなじめません。
Z世代は膨大な情報量に瞬時にアクセスできる環境で育ってきました。そのため、正解にたどり着くまでのプロセスよりも、その後の応用や工夫で差をつけることに価値を見出す傾向にあります。
Z世代の特性を生かすには、まず手本を見せてから、自分自身で考えて行動させる方法が効果的です。たとえばZ世代にOJT教育を行う際には、最初にやり方を伝え、「なぜその手順が必要なのか」といった理由を解説して自分で考える道筋を伝えるとよいでしょう。その上で自分なりに考えて作業を進めさせ、評価・指導の形でフィードバックをすれば、Z世代の特性に合った教育が可能です。
職場のタイムパフォーマンスを向上する方法

職場のタイムパフォーマンス向上は、Z世代社員の離職防止のためにも重要となる課題です。効率的で生産性の高い職場環境は、Z世代はもちろん、あらゆる世代で社員の仕事への満足度を高められるでしょう。
以下では、職場のタイムパフォーマンスを向上する6つの方法を解説します。
適材適所の人材配置を重視する
職場のタイムパフォーマンス向上には、適材適所の人材配置が欠かせません。適切な業務の割り当てがなされない場合、能力を持て余す社員が出る一方で、過剰な負担を背負う社員も生まれます。人材のデータを詳細に把握し、客観的かつ多面的な評価に基づいた人材配置を行えば、効率的な仕事の進行が可能です。
株式会社阿知精機では、人材配置を効率化して生産性を向上するため、従業員にスキルマップシートと技能育成シートを配布して技術力を確認しています。評価に応じて人材配置を適宜変更することで、主軸稼働率(機械の稼働時間)は2019年の26%から2022年には45%に増加しました。この事例は、適材適所の配置がタイムパフォーマンス向上に直結することを示しています。
社員のタスクを可視化する
タスクの可視化は、職場のタイムパフォーマンスの向上に有効です。作業管理ツールやToDoリストなどを活用し、社員のタスクや進捗状況を明確に把握できれば、業務の抜け漏れや納期遅れを防げます。
好例と言えるのが、真空ポンプメーカーであるアルバック・クライオ株式会社の取り組みです。業務管理ツールを導入し、タスクの進捗状況を「見える化」することで、各担当者の作業量を把握でき、効率的に業務を進められるようになりました。また会議の時間も大幅に短縮され、プロジェクトに関する情報の一括管理により、必要な情報をすぐに発見できるように変わったのも成果です。
短時間労働を導入する
短時間労働制度の導入も、職場のタイムパフォーマンスを向上させる効果的な手段です。この制度は、社員が自主的に効率的な働き方を見つけ、実行するためのものです。結果として、働き方に対する意識変化が促され、仕事の優先順位づけや時間管理のスキルが向上します。
アパレルメーカー大手であるZOZOの事例では、2012年5月から実施された1日6時間労働制により、スタッフ1人当たりの労働生産性が前年比25%上昇しました。働く時間が短くなっても給料は変わらず、8時間以上労働した際は従来通り残業代が出るようにしたのが、成功したポイントの1つです。会社全体でみても、社員の平均的な労働時間が9時間台から7時間台に減少し、効率的に業務を進める文化が醸成されています。
無駄な業務を削減する
無駄な業務の削減は、職場のタイムパフォーマンス向上に不可欠です。不要な作業や自動化できるものを特定し、削減・置換すれば、効率的な作業が可能になります。ERAS(Eliminate・Rearrange・Automate・Simplify)などの思考法を用いて業務を分類し、無駄を省くことが重要です。
岡崎製パンでは、品質管理のあり方を見直し、不良品の発生要因を特定しました。工程ごとに作業標準書を作成し、不良品率の低下に成功しています。また、事務所の配置変更や報告書の様式変更などの業務改善により、事務作業の効率性も10%向上しました。これは、ERASの観点から業務プロセスを見直し、無駄を削減した結果です。
テレワークやハイブリッドワークを採用する
職場のタイムパフォーマンス向上を目指すのであれば、テレワークやハイブリッドワークも検討しましょう。テレワークやハイブリッドワークは、移動時間の削減や社員にとって効率的な環境での業務遂行を可能にし、仕事の生産性を高めます。
東日本電信電話株式会社では、働き方改革「Value Working」の一環として、在宅勤務の活用やWeb会議の推進などを行いました。取り組みの効果として、時間外労働が13%減少し、月間時間外労働を45時間以上実施した社員の数も34%減少したと報告されています。さらに、ワーク・ライフ・バランスが改善し、計画性を持って仕事に取り組むようになったと好意的な意見が社員から上がっているなど好評です。
タイムマネジメント研修を受講してもらう
決められた時間内でタイムパフォーマンスよく仕事をするためには、タイムマネジメントの習得が不可欠です。タイムマネジメント能力を効率的に身につけたいのであれば、タイムマネジメント研修の受講が有効です。
タイムマネジメント研修では、時間管理の基本から始まり業務の優先順位づけ、スピードマネジメントや生産性向上のアプローチなどがレクチャーされます。研修の受講により、社員は業務を計画的に進め、限られた時間内で成果を最大限にする方法を学べるでしょう。
また、タイムマネジメントは個人だけでなく、組織全体での取り組みが重要です。リーダーの主導により業務内容の見直しやスキルアップのサポートをすることで、全体の生産性向上が目指せます。
まとめ
Z世代前後の新入社員が重視する概念として、タイムパフォーマンスがあります。職場のタイムパフォーマンス改善は、若い世代へのアピールになるだけでなく、生産性を上げ、ワーク・ライフ・バランス向上につながります。
Z世代の社員はハイブリッドワークを好み、優先順位を付けて効率よく仕事を時間内に行うことを目指すのが特徴です。したがって、職場のタイムパフォーマンス向上には、人材配置の適正化やタスクの可視化、無駄な業務の見直しと削減、短時間労働やハイブリッドワーク導入が有効です。
また、組織全体の時間に対する意識を変えるために、タイムマネジメント研修を導入し、限られた時間内で成果を出す方法を学ぶとよいでしょう。