- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- ハラスメント
- 【2025年最新】カスハラ防止条例とは?ポイントを分かりやすく解説
【2025年最新】カスハラ防止条例とは?ポイントを分かりやすく解説
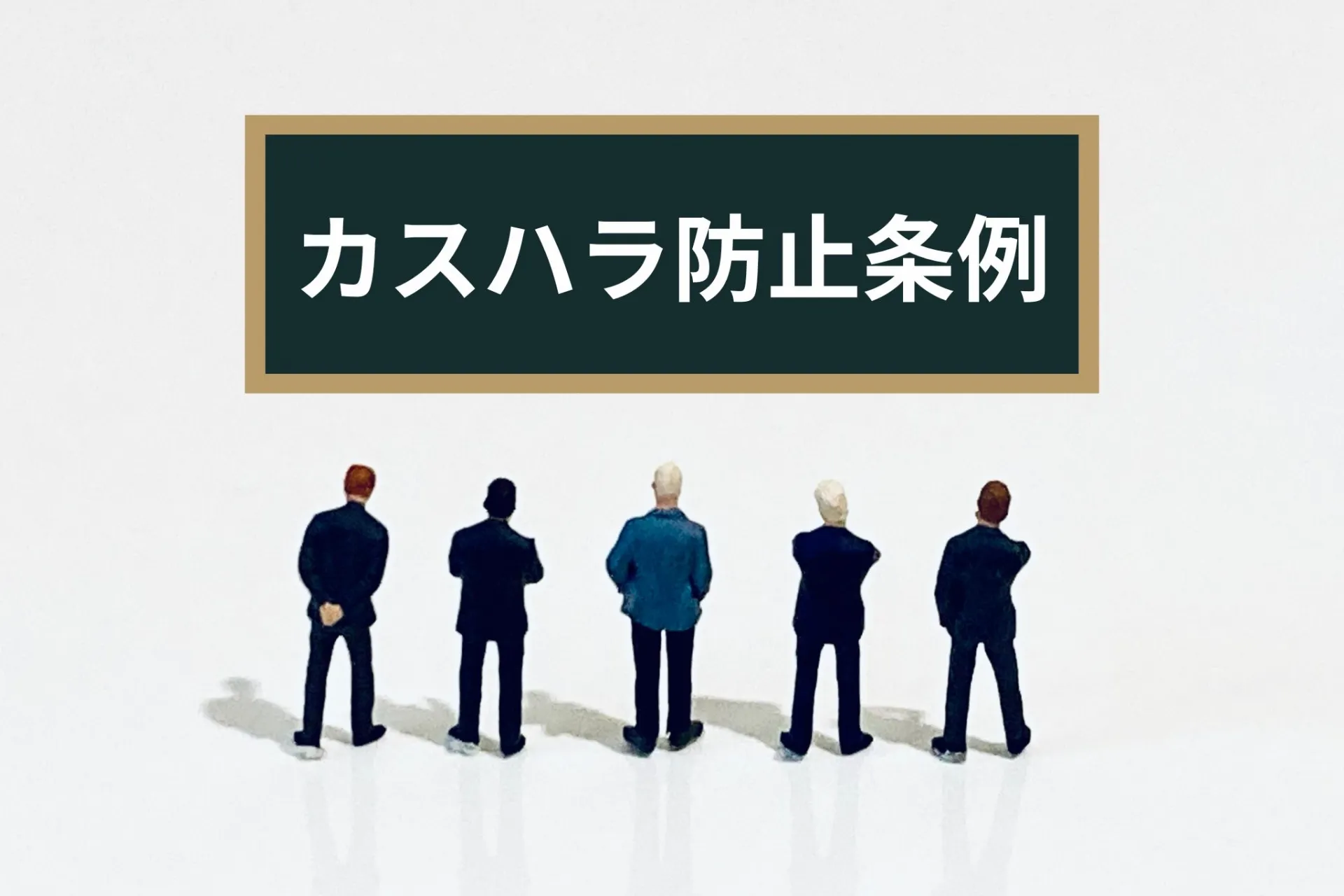
カスハラを防ぐために、国は2025年3月に労働施策総合推進法改正を閣議決定し、全企業に向けてカスハラ対策を義務付けました。それに先駆けて東京都をはじめとした各自治体で定められたのが、カスハラについて周知し、未然に防ぐための対策方法を伝えるいわゆる「カスハラ防止条例」です。
この記事では、東京都のカスハラ防止条例について、主な内容や定められた責務、罰則、事業者が取るべき措置などを解説します。東京都だけでなく、支店などの事業所や事務所が都内にある事業者すべて、および東京都の企業と取引がある企業も条例の対象になるので、事業者は必見です。
目次
Toggleカスハラ防止条例とは

カスハラ防止条例とは、顧客による悪質な迷惑行為(カスタマーハラスメント)から労働者を守り、職場環境を改善する目的で制定された条例です。東京都では全国に先駆けて、2024年10月に成立し、2025年4月1日より施行されます。
条例は顧客の権利を侵害しないよう配慮しつつも、顧客と就業者の対等な関係を明確化しています。
また、東京都だけでなく、カスハラ防止条例は全国の自治体で議論されており、以下の自治体でも同様の条例が成立しています。
・カスハラ防止条例が成立した自治体(2025年3月時点)
| 自治体名 | いつ成立した? | いつから施行される? |
| 東京都 | 2024年10月11日 | 2025年4月1日 |
| 北海道 | 2024年11月29日 | 2025年4月1日 |
| 三重県桑名市 | 2024年12月25日 | 2025年4月1日 |
| 群馬県嬬恋村 | 2025年3月4日 | 2025年4月1日 |
そもそもカスハラとは
カスハラとは、顧客や取引先などが就業者に対し、暴言や過度な要求など、社会通念上許容される範囲を超えた迷惑行為を行うことを指します。
カスハラとクレームは、以下のような点で異なります。
| カスハラ | クレーム |
| ・常識的な範囲を逸脱した暴言や要求などの迷惑行為である ・相手への攻撃や嫌がらせを目的としている ・言いがかりに近い非難や、暴力など社会通念上容認できない手段を取っている | ・常識的な範囲での建設的な指摘である ・相手の業務改善を目的としている ・正当性や妥当性のある範囲で批判している |
カスハラについて、詳しくは以下の記事も参考にしてください。
東京都でカスハラ防止条例が成立した背景
東京都でカスハラ防止条例が成立した背景には、カスハラが社会的に深刻化し、従業員の就労環境を害している現状があります。
厚生労働省が行った「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」では、ハラスメントによる相談を受けた企業のうち、過去3年間でカスハラを受けた企業の割合は86.8%に上りました。うち、カスハラが増加したと答える企業が22.6%と、減少したと回答する企業の割合12.6%を大きく上回ります。
※出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査
特に、顧客対応が多い飲食業やサービス業はカスハラによる離職の発生が深刻な問題となっている状況です。
東京都は事業者や就業者へのアンケートや実態調査を踏まえて、カスハラが労働環境を深刻に害しているものの、明確な基準がないことで事業者が十分な対応をとれていないと判断しました。そのため、全国に先駆けてカスハラ防止条例を制定し、社会問題に対処する姿勢を見せています。
東京都カスハラ防止条例の罰則
東京都が制定したカスハラ防止条例には、罰則規定がありません。理由として、条例の主な目的が罰則による処罰ではなく、カスハラを許さないという社会的な意識を広め、労働環境の改善を促すことにあるためです。また、罰則を定めることで、罰則の対象外となる迷惑行為が「許容される」という誤解を与えることを防ぐ狙いもあります。
ただし、条例そのものには罰則がない一方で、個々のカスハラ行為については法律によって罰則を受ける可能性があります。
| 2)禁止の法的効果 当該禁止規定に違反した場合の罰則規定はないが、行為の内容によっては、この条例にかかわらず、法律に基づく処罰等を受ける可能性がある。 (例) ア 刑法(明治 40 年法律第 45 号)や特別刑法(以下「刑法等」という。)に反する行為は、刑法等により処罰の対象となる可能性がある。 イ 財産的・精神的損害が発生した場合は、民法(明治 29 年法律第 89 号)の不法行為責任に基づく損害賠償請求権が発生する可能性がある。 ウ 企業間取引に関しては、下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)や私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)に違反する行為があった場合は、罰金(刑事罰)や課徴金(行政罰)等の対象となる可能性がある。 |
例えば、従業員に暴力を加えた場合は暴行罪や傷害罪、脅迫した場合は脅迫罪、長時間拘束した場合は威力業務妨害罪になるケースも多いでしょう。ほかにも、心身や財産に損害が発生したなら、民事裁判により加害者へ賠償させることもできます。下請けに対するカスハラは、下請法や独占禁止法違反となる行為です。
一方で、就業者に精神的・身体的被害が生じたにもかかわらず対応をしなかった場合、企業側が使用者から損害賠償責任を問われる恐れもあります。事業者は速やかにカスハラ対策を行い、カスハラを許容しない姿勢を見せましょう。
東京都カスハラ防止条例の基本となる3つの考え方

東京都カスハラ防止条例では、基本の考えとして以下の3つの柱を定めています。
| 1:何人も、あらゆる場において、カスハラを行ってはならないと規定 2:カスハラの防止に関する基本理念を定め、各主体(都、顧客等、就業者、事業者)の責務を規定 3:カスハラの防止に関する指針を定め、都が実施する施策の推進、事業者による措置等を規定 |
1つ目の柱は、都内すべての場所・場面において、いかなる人であってもカスハラを許容しない姿勢を示すものです。社会全体でカスハラへの認識を強化することを狙いとしています。
2つ目の柱は、東京都、顧客、就業者、事業者など、それぞれの立場に応じた責務を明確化するルールです。単にカスハラを禁じるだけでなく、すべての主体がそれぞれ積極的にカスハラ防止のために措置を講じることを求めています。
3つ目の柱は、東京都がガイドラインを策定し、それに沿って各事業者がカスハラへの対策を進めるという宣言です。都側が主導してガイドラインを公開することで、各事業者がどのような対策をするべきなのか分かりやすくしています。
3つの考え方は、誰かにカスハラの責務を一方的に負わせるのではなく、社会問題としてカスハラに対処するという思想の表れです。
都は、顧客の豊かな消費生活を守りつつ、就業者が安心して働ける職場環境を実現し、事業者の安定した事業活動を支えることで、公正で持続可能な社会の形成を目指しています。
東京都カスハラ防止条例の内容

カスハラ防止条例は3つの基本的な考え方をベースとして、カスハラの定義や対象者、禁止行為の例、必要な配慮について載せています。
以下では、東京都が公開した「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を参考に、カスハラ防止条例の内容を解説します。
カスタマーハラスメントの定義
東京都のカスハラ防止条例では、カスハラについて以下のように定義づけています。
| (1)顧客等から就業者に対し、(2)その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するものをいう。 |
カスハラ禁止条例におけるカスハラとは、1~3の定義をすべて満たすものです。
「その業務に関して行われる」とは、以下の2つのどちらかに該当する状況です。
| ・就業者の勤務時間内に受けた迷惑行為(労働基準法が適用されないフリーランサー等の場合はその他の法令で規定される勤務時間) ・勤務時間外に受けた、業務の遂行に支障をきたすような業務にかかわる迷惑行為 |
例えば、休憩時間や通勤時間など勤務時間中とは見なされないときに受けたとしても、業務にかかわる著しい迷惑行為についてはカスハラとみなされる可能性が高いと言えます。昼休みに顧客から受けた暴言や、帰宅中に顧客から受けた暴力は、カスハラにあたる行為です。
また、「著しい迷惑行為」とは、社会一般的に見て平均的な就業者が受けた場合、看過できないほど業務の遂行に支障が生まれる行為です。なお、著しい迷惑行為には、法人に向けたインターネット上の誹謗中傷など、直接就業者が受けるわけではない迷惑行為も含まれます。
ただし、要素をすべて満たさない場合でも、著しい迷惑行為は別途法的に処罰されると条例には明記されています。
カスハラ防止条例の対象者
カスハラ防止条例は、東京都民だけではありません。条例では、カスハラ防止条例の対象となる主体を、以下のように定義づけています。
| 事業者 | 都内で事業を行う法人、その他の団体、国の機関、個人事業主はすべて事業者とみなされます。 本社が都内にない場合でも、都内に支店などの事業所や事務所がある場合、事業者とみなされます。 |
| 就業者 | 就業者は法人と雇用関係にある労働者だけではなく、さらに広く「社会活動をする人全般」を意味する定義です。例として、以下はすべて就業者に含まれます。 ・正社員 ・派遣社員 ・パートやアルバイト ・社長や代表取締役、役員 ・警察や消防、学校などの公的機関の職員 ・NPO法人などの団体職員 ・フリーランス ・主婦(主夫) ・議員 ・インターンシップ生 ・教育実習生 ・地域のボランティア ・伝統文化の継承者 ・PTA役員 ・自治会役員 ただし、自分の趣味や家庭生活のために活動する人や、違法行為をしている人は就業者とはみなされません。 |
| 顧客等 | 顧客に限らず、店頭で商品の購入を検討している人、飲食店で入店を待つ列に並ぶ人など「これから商品やサービスの提供を受けるであろう人」もカスハラ防止条例では「顧客等」に含まれます。 条例では顧客等に含まれる範囲として、以下を挙げています。 ・配達先の隣人と配達員 ・沿道住民とマラソン大会のボランティア ・著名人と、著名人のSNS投稿にコメントを書き込む人 ・介護士と利用者の家族 |
なお、カスハラ防止条例は東京都内の主体を対象としますが、勤務地が都外であっても、都内の事業者の行う事業に関連する業務に従事している場合、就業者に含まれます。例えば、東京都内の会社から業務委託を受けた都外の企業に勤める方が、顧客からカスハラを受けた場合も、カスハラ防止条例の保護対象になります。
条例で禁止される行為の類型
東京都のカスハラ防止条例では、以下のような行為を禁止しています。
| 禁止行為 | 行為の例 |
| 瑕疵・過失が認められない商品やサービスへの要求 | 欠陥がない商品を新しい商品に交換するような要求など |
| 商品・サービスの内容とは関係がない要求 | 販売した商品と関係のない私物の故障についての賠償要求など |
| 身体的攻撃 | 殴る、物を投げつけるなどの暴力行為 |
| 精神的攻撃 | 大声での叱責、脅迫、金品の要求 |
| 威圧的な言動 | 揚げ足取り、物を叩く、話を遮るなどの行為 |
| 土下座の要求 | 謝罪としての土下座強要 |
| 就業者の拘束 | 長時間の居座りや長電話、個室での拘束など |
| 差別的な言動 | 人種、職業、性的指向などに関する侮辱的な言動 |
| 性的な言動 | わいせつな言動や行為、ストーカー行為など |
| 個人への攻撃や嫌がらせ | 服装や容姿等に関する中傷、SNSでの晒し上げなど |
| 過度な商品交換の要求 | 提供する商品やサービスより著しく高額な商品や入手困難な商品と交換するような要求 |
| 過度な金銭補償の要求 | 提供する商品やサービスより著しく高額な金銭補償の要求 |
| 過度な謝罪の要求 | 正当な理由なく上司や事業者の名前で謝罪文を書くよう要求、自宅に来ての謝罪要求 |
| 不可能な行為や抽象的な行為の要求 | 「法律を変えろ」などの不可能な要求や、「誠意を見せろ」などの抽象的な行為の要求 |
記載された行為だけがカスハラにあたるのではなく、以下の3パターンに類する行為の場合はカスハラとみなされる可能性が高くなります。
| ・顧客等の要求内容が妥当性を欠く ・顧客等の要求内容の妥当性にかかわらず、要求を実現するための手段や態度が違法又は社会通念上不相当である ・顧客等の要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当である |
行うべき顧客への配慮
カスハラ禁止条例の注意点として、正当性のあるクレームとカスハラはそれぞれ分けて考える必要があります。顧客が事業者に対して商品やサービスに関する問題を指摘し、改善を求める行為は、消費者基本法や日本国憲法が保障する「表現の自由」の範囲で尊重されるべきものです。
したがって、条例ではカスハラを禁止すると同時に、顧客への配慮を求めています。
東京都カスハラ防止条例で定められた顧客・就業者・事業者の責務
(顧客等の責務)
東京都カスハラ防止条例は、顧客、就業者、事業者のすべてにカスハラを解消する責務があるとして、それぞれがすべきことをガイドライン化しています。
以下では、カスハラにかかわるとき、具体的にどのような責務があるのか、立場別に解説します。
顧客等の責務
カスハラ防止条例において、顧客等は以下のような責務があると定められています。
| 第7条第1項 顧客等は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない。 第7条第2項 顧客等は、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。 |
サービスを受ける側は、カスハラに対する問題意識を持ち、自らの言動に注意を払うことが求められます。事業者側に商品やサービス上のミスや問題があったとしても、クレームや要望を伝える際の態度や方法に問題がないか考えて、自らの行動を適切に律する姿勢が顧客の責務です。
就業者の責務
カスハラ防止条例において、就業者は以下のような責務があると定められています。
| (就業者の責務) 第8条第1項 就業者は、基本理念にのっとり、顧客等の権利を尊重し、カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動をとるよう努めなければならない。 第8条第2項 就業者は、その業務に関して事業者が実施するカスタマー・ハラスメントの防止に関する取組に協力するよう努めなければならない。 |
就業者はどういった言動がカスハラで、何が正当なクレームなのか見分ける必要があります。また、顧客から不適切な行為を受けた場合の対応方法や、被害を受けた際にとるべき措置、相談窓口などのカスハラ対策について、社内ルールを知っておくことが努力義務です。
特に、管理職や経営層は現場の従業員をカスハラから守る責務があるため、一般従業員以上にカスハラについて知識を得る義務があります。
事業者の責務
カスハラ防止条例において、最も多くの責務を担うのが事業者です。事業者の責務は以下のように定められています。
| (事業者の責務) 第9条第1項 事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。 第9条第2項 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 第9条第3項 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
条例では、事業者に対し、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むことを義務付けています。事業者は、まず就業者が安心して働けるように、安全な労働環境を整える必要があります。事業者は東京都が定めるガイドラインに基づき、社内での相談窓口の設置、対応マニュアルの作成、従業員への教育研修の実施など、体制整備を行わなければなりません。
加えて、就業者が顧客の立場となった際にカスハラ行為を行わないよう、社内研修や啓発活動を通じて意識づけを図る必要があります。下請けに向けてカスハラにあたる行為をしていないかなど、法人の代表者は改めて顧客としての自社のありようを見直しましょう。
加えて、東京都が進めるカスハラ防止施策に積極的に協力し、行政の取組みの実効性向上に協力する責務も負っています。対応が不足している状況でカスハラが発生した場合、安全配慮義務違反に問われる恐れもあるので、速やかに社内の体制整備を進めるのが大切です。
東京都カスハラ防止条例を受けて事業者がとるべき措置

カスハラ防止条例の施行前に、事業者は自社を上げてカスハラ対策をする必要があります。以下では、東京都のガイドラインに基づいて、カスハラを防ぐために企業がやるべき措置を7つ紹介します。
社内外への基本方針・基本姿勢の明確化と周知
事業者はまず、カスハラ防止指針を定め、どのような方針や姿勢でカスハラに対処するのか、防止策を社内外に示す必要があります。組織がトップダウンでカスハラを許さないという明確なメッセージを社内外に示すことで、カスハラに対する抑止効果が生まれます。
カスハラの定義や、問題が起きた場合の対応について示せば、事業者に守られているという意識が就業者に生まれ、安心して業務ができる点もメリットです。従業員だけでなく顧客も「自分の言動がカスハラかもしれない」と啓発できるので、カスハラの防止にもつながります。
相談窓口の設置と体制の整備
カスハラをはじめとしたハラスメントの相談窓口を設けるのも大切です。カスハラが起きたときに誰に、どのように相談すればよいのか分からないと、カスハラが放置されやすい職場環境ができます。
電話、メール、面談など複数の相談手段を用意し、就業者が相談しやすい環境を整備しましょう。また、相談窓口の設置にあたっては、職場内に限らず、第三者機関や外部専門機関への委託を検討することも効果的です。
被害防止のマニュアル整備
カスハラを未然に防ぐためには、対応マニュアルの整備も必要です。カスハラ発生時の初期対応方法、報告手順、顧客等への対応例、カスハラ対策責任者への引継ぎ方法など、マニュアルを使って防止策を標準化しましょう。現場判断で動いた結果、問題がこじれにくくなります。
特に問題が悪化した場合、現場だけではカスハラ対応が難しくなるケースもあります。暴行や脅迫などの犯罪行為に対しては、警察に通報してよいのか現場の担当者だけでは中々分かりません。就業者に危害が加えられると、事業者にとっても安全配慮義務違反のリスクが生まれるため、警察や警備への通報方法や、弁護士など専門家との連携方法についてはマニュアルに必ず載せておきましょう。
被害を受けた者への配慮
カスハラ被害を受けた就業者は、まず心身の安全を最優先で確保する必要があります。特に暴言や暴力行為などに遭遇した場合、速やかに被害者をカスハラ加害者から引き離し、管理者が対応を引き継ぐ体制をあらかじめ整備しておくことが重要です。
また、就業者からの相談の際には丁寧に聞き取るよう担当者を教育し、メンタルヘルス不調が見られる場合は産業医などにアクセスできる体制を整えてください。また、相談にあたっては相談者のプライバシーを守ることに加えて、就業者が相談をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けることがない点も就業規則などに明記しましょう。
就業者への教育研修
就業者に「カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解」を深めてもらうためには、事業者主導で教育研修を実施する必要があります。研修では、カスハラの定義や言動の例、正当なクレームとの違いを正しく理解させることが重要です。
また、顧客との良好な関係構築方法や接客態度の改善、共感力や傾聴力を高めるトレーニングを行えば、ハラスメントを未然に防ぐコミュニケーションスキルを育成できます。また、カスハラ防止を目的とした研修は、中途入社者や異動者、非正規雇用者も含めて就業者全員が参加できるよう定期的に実施するのが大切です。経営層や現場の責任者も、カスハラが職場環境に与える影響や、トップダウンでの対策方法を知り、正しくカスハラに対応できるようになりましょう。
定期的な見直しや対策の継続
カスハラは、一度の取り組んだだけで解決するものではありません。事業者は定期的に自社の取り組み内容を検証し、改善を続ける必要があります。定期的に就業者へのアンケートやヒアリングを行い、過去の対応の成功事例や失敗事例を共有・分析することが重要です。
得られた知見に基づいて対応マニュアルの見直しや、教育研修内容の改善を行い、就業者全員が最新の状況を把握できるよう周知・徹底しましょう。
障害者や認知症の人への配慮
カスハラを防ぐ際に注意すべき点として、障害や認知症を抱える方への対応方法があります。本人が意図せず意思疎通が困難な状況が生じる場面も多いため、応対の際には障害のある方や認知症の方への理解を深め、特性に応じて柔軟に配慮するのが大切です。
事業者は障害者差別解消法や認知症基本法などが定める合理的配慮の例としては、以下があります。
| 障害者への配慮 | ・メニューや商品表示を分かりやすくする ・本人の意思を確認しつつ、書類の記入や機器の操作を代行する ・車いすによる移動を助ける ・筆談、読み上げ、手話などを用いて意思疎通する など |
| 認知症の人への配慮 | ・認知症について理解した上で、さりげない援助を行う ・認知症の人の自尊心を傷つける態度を取らない ・認知症の人の状態に応じて、相手の不安を和らげる など |
まとめ
カスハラを根絶するには、カスハラを受けた従業員をただ守るだけでなく、問題行為を許容しない姿勢を内外に示すことが求められます。各自治体や国がカスハラ対策を事業者や各就業者、顧客に求めている状況は、各企業がカスハラに取り組む機運を後押しする要素と言えるでしょう。
一方で、顧客からの正当なクレームや、障害者・認知症者が求める配慮までカスハラと取らないように、事業者は就業者に学ぶ機会を与える必要があります。正当なクレームの権利を守りつつ、過度な要求を許さない仕組みづくりをして、就業者が安心して働ける環境と、顧客が正当な要望を伝えやすい環境を両立するのが大切です。
関連記事
Related Articles
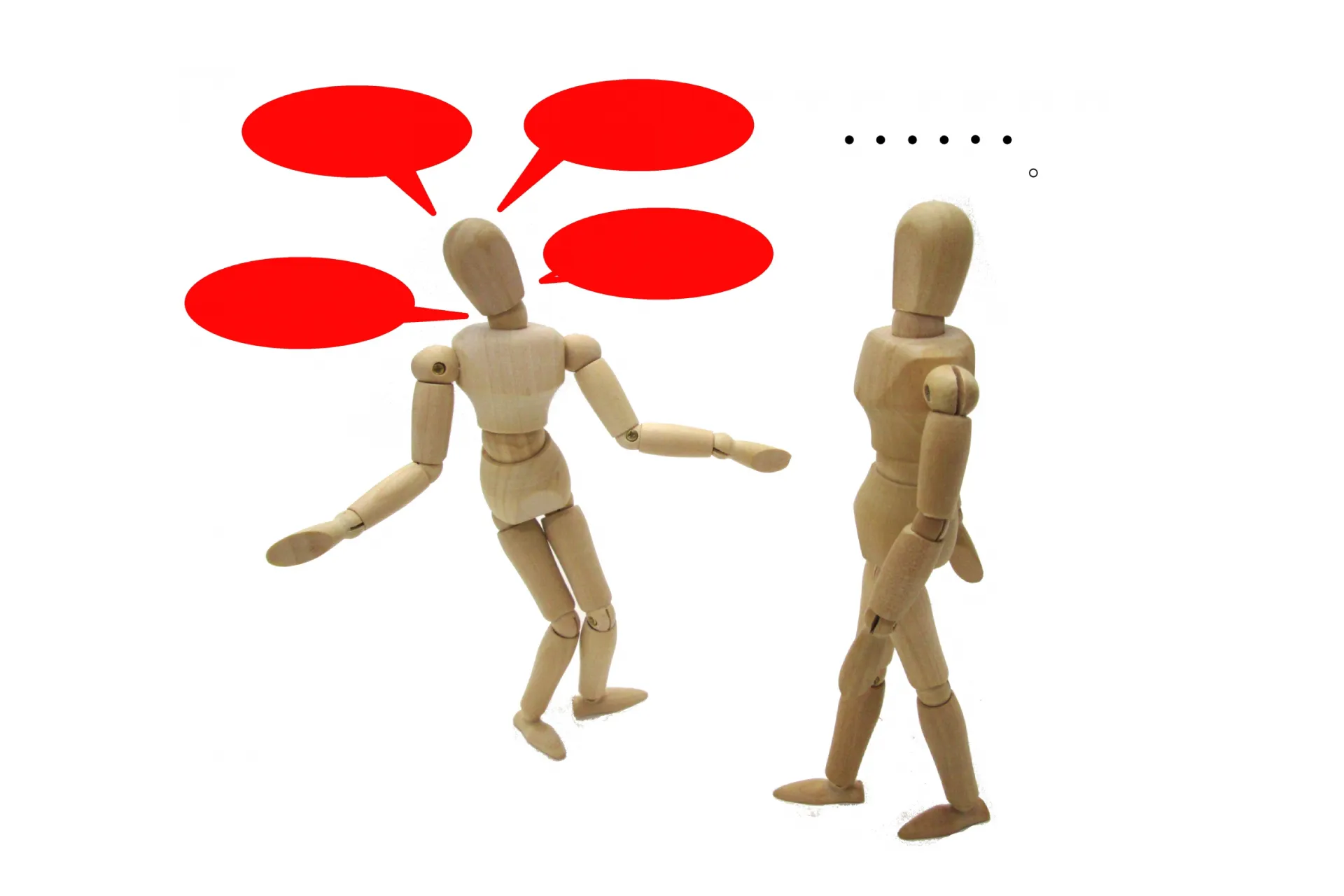
知らないと損する!セクハラする人の10の特徴と心理・対処法も解説
職場でのセクハラは、働く環境や従業員のメンタルヘルスに深刻な影響を与える問題です。セクハラをする人には特定の性格や行...
ハラスメント
加害者・被害者になる前に!パワハラチェックリストの設問や項目を紹介
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)は、加害者・被害者ともに自覚がないまま進行するケースが少なくありません。近年は...
ハラスメント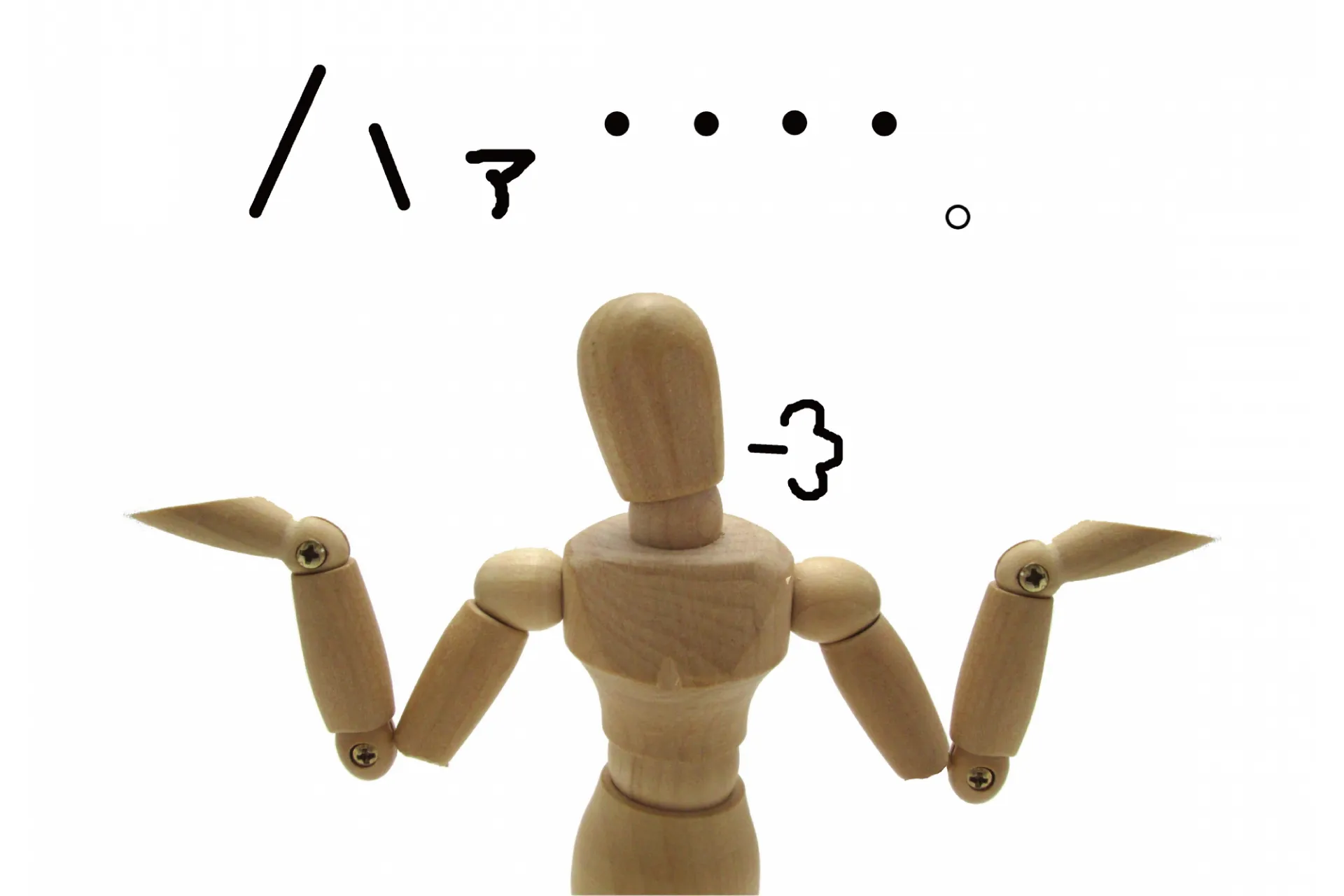
【不機嫌を放置しないで】フキハラの正しい対処法と組織を守る予防策
不機嫌な態度を周囲に振りまき、人間関係や業務に悪影響を与えることをフキハラ(不機嫌ハラスメント)と言います。パワハラ...
ハラスメント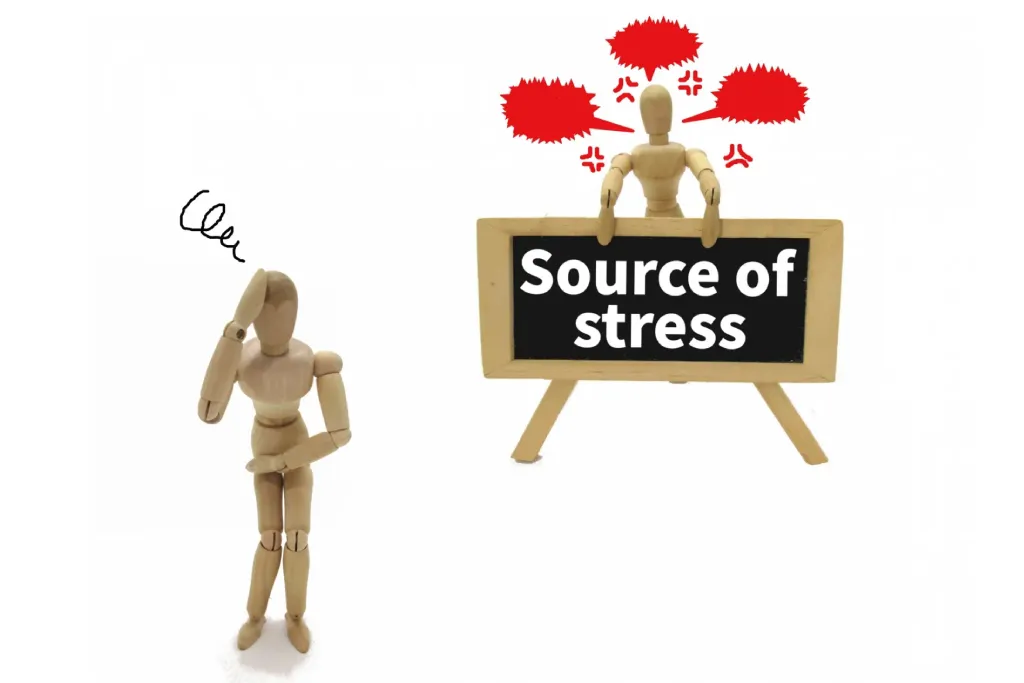
言ってはいけない言葉のパワハラ一覧!パワハラの判例についても解説
言葉によるパワーハラスメント(パワハラ)は、相手の人格や能力を否定する言葉や、仕事や職場からの排除を示唆する言葉、相...
ハラスメント





