- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- エンゲージメント
- コミュニケーション能力を鍛える方法|仕事で役立つ取り組みを解説
コミュニケーション能力を鍛える方法|仕事で役立つ取り組みを解説

商談だけでなく日常的なコミュニケーションもオンラインで行うことが増えた今、コミュニケーション能力は仕事や日常生活においてますます重要になっています。特に、新卒世代にはうまくコミュニケーションが取れない、伝えたいことが相手にうまく伝わらないといった悩みを抱えている人も少なくありません。
この記事では、そもそもコミュニケーション能力とは何か、どういった要素があるのか、コミュニケーション能力を高めるためにはどうすればよいのか解説します。社内のコミュニケーション能力に不安を抱えている管理職の方やHR部門担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
Toggleコミュニケーション能力とは

コミュニケーション能力とは、対人関係の意思疎通や協調に必要となる、さまざまなスキルが複合的に含まれたものです。です。また、コミュニケーションは、バーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションの2つに分類できます。
バーバルコミュニケーション
バーバルコミュニケーションとは、「言語コミュニケーション」、すなわち会話や文章を通じて行うコミュニケーションのことです。電話・メール・手紙などを介したやり取りのほか、通訳を介して行われる会話もバーバルコミュニケーションに含まれます。
バーバルコミュニケーションは、相手と直接対面できない場合でも、コミュニケーションを図れる点がメリットです。バーバルコミュニケーションが活躍する場面の例は、以下の通りです。
| ・チャット・メール ・リモートワーク ・オンラインミーティング・研修 ・ヘルプデスクなど |
ノンバーバルコミュニケーション
ノンバーバルコミュニケーションとは、言葉以外の手段で意思を伝える「非言語コミュニケーション」のことです。ノンバーバルコミュニケーションの例は、以下の通りです。
| ・表情 ・声のトーン ・目の動き ・ジェスチャー ・姿勢など |
ノンバーバルコミュニケーションでは、繊細なニュアンスや感情を伝えやすいのが利点です。また、メラビアンの法則によると「言語で伝える情報よりも、言語以外によって伝わる情報が圧倒的に多い」と言われています。コミュニケーションにおいては、言語領域のスキルだけではなく、非言語領域の表現スキルも重要です。
コミュニケーション能力が重要性を増している理由

ヒューマンアカデミーが、2024年に企業の人事・研修担当者向けに実施した調査によると、最も実施率が高かった研修は「コミュニケーション研修」でした。コミュニケーション能力の育成は、現在のトレンドであると分かります。
※出典:ヒューマンアカデミー「2024年の企業研修トレンドと今後の展望。人事・研修担当者300名のアンケート結果から考察」
また、マイナビは、2025年の新卒採用で重視する能力について調査しています。結果は1位が「協調性・チームで働く力」、3位が「言葉で伝える力(文章・会話内容など)」、4位が「身だしなみや見た目・雰囲気」でした。コミュニケーションにかかわる能力は、多くの企業で重視されている状況です。
※出典:マイナビ「マイナビ2025年卒企業新卒採用活動調査」
近年、コミュニケーション能力が社会的に重要性を増している理由について、次の2つを挙げて解説します。
若い世代にコミュニケーションについて悩みを抱えている人が多い
「コミュニケーションに悩みを抱える若者が多い」という点が、コミュニケーション能力の重要性が増している大きな理由です。2023年に、こども家庭庁が15~39歳の世代を対象に行った調査では、「自分の考えをはっきり相手に伝えることができない」と答えた人が43.3%でした。調査に回答した人の半数近くが、コミュニケーションについて悩んでいる傾向が見られました。
※出典:こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」
若者世代にコミュニケーションの悩みが広がる背景には、SNSなどの非対面型コミュニケーションの普及があります。オンライン上でのコミュニケーションが増加した一方で、リアルなコミュニケーションの機会は減少しました。時代や技術が作り出した環境要因が、コミュニケーション能力の重要性を高めていると考えられます。
コロナ禍でコミュニケーションの機会が減った
「コロナ禍でコミュニケーションの機会が減った」点も、コミュニケーションの重要性を高めている理由の1つです。コロナ禍で対面による接触が減ったことで、コミュニケーション能力に不安を抱える人が多く見られます。
内閣官房の調査によると、「人と直接会ってコミュニケーションをとること」が「減った」と回答した人は2021年で全体の67.6%、2022年は全体の69.2%でした。
※出典:内閣官房「人々のつながりに関する基礎調査」図表1-3-5 コロナ禍におけるコミュニケーションの変化
株式会社グローコムが、2022年に全国1,200人を対象として行った調査では、全世代の約2割がコロナ禍で「コミュニケーション力が衰えた」と回答しています。さらに、10代女性においては、3人に1人がコミュニケーション能力の衰えを実感していました。
※出典:株式会社Glocomm「深刻な「コロナコミュ障」の実態が明らかに コロナ禍きっかけに、2割が力の衰えを実感 53.3%が感染リスクなしでも「マスクなし会話」に抵抗感」
コミュニケーション能力の4つの要素

コミュニケーション能力には、「話す力・聞く力・伝える力・読み解く力」の4つの要素が含まれています。
コミュニケーションを鍛えるには、いずれか1つの要素にかかわるスキルだけを伸ばせばよいわけではなく、複合的にすべてのスキルを身に着ける必要があります。
話す力
話す力は、自らが持つ意見・感情を正確に言語化し、相手に分かりやすく伝えるために必要な力を指します。
話す力が向上すると、プレゼンや交渉アプローチの説得力が高まる点がメリットです。要点を的確に話す力が身につくと、コミュニケーションコストの削減につながるため、仕事の効率化・生産性向上も期待できます。情報を正確かつ分かりやすく伝えることで、ビジネスに限らず、対話相手との信頼や相互理解を深められるのも利点です。
話す力の磨き方としては、結論を最初に話す習慣を身につける、論理的な思考と適切なコミュニケーション表現を習得する、といった方法があります。また、相手の理解を得るために、状況に応じて、言葉の選び方・伝える順番などを工夫する柔軟性も求められます。
聞く力
聞く力は、コミュニケーションを円滑に進めるために重要な力を指しており、傾聴力とも呼ばれます。しかし、ただ相手の言葉を聞き取る訳ではありません。聞く力には、相手の意図や感情を理解する力も含まれています。聞く力がないと、相手の言葉を正確に理解できず、適切に応答できません。
聞く力が向上すると、会話中の不明点について、的確な質問を投げかけて正しい情報を確認できます。ビジネスでは、会話を注意深く受け止めて的確に質問することで、相手のニーズを引き出せる点もメリットです。
さらに、話を丁寧に聞く姿勢には、相手を尊重する気持ちが表れます。聞く力を身につけて、相手の言葉を丁寧に受け止めることで、良好な関係構築につながる効果が期待できます。
聞く力を磨くためには相手に共感しながら、前向きに相槌を打ち、相手の話を深く知りたいという姿勢をトレーニングするのが大切です。
伝える力
伝える力は、言語情報だけでは伝えきれない要素を表現する力です。言葉や文字だけでは、微妙なニュアンス・感情が伝わらず、コミュニケーションが円滑に進まない場合もあります。
伝える力が高まると、相手の関心を引きつけ、情報を効果的に伝えられる点がメリットです。また、仕事を依頼する際に「好感が持てるような態度・姿勢」を表現できれば、快く受け入れてもらえる可能性もあります。状況に合わせて柔らかい表情や声のトーンで会話ができると、相手に安心感を与え、スムーズなコミュニケーションにつながるでしょう。
伝える力を高めるためには、言語情報に合わせて、適切な表情・ジェスチャー・声のトーンといった表現方法を取り入れるのが重要です。
読み解く力
読み解く力とは、相手の話す言葉や、書かれている文章の背景にある本心を理解する力です。相手の本当の意図を理解するには、言葉だけを信用するのではなく、表情や身振り、書き手のバックグラウンドなどの情報も読み解く必要があります。
読み解く力を身につけるには、周囲の人に興味を持ち、観察しておくのが大切です。例えば、日頃から相手を気にかけていると、同僚や友人の様子が普段と違う場合でも適切な声掛けができます。また、普段から読書習慣を身に着け、多様な書き手の文章を読んで多角的な視点を持つことでも、読み解く力を鍛えられます。
読み解く力が鍛えられることで、相手の気持ちに寄り添ったコミュニケーションが取れるため、お互いの絆を深められる点もメリットです。
コミュニケーション能力が高い人・低い人の特徴

コミュニケーションのスキルアップを目指す際には、コミュニケーション能力が高い人と低い人の特徴を理解しておくのが大切です。それぞれにどのような様子が見られるのか、主な特徴を紹介します。
コミュニケーション能力が高い人の特徴
コミュニケーション能力が高い人の特徴は、以下の通りです。
| ・相手の考えを尊重しながら自己主張ができる コミュニケーション能力に優れた人は、アサーティブコミュニケーションが得意な傾向が見られます。アサーティブコミュニケーションとは、相手の考えを尊重しながら、自分の感情や思いも表現する対話技法のことです。 ・論理的に話す能力が高い コミュニケーション能力が高い人の多くは、ロジカルコミュニケーションも得意としています。ロジカルコミュニケーションは、「自分の考えと相手の考えを論理的に理解することで、円滑な対話を目指す」考え方です。話の要点や結論を伝えた後に、理由や具体例を話すなど、「伝わること」を意識した論理的な話し方にも長けています。 ・相手に合わせて会話ができる 相手に合わせた適切な言葉選び・対応ができるのも、コミュニケーション能力が高い人の特徴です。例えば、相手の理解度に応じて語彙を使い分ける、立場に応じてお互いが気持ちよくコミュニケーションできる言葉遣い・態度で接するなどの会話スキルを備えています。 ・人の話を聞く姿勢を見せる コミュニケーション能力が高い人は、傾聴の姿勢を徹底することで、相手が話しやすい雰囲気を作るのも得意です。頷き・相槌といった表現や質問を適切なタイミングで取り入れ、自然なコミュニケーションで相手の真意を引き出します。 |
コミュニケーション能力が低い人の特徴
コミュニケーション能力が低い人に見られる特徴は、以下の通りです。
| ・相手の話を聞いていない 自分が話そうとしている内容に意識が向いてしまい、相手の話を聞いていないケースが少なくありません。相手の話を途中で遮る、意見を否定するなど、自己中心的になってしまう人も見られます。 ・視線を合わせるのが苦手である 視線を合わせる行為に苦手意識があり、受動的になりやすいという点も、コミュニケーション能力が低い人に見られる特徴です。表情や視線から相手の反応が読み取れないため、心理的な距離が生まれやすく、コミュニケーションが円滑に進まなくなってしまいます。 ・会話を広げない コミュニケーション能力が低い人の中には、積極的に会話を広げようとする意識が乏しい人も見られます。会話を盛り上げたくても、話を広げる糸口が見つけられず、悩んでしまうケースも少なくありません。 |
コミュニケーション能力を鍛える方法

コミュニケーションスキルを鍛える際に意識したい方法として、次の3つを挙げて解説します。コミュニケーション能力を高め、職場環境や人間関係を改善するための参考にしてください。
コミュニケーション活性化につながるフレームワークを使う
コミュニケーション活性化につながるフレームワークの例としては、DESC法やPREP法が挙げられます。
DESC法は、アサーティブコミュニケーションを実践する際に役立つ対話技法です。以下の4つの順で会話を進めることで、相手を嫌な気持ちにさせない自己主張を実践します。
| ・Describe(客観的な状況を描写する) ・Explain(主観的な意見を説明する) ・Specify(提案する) ・Choose(相手の反応によって、次の行動を選択する) |
PREP法は、文章や口頭で情報を伝達する際に、「結論・理由・具体例・結論」の順で伝える方法です。情報を論理的に、分かりやすく伝えるためのフレームワークとして知られています。結論ファーストで端的に内容を伝えるだけではなく、理由や具体例で説得力を持たせられる点がメリットです。
傾聴力を身につけてもらう
コミュニケーションスキル向上の取り組みにおいては、相手の話に集中し、理解しようとする「傾聴力」を身につけてもらうのが重要です。傾聴力には、言語以外の相手の表情・仕草などから、意図や真意を読み解く力も含まれています。
特に、職場では立場・考え方が異なるメンバーと協力して業務を担当するケースが少なくありません。相手の意見や考え方を柔軟に受け入れる力がないと、コミュニケーションや仕事自体がスムーズに進まなくなってしまいます。
傾聴力を適切に発揮するには、「共感的理解」と「無条件の肯定的関心」、「自己一致」の3要素が必要です。共感的理解は、相手の立場を想像し、共感しながら理解しようとすることを指します。無条件の肯定的関心は、相手の話を評価しようとせず、肯定的な関心を持って聞くことです。自己一致とは、分からない部分を放置せず、真摯な態度で真意を確認することを意味します。
肯定的な言葉を使うルールを作る
コミュニケーション能力を鍛える際には、肯定的な言葉を使うルールを作るのもおすすめです。肯定的な言葉を使うことで、期待できるポジティブな影響は、以下の通りです。
| ・モチベーション向上 ・自己効力感の強化 ・チーム力の強化 |
肯定的な言葉には、やる気を引き出したり、自信を高めたりする効果が期待できます。さらに、肯定的なやり取りはメンバーの協力関係を促進するため、組織力の強化にもつながります。
また、相手の意見との間に相違があった場合に、頭ごなしに否定する行為は印象がよくありません。相手の話を肯定した上で自分の主張を伝える、相手をほめる言葉を意識するなど、ポジティブな表現をルール化しましょう。
コミュニケーション能力を向上するための企業の取り組み事例

コミュニケーション能力を高めるのに成功した企業事例として、次の3社を紹介します。コミュニケーションの活性化につながるアイデアを知り、自社で取り組みを推進する際に役立ててください。
社内部活動制度(株式会社SmartHR)
株式会社SmartHRでは、社内部活動の制度を浸透・充実させることで、コミュニケーション活性化に成功しました。2023年11月時点で、93個もの社内部活を設けており、部活動をサポートする制度も実施されています。新型感染症の流行により、強制リモートワークが適用された時期には、気軽なコミュニケーションを目的とした「オンライン部活支援制度」も取り入れました。
規模が大きい会社では、部署間のコミュニケーション自体が希薄化する場合があります。部活動を活用することで、普段は関わりのない社員・従業員とも新たな関係を構築できる点がメリットです。取り組みの結果、部署や年齢といった垣根を超えた交流が生まれ、コミュニケーションの活発化や質の向上といった効果が見られました。
イドバタ(株式会社博報堂プロダクツ)
株式会社博報堂プロダクツは、コミュニケーション活性化を図る取り組みとして、「イドバタ」という社内オープンスペースを設置しているのが特徴です。社員が立ち寄りやすいように、すべての拠点で、主導線上にオープンスペースを設けています。
広告業では、日々、新しく・独創的なアイデアが求められます。社員が集ってアイデアを磨き合う「共創」の過程で、コミュニケーションが活性化するだけでなく、1人では思いつかないような新しいアイデアが生まれる点がメリットです。さらに、イドバタをより働きやすい空間にするために、オンライン会議専用の環境整備やブレイクタイムのおやつ販売といった工夫も取り入れられています。
週1回の1on1ミーティング(LINEヤフー株式会社)
LINEヤフー株式会社では、週に1回・30分の1on1ミーティングを実施し、コミュニケーションの円滑化に取り組んでいます。1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で行うミーティングのことです。
LINEヤフー株式会社は、一連の取り組みを部下のためのミーティングと位置づけました。研修で専門知識を習得した上司が、現状を踏まえて「どのように次につなげていくか」という視点で問いかけて経験学習を繰り返すことで、部下の内省を支援しています。
特徴的なのは、部下が上司の1on1ミーティングをフィードバックする機会も取り入れている点です。形式的なやり取りではなく、本質的な対話によって、より充実したコミュニケーションを実現しています。
まとめ
管理職やHR担当者の方にとって、従業員のコミュニケーション能力の向上は、チームワークや業務効率を高めるために欠かせない要素です。コミュニケーション能力の向上には、話す力、聞く力、伝える力、読み解く力という4つの要素を意識的に鍛えることが重要です。
各スキルを育成するためには、積極的なフィードバックや、傾聴の環境を整えることが求められます。1on1ミーティングや定期的な社内研修などを通じて、従業員にコミュニケーション能力を鍛える機会を提供することが効果的です。
関連記事
Related Articles

自己肯定感とは|Z世代社員の自己肯定感を高めるコツ4ヶ条
この記事は2023.12.26に公開した記事を再編集しています2025年1月27日更新 Z世代の新入社員や、ミレニア...
HRトレンドエンゲージメント
リスキリングとは|DX時代における重要性やメリット・資格例を解説
リスキリングとは、労働者が新しいスキルや知識を習得するプロセスのことです。リスキリングは主に、技術の進歩や市場の変化...
HRトレンドエンゲージメント
職場の人間関係にも役立つ「アドラー心理学」をわかりやすく解説!
オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーが提唱した「アドラー心理学」は、職場の人間関係改善や人材育成に役立つ心理...
エンゲージメント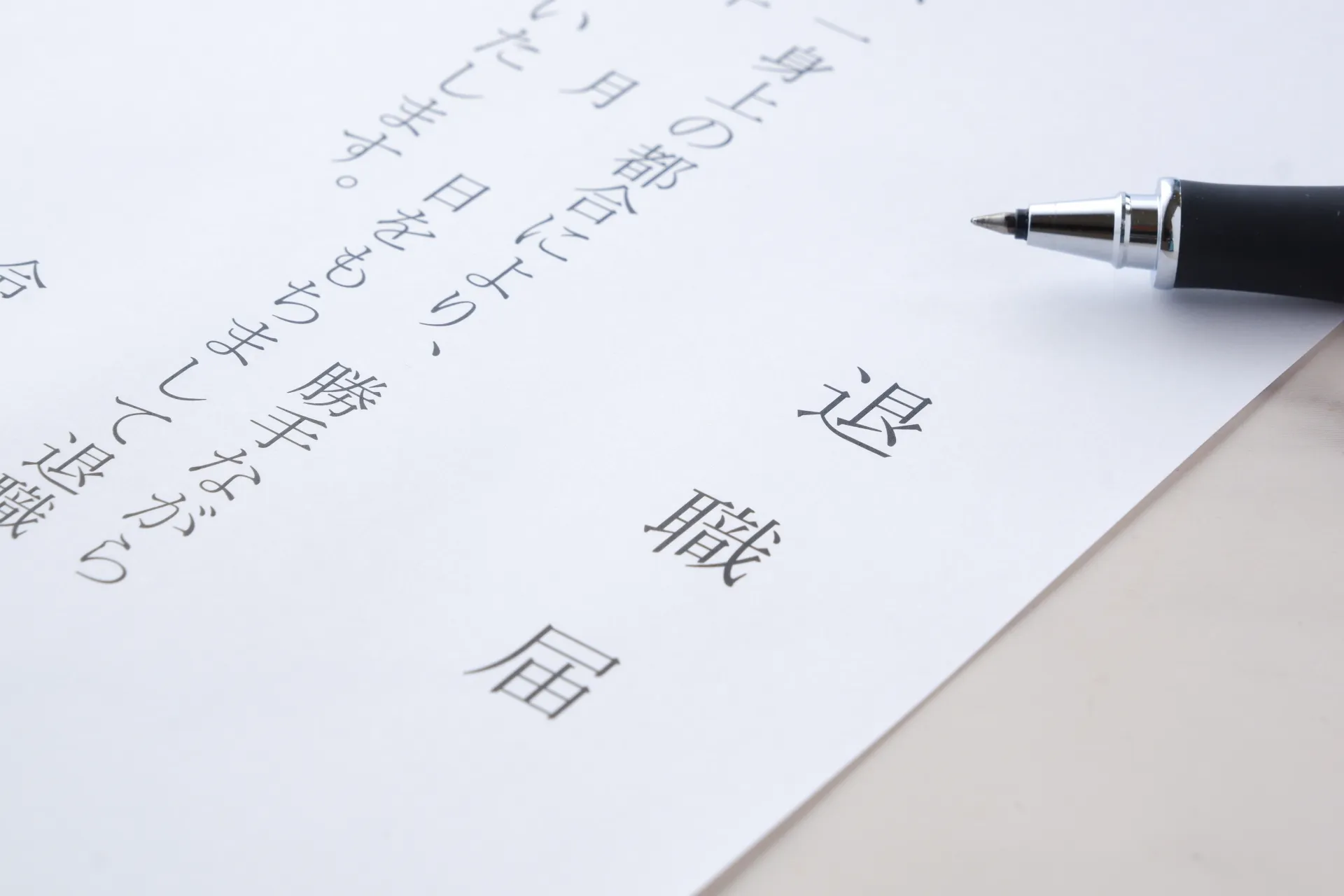
離職防止ができる対策事例10選!若手社員の離職防止アイデアを解説
当記事では、平均的な離職率から離職が発生する理由、さらに離職防止を怠った場合に起こり得る損失、企業が離職防止のために...
エンゲージメント
職場の人間関係は割り切りが鍵!気にしない方法4つと解消法を解説
職場の人間関係に悩む方は少なくありません。上司や同僚との関係がうまくいかないと、日々の業務がストレスとなり、最悪の場...
エンゲージメント
離職率に悩む企業必見!先輩社員が新入社員を支援するメンター制度とは
人手不足の中で社員の離職率の高さに悩む企業が増えています。このような状況下で注目されているのが、メンター制度です。新...
エンゲージメント
アクティブラーニングとは?主体的な人材を育てる手法を事例で解説
生徒が受動的に教育されるのではなく、能動的に考えて自主的に学ぶよう促すアクティブラーニングは、学校教育以上にビジネス...
HRトレンドエンゲージメント
コーチングで組織の生産性向上|今すぐ実践できる4つのステップ
近年では、個々の社員が自己理解を深め、自己成長が行える環境を提供するために、「コーチング」という手法が注目されていま...
エンゲージメント企業研修


