- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 「デキる人」の秘密はココ!問題解決能力が高い人の特徴と現場で役立つ鍛え方
「デキる人」の秘密はココ!問題解決能力が高い人の特徴と現場で役立つ鍛え方

業務上の課題やトラブルに直面したとき、迅速かつ適切に対応できるかどうかは、成果を左右する大きな分かれ道となります。問題解決能力は、与えられた仕事をただこなすのではなく、主体的に改善や成果につなげるために欠かせないスキルです。
特に変化の激しいビジネス環境では、想定外の出来事や複雑な課題に向き合う機会が増えており、論理的な思考と柔軟な対応力の両立が求められています。
当記事では、問題解決能力の定義や分類、優れた人に共通する特徴、能力を高める方法などを解説します。課題に正面から向き合い、自ら道を切り開いていく力を身につけるためにぜひ参考にしてください。
目次
Toggle問題解決能力とは

問題解決能力とは、発生している問題の原因を的確に把握し、状況を整理・分析した上で、適切な対応策を見出し、実行に移す力を指します。
業務においては、問題の全体像を正しく認識し、自分にできる範囲を見極めることが大切です。仮に自力での解決が難しい場合でも、上司や関係部署に適切に支援を求め、解決に導く調整力も問題解決能力に含まれます。
特にビジネスの現場では、複数の課題が同時に発生することが多く、論理的かつ柔軟な対応が求められます。問題解決能力は、職種や業種を問わず、あらゆる業務の基礎となる力です。
ビジネスにおける問題解決能力の必要性
ビジネスの現場では、業務上の課題やトラブルが日常的に発生します。問題解決能力は、品質向上や業務効率化、顧客満足度の向上といった企業の成長に直結します。さらに、自らの担当領域にとどまらず、顧客やチームの課題にも対応できるようになることで、社内外からの信頼も高められるでしょう。
ビジネスパーソンにとって、問題解決能力は仕事の価値と自身の市場価値を高める基盤となる重要なスキルです。
問題の種類
ビジネスにおける問題は、大きく3つのタイプに分類されます。それぞれの特性を理解しておくことで、適切な対応が可能になります。
| ・発生型 目の前で起きているトラブルや業務上の不具合など、すでに顕在化している問題を指します。納期遅延やクレーム対応など、迅速な対処が求められる場面でよく見られます。 ・設定型 目標と現状とのギャップにより発生する問題です。たとえば売上目標を達成できていない状態など、数値目標と照らして課題を抽出する必要があります。 ・潜在型 まだ顕在化していないものの、将来的に問題になりうるリスクを指します。業務フローの非効率性や顧客ニーズとのズレなどが挙げられます。 |
問題を正しく分類することは、効果的な解決策を導く上で欠かせないプロセスです。
問題解決能力が高い人に共通する特徴

問題解決能力が高い人は、思考と行動のバランスが取れており、論理的かつ柔軟に課題へ取り組んでいます。状況に応じた判断ができ、日頃から改善意識を持って行動している点が特徴です。
| ・ 論理的に考える力がある ・ 原因を深く掘り下げる姿勢がある ・ 柔軟な思考をしている ・ 決断と実行ができている ・ 振り返りを習慣化している ・ 学び続ける意欲がある |
問題解決能力が高い人は、物事を筋道立てて捉え、課題の本質を的確に見極められます。また、成果や失敗から学びを得て次に生かす習慣が身についており、継続的な成長を目指して主体的に学習する姿勢があります。
こうした行動特性を持つ人は、変化の激しいビジネス環境でも安定して成果を出し、組織から高く評価されやすい傾向があります。
問題解決能力が低い人に共通する特徴

問題解決能力が低い人には、課題の本質を見極める力や実行力が不足している傾向があります。問題の原因を深掘りせず、表面的な対応で済ませるため、同様のトラブルを繰り返すケースが少なくありません。
他にも、次のような特徴があります。
| ・問題の表面しか見ていない ・論理的に考える力が弱い ・柔軟に対応できていない ・行動に移すまでに時間がかかっている ・批判のみで代案を提示しない ・同じミスを繰り返している ・無理な計画を立ててしまう ・状況に流されて判断を誤る |
これらの傾向は業務の質やスピードに影響しやすく、結果的に信頼を損なう要因にもなり得ます。
問題解決能力を高めて得られるメリット

問題解決能力は、単なるスキルの1つではなく、企業の競争力や個人の成長に直結する能力です。ここでは、問題解決能力を養うことによるメリットを詳しく解説します。
社員の論理的思考力が高まる
問題解決能力を高める過程では、状況を整理し、因果関係を把握する論理的思考が求められます。この力が養われると、複雑な問題も段階的に分解し、解決に必要な要素を的確に把握できるようになります。
中でも有効なのが「なぜなぜ分析」です。これは、1つの事象に対して「なぜ?」を繰り返し問いかけることで、根本原因を突き止めていく手法です。トヨタの現場で実践されてきたこの分析は、表面的な対処にとどまらず、本質的な改善につながる方法として知られています。
論理的思考力を養うためには、問題の背後にある要因を深掘りする習慣が不可欠です。
※参考:日経クロステック「真因を究明できないのには訳がある、「トヨタ式問題解決手法」の訓練」
変化やトラブルに柔軟に対応できる
現代のビジネス環境は変化のスピードが速く、想定外のトラブルも多発します。問題解決能力が高ければ、そうした予期せぬ出来事に直面した際でも、冷静に状況を把握し、柔軟に対応することが可能です。
変化に対して構えるのではなく、受け入れて対応する柔軟性は、個人だけでなく組織にとっても強みとなります。不確実性の高い時代において、柔軟な対応力を持つ人材は、どの業界でも重宝される存在となります。
業務の正確さと効率が高まる
問題解決能力を高めることで、業務遂行における精度とスピードがともに向上します。原因の特定から改善策の実行までを一貫して進める力が身につくため、作業のムダを減らし、成果を安定して出せるようになります。
また、問題の本質に即した対応ができるようになるため、同じミスを繰り返さなくなります。組織内でのノウハウ共有も促進され、全体の生産性向上にも貢献します。
現場で差がつく!問題解決能力の身に付け方

問題解決能力を身につけるには、単に知識を得るだけでなく、実際の業務で活用できるプロセスを段階的に習得することが不可欠です。ここでは、実務の中で成果を生み出すために欠かせない3つのステップを紹介します。
問題を正しく認識して本質を見極める
問題解決の第一歩は、「本当に何が問題なのか」を見極めることです。表面的な現象だけを追うのではなく、背景にある構造や原因を整理し、真因に迫ることが重要です。
トヨタ自動車では、品質改善のために「なぜなぜ分析」を活用しています。たとえば広告宣伝費の過剰という課題に対して、なぜなぜ分析を繰り返し、根本にある顧客ニーズの変化やチャネル選定の誤りなどを発見します。
問題の本質を見誤れば、その後の対応策すべてが的外れになるおそれがあるため、最も慎重に進めるべき工程です。
問題を分析して解決策を立案する
問題の本質が見えたら、次はその内容を分析し、解決策を検討します。この段階では、「MECE」や「ロジックツリー」といった論理的思考ツールが有効です。原因や選択肢を重複なく、漏れなく整理することで、適切な打ち手が見えてきます。
分析の質が高まるほど、実行可能で効果的な解決策を導き出せるようになります。
解決策を実行して成果につなげる
立案した解決策は、計画通りに実行して初めて意味を持ちます。優先順位の明確化と担当の割り振り、期限の設定を行い、スムーズな遂行を目指しましょう。ビジネスでは「スピード」「コスト」「インパクト」のバランスを見極めることが重要です。
物流大手のSGホールディングスでは、2025年問題(労働人口の急減)に対応するため、DXを活用した物流最適化を推進しています。AIやロボットの導入についてしっかりと計画を立て、属人的だった業務の標準化と効率化を実現し、人的資源の負担軽減にもつなげています。
解決策の実行フェーズでは、具体的な行動とPDCAサイクルの徹底がポイントです。
まとめ
問題解決能力は、論理的に物事を整理し、適切な解決策を導き出す力であり、あらゆる職種・業種に共通して必要とされる基礎スキルです。表面的な対処ではなく、原因の本質に迫る姿勢が、持続的な成長や信頼構築につながります。
問題解決能力が高い人は、学び続ける意欲を持ち、変化に対して柔軟に対応できる点が共通しています。こうした行動特性を意識することで、自らの成長だけでなく、チームや組織の成果にも貢献できるでしょう。問題解決能力を日々の実務に落とし込み、安定して成果を出す習慣を築くことが大切です。
関連記事
Related Articles

オンボーディングとは?導入目的と方法、成功のポイントを解説
オンボーディングとは、入社した新入社員や中途社員がいち早く仕事に慣れて仕事ができるようにサポートを行うことです。オン...
HRトレンド企業研修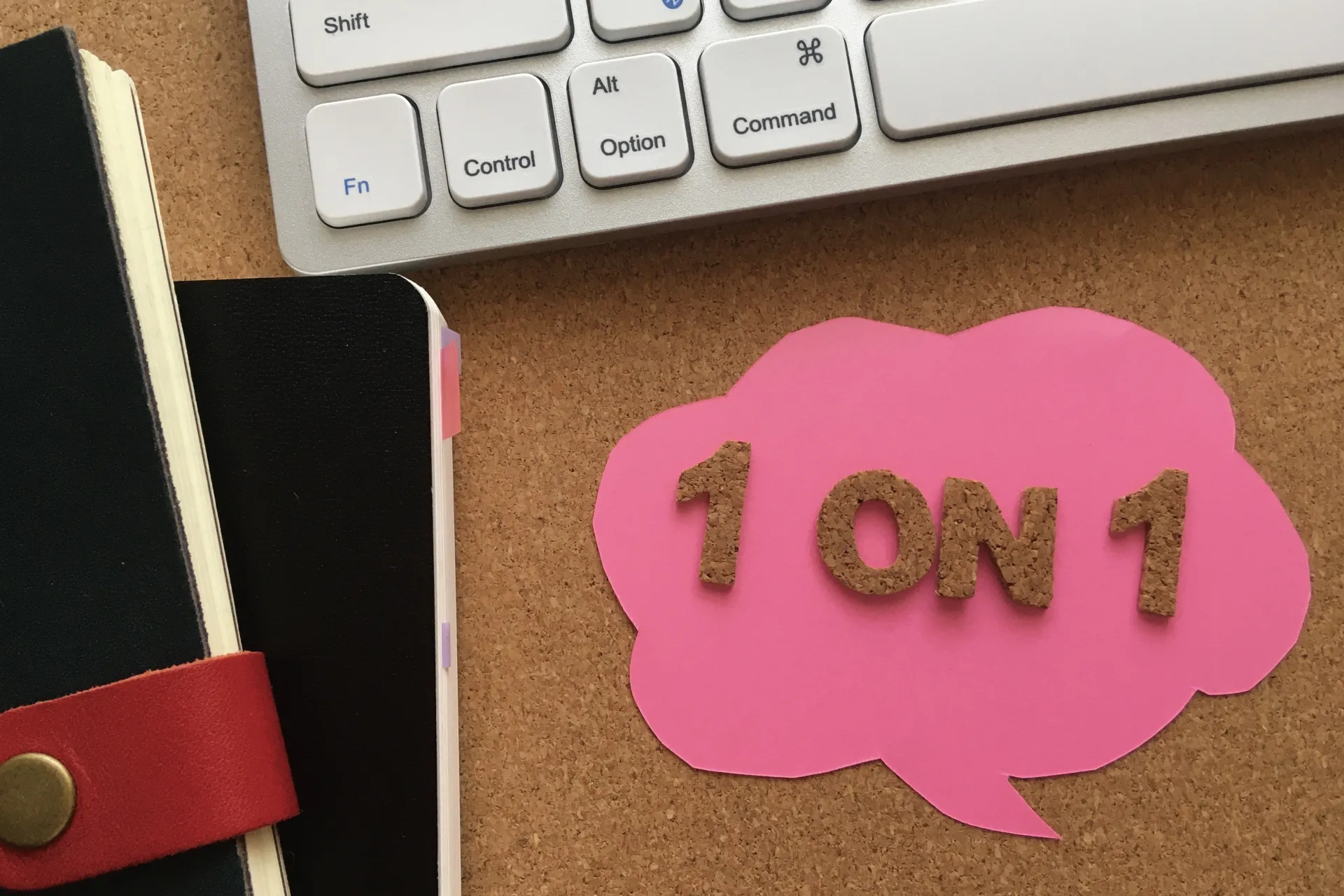
1on1とは?目的や会社組織を強化する効果的なやり方を解説
1on1ミーティングでは、部下に対して期待値をしっかりと明示し、これまでの業務や成果に対する賞賛を行うことが大切です...
エンゲージメント企業研修
2030年に必要な未来のスキルも解説|社会人に必須のビジネススキル一覧
ビジネススキルは、仕事を効率的に、かつ効果的に遂行するために必要なスキルです。社会人として昇給や昇格を目指す場合にビ...
企業研修
【7社の事例から学ぶ】ダイバーシティマネジメントで企業が強くなる理由
ダイバーシティマネジメントは、多様な人材の特性や価値観を尊重し、組織の成長に生かす経営手法です。イノベーション創出や...
企業研修
【アイスブレイク鉄板ネタ9選】ビジネスですぐ使える事例を徹底解説
アイスブレイクとは、会議や研修、ワークショップなどの開始前に短い時間で行うアクティビティです。参加者同士の親睦を深め...
HRトレンド企業研修





