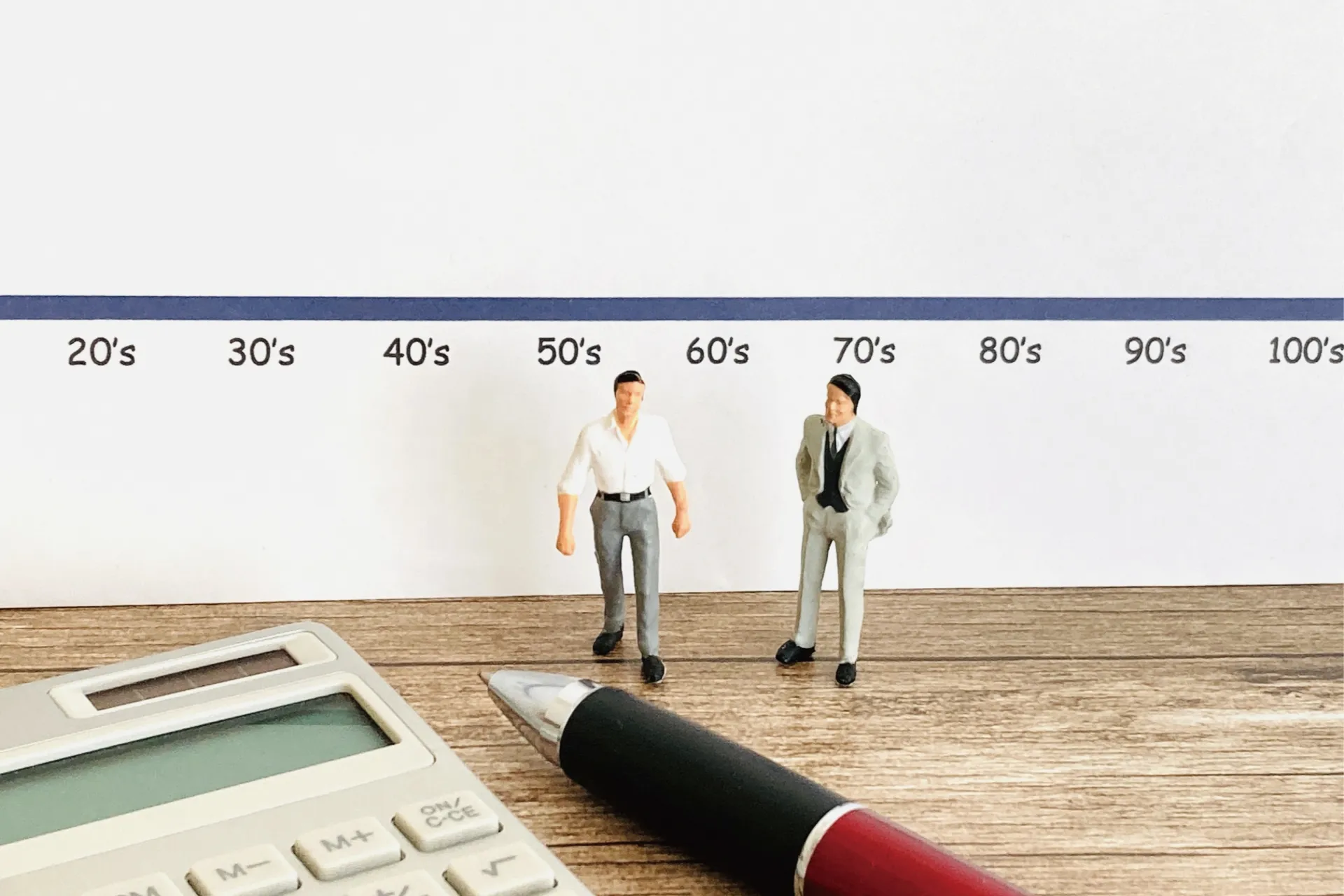- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- 企業研修
- 今見直すべき研修制度とは?最新トレンドと充実している企業事例も解説
今見直すべき研修制度とは?最新トレンドと充実している企業事例も解説

近年、多くの企業が人材育成や組織力の強化を図る手段として、研修制度の充実に取り組んでいます。産労総合研究所の2024年の調査では、6割強の企業が「今後研修費用を増加させる見込みがある」と答えており、2023年に引き続いて増加傾向です。
※出典:産労総合研究所「2024年度 教育研修費用の実態調査」
一方で、研修内容のトレンドは移り変わっています。従業員が必要なスキルを身に着け、モチベーションを高め、組織の生産性を高めるためには、「今、どういった研修が望まれているのか」を知ることが欠かせません。
この記事では、研修制度の目的やメリット、代表的な研修の種類を整理するとともに、現代ならではの研修トレンドを掘り下げ、実際に成果を上げている企業事例を紹介します。
目次
Toggle研修制度を充実させる目的・メリットとは

研修制度とは、実務に必要なスキルの習得や業務への意欲向上を目的に実施する、人材育成の取り組みです。企業側でさまざまな研修環境を整えて制度化することで、従業員一人ひとりの能力向上と業務への意識改革を図ります。
ここでは、研修制度を充実させる目的や研修によって得られるメリットを紹介します。
業務に必要なスキルを習得させる
研修制度の大きな目的の1つが、業務に必要なスキルの習得です。業務に欠かせないスキルを学ぶ機会を設けて、実務に生かせる知識や技術を網羅的に身に付けます。
特に専門的な知識・技術が必要な部署の場合は、スキルアップのための研修が欠かせません。OJTとして現場で実践的に訓練しながら学ぶのも大切ですが、研修で座学を取り入れると、より深い知識を習得するのに役立ちます。現場とは別に学ぶ環境を用意することで、実践業務では説明しないような細かな情報の補完が可能です。従業員の業務全体への理解度向上も図れます。
従業員に共通認識を与え一体感を高める
研修制度を取り入れて業務への理解を深める機会を設けるのは、従業員に共通認識を与えるのにも役立ちます。業務に必要なスキルのほかに企業理念や社内方針、社内における各種ルールなどを学ぶ内容も研修に盛り込むと、従業員間での一体感がより高まるためおすすめです。
社内全体で認識を一致させなければならない事項などは、多くの従業員を集めて実施する研修での周知が特に有効に働きます。部署ごとや少人数を対象に都度周知する形では、些細な言い回しの違いで従業員の認識にズレが生じてしまう可能性が否定できません。そのため、多くの従業員の認識を一致させる場として、研修の機会を設けるのが効果的です。共通認識によって従業員の一体感が高まると、組織力の向上も期待できます。
社内風土を変えて業績向上につなげる
研修制度は、社内風土を変えて既存の体制を改善・強化させるのにも役立ちます。たとえば、人材育成に課題がある企業の場合、管理職を対象としたマネージメント術などの研修を取り入れるのがおすすめです。管理職としての意識の持ちようや行動を改善するきっかけとなるほか、人材育成への関心を高められます。
研修によって既存の人材育成方法の問題点について広く認識を合わせられると、社内全体で育成環境の改善に取り組みやすくなるのもメリットです。優秀な人材の育成に役立つだけではなく管理職の成長にもつながり、結果的に業績の向上も期待できます。
研修制度構築でよく取り入れられる代表的な研修の種類

企業が取り入れる研修制度には、さまざまな種類があります。取り入れる目的や強化したい内容によって効果的な研修が異なるため、まずはどのような種類があるのか把握し、制度構築に役立ててください。
ここでは、研修制度構築でよく取り入れられる代表的な研修を大きく3つに分けて紹介します。
階層別研修
階層別研修とは、従業員を立場や役職ごとに分けて、それぞれに必要なスキルや業務に取り組む姿勢を身に付けることを目的とする研修です。階層は主に、新入社員や若手社員、中堅から管理職・役員といった形で分けられます。
それぞれの階層では、下記のようなカリキュラムでスキルアップを図ります。
| ・若手社員研修 ・中堅社員研修 ・管理職研修 など |
若手社員研修の対象は、主に入社2~5年目の従業員です。仕事の効率化に役立つスキルの習得や、将来的に部下を教育する立場になるときに備えて、指導力の習得を目指す研修を行います。
中堅社員研修は、チームリーダーなどのまとめ役を担う従業員が対象の研修です。管理職研修は、中堅社員よりさらに上の重要な判断を下す立場の社員を対象としています。責任が重い立場を対象とした研修になるほどリーダーシップやコーチング、安定した業務の遂行ができるような組織づくりを学習するのが特徴です。
部門・スキル別研修
部門・スキル別研修は、各部門や従業員それぞれの役割に応じて行う研修です。たとえば、下記のような研修によって、部門ごとや従業員の特性を高められると、チーム力だけではなく結果的に企業全体の組織力向上を図るのに役立ちます。
| ・事務・スタッフ社員研修 ・人材開発担当社員研修 ・製造部社員研修 など |
事務職を対象とした研修が、事務・スタッフ社員研修です。専門的な部門に比べて成果が見えにくい事務職で、業務への意欲を維持する方法などを学びます。
人材開発に役立つ知識やスキルの習得を目指すのが、人材開発担当社員研修です。主に人事部などの人材育成に携わる従業員を対象とします。
製造部社員研修はあらゆる製造現場で役立つ、整理・整頓や清掃などの基本事項を学ぶ研修です。ほかにも部門・スキル別研修には、法務部やシステム開発部のほか経営企画部、広報部などの専門性の高い部門を対象とした研修が存在します。
自己啓発支援
自己啓発支援は、従業員が自らの意思で専門的なスキルの向上を図れるよう、企業がさまざまな講座の受講体制を整えてサポートする、研修制度の導入方法の1つです。企業側が義務付けた研修と異なり、従業員自らの意思による講座の受講を促すことで、自律的に学習する社内風土を作れます。
たとえば自己啓発支援として、企業側は下記のような研修カリキュラムを整えるのが効果的です。
| ・ロジカルシンキング研修 ・アート思考研修 ・ストレスマネジメント研修 ・エンゲージメント研修 など |
ロジカルシンキング研修やアート思考研修は、思考力の習得を目的としています。計画の立て方や打ち合わせなどで生かせるスキルの学習です。
ストレスマネジメント研修では、ストレスに対する理解を深めます。ストレスの原因となり得るものやそのケア方法などを学んで、個人や組織単位での快適な職場環境の構築に役立てる研修です。
エンゲージメント研修は、従業員が抱く企業への愛着や貢献意識を高めるために行います。組織全体の目標の理解や個々のキャリア形成などをテーマに取り上げて業務意欲を高め、生産性の向上につなげる研修です。
現在トレンドになっている研修テーマ

企業研修のトレンドは、時代とともに変化しています。現在はどのような研修が注目を集めているのか把握し、自社に必要な研修テーマを選びましょう。
ここでは、現在の企業研修のトレンドと言える5つのテーマについて解説します。
ウェルビーイング
ウェルビーイングとは「良い」を意味するWellと、「状態」を意味するBeingで構成された言葉です。個々における社会的な面や、身体的・精神的にも良好な状態を指しています。具体的には、仕事や日々の生活だけではなく心身の健康が確保できており、経済的な不満などもない状態です。
ウェルビーイング研修が注目を集めるのは、近年多くの企業が働き方改革などを通して、企業と従業員の満足度向上に取り組む姿勢とマッチしているのが理由です。研修ではメンタルヘルスやコミュニケーションなど、多岐にわたる項目について学び、企業の成長と従業員の満足度向上を図ります。
例として、丸井グループでは従業員一人ひとりの意識や行動の変化を促して生産性の向上を図るため、ウェルビーイング活動を強化しています。研修に参加するメンバーを1年ごとに入れ替える方法で活動を続け、グループに所属する従業員全体の意識改革を図る方針です。
※出典:MARUI GROUP「人と社会のしあわせを共に創る「Well-being経営」
『ストレス耐性、モチベーションUP に マインドフルネス研修』はこちら
エンゲージメント
エンゲージメントとは、「契約」や「約束」といった意味があるほか、深いつながりを持つ関係性も表す言葉です。人事においては企業と個人の関係性を指しており、エンゲージメント研修では従業員の企業へ対する愛着や貢献意識、働きがいの向上を目指します。従業員の仕事に対する幸福感を高めることで、生産性の向上やメンタルヘルスの良好な状態の維持なども期待できる研修です。
エンゲージメントを高めるためには、企業側は従業員の意見を調査した上で研修を通じて働きやすい環境を整えたり、キャリア形成のサポートをしたりするのが効果的です。製品製造に用いる機械の開発をしているコマツでは、持続的な会社の成長には従業員のエンゲージメント向上が欠かせないと考えています。実際に従業員一人ひとりの意見を把握する取り組みを続けており、それぞれが活躍できる職場環境の実現を目指す方針です。継続的にエンゲージメントの向上に取り組み、従業員の仕事に対する意識改革を促しています。
※出典:KOMATSU「多様な能力開発機会の提供とエンゲージメントの向上」
『エンゲージメントとは?ビジネスにおける意味や高める施策を徹底解説』はこちら
DX・AI活用
DXとは、あらゆるデータやデジタル技術を活用して、組織力の向上を図ることを意味する言葉です。組織や業務単位でDXを取り入れ、より価値の高いサービスを顧客に届けられるよう目指します。DX研修は主に、DXに対応できる人材育成が目的です。データ活用やデジタル技術に関する学習機会を設けると、多くの企業で課題となっているDX人材の不足解消が期待できます。
AI研修は、生産性の向上やコスト削減を目的に注目を集めている研修です。発展を続けるAIを活用できるスキルを習得するため、基礎から専門的な使用方法まで学び、企業の成長につなげます。
ダイキン工業株式会社はデジタル技術を学ぶ教育体制を整えて、情報系の人材育成に取り組んでいる企業の1つです。徹底したデジタル技術を学習した後は出向による実践経験で、さらなる知識の習得やスキルアップの向上につなげています。
※出典:DAIKIN「社内大学で学んだ優秀な新人を出向させる“ダイキン流データ活用人材育成術”とは?」
コミュニケーション研修
コミュニケーション研修は、従業員の対話力や表現能力を高められる研修です。研修で得た知識やスキルは、現場での情報共有の促進や良好な人間関係の構築に役立てられます。
近年、コミュニケーション研修が注目を集めているのは、社会のグローバル化や個々の価値観、働き方の多様化を受けているのが理由です。リモートワークの実施率も高まっており、オンライン上での円滑な業務遂行を目指して、研修が取り入れられるのも珍しくありません。
ヒューマンアカデミーが人事・研修担当者300名を対象に2024年に行った調査では、最も実施率が高い研修としてコミュニケーション研修が1位となる結果が出ています。多様な働き方に対応するためチームワークの強化を目指す企業にとって、コミュニケーション能力の向上が重要視されていることが分かる結果です。
※出典:ヒューマンアカデミー「2024年の企業研修トレンドと今後の展望。人事・研修担当者300名のアンケート結果から考察」
ハラスメント研修
ハラスメント研修は、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント行為への対応方法や、発生防止に向けた知識を学ぶための研修です。ハラスメント行為への対策は2019年の法改正で大企業において義務化されており、2022年4月からは対象が全企業になりました。企業関係者はハラスメントを防ぐために周知や教育をするとともに、実際に発生した際の対応方法も定める必要があります。
※出典:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
2024年のヒューマンアカデミーの調査では新入社員や若手・中堅社員、管理職に至るまでのすべての階層で、ハラスメント研修の実施率が70%を超える結果となりました。法改正による義務化が実施され注目度が高まっているハラスメント問題に取り組むため、各企業でハラスメント研修のニーズが高まっていることが分かります。
※出典:ヒューマンアカデミー「2024年の企業研修トレンドと今後の展望。人事・研修担当者300名のアンケート結果から考察」
研修制度の構築に成功した企業の事例

研修制度は自社に適した種類を選ばなければ、想定していたような効果が得られない可能性があります。そのため、研修制度を導入する際は、制度構築に成功している企業の事例を参考に、自社ではどのように取り入れるべきか検討するのがおすすめです。
ここでは、研修制度の構築に成功した4つの企業の事例を紹介します。
サントリー
サントリーは、階層別や国外での活躍を視野に入れた研修など、豊富な研修制度を整えている企業です。
階層別では、主に部長層や課長層を対象にした「次世代経営者研修」やマネージャー層の能力強化を目的とした研修を実施しています。若手社員が対象のプログラムでは、たとえば入社半年後に、泊まりがけで自社の創業精神をテーマにした研修が行われます。入社から間もない時期に自社について学ぶ機会を設けて、経営方針や方向性を体験的に理解してもらい早期成長を促す狙いです。
また、世界で活躍する人材を育成するため、国外のビジネス・スクールと連携して独自の研修プログラムを開発しているのもサントリーの特徴です。国外と連携して研修プログラムを開発し実施することで、国境を越えたネットワークの形成にも成功しています。
伊藤忠商事
伊藤忠商事は企業ブランドの価値向上のため、すべての階層で継続的な研修の開発と実施をしています。階層別だけではなく従業員個人のキャリア形成の支援もしており、約13,000の講座の中から選べる研修制度を取り入れているのも特徴です。オンラインで学べる研修もあるため、場所を選ばず海外従業員も活用できる環境を整えています。
なお、2023年度、伊藤忠商事で従業員の能力開発研修にあてられた年間の総研修時間は、115,649時間です。1人当たりに換算すると28.22時間、55.5万円のコストをかけています。
基礎力強化やグループ経営、海外を視野に入れた研修など、複数の視点から教育環境を整えて従業員の能力開発に取り組んでいます。複数の視点からさまざまな研修を実施することで従業員は幅広い内容を学べるほか、専門分野に特化したスキルアップを目指すのも可能です。
ソフトバンク
ソフトバンクは、全従業員を対象にした必須研修を実施しているほか、それぞれが任意で受けられる研修項目も用意しています。
任意研修は、オンラインでどこからでも学べる選択型の研修以外に、貸与している端末を使って学べる「Web-Learning」があるのが特徴です。Web-Learningでは、別会場で行っている研修の配信もしているため、従業員は実際の講義を受ける感覚で学べます。
また「ソフトバンクユニバーシティ」と呼ばれる人材育成機関があるのも、ソフトバンク特有の研修制度の1つです。ソフトバンクユニバーシティで実施する研修の中には、ソフトバンクの社員が講師を担当する講義も存在します。そのため、実務で生かせる知識や技術を学べるのはもちろん、リアルな経験に基づく学習が可能です。
日本航空
日本航空は航空会社という特性から、エアラインや安全に関する研修・セミナーを取り入れているのが特徴です。多くの企業が実施している階層別の研修などにくわえて、事業に沿った内容の研修を盛り込むことで、専門性の高い人材育成につなげています。
たとえば、リアルに業務内容についてのシミュレーションを実施するために、講師のほかに顧客役を用意した研修をしているのが特徴です。顧客と対峙した時にどうするのか、トラブルへの対応方法や考え方について研修を通して学びを深めます。リアルなシミュレーションは、働く際の意識の持ち方を学ぶ機会として効果的に働き、特に新入社員にとっては現場で生かせる重要な経験となる研修です。
まとめ
研修制度の刷新や導入は、経営戦略や企業文化にまで影響を与える大きなプロジェクトです。自社の組織課題や業界動向に照らし合わせながら最適な研修を選定し、従業員のモチベーション向上や専門知識の強化を目指すことが重要です。
また、成功事例に見るように、制度構築では企業理念やビジョンを共有する場づくりが欠かせません。研修の運営方法を工夫し、参加者の主体的な学びを促すことで、研修で培われた意識が現場でしっかりと実践に結び付きます。社員が自発的に取り組める環境を整えることも欠かせません。
関連記事
Related Articles

厚労省推奨!管理職の「必須スキル」ラインケアで職場と部下が劇的に変わる秘訣とは?
ラインケアとは、職場における管理職が中心となって行うメンタルヘルス対策です。当記事では、ラインケアの定義や必要性、厚...
企業研修