- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- HRトレンド
- 必要最低限の仕事しかしない「静かな退職」の問題点と対処法とは?
必要最低限の仕事しかしない「静かな退職」の問題点と対処法とは?
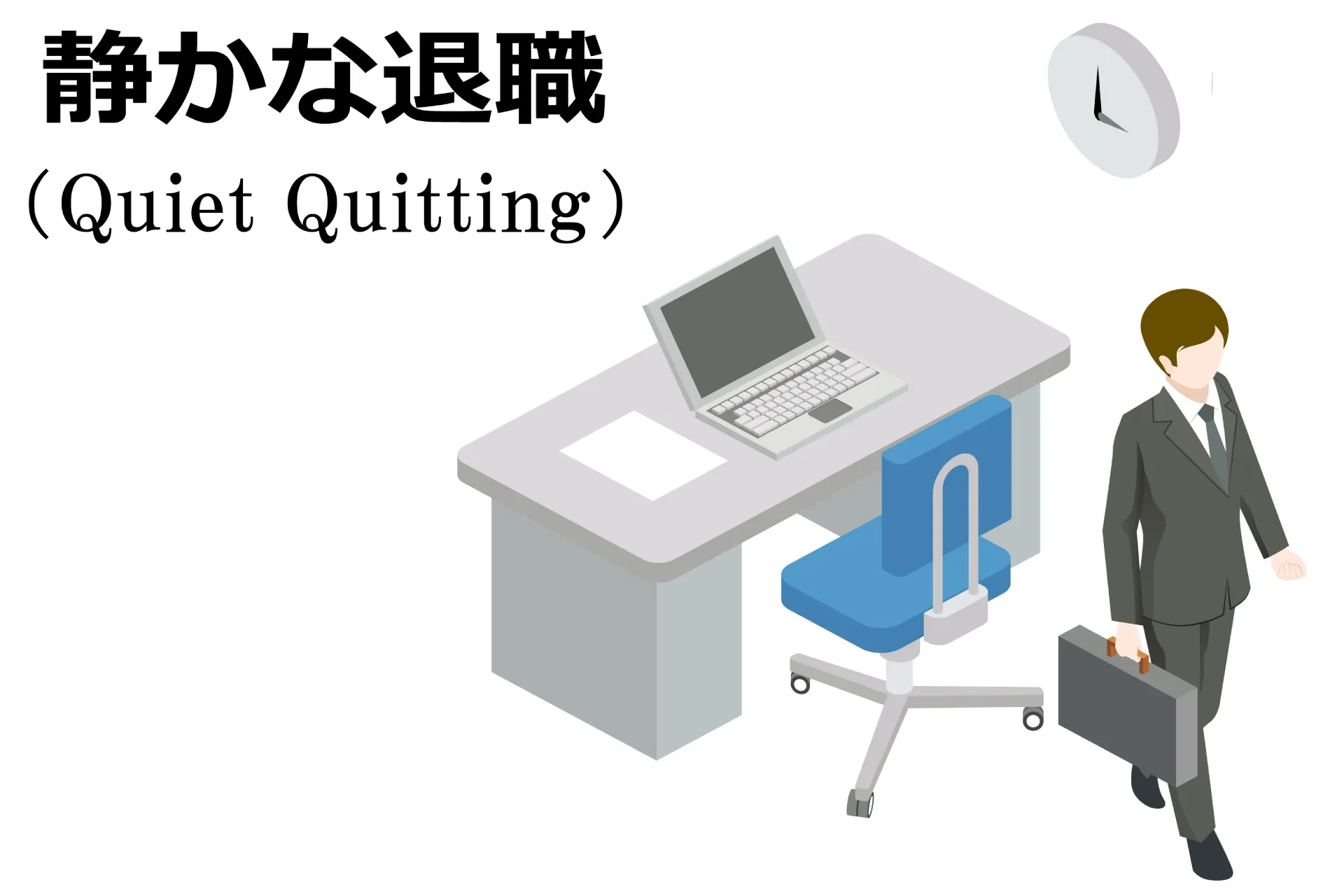
「静かな退職」という言葉は、必要最低限の仕事だけをこなす働き方を指します。近年は仕事に対する価値観や働き方が変化しており、仕事への意欲があまりなく、求められる仕事のみを行う人も増えています。
当記事では、静かな退職がなぜ増加しているのか、原因や静かな退職が増えることによる影響、企業がどのように対処すべきかについて解説します。従業員が生き生きと働ける会社を作れるよう、制度や体制を整えることが大切です。
目次
Toggle静かな退職とは?

「静かな退職」とは、必要最低限の仕事だけを行い、積極的に働かない状態を指します。既に退職が決まっている社員・従業員のように、精神的にゆとりを持った状態で働く様子から、静かな退職と呼ばれています。
2022年に、米国在住のエンジニアであるザイド・カーン氏が発信した働き方に関するSNS投稿がきっかけで静かな退職の概念が広く知られるようになりました。
静かな退職が広まっている理由
静かな退職が増えている背景として考えられる理由は、以下の通りです。
| ・仕事に対する価値観の変化 仕事よりもプライベートの充実を求める価値観を持つ労働者が増えたことが、静かな退職という働き方が広まっている1つの要因です。日本には、高度経済成長期に代表されるように、プライベートの時間までも仕事に捧げる「ガムシャラな働き方」が流行した時代がありました。しかし、経済低迷や新型感染症による混乱を経験したことで、近年は仕事のために生きる働き方に疑問を持って「必要以上に働かない」選択をする人が増えています。 ・働き方の変化 時代とともに、働き方が多様化した点も静かな退職が増えている原因です。例えば、以前は、「終身雇用」という概念の下、生涯で1つの会社に勤める働き方が主流でした。しかし、現在ではより働きやすい環境を求めて転職を繰り返す人も増えており、キャリアアップや昇進に重きを置かない働き方も珍しいものではなくなりつつあります。ワークライフバランスがとれた働き方が支持される中で、「静かな退職」状態になる労働者が増えています。 ・先行きの不透明さ 人口減少や不安定な経済状況を背景とした先行きの不透明さも、静かな退職の広がりに拍車をかけています。企業の将来性や待遇に対して、希望を持てない人も少なくありません。将来に期待できないことでモチベーションが下がり、仕事に対して消極的になってしまうケースが見られます。 |
静かな退職を選びやすい人の特徴
静かな退職状態と言える人の特徴は、以下の通りです。
| ・業務に対する意欲が見られない ・求められている以上の仕事はしない ・会議中にほとんど発言しない ・ストレスなく働き続けることを重要視している ・現状に満足していて、期待や責任を背負うことを嫌う |
上記のような静かな退職状態と言える人は、20代から30代の若手世代に多く見られます。ただし、40代以上の働き盛りの世代の中にも、静かな退職を選択している人が少なくありません。静かな退職は、社会全体の課題として注目されています。
「静かな退職」による企業側のデメリット

静かな退職は実際に人材流出が起きる訳ではありませんが、企業に対してさまざまな問題を発生させる可能性があるため、注意が必要です。静かな退職の具体的なデメリットとして、次の3つを解説します。
生産性が低下する
静かな退職の大きなデメリットは、組織の生産性が低下する点です。静かな退職という働き方を選択する人は、求められている以上の仕事はしません。また、業務中やミーティングでの発言も少なめです。
上記のような静かな退職状態の社員が存在すると、部署・プロジェクトチームといった組織の士気が下がってしまう恐れがあります。業務上のコミュニケーションに積極的に参画する社員が減少することで、新しいアイデアが生まれにくくなり、企業全体の生産性低下につながる場合がある点も問題です。
職場の人間関係が悪化する
職場における従業員同士の関係性を悪化させる点も、静かな退職のデメリットと言えます。静かな退職状態の社員は、基本的に、与えられた業務範囲以外の仕事はしません。業務指示があるまで積極的に働こうとしない人がいると、どうしても周囲のメンバーの業務負担が増加してしまいます。
さらに、静かな退職状態の社員は組織への貢献意欲が低く、トラブルが発生しても見て見ぬふりをしてしまうケースも少なくありません。静かな退職状態の労働者に対して、周囲の不満が積み重なることで、人間関係や職場全体の雰囲気が悪化するリスクがある点を理解しておく必要があります。
優秀な人材がいなくなってしまう
静かな退職の問題を放置していると、優秀な人材が流出してしまう危険性があります。静かな退職が増えると、いくら仕事に対する意欲が高い人材でも、次第に組織への不満を抱くようになるでしょう。
「仕事に対するやりがいを感じられない」、「成長機会を逃す」などの理由で優秀な人材が離職してしまうのは、企業にとって大きな損失です。また、静かな退職に対処しないままでいると、新たに「静かな退職状態の社員」が増えてしまう可能性もあります。
「静かな退職」にはどのように対処すればよい?

静かな退職に対処した上で、優秀な人材を確保し活気ある会社を実現するにあたって、いくつかの対処方法があります。具体的な方法として次の3つを解説するので、自社の労働環境を改善する際に役立ててください。
従業員エンゲージメントを把握する
静かな退職を防ぐには、従業員のエンゲージメントや本音を把握するのが重要です。従業員のエンゲージメントとは、従業員が自社や自社の商品・サービスに対して抱く愛着・信頼のことです。エンゲージメントが高い組織では、企業と従業員が、お互いの成長に貢献しようとする関係が見られます。
しかし、エンゲージメントが低い人材は仕事への意欲・積極性を失いやすく、静かな退職につながるリスクがあります。定期的な調査を行って従業員の本音に向き合うことで、職場に潜む問題を早い段階で発見し、エンゲージメント向上につなげるのが大切です。
具体的なエンゲージメント調査方法としては、個別面談やインタビューなどが挙げられます。従業員の声に耳を傾け、エンゲージメントが低いと分かった場合は、なぜそのような事態が起こったのかを分析して改善につなげる必要があります。
人事評価制度を見直す
静かな退職を防ぐためには、社員が感じている待遇面の不満を解消するのも重要です。社員を適切に評価することで、モチベーションアップにつながる効果が期待できます。評価の際は目に見える成果だけではなく、社員個人の貢献度・創造性といったプロセスを評価できる仕組みを導入するのも有効です。
ただし、評価に透明性が感じられないと、社員・従業員からの会社に対する信頼を失う可能性があるため注意が必要です。人事評価の評価項目や評価基準を明確に設定した上で、透明性・公平性の面で問題がないかも検討する必要があります。
規模が大きい会社の場合は、人事評価システムを導入するのも1つの方法です。また、評価者が一方的に評価して終わるのではなく、社員が評価を成長につなげられるようなフィードバックの機会を設けるのも大切です。
自由なキャリアパスを用意する
社員・従業員それぞれに合った自由なキャリアパスの設定も、静かな退職対策の1つとして挙げられます。社員がやりたい仕事や希望のキャリアパスを見出せない状態では、やる気やエンゲージメントの低下、静かな退職につながってしまう傾向があります。
近年は、出世・昇進を目指すキャリア観だけではなく、自分のライフスタイルに合った自由なキャリア形成を思い描く人材も少なくありません。企業側は、従業員が望むキャリアプランを実現できるよう、複業・転職なども含めた多様なキャリアパスを用意する役割が求められます。
まとめ
「静かな退職」の状態に陥っている人を放置しておくと、組織全体の生産性や従業員同士の関係が悪化するリスクがあります。また、優秀な人材が他社に流出してしまう可能性もあるので、企業は静かな退職に対して正しく対処する必要があります。従業員が積極的に業務に取り組めるよう、企業は従業員のエンゲージメントを把握し、人事評価制度を見直したり、多様なキャリアパスを提供したりしましょう。
従業員の本音に向き合い、働きがいを生み出すことが、長期的に優秀な人材を引き留める鍵となります。
関連記事
Related Articles

なぜIQよりもEQが重要なのか|人生を幸福に導く心の知能指数の高め方
ビジネスでは、知能指数を示すIQだけでなく、EQも必要だと言われています。心の知能指数を表すEQが高い人は、自身の感...
HRトレンド企業研修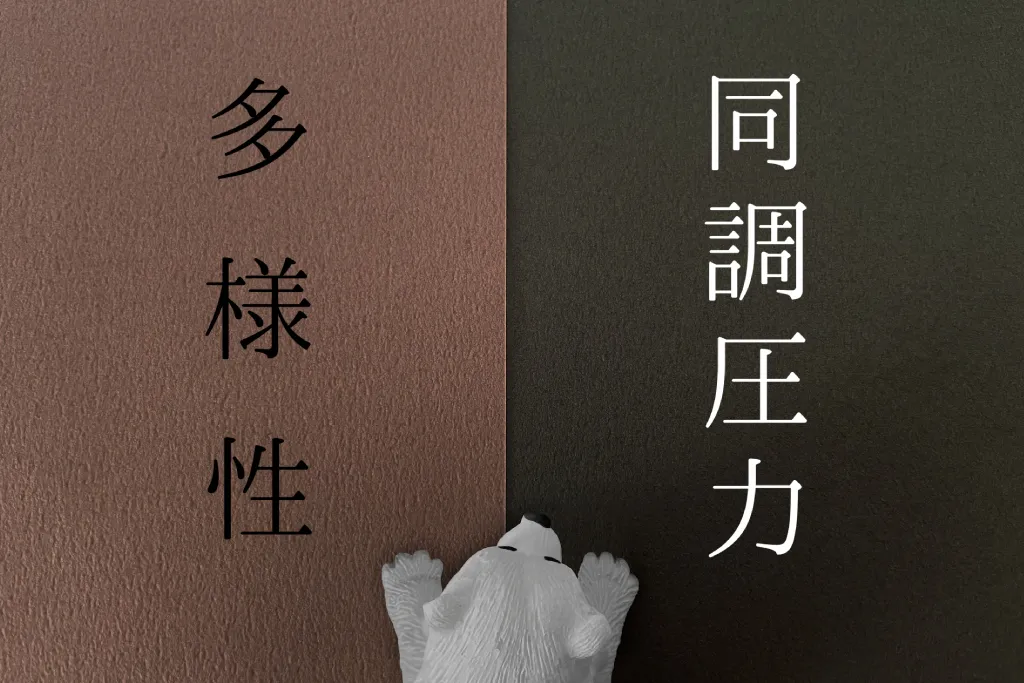
同調圧力に屈しない人はなぜブレない?他人に左右されない思考の磨き方
同調圧力に流されて意見を言えないと悩んでいる方に向けて、同調圧力に屈しない人の特徴を整理した上で、周囲に振り回されず...
HRトレンド
アンコンシャス・バイアスとは?意味や具体例・職場への影響を解説
この記事は2023.11.21に公開した記事を再編集しています2025年2月25日更新 「上司よりも先に部下が帰るの...
HRトレンドエンゲージメント
アクティブラーニングとは?主体的な人材を育てる手法を事例で解説
生徒が受動的に教育されるのではなく、能動的に考えて自主的に学ぶよう促すアクティブラーニングは、学校教育以上にビジネス...
HRトレンドエンゲージメント





