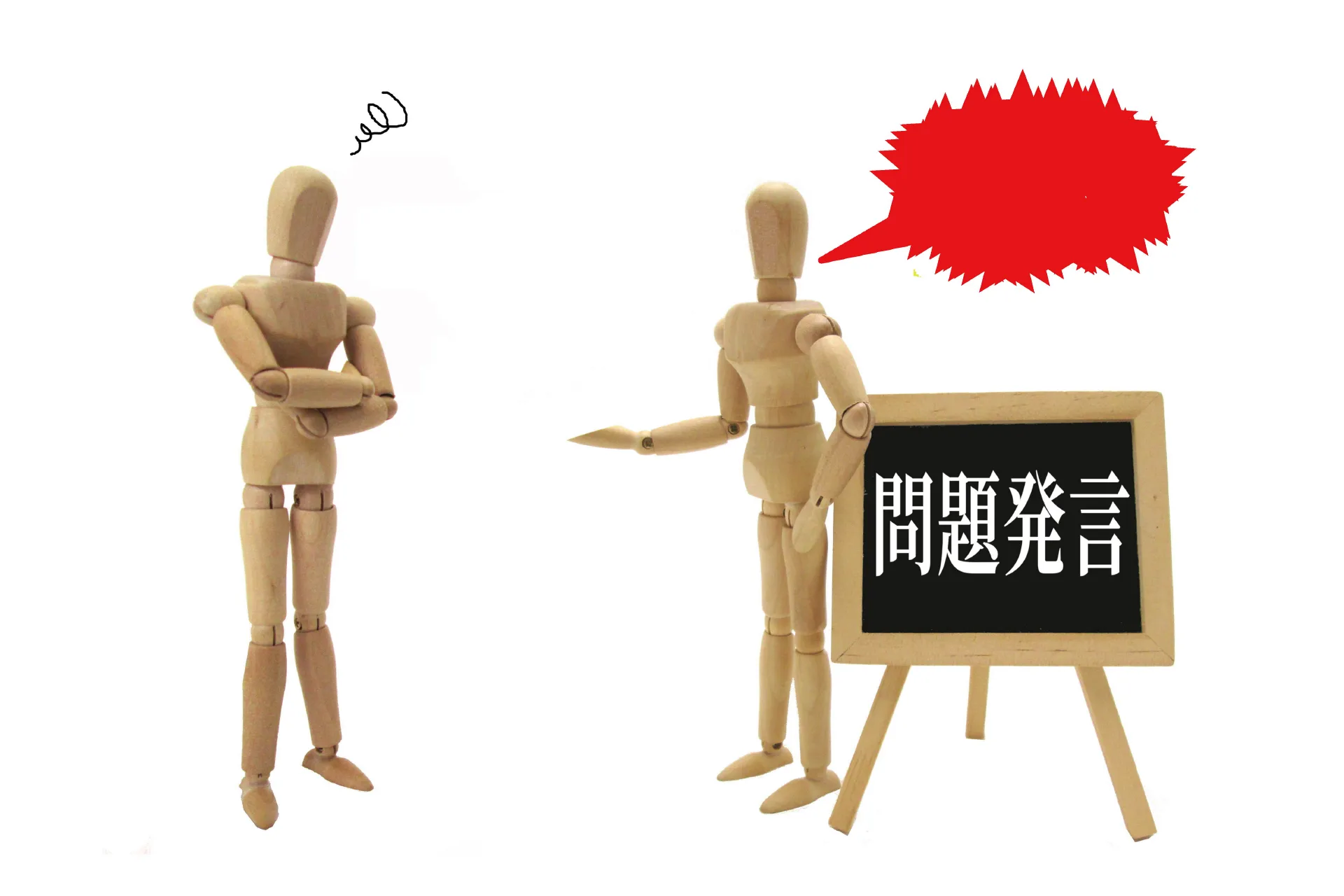- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- ハラスメント
- 【事例あり】セカンドハラスメントの3つの原因と予防・対処法を解説
【事例あり】セカンドハラスメントの3つの原因と予防・対処法を解説
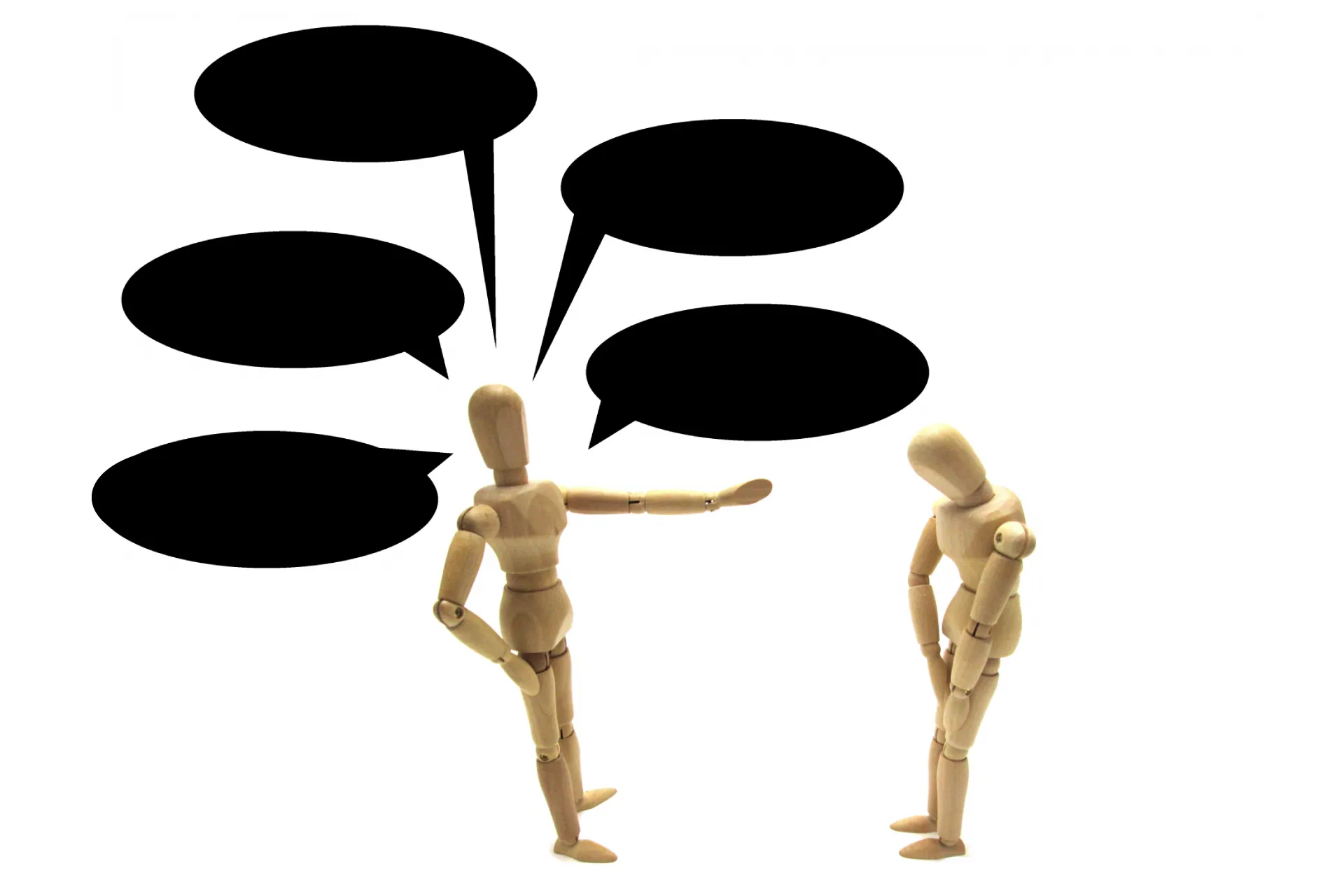
セカンドハラスメントとは、ハラスメント被害者が相談・申告した際にさらに精神的苦痛を受ける二次被害のことです。例えば、勇気を出して相談したにもかかわらず、内容を否定されたり周囲に噂されたりすることが該当します。セカンドハラスメントを未然に防ぐためには、組織全体での意識改革が欠かせません。
当記事では、セカンドハラスメントの定義や発生原因、具体例、防止策、発生時の対処法について詳しく解説します。ハラスメント問題に直面している方や、職場環境の改善を目指す経営者・管理職の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
Toggleセカンドハラスメントとは

最近では、セクハラやパワハラをはじめとするさまざまなハラスメントが社会問題として注目されています。企業のハラスメントに対する問題意識は年々高まりつつあるものの、セカンドハラスメントへの理解が十分に深まっているとは言えません。セカンドハラスメント対策が適切に講じられておらず、企業内部でセカンドハラスメントが実際に発生してしまうケースもあります。
まずは、セカンドハラスメントとは何かという点について詳しく解説します。
セカンドハラスメントの定義
セカンドハラスメントとは、ハラスメントの被害者が二次被害を受けることです。ハラスメントの被害者が勇気を出して相談・告発したにもかかわらず、相談窓口の担当者や上司・同僚、加害者本人などからさらなる精神的苦痛を受けることを指します。例えば、相談内容を否定されたり、嫌がらせや誹謗中傷を受けたりといったケースもセカンドハラスメントに該当します。
セカンドハラスメントの難しいポイントは、加害者が被害者に対してセカンドハラスメントを行っている自覚があるとは限らないことです。むしろ親切心から声かけを行い、無自覚の内に加害者になっているケースも少なくありません。セカンドハラスメントは傷ついている被害者をさらに追い詰めることになるため、企業は正しい知識を持ち、適切な対策を講じることが重要です。
法律改正に伴うパワハラ防止策の強化
2020年6月1日に、労働施策総合推進法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が改正されました。
※出典:e-Gov 法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
法律改正後の労働施策総合推進法はパワハラ防止法とも呼ばれ、ハラスメント防止策が強化された内容となっています。
法律改正によって職場におけるパワハラの定義が明確化され、大企業だけではなく中小企業に対しても具体的な措置を講じることが義務づけられました。そのため、パワハラに伴うセカンドハラスメントについても、企業は定義や対処法に関する理解を深めることが必要です。
セカンドハラスメントが発生する原因

厚生労働省より委託を受けたPwCコンサルティング合同会社が2024年に発表した「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」では、企業側がハラスメント対応を適切に行えていない現状が浮き彫りになっています。
パワハラ被害やセクハラ被害を相談した社員に不利益な取り扱いをした職場は、パワハラの場合6.1%、セクハラの場合10%という結果となりました。社員への不利益な取り扱いの例としては、解雇や降格、減給、不利益な配置転換などが挙げられます。また、パワハラやセクハラの相談があったにもかかわらず対処しなかった職場は、パワハラの場合53.2%、セクハラの場合42.5%にも上りました。
※出典:PwCコンサルティング合同会社「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)」
職場でセカンドハラスメントが発生する原因としては、以下で紹介する3つが考えられます。
セカンドハラスメントの知識が不足している
セカンドハラスメントへの知識不足・認識不足は、無自覚なセカンドハラスメントにつながる可能性が高いです。パワハラやセクハラなどに比べて、セカンドハラスメントの認知度はまだ高くありません。そのため、どのような行為や発言がセカンドハラスメントにあたるのかを知らず、無意識のうちに加害者になってしまうケースが発生します。
被害者に対する配慮が不足している
加害者の想像力の欠如がセカンドハラスメントにつながる場合もあります。例えば、パワハラやセクハラの被害者に対する「気にするほどのことではない」といった言葉も、被害者に二次的な精神的苦痛を与えている可能性があります。セカンドハラスメントを発生させないためには、被害者の気持ちや精神状態を汲み取り、相手に寄り添うような言葉を選ぶことが大切です。
社内のルールが整備されていない
ハラスメントに関する社内のルールが整備されていないことや、相談窓口が機能していない状況もセカンドハラスメントが発生する原因になり得ます。ルールが整備されていない場合、相談内容への適切な対応ができないのはもちろん、相談者のプライバシーが漏えいするといった二次被害も発生しかねません。
セカンドハラスメントの事例(具体例)

セカンドハラスメントにはいくつかの種類があります。以下ではセカンドハラスメントの種類を事例・具体例を交えながら紹介するので、社内で発生させないためにも一度確認しておきましょう。
ハラスメントの事実を否定される
ハラスメントの事実を否定されたり、信じてもらえなかったりすることは、セカンドハラスメントに該当する可能性が高いと言えます。特に人望がある社員や優秀な社員が加害者となっている場合、「○○さんがそのようなことをするはずがない」という先入観が生じやすい傾向です。結果として、相談者への「あなたの考えすぎだ」「○○さんに悪気はない」といった配慮が足りない声かけにつながります。
しかし、ハラスメント行為は基本的に、人目につかないような場所で発生します。特に相談内容が具体的な場合は、頭から否定せずにしっかりと傾聴し、調査を行うことが必要です。
相談者側が逆に責められる
ハラスメントの被害者が、相談をした相手から責められるのは、セカンドハラスメントの代表的な事例の1つです。例えば、「あなたが露出度の高い服を着ているからだ」「あなたが食事の誘いに応じたのが悪い」のように、相談者側に非があるような言葉をかけられるケースがあります。相談者が責められる原因として考えられるのは、相談を受けた側の想像力の欠如や事なかれ主義などです。
相談者側が責められるような環境では、「泣き寝入りをしたほうがまだいい」と考える相談者も少なくありません。結果としてハラスメントが横行し、ハラスメントの被害者たちから組織に対する不信感が募る可能性もあります。
相談内容が周囲・加害者に伝わる
ハラスメント被害はセンシティブな問題であり、被害者のプライバシーへの配慮が不可欠です。しかし、相談内容が許可なく社内に広められたり、噂として流れたりするケースもあります。
ハラスメントの相談内容が社内に漏れる大きな問題の1つが、被害を第三者に相談した事実が加害者本人に伝わることです。相談内容が加害者側に伝わると、被害者ができるだけ円満に解決したいと願っていても関係がこじれやすくなります。また、ハラスメント被害者が加害者からの逆恨みを恐れているケースは少なくありません。加害者の処分の際にも、被害者の情報は出さないよう注意することが必要です。
ハラスメント被害が黙認・隠蔽される
企業がハラスメントの存在を知っていながら黙認するケースもあります。例えば、相談窓口に相談がきていたにもかかわらず、何も対処せずにハラスメント被害が拡大すれば、それは企業がハラスメントを黙認していたと言えるでしょう。
また、相談を受けた人によってハラスメント被害が隠蔽されるケースもゼロではありません。ハラスメント被害の隠蔽は、相談を受けた人がハラスメント加害者と親しい場合などに起こりやすい事例です。
ハラスメント被害の黙認・隠蔽は、企業がその事実を確かに知っていることが前提となります。万が一企業に被害を黙認・隠蔽された際に責任を問うためには、被害者側も「相談した」という事実をしっかりと残すことが重要になります。
被害者が会社に居づらくなる
ハラスメントの被害を訴えたことで周囲の社員の態度が変わり、被害者が会社に居づらくなるのもセカンドハラスメントの一種です。周囲の社員から、「○○さんは些細なことでも告げ口する」「○○さんには気を使わなければならない」などのように噂されるケースもあります。
特に相談内容が周囲・加害者に伝わった場合、被害者が会社に居づらくなる可能性は高いでしょう。企業は被害者のプライバシーを保護するのと同時に、被害者が今後も働き続けられるよう十分に配慮する必要があります。
セカンドハラスメントを未然に防ぐには?

世間でのセカンドハラスメントへの関心は高まりつつあるものの、実際にはセカンドハラスメントを受けて心にさらなる傷を負う被害者が後を絶ちません。被害者を守り、新たな被害者を生まない環境を作るためには、セカンドハラスメントを未然に防ぐための具体的な対策を講じることが重要です。
企業が行うべきセカンドハラスメントの予防策を4つ紹介するので、参考にしてください。
ハラスメントの研修やセミナーを実施する
セカンドハラスメントが発生する原因として挙げられるのは、セカンドハラスメントそのものへの理解不足です。そのため、ハラスメントの研修やセミナーを実施し、二次被害の防止やセカンドハラスメントへの理解を全社的に深めることが有効な予防策となります。
研修やセミナーを通してハラスメントの定義や模範行動などを学べば、セカンドハラスメントへの理解も自然に深まるでしょう。加えて、各自の無意識の思い込みや偏見を矯正することも期待できます。
また、被害の相談に適切な対処をするためには、相談窓口の担当者に教育を行うことも重要です。
【通信講座】『「判断するのは相手です」職場のハラスメント対策100』について詳しくはこちら
ハラスメントに対する社内のルールを策定・周知する
セカンドハラスメントの発生を未然に防ぐためには、社内でルールを策定・周知する必要があります。ハラスメントへの対応方法を個人に委ねると、対応にばらつきが生まれ、被害の黙認や隠蔽を生む原因にもなりかねません。
ハラスメントの改善・対策が必要であること、ハラスメントがコンプライアンス違反であることなどを明文化し、社内に周知しましょう。ルール化によって、セカンドハラスメントの要因となるハラスメント自体への理解を深め、社員が適切な行動を取れるようになることも期待できます。
ハラスメントの相談窓口を設置する
ハラスメントの被害を直属の上司やチーム内の先輩社員などに相談すると、内容が加害者本人に伝わってセカンドハラスメントにつながる可能性があります。対策としては、ハラスメントの相談窓口の設置が有効です。社内に相談窓口があるという事実だけでも、ハラスメントへの抑止力になるでしょう。
ただし、セカンドハラスメントは社内の窓口に相談しても「理解されなかった」「裏切られた」と感じるケースもあります。不安な場合は以下のような社外の相談窓口を利用するのも1つの手です。
| ・みんなの人権110番 ・法テラス ・総合労働相談コーナー ・都道府県労働局雇用環境・均等部(室) |
NOと言いやすい環境を整える
自己主張が控えめな人や気弱な人、人に気を使いすぎる人などは、ハラスメントの標的にされやすい傾向があります。誰もが迷惑行為に対してNOと言える環境を整えることは、セカンドハラスメントの予防策として効果的です。
社員がNOと言いやすい環境づくりのためには、経営者やチーム内での信頼関係の構築が欠かせません。環境づくりの土台として、経営者やマネージャーなど、リーダー的立場の人たちの育成を行うことが大切です。
セカンドハラスメントが発生した場合の対処法

セカンドハラスメントが発生した場合、対応を被害者自身に委ねるのは企業の対応として適当とは言えません。企業はセカンドハラスメントに適切に対処し、被害者の心理的負担に配慮するとともに、被害の拡大を防ぐことが重要です。
セカンドハラスメントが発生した際にできることとしては、以下で紹介する内容が挙げられます。
セカンドハラスメントの事実を記録に残す
セカンドハラスメントの被害者本人の対処として大切なのが、被害に遭った事実を記録に残すことです。パワハラやセクハラの場合と同様に、以下のような内容を記録しておくとよいでしょう。
| ・日時 ・場所 ・被害の内容 ・同席していた人 |
また、相談内容の客観的な証拠がない場合はうやむやにされる可能性もゼロではないため、可能な限り証拠を集めておくことをおすすめします。例えば、会話の録音やメールのやり取りなど、被害の事実が客観的に分かる証拠であればなお有効です。証拠集めという目的があれば、ハラスメントを受ける苦痛がある程度軽減されるというメリットもあります。
ハラスメント被害者の話を傾聴する
セカンドハラスメントの被害に遭った社員は、社内に対して疑心暗鬼になる傾向があります。そのため、相談を受けた人は相手の言葉を否定したり、安易にアドバイスしたりせず、まずは傾聴する姿勢を見せることが重要です。被害者の「理解されなかった」「裏切られた」という心情に寄り添い、苦しみや悩みを傾聴することで、被害者との信頼関係を築きやすくなるでしょう。
ハラスメントかどうかよく分からない相談でも、真摯に向き合うことが状況把握につながります。状況を正確に把握するためには、相談を受ける側の個人的な価値観を排し、何が起こったかという事実に重点を置いてヒアリングを行うのがコツです。
プライバシーに配慮する
セカンドハラスメントの代表的な事例の1つとして、相談を受けた人が相談者の許可なく周囲に話すなどして広めてしまうことが挙げられます。そもそもセカンドハラスメントの被害者は二重のハラスメントで精神的負担を抱えているため、通常よりもプライバシーへの配慮が必要です。
相談を受けた人は、社内の人はもちろん、自分の家族や親しい人であっても守秘義務を守らなければなりません。イニシャルや例え話でぼかしたとしても分かる人には伝わる可能性があるため、相談者のプライバシーの保護を第一に考え、厳しく遵守する必要があります。
弁護士などの第三者に相談する
セカンドハラスメントが発生したということは、社内のルールや対応に不備がある可能性が高いと言えます。つまり、セカンドハラスメントが発生した時点で、その企業だけで適切に対応し解決に導くのは難しいと言えるでしょう。
セカンドハラスメントが発生した際には、弁護士などの第三者に頼るのも有効な対処策の1つです。社内でハラスメントへの対応を行うためには社員教育が必要になりますが、弁護士に相談すればすでに知識を身に付けている専門家がしっかりと対応してくれます。
ハラスメントの相談を受けたときの流れは?処分はある?

社内の相談窓口担当者は、ハラスメントの相談を受けた際には以下の流れを参考に対応を行うとよいでしょう。
| 1 | 窓口への相談に応じる |
| 2 | 事実確認を行う |
| 3 | 被害者・加害者への措置を検討する |
| 4 | 被害者・加害者のフォローを行う |
| 5 | 再発防止策を検討する |
ハラスメントの相談を受けた際に、相談者の心情に寄り添うことは大切ですが、相談内容をすべて真実と決めつけてはなりません。相談者へのヒアリングや提示された証拠のチェック、関係者へのヒアリングなどを通して事実確認を行うことが大切です。加害者と被害者の供述が食い違っている場合は事実確認が特に重要になります。
調査を行った後、ハラスメントの有無を総合的に判断し、被害者・加害者への措置を検討しましょう。ハラスメントがあったと判断された場合は、加害者に対して謝罪・人事異動・戒告・減給・降格といった処分を検討します。処分内容を決める際には、被害の大きさや加害者の態度、再発の可能性の高さ、就業規則や過去のハラスメントの裁判例なども考慮するとよいでしょう。
被害者・加害者への措置が決まったら、双方に通知するとともに、被害者が安心して働き続けられるようフォローすることが大切です。また、問題が解決した後には、ハラスメントの再発防止策を検討することが重要になります。ハラスメントを加害者個人の問題にするのではなく、新たな加害者が発生し得る職場環境ではないかを確認し、効果的な再発防止策を企業全体に向けて実施しましょう。
まとめ
セカンドハラスメントは、被害者が勇気を出して相談したにもかかわらず、さらに精神的な苦痛を受けることです。相談内容が周囲に漏れる、被害者が責められるなどの事例は、企業の対応力不足を浮き彫りにしています。セカンドハラスメントを放置すれば、被害者の離職や職場の士気低下を招く恐れがあります。
職場でセカンドハラスメントを防ぐには、明確なルールの策定や相談窓口の設置が欠かせません。また、社員がハラスメント問題について正しい知識を持ち、被害者に寄り添った対応を取れるよう教育を徹底しましょう。一人ひとりが行動を変えることで、職場をより安心して働ける環境に変えていきましょう。
関連記事
Related Articles
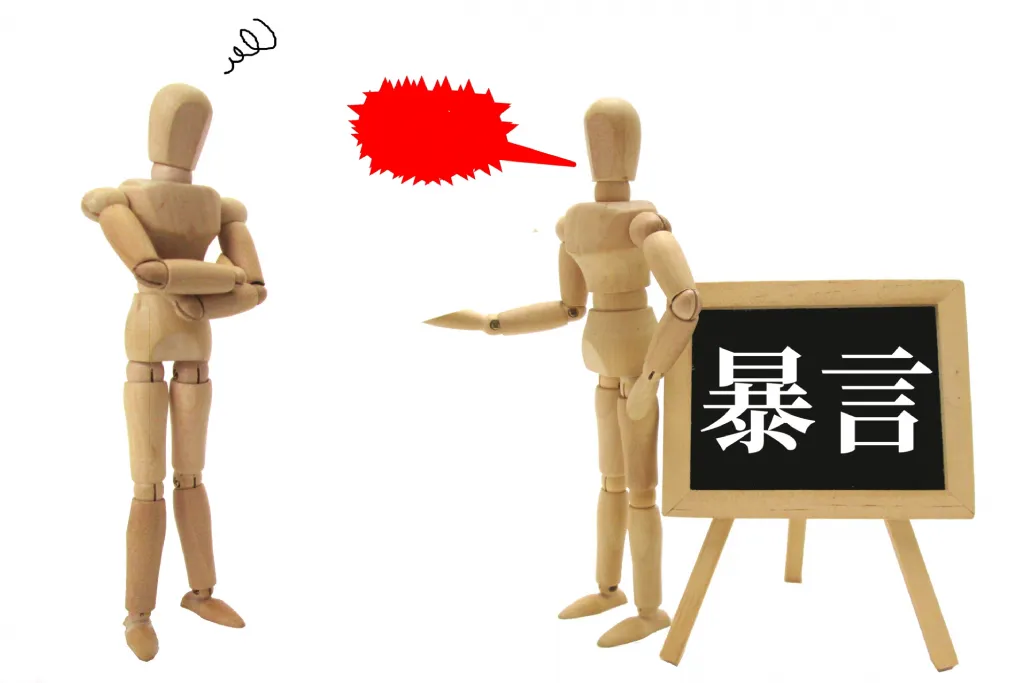
あなたの指導は大丈夫?パワハラにならないための5つのチェックポイントと解決策
部下への指導が「パワハラ」にならないためには、目的や態度、伝え方に注意が必要です。パワハラと指導の違いや見極め方、具...
ハラスメント
無意識のスメハラが職場を壊す?適切な伝え方のポイント・対策を解説
当記事では、スメハラ(スメルハラスメント)とは何かという点を解説した上で、スメハラの具体例や日頃からできる対策、相手...
ハラスメント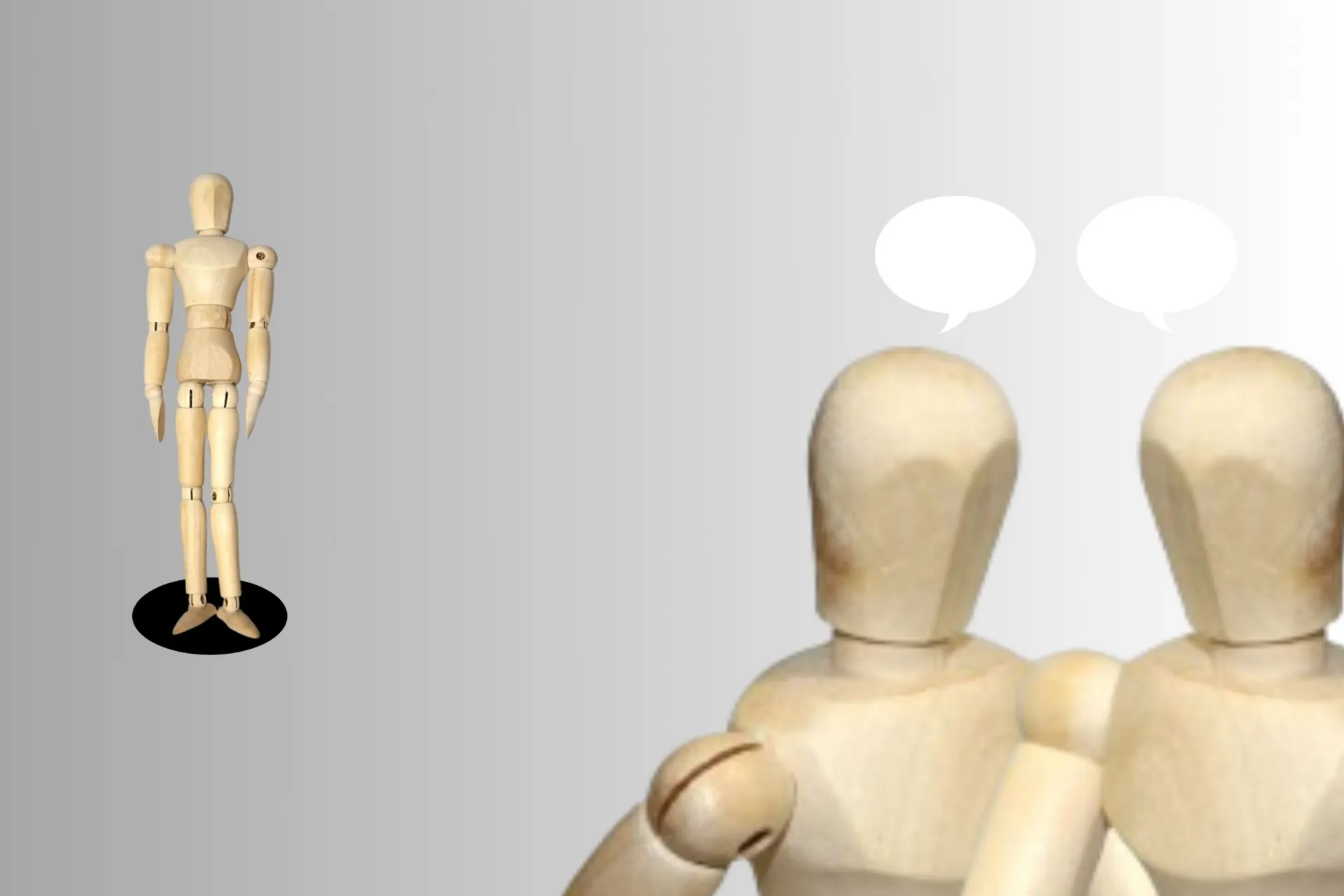
優しさがハラスメントに?ホワイトハラスメントの意味と具体例を解説
パワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)など、近年はさまざまなハラスメントに注目が集まる中...
ハラスメント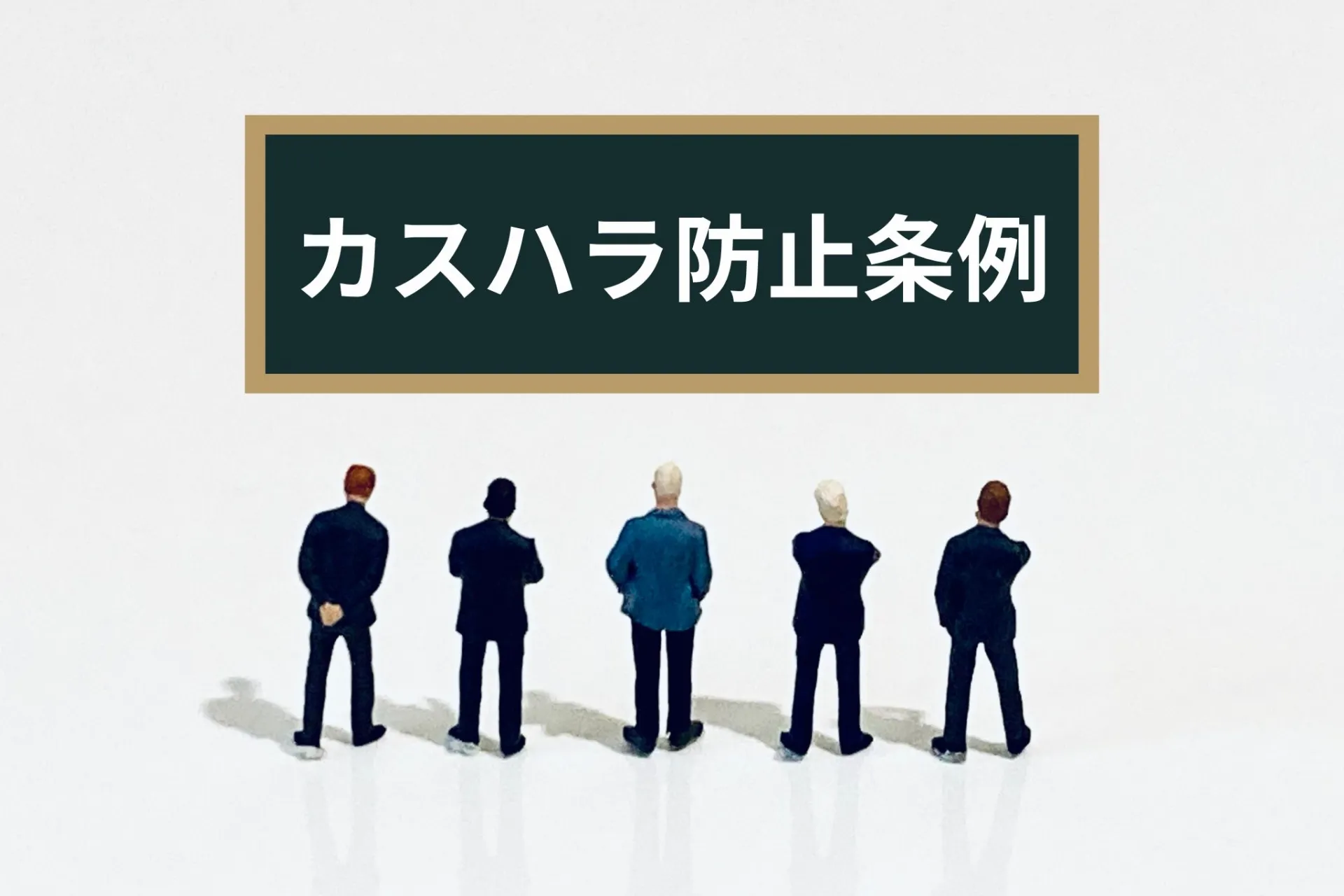
【2025年最新】カスハラ防止条例とは?ポイントを分かりやすく解説
カスハラを防ぐために、国は2025年3月に労働施策総合推進法改正を閣議決定し、全企業に向けてカスハラ対策を義務付けま...
ハラスメント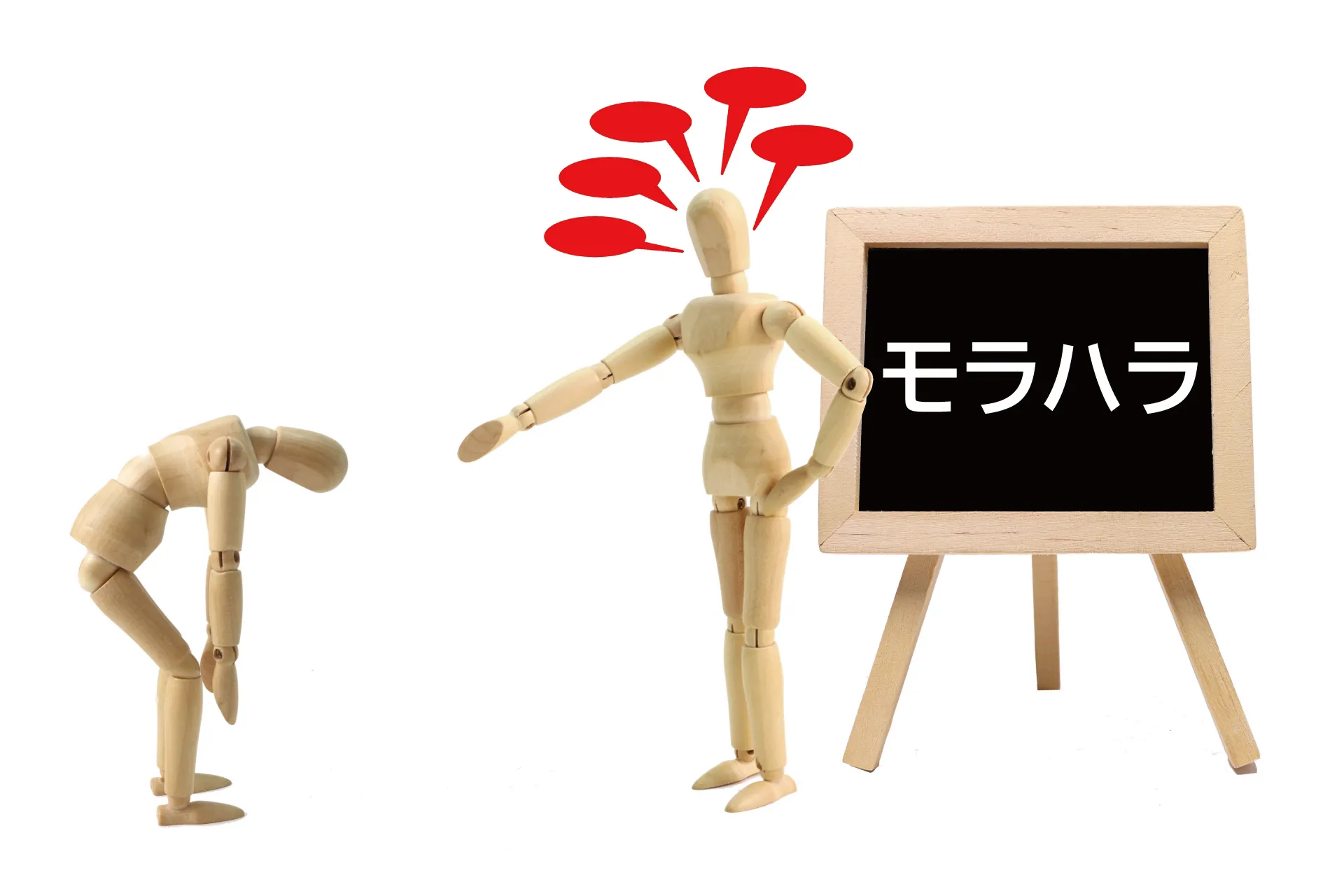
こんな人には要注意!職場のモラハラ上司の特徴と有効な6つの対処法
モラルハラスメント(モラハラ)は道徳や倫理に反する嫌がらせ行為のことで、言葉や態度による精神的な攻撃が該当します。上...
ハラスメント