- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- エンゲージメント
- 人間関係がめんどくさい心理・理由は?疲れたときの対処法も7つ解説
人間関係がめんどくさい心理・理由は?疲れたときの対処法も7つ解説

人間関係がめんどくさいと感じる理由は、心理的な負担やストレスが大きく関係しています。相手に合わせすぎたり、過去のトラウマを抱えていたりすると、人と接することが苦痛に感じられる場合もあります。また、周囲の評価を気にしすぎたり、自分の意見を押し殺してしまうことで、関係が負担になることも少なくありません。
当記事では、人間関係がめんどくさいと感じる心理や理由を深掘りし、疲れたときに実践できる具体的な対処法を7つ紹介します。人間関係に疲れを感じている方や、ストレスを軽減したい方はぜひ参考にしてください。
人間関係をめんどくさいと感じるのはどのようなとき?

仕事や日常生活において、人間関係がストレスになるケースは少なくありません。他人に合わせたり、気を使ったりするのに疲れると、人間関係をめんどくさいと感じてしまうでしょう。
まずは、人間関係をめんどくさいと感じやすい典型的な状況について解説します。
相手の機嫌を取らなければならないとき
職場で上司や同僚の顔色をうかがいながら会話をするなど、相手の機嫌を取らなければならない状況が続くと、人間関係をめんどくさいと感じることが増えます。
特に、上司や同僚に、不機嫌を表に出して八つ当たりをする人がいる場合は厄介です。嫌なことがあるたびにネガティブな感情を表に出す人がいると、気分を害さないように言葉を選び、慎重に行動する必要が出てきます。
仕事を円滑に進めるために、自分の感情や時間を犠牲にして相手の機嫌をうかがわざるを得ないケースもあるでしょう。自分の感情を抑え、不満を押し殺すことが習慣化することで、精神的な疲労から人間関係をめんどくさいと感じやすくなります。
嫉妬やマウントを受けるとき
嫉妬やマウントの対象になると、精神的な疲れから人間関係をめんどくさく感じるでしょう。嫉妬やマウントをする人は、自身の劣等感や周囲から認められたいという欲求を満たすために、ネガティブな感情をぶつけてきます。
たとえば、努力の結果を認めてくれなかったり、陰口を言われたり、嫌な態度を取られたりすることがあります。自分に身に覚えのないことで相手との関係性が悪化するため、悩んでしまう人も少なくありません。「また嫉妬やマウントをされるのでは」と気を使うようになり、人間関係のストレスが増してしまいます。
愚痴や噂話に巻き込まれるとき
他人の愚痴や噂話を聞かされることがストレスになり、人間関係をめんどくさいと感じる人も多くいます。
愚痴やネガティブな噂話は、たとえ共感できる部分があったとしても聞き続けると気分が沈みます。特に、不満を延々とこぼされたり、第三者を貶めたりするような話題には、不快感を覚える人が多いでしょう。
自分が噂話の標的ではなくても、ネガティブな噂話をする雰囲気に嫌気がさし、人間関係が億劫に感じられる場合もあります。
集団行動やルールに縛られるとき
集団行動やルールに縛られるときも、人間関係をめんどくさいと感じる状況の1つです。特に職場では、効率よりも周囲や暗黙のルールに合わせた行動を求められることが多くあります。逸脱すると「協調性がない」と評価され、周囲になじめないと感じたり、精神的に負担を抱えたりする人も少なくありません。
不要な集団行動や暗黙のルールが負担となっている場合、職場の働きにくさを改善することが必要です。
たとえば、三井不動産株式会社では、社員が安心して働ける環境をつくるために、職場全体でメンタルヘルス対策を推進しています。メンタルの不調を早期発見して対処することで、職場復帰がスムーズになり、再休業率をほぼ0に抑えることに成功しました。定期的な研修や面談を通じて課題を洗い出し、スピーディーに改善する仕組みを構築しています。
自分を否定されたと感じるとき
自分の意見や価値を否定されたように感じる場面は、人間関係をめんどくさいと感じる大きな要因となります。
たとえば、自分の努力を認めてくれずにネガティブな反応ばかりが返ってくる状況が続くと、自己肯定感が低下してストレスが溜まります。精神的な疲れから人と関わることが面倒になり、距離を置きたいと感じるでしょう。
人間関係をめんどくさいと感じる心理・理由

人間関係をめんどくさいと感じるのは、相手に合わせすぎたり、トラウマを抱えていたりするなど、さまざまな心理的背景や理由があります。
ここでは、人間関係をめんどくさいと感じる心理や理由について、掘り下げて解説します。
我慢して相手に合わせる必要があるため
人間関係をめんどくさいと感じるのは、価値観や意見の違う相手に合わせようとして、ストレスを感じるためです。
人との関係において、完全に価値観や意見が一致することはまれです。良好な関係を築くために、自分の感情や意見を抑えて相手に合わせることもあります。しかし、相手の気持ちを考えすぎて自分の好みや意見をのみ込んだり、嫌われるのを恐れて無理に明るく振る舞ったりするのは、精神的に疲れます。
妥協や無理をして相手に合わせ続けると、自分の本音を言えない関係になってしまうでしょう。次第に相手との関係がストレスになり、人間関係をめんどくさいと感じるようになります。
周囲の評価や視線が気になるため
周囲の評価や視線を気にすることで、心理的な負担が増し、人間関係をめんどくさいと感じることもあります。他人からの評価が気になるのは、自分に対する自信のなさが影響しています。自分の選択や言動に不安を感じ、周囲からどう見られるのかを過剰に気にしてしまうことが原因です。
その結果、他人の視線を気にするあまり自分の意志に沿った行動ができなくなり、人間関係に息苦しさを感じるようになります。
他人に嫌われたくない気持ちがあるため
他人に嫌われたくないという気持ちが強いと、人間関係を負担に感じる場面が増えます。相手の期待に応えようと無理をしたり、本音を隠したりすることが多くなるためです。その結果、自分の本当の意見や感情を伝えられずにストレスが溜まり、精神的に疲れるでしょう。
嫌われたくない一心で周囲に気を使いすぎると、自分らしく振る舞えなくなり、人間関係をめんどくさいと感じてしまいます。
自己評価が低いため
自己評価の低さも、人間関係をめんどくさいと感じる理由の1つです。自己評価が低い人は自分に対する信頼がなく、他人とのコミュニケーションに自信を持てない傾向にあります。常に不安を抱えながら接するため、他人の行動や言動に敏感に反応し、ストレスを感じやすくなります。
他人からの評価を過度に求めてしまうので、結果的に人間関係をめんどくさいと感じることが増えるでしょう。
過去のトラウマがあるため
過去に受けたトラウマが原因で、人間関係をめんどくさいと感じることもあります。たとえば、友達に裏切られたり、感情的になって関係を壊したりした経験がトラウマとなり、他人との関わりを避けてしまうケースです。
「同じ失敗を繰り返したくない」と考えるあまり、過度に気を使って疲れてしまう人もいるでしょう。他人との関わりに不安や恐怖を感じたり、考えすぎてしまったりすると、人間関係の構築に慎重になります。心理的な負担から、人間関係をめんどくさいと感じるでしょう。
人間関係がめんどくさいと感じやすい人の共通点

人間関係がめんどくさいと感じるのは、性格や行動パターンが大きく影響しています。
ここでは、人間関係を負担に感じやすい人に共通する特徴を、具体的に解説します。自分に当てはまるものがあるかを確認しながら、読み進めてください。
内向的で1人の時間を好む人
内向的な性格の人は、他人と関わるよりも1人で過ごす時間に安らぎを感じる傾向があります。そのため、外向的な人と比べて、人間関係を負担に感じやすいでしょう。
内向的な人は、少人数でじっくり話し合ったり、1つのことを深く考えたりすることを好みます。一方で、多くの人と社交的に接する場面や、広く浅いコミュニケーションが求められるシーンは苦手なタイプが多く、気を使って消耗してしまいます。
そのため、内向的な人が無理に積極的なコミュニケーションを取ろうとすると、精神的な負担や疲労感が増し、人間関係をめんどくさいと感じる原因になるでしょう。
完璧主義で人間関係にも理想を求める人
完璧主義の人は、自分だけでなく他人にも高い基準を求める傾向があります。人付き合いにおいて「こうあるべき」という理想を追い求めると、無意識のうちに自分や相手を疲れさせてしまうでしょう。
たとえば、職場や友達の小さなミスが気になって不満を感じたり、相手に弱みを見せられないと考えて必要以上に気を張ったりする人もいます。
完璧主義の傾向が強いと、理想通りにならない人間関係に対して不安や苛立ちを感じやすくなり、人間関係をめんどくさいと感じる原因となるでしょう。
感受性が高く人の気持ちに敏感な人
感受性が高い人は、人間関係で気を使いすぎるため、疲れやすい傾向があります。他人の感情に敏感で、相手の表情の変化や声のトーンを察知しようとすることで、日常的なコミュニケーションでも消耗してしまうのが理由です。
特に、HSP(Highly Sensitive Person)と呼ばれる人は、生まれながらに非常に感受性が高く、繊細な性質を持っています。
相手の気持ちを深く考えて行動できる反面、不安や恐怖といったネガティブな感情にも強く反応してしまうので、人間関係に悩みや苦痛を抱えやすいでしょう。
相手に合わせすぎてしまう人
相手に合わせすぎてしまう性格の人は、自分の感情を犠牲にして相手に気を使うため、人間関係に疲れやすい特徴があります。相手を嫌な気持ちにさせないために本音を隠したり、周りから浮かないように同調したりするケースです。適度に相手に合わせることは大切ではありますが、自分を犠牲にし続けると自分らしさを見失ってしまうため注意が必要です。
社会人になると、精神的な疲れを溜めこんだことでメンタルに問題を抱え、休業する人も少なくありません。理由は人それぞれありますが、復帰支援が整った職場であればスムーズに復帰しやすいでしょう。
たとえば、「アビームコンサルティング株式会社」では、職場復帰プログラムや再発予防プログラムを通じて、社員の状態に合わせたフォローを行っています。また、社員が健康的に活躍できるよう、セルフケアを促進しており、職場と個人の両面から人間関係の負担軽減に取り組んでいます。
人間関係がめんどくさい・疲れたときの対処法7選

人間関係に疲れてしまうことは、誰にでもあります。そこでここからは、人間関係をめんどくさいと感じたり疲れたりしたときに実践したい対処法を紹介します。
人間関係にストレスを感じている人は、心の負担を軽減するため、ぜひ取り組んでみましょう。
関わりたくない人との距離を取る
人間関係をめんどくさいと感じるときは、関わりたくない人と距離を取ることが効果的です。無理に人間関係を円滑にしようと努力すると、かえってストレスを感じる原因になります。特に職場では、上司や同僚と、友達のように親密になる必要はありません。仕事に支障が出ない程度のコミュニケーションが取れれば十分です。
関わりたくない人とは必要以上に距離を縮めず、適度な距離感を保つことで心理的な負担を軽減できます。全員に好かれる必要はないと割り切ることで、余計なストレスを減らし、自分の心の余裕を保てるでしょう。
自分のペースを最優先にする
他人に振り回されず、自分のペースで行動することを心がけましょう。常に他人を優先し、自分の希望や都合を後回しにしていると、次第に自分らしさを見失ってしまいます。
そのため、自分自身を第一に考え、自分のために時間を使いましょう。人の目線や評価を気にせずに興味のあることに没頭したり、ありのままでいられる場所で過ごしたりする時間を作ることがおすすめです。
特に、仕事や友達との関係で周囲の意見に流されやすい人は、「自分がどうしたいか」をしっかり考え、物事を判断するように意識してください。自分のペースを優先することで、自分の心と向き合いやすくなり、他人に振り回されずに良い人間関係を築けるようになります。
複数の居場所・趣味を持つ
複数の居場所や趣味を持つことは、人間関係の負担を軽減し、気分転換につながる効果的な方法です。たとえば、職場以外にも地元の友達や趣味の仲間など、複数のつながりを持っておくと、特定の人間関係に悩んだときに別の居場所が心の支えとなります。
さまざまな価値観や考えを持つ人との交流により、気の合う友達を見つけたり、趣味を共有できる仲間と出会えたりすることも大きな魅力です。
大人になってからの友達は、学生の頃とは違い、適度な距離感で付き合いやすい傾向にあります。複数の居場所や趣味のつながりを持つことで、気分転換しながらストレスを上手に発散できるでしょう。
表面上の関係にとどめ深入りしない
職場では特に、必要以上に深く関わると、仕事の効率が下がったりトラブルが発生したりする危険性があります。そのため、表面上の付き合いで十分と割り切るのも1つの方法です。
たとえば、仲良くなりすぎてミスを指摘しづらくなったり、プライベートにまで干渉を受けたりして、仕事がしづらくなるケースは少なくありません。
挨拶や仕事に関連する基本的なコミュニケーションに集中することで、余計なストレスを避けられます。人間関係にストレスを感じやすい場合は、仕事で必要となる表面上の関係を維持し、必要以上に深入りしないようにしましょう。
タイミングに応じて関係を再評価する
相手との関係に疲れを感じ、めんどくさいと思ったときは、関係性を見直すタイミングと言えます。ライフステージや環境の変化に伴い、人の価値観は変わります。そのため、一度気が合って仲良くなった友達でも、疎遠になるのは珍しいことではありません。
ストレスを感じながら付き合っているなら、時には相手との関係を見直し、整理することも必要です。めんどくさいと感じる相手とは無理に付き合うのは避け、さりげなく距離を置くことも選択肢の1つです。
印象の良い見た目や雰囲気を意識する
初対面の人や職場での人間関係をスムーズに進めるには、印象を良くすることが大切です。外見は、第一印象を左右する重要な要素です。清潔感のある身だしなみや、笑顔で抑揚のある話し方を心がけることで、相手が良い印象を持ち信頼を得やすくなります。
また、見た目や雰囲気に気をつけることで、相手に安心感を与え、コミュニケーションを円滑にする効果も期待できるでしょう。
転職・部署異動を検討する
人間関係の改善が難しく、精神的に追い詰められている場合は、転職や部署異動も1つの選択肢です。無理に現在の環境にとどまると、心身に悪影響が出る可能性もあります。もし、状況が改善しないと感じるなら、思い切って転職や部署異動で環境を変える方法もあります。
まずは、信頼できる上司や同僚に相談し、他の解決策がないときは、転職や部署移動を検討するとよいでしょう。
人間関係がめんどくさい場合でも心がけるべき行動は?

人間関係に負担を感じていても、完全に関係を断つことが難しいケースもあります。相手との関係を保つために、どのように振る舞うべきか迷う人もいるでしょう。
ここでは、人間関係がめんどくさい場合でも、心がけるべき行動を解説します。
素っ気なくしすぎないように心がける
苦手な相手だからといって、あからさまな態度を取るのは避けてください。怒りや不満などの感情的な反応をしたり、仕事以外の雑談を拒否したりすると、社会人としての対応ができない人だと思われ、自分の評価を下げかねないためです。
また、失礼な態度を取って相手を怒らせると関係がさらに悪化する事態にもつながります。業務に影響を与えないように、面倒でも冷静に対応することが大切です。素っ気なくしすぎず、おだやかな表情や態度を意識して、礼儀正しく接するよう心がけましょう。
誰かの悪口や陰口は言わない
人間関係がめんどくさい場合や不満がある場合でも、関わりたくない人に限らず、誰に対しても悪口を言うことは控えましょう。
悪口や陰口は、言うことで一時的なストレス解消にはなるかもしれませんが、聞かされる相手にとって気持ちの良い内容ではありません。悪口を聞かされた相手が「陰で自分の悪口も言っているのではないか」と感じ、不信感を持つことにもつながります。
悪口や陰口を言うのは、職場で嫌われやすい人の特徴でもあります。自分が嫌われたり、周囲との信頼関係に悪影響を及ぼしたりするリスクを高めるため、悪口や陰口を言うことは避けましょう。
相手の意見を無理にすべて受け入れない
自分の意見と異なるときは、相手の意見にすべて同意する必要はありません。価値観は、育った生活環境や積み重ねてきた経験によって人それぞれ異なります。人間関係を円滑にしたいという気持ちから相手の意見に無理に同意すると、自分の意見を押し殺すことになり、人間関係に疲れる原因となります。
相手の意見を受け入れるのが難しい場合は、考え方の違いを受け止め、なぜそう考えるのか理解する姿勢が重要です。その上で、自分の意見を伝え、対話を通じて理解を深めていくことで、お互いを尊重し合えるより良い関係を築きやすくなるでしょう。
まとめ
人間関係をめんどくさいと感じるのは、相手に合わせすぎることや他人の評価を気にしすぎる心理が大きな原因です。自分を押し殺して相手に合わせ続けると、心の負担が増してしまい、「関係を続けるのがしんどい」と感じるようになります。また、自己評価が低い場合や過去のトラウマが影響して、人間関係に対するハードルが高くなることもあるでしょう。
こうした心理的な背景を理解し、自分のペースを大切にしたり適度な距離を取ったりすることで、負担を軽減できます。自分らしく生きるために、無理をしない人間関係の築き方を意識しましょう。
関連記事
Related Articles

職場の人間関係にも役立つ「アドラー心理学」をわかりやすく解説!
オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーが提唱した「アドラー心理学」は、職場の人間関係改善や人材育成に役立つ心理...
エンゲージメント
職場の人間関係は割り切りが鍵!気にしない方法4つと解消法を解説
職場の人間関係に悩む方は少なくありません。上司や同僚との関係がうまくいかないと、日々の業務がストレスとなり、最悪の場...
エンゲージメント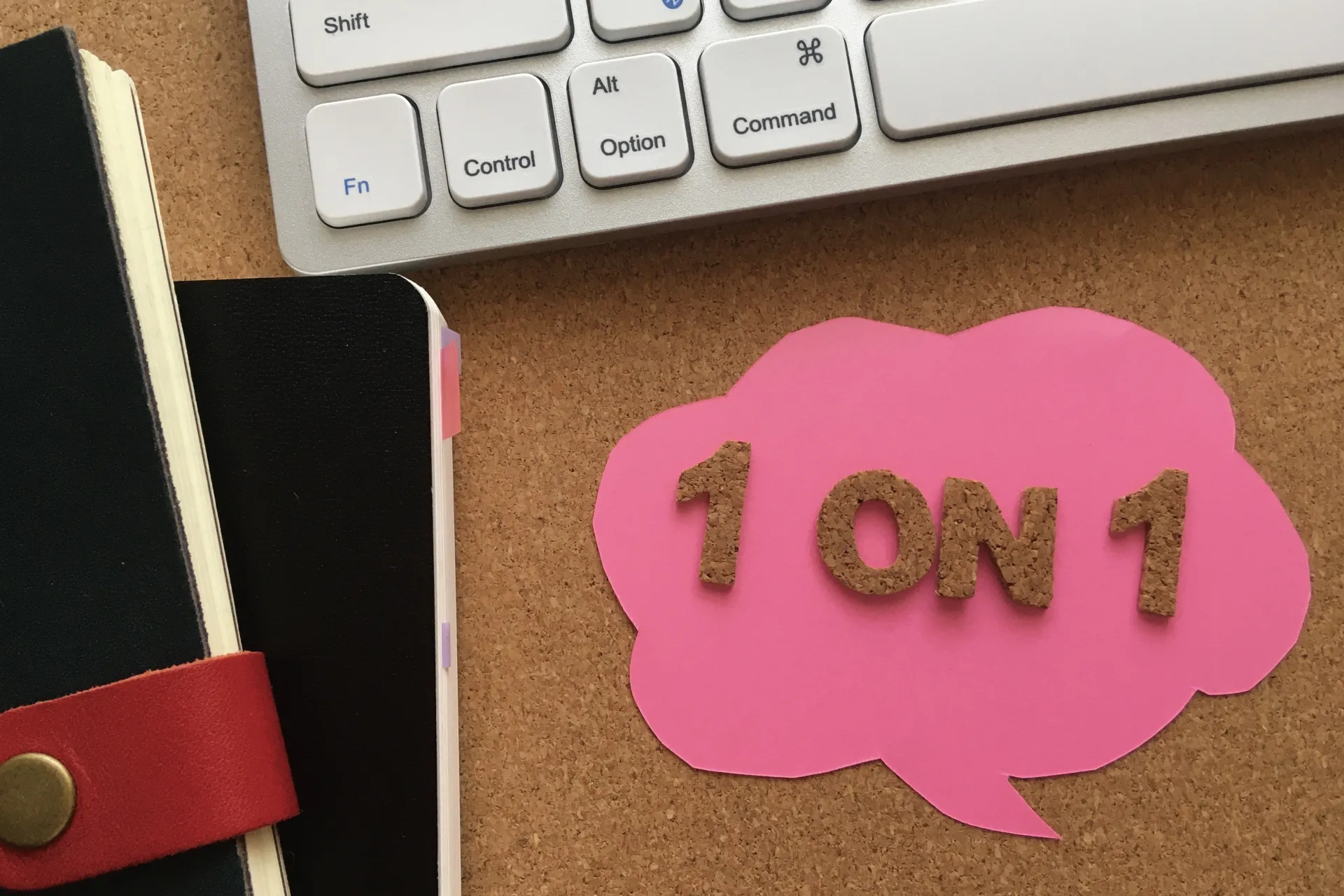
1on1とは?目的や会社組織を強化する効果的なやり方を解説
1on1ミーティングでは、部下に対して期待値をしっかりと明示し、これまでの業務や成果に対する賞賛を行うことが大切です...
エンゲージメント企業研修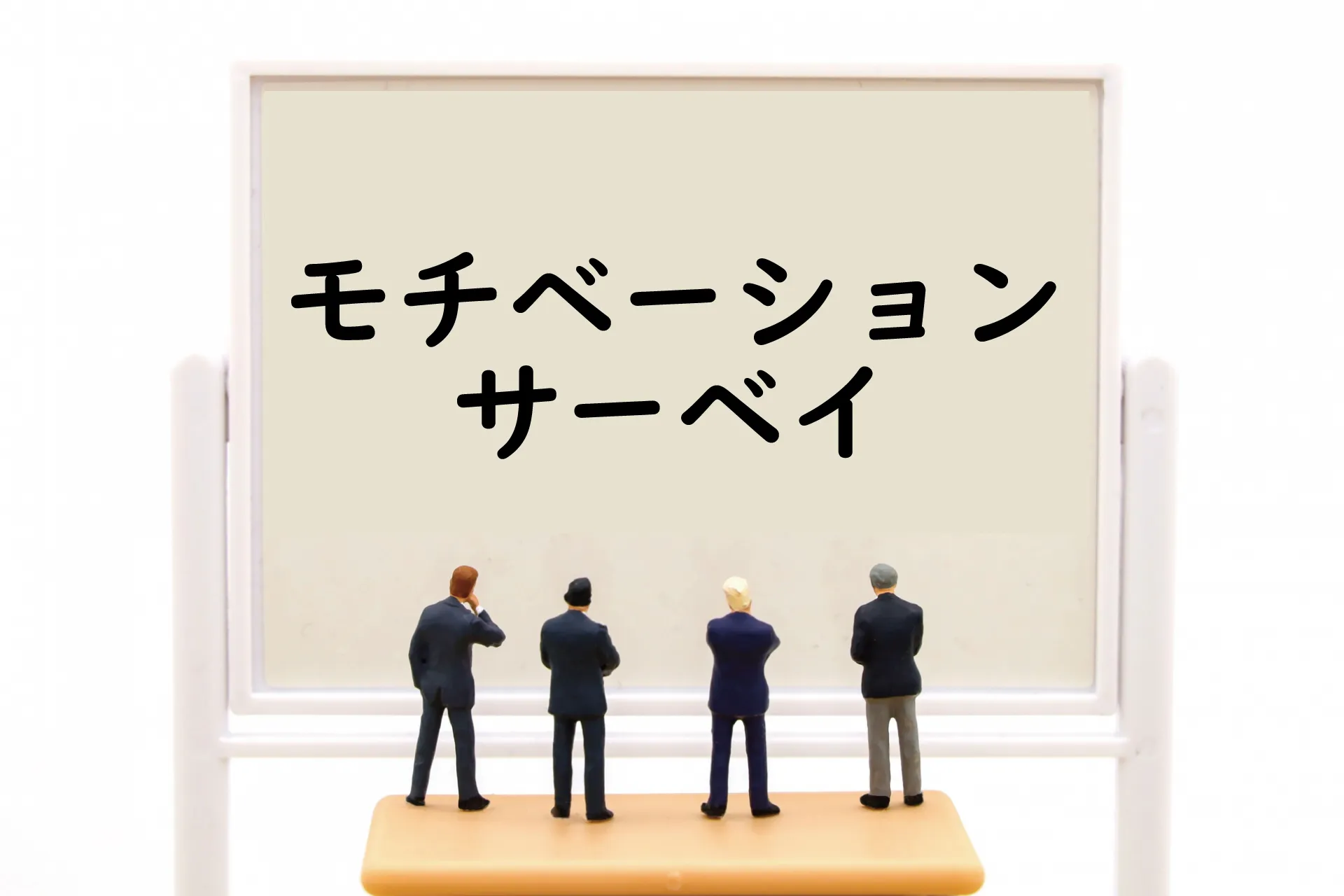
組織課題を炙り出して売り上げを伸ばすモチベーションサーベイとは
企業が自社の抱える潜在的な課題を明らかにし、成長を続けるには、従業員のモチベーションを理解することが不可欠です。しか...
HRトレンドエンゲージメント
心理的安全性の高い職場を作る5つのポイント|ぬるま湯組織との違い
社内のコミュニケーションを活発に行い、アイデアが共有されやすくするためには、組織内の心理的安全性を高めることが大切で...
HRトレンドエンゲージメント
ジョブクラフティングとは?メリット・デメリットや研修の手順を解説
グローバライゼーションやデジタル技術の発達により、社会の価値観は多様化し、社会環境の変化は高速化しています。企業が変...
HRトレンドエンゲージメント
【事例付き】朝礼で失敗しないネタ8選と話の組み立て方の秘訣とは
この記事は2024.3.25に公開した記事を再編集しています2025年6月23日更新 朝礼は部署やチーム内で情報共有...
エンゲージメント
エンゲージメントとは?ビジネスにおける意味や高める施策を徹底解説
この記事は2023.11.14に公開した記事を再編集しています最終更新日:2024.12.18 少子高齢化が進む日本...
エンゲージメント


