- 人事・総務担当者の課題解決コラム
- エンゲージメント
- 職場の人間関係にも役立つ「アドラー心理学」をわかりやすく解説!
職場の人間関係にも役立つ「アドラー心理学」をわかりやすく解説!

オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーが提唱した「アドラー心理学」は、職場の人間関係改善や人材育成に役立つ心理学の1つです。「人は誰もが幸福になれる」という前提に立ち、自己決定性や目的論、全体論、認知論、対人関係論という5つの理論を通じて、個人の成長と社会的連帯感の向上を目指しています。
当記事では、アドラー心理学の内容や理論、思想について、ビジネスシーンでの具体例も交えてわかりやすく解説します。理論だけでなく実践に役立つ情報も網羅していますので、職場や日常生活においてより豊かな人間関係を築くための指針となる知識を得られるでしょう。
目次
Toggleアドラー心理学とは?わかりやすく解説

アドラー心理学とは、オーストリアのウィーンで精神科医として活躍したアルフレッド・アドラーが提唱した心理学です。アドラー心理学は「人は誰もが幸福になれる」という前提に立ち、「人生には目的があり、幸せになるには勇気が必要」と説いています。つまり、個々人が自らの目標に向かって行動する過程で、自己肯定感や共同体感覚を育むことが、精神的な充実と幸福への近道であると考えられています。
この考え方は、単に個人の内面だけでなく、社会や職場といったビジネス環境にも大きな影響を与えます。たとえば、上司や同僚との円滑なコミュニケーション、チームとしての目標達成に向けた協力体制の構築など、組織内の人間関係や勤務環境の改善に応用することが可能です。
また、アドラー心理学は、人間を精神と肉体、意識と無意識といった相反する要素で分割するのではなく、統合された「単一の存在」として捉える点もポイントです。このことから、アドラー心理学は正式には「個人心理学」とも呼ばれます。
アドラーとフロイトの違い
アドラーとジークムント・フロイトはともにオーストリアで同時代に活躍した精神科医ですが、その心理学のアプローチは大きく異なります。フロイトは、人間の心の大部分は無意識に支配され、無意識の欲求や過去の経験が行動の根源であると説きました。意識を「氷山の一角」に例え、見えている部分よりもはるかに大きな無意識の領域が存在すると主張しています。
一方で、アドラーはフロイトと共同研究を行ったものの、次第にその見解から逸脱し、「人は過去に支配されず、未来に向かって目的を持って生きる創造的存在である」という考えに至ります。つまり、「人間の行動は過去にとらわれるのではなく、目的意識や社会的所属、そして貢献意欲によって動かされる」というのがアドラーの主張です。アドラーは「人は社会の中で居場所を見つけ、貢献することで幸福になれる」と考え、個人の自由な選択や未来志向の行動を強調します。
ビジネスの現場では、フロイトの無意識へのアプローチは顧客の潜在的なニーズや反応を読み解くマーケティングリサーチに応用できる一方、アドラーの考え方は組織内でのチームビルディングや部下のモチベーション向上、リーダーシップの強化につながります。両者の理論はそれぞれ異なる角度からビジネスの課題解決に貢献すると言えるでしょう。
アドラーとユングの違い
カール・グスタフ・ユングは、スイスの精神科医として「分析心理学」を創始したことで知られています。ユングは、無意識を「個人的無意識」と「集合的無意識」に分けた点が特徴です。人間の心に共通する深層の要素、すなわち神話や伝説、夢に現れる「元型」の存在を「集合的無意識」として提唱しました。夢分析や連想実験を通じて、個人が意識できない深層心理のパターンや元型が人間の行動に影響を与えると説明しています。
対してアドラーは、人は個々の経験や社会的所属、目的意識に基づいて行動し、自らの目標に向かって生きる創造的な存在であると考えています。人間を意識と無意識で分けず、個人の精神は社会と密接に結び付いているとするため、アドラーとユングはそもそも研究の方向性や思想が違うと言えるでしょう。
なお、ユング心理学における「ペルソナ」の概念は、マーケティングにおけるブランドイメージの形成やターゲットの設定に応用できます。ペルソナとは、人間が社会や他者に対して見せる自己の側面のことです。「企業として社会や他者にどのように評価されたいのか」「顧客はどのように見られたいのか」を追求することで、顧客と強いエンゲージメントを構築できるでしょう。
企業と従業員の間の信頼関係は「従業員エンゲージメント」と呼ばれます。人手不足を解消する一手として従業員エンゲージメントの向上を検討されている場合は、以下の記事を参考にしてください。
アドラー心理学が注目された背景

現代の日本においてアドラー心理学が注目される背景には、「嫌われる勇気」の出版とSNSの台頭が大きく影響しています。2013年に刊行された「嫌われる勇気」は、他者の評価を気にせず自分らしく生きるための方法を示し、対人関係に悩む多くの人々から大きな反響を得て、300万部を超えるベストセラーとなりました。
刊行当時はSNSが広く普及し、「いいね!」や評価を求める風潮にあったタイミングです。常に他者の反応を意識せざるを得ない中で、自己のアイデンティティを確立し、他人の期待に縛られない生き方を模索する動きが広がり、アドラー心理学の教えが多くの支持を受けました。今も自己表現や対人関係のストレスに悩む多くの人々に、ありのままの自分を受け入れるヒントとして、アドラー心理学は大きな影響を与え続けています。
アドラー心理学が提唱する5つの理論

アドラー心理学は、幸福実現に不可欠として「自己決定性」「目的論」「全体論」「認知論」「対人関係論」の5つの理論を提唱しています。ここからは、ビジネスシーンにおける行動例とともに、その有用性を詳しく解説します。
自己決定性
自己決定性とは「自分の行動は自分で決められる」という考え方です。たとえ育った環境や過去の経験にハンデがあったとしても、どのように解釈して行動するかは自分自身で決めることができます。アドラーは「自分の運命の主人公は他ならぬ自分自身だ」と説き、環境や過去の出来事を言い訳にして自分の可能性を自ら犠牲にすることに否定的です。
たとえば、希望の部署に配属されなかった場合、それを新たな成長の機会と捉え、自らのスキルアップや別の役割での活躍を模索することが求められます。自分ではどうにもできないことのせいにして嘆くのではなく、主体性や独自性を持って行動することが、自己成長と組織の発展に寄与するのです。
目的論
目的論とは「人の行動にはすべて未来に向けた目的がある」という考え方です。アドラー心理学では、過去の原因によってではなく、自ら定めた目標に向かって選択した行動を実行した結果、今があると捉えます。つまり、人はどのような目的で行動するのかによって、現状や未来を変えることができると言えるでしょう。
たとえば、会社でストレスを感じて出社を拒む社員の場合、「社内でのプレッシャーを避けて安心できる環境を求める」という目的が背後にあると考えられます。「なぜ出社したくないのか」という原因や理由の追求に終始するのではなく、そのように行動する目的を突き詰めるのがアドラー心理学です。人は目的達成に向かって生きており、その目的次第で人生は変えられるというのがアドラー本人の考え方なので、未来の成功に向けた改善策を見出す姿勢が重要になると言えるでしょう。
全体論
全体論とは、心と身体、理性と感情、意識と無意識といった要素で分断せず、1つの統一体として捉える考え方です。アドラー心理学では、「わかっているのにやめられない」という行動は、心と体が一体となって「やめたくない」という意志を表していると理解します。つまり、矛盾している状況が生まれているときは、自分の思考と行動を一致させることで改善を図ることが可能です。
たとえば、重要なプレゼンに向けて頭では準備を進めるべきとわかっていても不安が邪魔をする場合、精神面だけでなくトークスキルも鍛えると前向きに取り組めるようになるでしょう。メンタル面と実践的なスキルを同時に改善することで、理性と感情の調和を図り、統一されたパフォーマンスを発揮できるはずです。
認知論
認知論とは「人は事実そのものではなく、自分だけの主観的な意味付けを通して現実を捉えている」という考え方です。同じ出来事でも、人それぞれの「心のメガネ」を通して解釈するため、感じ方や価値は変わります。解釈の仕方によっては、間違った思い込みに陥るケースも少なくありません。
たとえば、業務で小さなミスをしたときに「自分は向いていない」と過度に否定的に捉えてしまえば自己評価が下がり、成長の機会を逃す原因となります。しかし、同じミスでも「成長のチャンス」と思えば、次回以降のパフォーマンス向上を図れます。物事や体験の価値は、すべて自分の解釈次第です。
対人関係論
対人関係論とは「あらゆる行動や感情の背後には必ず相手が存在し、お互いに影響を与え合う関係性がある」という考え方です。人は、職場や家庭、地域などさまざまな場面で相手に合わせた態度や言動をとり、行動や感情を使い分けます。
たとえば、部下が失敗した際は叱責を通じて改善を促し、上司が同じ失敗をした際にはフォローをするなど、相手によって対応が変わることもあるでしょう。アドラーの考えに則れば、顧客との対話やチーム内のコミュニケーションを円滑に進めるには、相手がどのような場面でどのように行動するのか観察を通して理解することが大切となります。
アドラー心理学の特徴的な思想|部下の指導に役立てるコツは?

アドラー心理学の独自の思想は、部下の指導に生かすことも可能です。ここからは、実践的なアプローチも交えながら、アドラー心理学の基本的思想をわかりやすく解説します。
課題の分離
「課題の分離」とは、自分と他人の課題を明確に切り離し、他者の問題に不用意に介入しないという思想です。自分と他人を切り離して考えることは、人間関係のトラブルを避けることにもつながります。
上司の立場から見ると、部下が失敗したときに上司は過剰に関与せず、まずは本人が問題に向き合い、解決する力を養うことが重要です。これにより、部下は自らの課題を自覚して成長の機会と捉え、結果として自立した行動が促進されるでしょう。
勇気づけ
「勇気づけ」とは、相手が自らの課題に向き合い、困難を乗り越えるための内なる力を引き出す働きかけを意味する用語です。自分自身に限らず、他者をサポートすることも含まれます。その際、アドラー心理学では勇気づけを上下関係や命令に従って行うのではなく、対等な立場から相手の存在を認め、感謝や共感を示すことが重要としています。
たとえば、部下が失敗を恐れてチャレンジできない状況では、上司がその失敗を個人の成長のチャンスとして捉え、具体的な改善策や次のステップをともに考えると、部下自身が自信を持って再挑戦できるよう促すことが可能です。こうした勇気づけは、部下の主体性を尊重し、お互いに協力し合う環境づくりに貢献するでしょう。
共同体感覚
共同体感覚とは、自分は所属する集団の一員であるという実感を持ち、他者と協力し合いながらともに成長する感覚です。アドラー心理学では、自己受容や他者信頼、他者貢献を通して、支配や依存ではなく、信頼と協力に基づく横のつながりを築くことを重視しています。
たとえば、上司が部下の解決策を考える話し合いの場を設け、意見を尊重することで、部下は自分が共同体の大切な一員であると感じ、お互いに支え合う風土が生まれる効果が期待できます。こうした実践は組織全体の連帯感や成長意欲を高め、より建設的な職場環境の形成につながるでしょう。
ライフ・スタイル
ライフ・スタイルとは、個人が持つ自己概念、世界観、理想などの内面的な価値観や行動傾向のことです。アドラー心理学では、幼少期の家族環境や経験などがその原型を形成し、大人になるにつれて成熟していくと考えます。ライフ・スタイルは物事の解釈を左右するものさしであり、その解釈によって行動も変容します。
アドラーは、ライフ・スタイルは誤って築かれることがあり、それを正しいものに修正するよう働きかけることが大切としています。部下が「自分には能力がない」などの極端な考え方をしているときには、上司は部下が自らの価値観と目標を見つめ直す機会を提供し、正しいライフ・スタイルに導くとよいでしょう。
ライフタスク
ライフタスクとは、人生における主要な課題である「仕事の課題」「交友の課題」「愛の課題」という3つのテーマの総称です。アドラー心理学の根底には、すべての悩みは対人関係の中に集約されるという対人関係論があり、その悩みを細分化したものがライフタスクです。
アドラー心理学では、ライフタスクが1つでも欠けた状態になると社会的存在である人間は不幸になり、反対に3つともうまくいくと安定すると考えています。そのため、上司として部下と関わる際には、部下を観察して人物像を理解した上で、欠けているタスクを補うように支援することが重要になるでしょう。
承認欲求の否定
承認欲求の否定とは、他人の期待に応えるためだけに行動するのではなく、自らの価値や目標に基づいて行動するべきだという思想です。アドラー心理学は、賞罰教育により「褒められたい」「罰せられたくない」という動機が生じる現状を批判し、上下関係から解放された対等な関係を重視しています。
社員教育においては、上司は部下に対して単に成果を褒めるのではなく、部下自身が内発的な動機で課題に取り組めるよう目標設定や評価の方法をともに考えることが望ましいでしょう。自律性を育む指導を行うことで、部下は外部からの承認に依存せず、自己成長を実感できるようになります。
アドラー心理学を学べる書籍

ここでは、数多くあるアドラー心理学関連の書籍の中から、初心者に特におすすめの3冊を厳選しました。各書籍の魅力と学び方を詳しく紹介します。
「嫌われる勇気」
「嫌われる勇気」は、アドラー心理学の基本概念を対話形式で平易かつドラマチックに解説した名著です。岸見一郎氏と古賀史健氏の共著による本書は、「他人の期待に応えるために生きるな」というメッセージを核に、劣等感や自己否定を克服し、真の自由と自己実現を目指す方法を示しています。
対人関係の悩みを根本から見直し、よりよい人間関係を築くために自らの内面を変革する実践的かつ具体的なアプローチを学べるでしょう。現代社会における心の問題に対処する力を養える点が、本書の大きな魅力です。
「アドラー心理学入門」
「アドラー心理学入門」は、アドラーの思想を基礎から解説し、幸福に生きるための具体的な実践方法を示す入門書です。本書では、自己理解や対人関係の問題解決、子育てや職場でのコミュニケーション改善など、日常生活で直面するさまざまな課題に対して、アドラー心理学の視点からどのようにアプローチすべきかを丁寧に解説しています。
自分自身のライフスタイルや価値観を見直し、他者とより健全な関係を築くための指針、自己成長や幸福実現に向けた具体的なヒントを学べます。また、オーディオブック版も提供されており、忙しい方でも手軽に学習することが可能です。
「アドラー心理学―人生を変える思考スイッチの切り替え方―(スッキリわかるシリーズ)」
「アドラー心理学―人生を変える思考スイッチの切り替え方―(スッキリわかるシリーズ)」は、臨床心理士の八巻秀氏が執筆し、イラストやマンガ、図版をふんだんに用いてアドラー心理学の基本概念と実践的応用をわかりやすく解説する入門書です。本書では、自己改善や対人関係における悩み、消極的な思考や短気などの性格上の弱点を、具体的な思考スイッチの切り替え方法を通じて改善するアプローチが示されています。
さらに、実際のカウンセリングシーンを対話形式で紹介しているため、自分自身の内面を見つめ直し、悩みを解決するための具体的な手法や、より前向きで充実した人生を実現するためのヒントを得られるでしょう。
まとめ
アドラー心理学は、自己決定性・目的論・全体論・認知論・対人関係論の5つの理論を基盤に、個人が自らの目標に向かって行動する重要性や、対人関係の中で自立と協力を実現するための実践的な手法を説いています。
特に上司による部下の指導においては「課題の分離」や「勇気づけ」といった技法が大いに役立つでしょう。対人関係の悩み解消や自己肯定感の向上を目指す場合には、アドラー心理学を取り上げた書籍が概念の理解と実践の両面から大いに役立つ情報源となります。部下の育成やチームの連帯感向上に、アドラー心理学をぜひ応用してみましょう。
また、アドラー心理学は子育てにも生かすことが可能です。親として子どもの育て方や関わり方に悩んでいる場合は、育児の指針が得られる「アドラー式・子育て講座」を受講してみてはいかがでしょうか。
関連記事
Related Articles
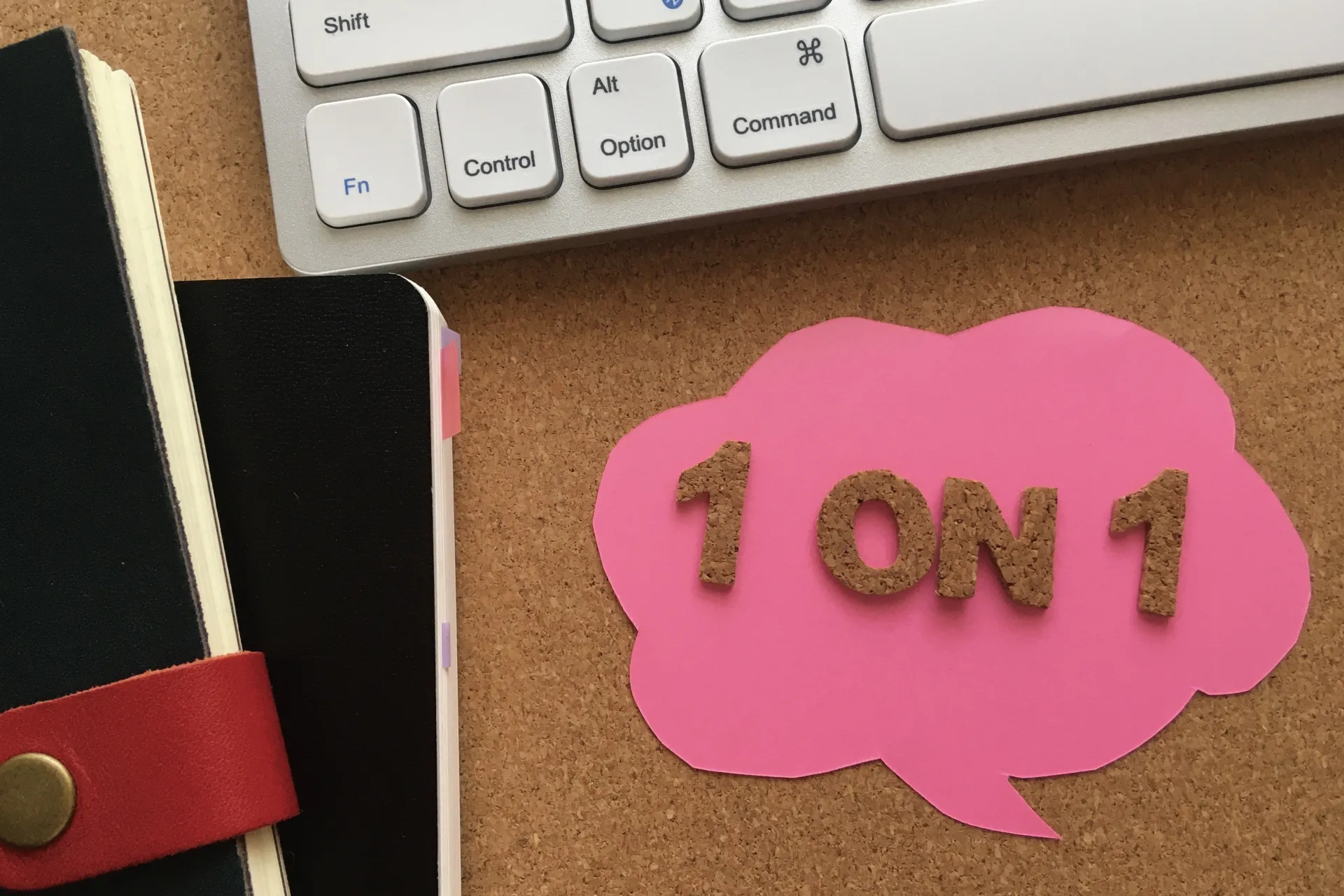
1on1とは?目的や会社組織を強化する効果的なやり方を解説
1on1ミーティングでは、部下に対して期待値をしっかりと明示し、これまでの業務や成果に対する賞賛を行うことが大切です...
エンゲージメント企業研修
エンゲージメントとは?ビジネスにおける意味や高める施策を徹底解説
この記事は2023.11.14に公開した記事を再編集しています最終更新日:2024.12.18 少子高齢化が進む日本...
エンゲージメント
【事例付き】朝礼で失敗しないネタ8選と話の組み立て方の秘訣とは
この記事は2024.3.25に公開した記事を再編集しています2025年6月23日更新 朝礼は部署やチーム内で情報共有...
エンゲージメント
目標管理制度(MBO)とは?メリットや具体的な導入方法、注意点も
成果主義が一般的になっている昨今、注目を集めているのが目標管理制度です。目標管理制度では、社員が自ら目標を決め、面談...
HRトレンドエンゲージメント
管理職になりたくない社員が急増!理由と企業ができる対処法を解説
近年、「管理職になりたくない」と思っている社員が増えていることで、企業は管理職不足に陥ってしまう可能性があります。責...
エンゲージメント
共感力のある人はここが違う!身に付けるメリットとトレーニング方法は?
共感力とは、他者の感情や立場に寄り添い理解しようとする力です。ビジネスや人間関係で信頼を築く上で欠かせないスキルであ...
エンゲージメント
自己肯定感とは|Z世代社員の自己肯定感を高めるコツ4ヶ条
この記事は2023.12.26に公開した記事を再編集しています2025年1月27日更新 Z世代の新入社員や、ミレニア...
HRトレンドエンゲージメント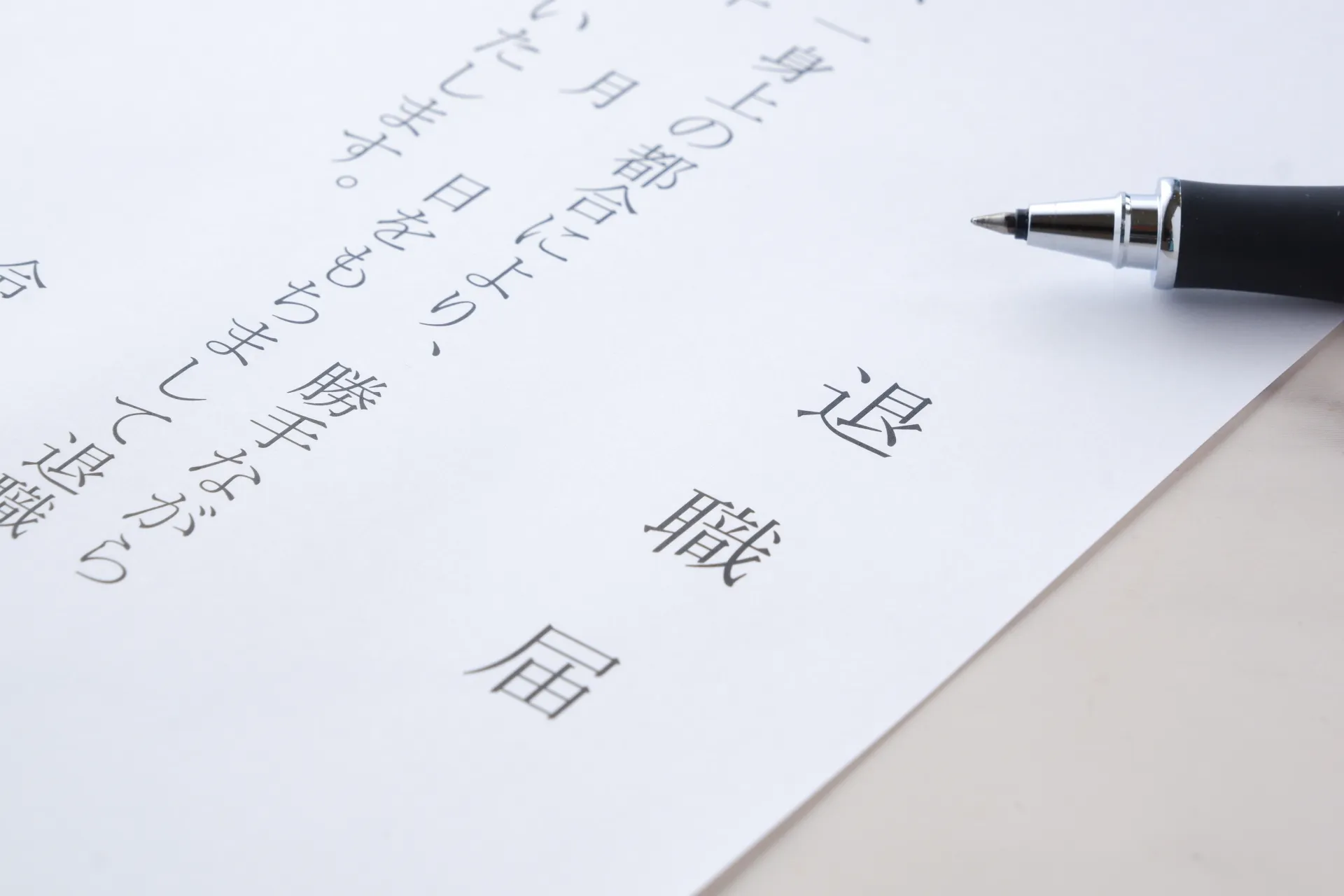
離職防止ができる対策事例10選!若手社員の離職防止アイデアを解説
当記事では、平均的な離職率から離職が発生する理由、さらに離職防止を怠った場合に起こり得る損失、企業が離職防止のために...
エンゲージメント


