 2011.01.25
2011.01.25- INTERVIEW
20歳のときに知っておきたかったこと ティナ・シーリグさん特別インタビュー
●ティナ・シーリグさん略歴
(BOOK著者紹介情報より)
スタンフォード大学医学部で神経科学の博士号を取得。
現在、スタンフォード大学工学部に所属するアントレプレナー・センター、スタンフォード・テクノロジー・ベンチャー・プログラムのエグゼクティブ・ディレクター。さらに、スタンフォード大学の経営工学・エンジニアリング課程やハッソ・プラットナー・デザイン研究所でアントレプレナーシップとイノベーションの講座を担当。
全米の起業家育成コースのなかでも高い評価を得ている。幅広い分野の企業幹部を対象に、頻繁に講演とワークショップを行なっている。
『20歳のときに知っておきたかったこと (What I Wish I Knew When I Was 20)』は、2010年のベストセラーとなりました。その著者で、スタンフォード大学でアントレプレナーシップとイノベーションの講座を担当しているティナ・シーリグさんに、本の話、クリエイティビティの話、アントレプレナーシップの話などをうかがいました。
Not Giving Up イノベーションへの第一歩
清水
それでは、始めましょう。まず、そもそもなぜこの本を書こうと思ったのですか?
シーリグ
それには、とても長い話があります。まず、息子のジョシュが20歳になる時までに、私自身が今から振り返って20歳の時に知っておけばよかったと思うことをリストにしておこうと思ったのです。息子へのリストアップだったのです。その時は、本にしようとは考えてもいませんでしたし、本になるとも思っていませんでした。
清水
そうだったのですか。なぜそれがベストセラーのこの本につながっていったのですか?
シーリグ
少しずつリストアップしていったのですが、そんなことをしているうちに、スタンフォードの企業リーダーシップ・プログラムで学生に話をする依頼が来たのです。そこで、このリストを使って話をしようと考えて、講演のタイトルも『20歳のときに知っておきたかったこと』にしました。
清水
学生への講演がきっかけだったのですか?
シーリグ
この講演は好評で、いろいろなところに招かれました。何度も同じ講演をしているうちに、これは本になるんじゃないかと思ったのです。ただし、ここから本にするまでがまた長いのです。本の企画書はすぐに書きました。そこで、まずはある出版のエージェントに見せてみました。
清水
反応はどうでしたか?
シーリグ
残念ながら、そのエージェントは気に入らなかったようです。でも、まあ、しょうがない。ただ、自分の仕事もあり、とにかく忙しくて、他の出版社には送れずにいたのです。しばらくはおいておいたのです。ただ、あきらめたわけではありませんでした。
シーリグ
それから、2~3年が経ったでしょうか。ある日、出張のために乗った飛行機でたまたま隣の席の人が出版社に勤めている人だったのです。おしゃべりをして仲良くなり、その時、偶然にも本の企画書を持っていたのです!
清水
企画書を見せたわけですね。
シーリグ
そう。でも、『自分の出版社では出せない』と言ったのです。それから、違うプロジェクトでまた彼と一緒になりました。彼は、私のクリエイティビティのクラスにも来ました。そして、ある日、彼に私の学生と一緒にやったプロジェクトを送ったのです。それが彼のチームに渡り、ある編集者が興味を持ったのです。その編集者からコンタクトがあり、彼がスタンフォードにやってきました。そこで、前と同じ企画書を見せました。
清水
スタンフォードにやってきた編集者に? 同じ企画書を?
シーリグ
そう。
清水
でも、その編集者の上司は、『自分の出版社では出せない』と言っていたのですね?
シーリグ
そうです。でも、その編集者は『面白い!ぜひ本にしましょう!』と言ってくれたのです。そこから打ち合わせを重ね、出版に至ったのです。
清水
偶然の出会いだったわけですね。
シーリグ
偶然ではあったのですが、偶然をたぐりよせたとも言えるのですよね。とにかく出版を決してあきらめずに、常に企画書を持ち歩いていたわけですから。
清水
Not Giving Upですね。
シーリグ
そう。あきらめないことは、本当に重要だと思います。それと、人に意見を求めたときに、常に正しい意見を得られるわけではないと言うことも示していると思います。だって、本は大成功でしょう? 他の人がNOといっても、自分がYESと思ったら諦めないことは大切ですね。
清水
そうですね。ところで、ジョシュに『20歳のときに知っておきたかったこと』はあげたのですね? そもそも彼にむけたリストだったわけですから。
シーリグ
もちろん!
清水
反応はどうだったんですか?
シーリグ
ちょっと困ったことがありました(笑)。ある日、ジョシュが、あるアイディアを思いつき、それを実行しようかどうか相談しに来たのです。それが、あまり賛成しかねるアイディアだったので、私はNOと言ったのです。そうしたら、『ありがとう。ぜひやってみる』と彼は言いました。
清水
あはは。なぜですか? NOと言ったのですね。
シーリグ
そうなのです。NOと言ったのに。でも、私は『NOと言われるものには、常識を破るクリエイティビティの源がある』と本の中で書いているのですよね。彼は、それを読んで、親がNOというものでも、チャレンジするようになったのです(笑)。
恥ずかしいの?それは大問題!
清水
日本の企業の話をしましょう。日本の企業は競争力を失っていますね・・・
シーリグ
それそれ! 今日は日本に来て2日目なのですけど、みんなそれを言うのです。『日本企業は国際競争力を失っている』 『どうしたら良いのだろう』って。
私には、人々が語るそのストーリーが問題だと思います。もしも、みんながそれを言い続けたらどうなると思いますか? それが現実になるのです。日本は負けてきているとみんな思っているのですか?
時代の感覚として、日本はその競争力を失いつつあるという意識が醸成されてきているようですね。まるで、私の本が売れたのは、日本の経済が上手くいかず、社会に出た若い人が多くの機会には恵まれないと感じているからだという気もします。どう思いますか?
清水
難しい問題ですね。ただ、本は、今とは違う考え方を提示してくれていますね。
シーリグ
面白いことがあります。アメリカの経済が不調だったとき、実はスタンフォードでは学生がたくさんのベンチャーを生んだのです。経済が不調だからこそ、ベンチャーが生まれたわけです。
清水
経済が不調になって、学生が大企業志向になっている日本とは反対の方向ですね。
シーリグ
そうですね。これはとても面白い。リスクを考えてみてください。大企業に入るリスクと、自分で会社を立ち上げるリスク。どちらが高いですか? これまでは自分で会社を立ち上げるリスクはとても高かったのですが、それが今ではかなり小さくなっています。また、大企業に入ったとしても、その仕事を失うリスクは高くなってきています。つまり、自分でスタートアップするのと、大きな組織に入ることを、リスクという観点から比べると、ほとんど変わらなくなってきたのですね。
清水
でも、スタンフォードと日本では逆の動きですね。
シーリグ
ポイントは、ロールモデルだと思います。アメリカには、自分で企業を立ち上げて成功したロールモデルがたくさんあります。もちろん、スタートアップで失敗した人もたくさんいるわけですが、社会に成功したロールモデルがあるからこそ、たくさんの人がチャレンジするのです。ポイントは、スタートアップしようとするときに、実際に具体的なロールモデルがあるかどうかです。日本では、人々はどうしても失敗を怖がってしまうようです。失敗することを恥だと感じてしまうようです。失敗は恥ずかしいことだと思いますか?
清水
そうですね。そう思う人は多いようですね。
シーリグ
それは私にはなかなか理解出来ないですね。おそらくそういう文化なのかもしれません。例えば、ここに来る途中、日本人の友人と話していたのです。彼女には、2歳の娘がいます。『2歳の娘は、失敗することを恥ずかしいと思っている?』と聞いたところ、もちろん答えは『No』です。2歳の子どもは、自分のやりたいようにやるのです。失敗もなにも恥ずかしいと思っていません。つまり、ある時から「失敗すると恥ずかしい」と思うようになってきてしまうのです。何歳ぐらいから恥ずかしいと思うようになってくるのですか?
清水
中学生ぐらいからでしょうか。
シーリグ
だんだん学習してしまうわけです。これは大きな問題です。だれだって、人から批判されたり、バカにされたりするようなことはやろうとは思いません。これは、チャレンジすることへの大きな障壁となってしまいますね。
シーリグ
日本の文化は古く、歴史に根ざしており、尊敬されるべきものです。これに対して、カリフォルニアにはそういった古い、歴史のある文化はありません。多様なバックグラウンドを持った人々が、いろいろなところからきています。中国やメキシコ、ドイツ、チリ・・・本当にいろいろなところから人が集まっています。道徳や倫理、文化などは本当に多様です。そういうところでは、人々はみな違い、同じであることはほとんどありません。日本は、まだ多様性が少ないため、「失敗したら恥ずかしい」という固定観念がなかなかとれないのかもしれませんね。
シーリグ
本を出版してから手紙をたくさんいただくようになりました。そこには、日本からの手紙も多いのです。そして、興味深いのは、日本からの手紙のメッセージは、本から大きなインスピレーションはもらったけれども、『私は何をしていいか分からない』というものなのです。今の生活はなんとか変えたいと思っているものの、どうやって良いか分からないというメッセージが本当に多いのです。

20歳のときに知っておきたかったこと
スタンフォード大学集中講義
著者:ティナ・シーリグ
出版社: 阪急コミュニケーションズ
ゲームのルールを変えろ!
清水
文化の話から、もう少しレベルを落として、組織の話に移しましょう。チャレンジができる組織にするためには、どうすれば良いでしょうか?
シーリグ
それには、いろいろありすぎてリストアップするのは難しいですね。今、執筆中の本はクリエイティビティについてのものです。ただ、ひとつ話をするとすれば・・・
シーリグ
人生は、ゲームです。ゲームにはルールがあります。例えば、お箸を使ったり、名刺を渡したり・・・。私たちの生活の周りにあるものは、すべてゲームのルールです。日本ではビジネスで初めて会った人には、名刺を渡すわけですね。もしも渡さなかったら? きっと変な人だと思われるかもしれませんし、ビジネスチャンスをなくすこともあるかもしれません。それは、ルールに従わなかったことへのパニッシュメントです。チェスや野球、トランプなど、私たちのまわりにはいろいろなゲームがあります。ルールを決めて、何かを競うというゲームが好きなのです。
シーリグ
そして、自分の会社ではそのルールを創れるのです。会社をクリエイティビティの高い組織にしたい場合には、そのようなルールを創れば良いのです。例えば、失敗をしても大きなパニッシュメントが与えられないようなルールを創るのです。失敗に対してパニッシュメントが大きいルールがある組織では、チャレンジはなかなか起こりません。私たちは、ゲームのルールを学ぶのは本当に早いのです。どこかで、チャレンジして失敗し、大きなパニッシュメントを受けている人を組織の中で見かけたら、すぐにそのルールを学んでしまうのです。そのルールを学んだら、チャレンジしようとは思いませんね。
清水
チャレンジやクリエイティビティを高めるルールを創れば良いわけですね。
シーリグ
そうですね。例えば、階層的な会社を考えてみましょう。何をするのにも上司の許可が必要だとします。どんな提案をしても、上司がYESというかどうかがポイントになるとします。その組織では上司が“正しい”というルールになるわけです。これでは組織のクリエイティビティは当然低くなりますね。アイディアはどこからでも湧いて来て、どんどんチャレンジできるようなルールにしないといけないのです。
清水
ゲームのルールですね。
シーリグ
スタンフォード大学には、チャレンジを促進するようなルールがあります。発言しない人は評価されません。新しいアイディアが出てきたときには大きく評価します。日本人であろうが、アメリカ人であろうが、スタンフォードのゲームでは同じルールの中で競争するのです。それが、企業家がどんどん生まれてくる土壌となっているのです。
清水
これは日本人や日本の会社を大きく勇気づけるものですね。ゲームのルールが違えば、高いクリエイティビティを発揮できるという話ですね。
シーリグ
そう。大切なのは、ゲームのルールは変えられるということです。もしも、あなたが今のゲームのルールが気に入らなければ、あるいは今のルールではなかなか勝てないとすれば、ゲームのルールを変えれば良いのです。もしもゲームのルールを変えることが難しければ、自分に合うようなルールでゲームをしているところに移れば良いのです。
清水
日本人は、ルールに従うのはとっても得意ですね。だからこそ、余計にルールが大切ですね。
シーリグ
本当にそうです。日本の組織はどうも、多様性を少なくしてしまうようなルールを持っているところが多いような気がします。新しいアイディアやフレッシュなインプットがなくなってしまうようなルールはまずい。女性やマイノリティ、日本人ではない人、違うバックグラウンドを持つ人などが増えてくると良いですね。
清水
ようやく日本の企業も、グローバルに人材を集めようとし始めました。これは、多様性を増やすという点では大きな刺激になるかもしれませんね。大きなターニングポイントになると良いですね。
シーリグ
ロンドンやニューヨーク、サンフランシスコ、香港など、最もイノベーティブな街は、最も多様性があるところなのです。多様性があるところにこそ、イノベーションは生まれてきたのです。
<<end>>

清水洋氏プロフィール
1973年横浜市生まれ。
一橋大学商学研究科博士課程単位取得退学(2005年) London School of Economics and Political Science、Ph.d(2007年)
企業の組織と戦略を歴史的に分析しています。 研究テーマは、競争とイノベーション・意図せざる結果。論文は、「産業政策と企業行動の社会的合成:石油化学工業の『利益なき繁栄』」米倉誠一郎編著『企業の発展』八千代出版、2002年など。 一橋大学イノベーション研究センター准教授。 コラム「雲外蒼天」好評連載中。
●インタヴューを終えて
『20歳のときに 知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義(What I Wish I Knew When I Was 20)』の中に、 面白い実験があります。
スタンフォード大学の学生に5ドルをわたして、ビジネスをさせるというものです。
詳しくは本を読んで欲しいのですが、5ドルに惑わされる学生たちや、自由にビジネスを創れる学生など様々でとても面白いのです。
実は、これと同じエクササイズを一橋大学の1年生のゼミ (一橋は1年生からゼミがあるのです!)でやってみたのです。
その結果は現在執筆中のシーリグさんの本に書かれるそうなので、それを楽しみに待っていて欲しいのですが、日米で1つ大きな違いがあったのです。
それはリーダーシップでした。
エクササイズは、1年生の最初のゼミでやりました。高校を卒業したばっかりの学生たちです。
彼らには、「グループごとにリーダーを決めて、ビジネスをやってください!」とアナウンスしたのですが、1つのグループはそれを聞いていなかったのです。リーダー を決めずに動きだしてしまったのです。
結果はどうでしょう? なんとそのグループは最も多くのビジネスプランを考えついたのですが、どれ一つやってみることができなかったのです。
スタンフォードでは、「リーダーを決めろ」と言わなくても、こういうことは起きなかったそうです。日本で、役割としてリーダーを決めてあげることの大切さを改めて思い知りました。
タイトなスケジュールの中でも、インタビューは刺激に満ちていました。アメリカの大学の先生らしく、どんどん話題が飛んでいきます。
本から受ける印象そのままの人だったのですが、なにより、とにかく自分で話しているのを楽しんでいるのがとても印象的でした。
彼女は、必ずしも自分の専門ではない本を書くことはチャレンジだったといいます。でも、チャレンジって、すごく楽しいのですね。
次のシーリグさんの本がとても楽しみです。

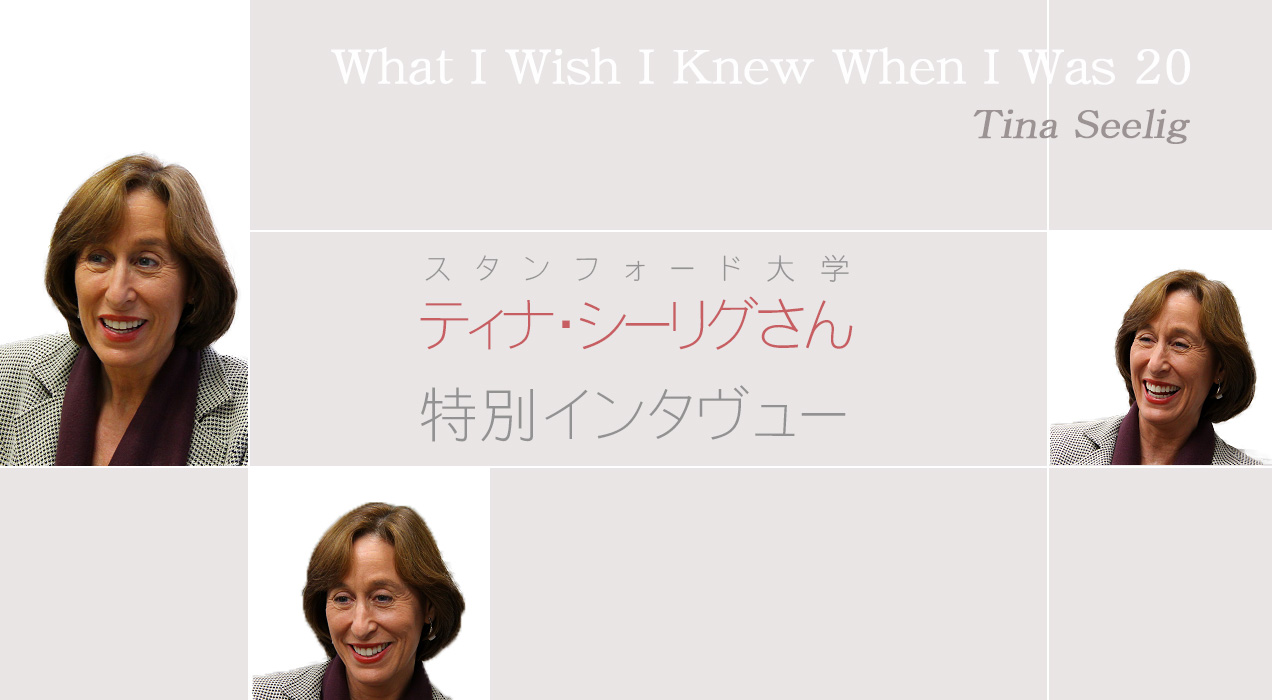
 イノベーション
イノベーション

