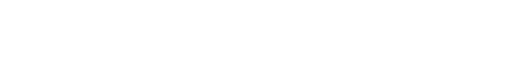のどもと過ぎれば熱さを忘れる
It means... どんな苦しみも恩義も熱さ同様過ぎ去ってしまえば忘れてしまう

食道の構造
熱いものも、飲み込んでしまえば、もはや熱さを感じなくなること。このことから、苦しいときに人に助けられても、楽になればそのことを忘れ、恩を感じなくなることをいう。人生のいろいろな場面に当てはまることわざである。「病治りて医師を忘れる」「苦しいときの神頼み」「雨晴れて笠を忘れる」など、実にいろいろな表現がある。
では、実際に熱いものを飲み込んだとき、本当にのどを過ぎてしまえば熱さを感じないのだろうか。口に入れた飲物などは、のどから食道に向かうが、食道の入口は狭いじょうご形になっているので、飲物はそこに殺到する。これが熱い飲物であれば、食道の入口を支配している迷走神経が突然の強い刺激を受けて反射的に食道の筋肉を緊張させ、熱い飲物を通さなくしてしまう。こうして熱い飲物に目を白黒させることになる。
つまり、熱いと感じるまでもなく、瞬間的に飲み込めなくなるのだ。言いかえれば、熱さを飛び越して、肉体的な苦痛を感じてしまうのである。このあと、少し時間がたつと筋肉はゆるんで、飲物は少しずつ食道を通るようになり、今述べた苦痛も解消され“熱さをわすれた”状態になる。やたらと熱い茶がゆなどを流し込むように食べることも可能である。これは、のどもとが熱さに耐えかねて、つい飲み込むためだが、その場合、確実に鈍い“熱さ”が食道から胃へ入って行くのも感じるものだ。
これが問題で、のどもとほどの苦しさはないため、本人は意識しないものの、厳密に言えば、食道や胃は熱さを感じているのである。これを常にやっていると、丈夫な胃もたまったものではない。「大和の茶がゆ」というように、昔から奈良県の人は熱い茶がゆが好きだが、そのためか、他の地方より胃病が多いようだ。
飲物の適温
では、私たちは健康を考えた場合、すべての飲物を常温近くまで冷ましてから飲み込む必要があるのだろうか。それで頼りないのなら、せめて体温(36~37℃)ぐらいまで温度を下げる必要があるのか。だが、体温ぐらいのものは、飲めば実に味気ないものである。よく酒カンは“人肌”なんていうが、体温ぐらいの飲物など、決しておいしいものではない。そんなわけで、おいしさと健康が両立する適温というものもあるわけだが、一般には風呂の温度(42~45℃)がよいとよく言われる。この程度ならストレートに飲み込めて、体へのダメージも少ないだろう。
また、一般に人間がお茶などをがぶ飲みできる限界温度は50℃ぐらいだが、この程度でもよいだろう。60℃になると、くちびるや舌が熱さを感じるが、口の中でいくらかさめるので、これも少しずつなら飲み込める。さらに70℃になると、これは危険温度で、すすり飲みしたり、飲む前にフーフー吹いてさまさないと口に入らない。もちろん、ホットコーヒーでも紅茶でも緑茶でも、容器の中の飲物の上の方だけであれ、口で吹いてさますのは簡単ではない。
それより、すすり飲みの方が断然、効果的である。すすり飲むと、大量の空気も同時に吸い込むので、その冷却効果が役立つ。しかし、すすり飲みできる人種は意外に少なく、欧米の人びとは、これが大の苦手である。この人たちは、ゴクリと直接飲む。一般にすすり飲める人種は、うどんやそばもすすりながら食べられるもので、つまりは箸を使う民族だと考えてよいと思う。
ある一流ホテルのマネージャーに確かめたところ、一般にコーヒーなどはお客のテーブルに置いたときに70℃ぐらになるように加減しているという。これで、すぐにすすり飲めるのだが、だからといって気を遣ったつもりで、欧米の人びとに70℃より低い温度のコーヒーを出すと、日本人と差別をしているように考えて、機嫌が悪いということだった。
皮膚感覚と口内感覚の差
それにしても、コーヒーなどの飲物の温度は5℃ぐらいの差はあまり気づかないが、風呂の湯は5℃も違うと大変である。人によって熱め好き、ぬるめ好きがあるが、一般的な適温は42℃。これに対し、47℃にもすると、とても入れないくらい熱いし、反対に37℃にすると体温と同じくらいになってカゼをひく。
試しに50℃のコーヒーに指を入れてみると、びっくりするくらいに熱い。
“猫舌”の人は別として、熱で調理するという人類の長年の習慣によって、口の粘膜が熱に対してどんどん強くなり、手足や、体全体の皮膚感覚と大きく違ってきたのだろうか。