|
どんなシステムにも向き、不向きがあります。
向いている場面で使ってあげれば実力を発揮しますが、向いていないことをいくらがんばってやってみても逆効果です。
現在のeラーニングは、どうもボタンの掛け違いというか、認識の誤りによって「不向き」な部分で能力を発揮しようとしているようなのです。
一見最も向いていると思われていた「パソコン画面で学習する」という点が、実は向いていない部分であったということは先ほども述べました。
それでは、eラーニングに向いていることとはどんなことなのでしょうか?
eラーニングは、「迅速な添削レスポンス」、「柔軟な企業別対応力」,そして「リアルタイムな双方向コミュニケーション」といった分野において最もアドバンテージが発揮されます。
インターネットの利用によって、従来の郵送による添削のやりとりとは比べ物にならないほど速く添削を返信できますし、デジタルの持つ「変更しやすさ」を利用すれば様々な企業に対応した提出課題を用意することができます。
また、Webのインタラクティブなプログラムを活用すれば、講師と受講生、あるいは受講生間のコミュニケーションをリアルタイムに行うことも可能です。
ですので、これらの優位性によって、従来の通信教育においてネックになっていた「添削の遅さ」と「自分の企業に合った教材がない」、「先生の顔が見えない」、「1人で学習してもなかなか続かない」といった様々な懸念を消し去ることが可能になるのです。
つまり、「紙のテキスト」、「企業の業務に合った提出課題」、「Webを利用した迅速で決め細やかな添削」。
これらを満たしたeラーニングこそが、もっともeラーニングの特性を活かした教育システムだとアイ・イーシーは考えます。
実に単純明快な答えなのですが、「eラーニング」という言葉の持つ響きによって踊らされてしまい、本質的な「教育」という概念が抜けてしまっていたのが今までのeラーニングだったのです。
これらをふまえてアイ・イーシーが開発した全く新しいeラーニングシステムを作り上げました。
それが次に紹介する「快速てんさ君」です。
|
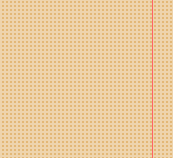
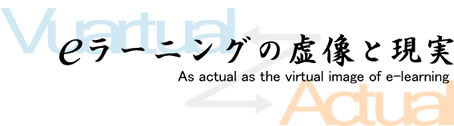
![]()
![]()